ドクゼリの育て方

育てる環境について
園芸用に育てるということでは、斑入り、ふいりと読みますが、そのような品種がどちらにもあり、園芸用として育てられているようです。斑入りとは、普通は葉なども緑だけですが、その葉に白い色が混じっているように品種改良した植物で、葉の外側だけ白くなったりしている植物です。
とてもきれいなのでわかりやすいですが、園芸用の植物を販売しているお店や花屋さんなどにも見られる植物です。色々な植物であるようです。セリ科ということでは、園芸用のホワイトレースフラワーは同じセリ科で、ドクゼリモドキ属という親戚の関係ですが、これらのセリの関係では一番育てやすいのではないかという品種です。
花も綺麗で純白のレースのカーテンのような繊細な花を咲かせるので、これらの種類の中では一番美しいのではないかという品種です。同じセリ科なので花も似ていますが、このホワイトレースフラワーの育て方で、他のセリ科の植物も育てられるのではないかとも予想できます。ガーデニングでは背丈が1,5メートルぐらいになりますので、メインの花として栽培するということですが、元々が水を好むこれらの花ですので、
日当たりと水はけの良い所で育てるということが良いようです。また関東地域の気候では問題なく育つということで、秋に種を蒔いて、5月から7月頃楽しむという植物です。初心者におすすめの植物で、種からでも育てやすいのですが、注意点としては、大きくなりやすい植物ですので、肥料をやり過ぎると巨大化してしまうということです。
種付けや水やり、肥料について
自生しているそれらの野草を栽培するということはあまりないでしょうが、都会などでは余り食べるという目的がないので育てるということでは、育て方を考えながら、観賞用として試しに育ててみるのも面白いということですが、元々が日本に自生している野草なので、初心者でも育てやすいのがメリットということになります。
特に花が美しいということで、ホワイトレースフラワーなどでもわかりますが、レースの斑点のような花が咲くということからもガーデニングで利用しても面白い彩りになるのではということになります。また切り花用に育てる人もいるようで、背丈があるので、そのような利用の仕方もできますし、園芸用に鉢植えで育てられる品種も作られているので、
ベランダなどでは、そのような品種で鉢植を楽しむということが良いようです。また害虫などは、つかないということですので、その点も初心者には向いています。むしろ肥料を与え過ぎたりして、育ちすぎる危険があるということが注意点になるので、その点も育てやすい植物ということがわかります。またホワイトレースフラワー関連では、
ブルーレースフラワーという青い鮮やかな花もあるので、同じセリ科ですが一緒に育ててみるのも面白いということです。セリ科はやはり花が美しいので、食べる用途よりも観賞用として育てるということが良い植物ということになります。特にこのブルーレースフラワーは非常に魅力的な花で、セリの進化型という感じでぜひ育てたい花でもあります。
増やし方や害虫について
セリもそうですがドクゼリも名前は毒々しいということで、嫌われそうですが、花をみるとほんとうに美しい花を咲かせます。要は食べなければ良いということで、観賞用ということで利用すればよいわけで、毒ということで嫌うにはあまりにも惜しい美しい花を咲かせます。園芸用の改良された品種が販売されているのもよくわかります。
この毒ということでは、具体的にはどのようなものがあるかというと、シクトキシン、シクチンという成分が原因で、中毒症状では、痙攣、呼吸困難、嘔吐、下痢、腹痛、眩暈、意識障害などだそうで、直接食べたりして摂取した場合には、死に至る場合もあるということです。また皮膚からも吸収され易い性質があるということですので、あまり触らないほうが良いのかもしれませんが、
やはり野草として食べてしまうということで、毎年トラブルが発生しているということです。ですので野生種よりは栽培用の品種で育てたほうが良いのかもしれませんが、ガーデニングでは園芸用を育てるでしょうから、先ほどのホワイトレースフラワーやブルーレースフラワーなどを庭で育てるのが無難なところでしょう。
最近は食べられる野草や山菜などもブームですが、中毒ということがあるので、やはりガーデニングなどで観賞用に楽しむのが良いということになります。どうしても食べたい場合には、スーパーなどで販売していたり、通販などで手に入れるのが無難でしょう。しかし魅力的な花達ですので、栽培用はおすすめの植物ということになります。
ドクゼリの歴史
ガーデニングなどの植物を育てるということは、本来自然にある自生の植物を自分の所有する庭に囲い込み、好みに合わせた箱庭を作り楽しむということですが、特に女性に多い理由としては、もともと男性と女性の役割の違いからきているという考え方があります。男性の場合には、太古の昔からの役割として、外に出て狩りをして、家族の食料を確保してきました。
しかし女性の場合には、その間木の実などを集めたり、家族の世話をしたりして、長い年月暮らしてきたという歴史があります。それで女性の場合には、物を集めたり、安定した状態を求めたりするということで、視野が自分の周りのものに限定されて執着するということだとありましたが、庭を美しくするということも、そのうちのひとつということになります。
そしてそれは、普通のガーデニングだけではなく、集めるということで、より自分たちに有効な植物を集めて安心したいという心理にもなりやすいということになります。例えば木でも美しいだけではなく、実が稔り食べられる果実がつくものや、野草などでも、食べられる野草なども作りたいと考えるなどです。例えば春の七草なども、その中に入りますが、その中ではセリなども面白い植物です。
セリは食べられる野草で、田舎ではよく見られるものなので、自生しているということでも、採取して食べたりしていますが、その時に気をつけなければならないのがドクゼリです。とても似ているので、間違って採取して食べたりしてしまうことがあります。しかしこのドクゼリは名前の通り毒があり、日本三大有毒植物のひとつにもなっています。
ドクゼリの特徴
セリを利用する場合には、ドクゼリとの違いを理解しないと危ないということで、最近では春の七草を食べる頃にはスーパーなどでもセリは販売されるので、そのような入手方法で利用するというのが一番安全ですが、その他でも、ガーデニングなどで、育てても面白いということになります。
セリだけを育てれば良いからですが、このセリは育てるのが難しいそうで、商業ベースに乗せるのも難しい植物になっているそうです。それで自生している野草ということで利用されてきたということもあるのでしょう。両者の見た目が似ているのは、同じセリ科だからでもありますが、ドクゼリの方はセリ科のドクゼリ属ということで親戚同士でもあります。
片方は毒があり、片方は毒がないということですが、同じセリ科なのにどうしてそうなったのかも面白いところです。ドクゼリとセリの違いですが、ドクゼリのほうが大きめだということです。また大きな特徴としては、根が違いすぎるということで、ドクゼリは根が筍状になっているので一度見ればわかるほどの違いがあります。
それで区別するとわかりやすいということでした。原産地や生息地は日本全国で、アジアにも広く広がっている植物です。どこにでも見られますが、水辺や湿原に生育する抽水植物ということです。セリもそうですが花が美しく園芸用に改良されたりして、ガーデニングに利用できるようになっている植物でもあります。ですのでそのような園芸用に栽培されている品種を育ててみるのも良いのではないかということになります。
-

-
ハナズオウの育て方
ハナズオウはジャケツイバラ科ハナズオウ属に分類される落葉低木です。ジャケツイバラ科はマメ科に似ているため、マメ科ジャケツ...
-

-
ディモルフォセカの育て方
ディモルフォセカは、南アフリカ原産のキク科の一年草で、日本名ではアフリカキンセンカと呼ばれています。よく似た花に、多年草...
-

-
真珠の木(ペルネティア)の育て方
真珠の木と呼ばれているベルネッチアは、カテゴリーとしてはツツジ科の植物になります。吊り鐘状という少し珍しい形で、春遅い時...
-

-
球根ベゴニアの育て方
ベゴニアの原種は、オーストラリア大陸を除いたほぼ世界中の熱帯や亜熱帯地域に分布しています。ベゴニア自体は日本でも原種が存...
-

-
ニセアカシアの育て方
ニセアカシアは北米原産のマメ科ハリエンジュ属の落葉高木です。北アメリカを生息地としていますが、ヨーロッパや日本など世界各...
-

-
カロライナジャスミンの育て方
カロライナジャスミンは、北アメリカの南部から、グアテマラが原産の、つるで伸びていく植物です。ジャスミンといえば、ジャスミ...
-

-
植物の育て方や栽培方法についてのコツとは
老後の趣味やインテリアの一環として観葉植物を育てる方が増えており、それに比例して園芸店なども人気が上昇中となっています。...
-

-
ワケギの育て方
原産地については西アジアから地中海東部であるいう説やユーラシア南部を生息地とする説もあればアフリカやヨーロッパが原産地で...
-

-
ガイラルディアの育て方
ガイラルディアは、北アメリカおよび南アメリカを原産地として、20種以上が分布しているキク科の植物で和名を天然菊と言い、一...
-

-
モミジの育て方
モミジは日本人に古くから愛されてきた植物です。色づいたこの植物を見に行くことを紅葉狩りといい、秋の風物詩として古くからた...




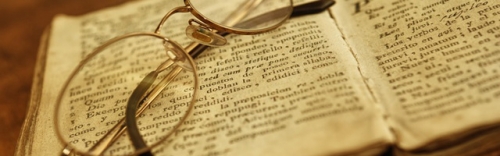





ガーデニングなどの植物を育てるということは、本来自然にある自生の植物を自分の所有する庭に囲い込み、好みに合わせた箱庭を作り楽しむということですが、特に女性に多い理由としては、もともと男性と女性の役割の違いからきているという考え方があります。ドクゼリの方はセリ科のドクゼリ属ということで親戚同士でもあります。