コエビソウの育て方

コエビソウの育てる環境について
コエビソウを栽培する一歩として、用意する土は水はけの良いものを選ぶようにします。お店で売っている培養土などでも十分育ちます。熱帯地域を主とすることからも想像できるように、温かい気候を好みます。湿地の植物ではないので、多湿は避けカラリとした土を用意します。
コエビソウは日光のよく当たる場所でも、日陰の場所でもしっかり育ってくれることが利点です。日陰で育てると茎の様子はツルのような状態になり、広がっていきます。きちんと育ってくれますが、日向と比べると花つきがあまり良くありません。色も少し薄い色になります。
日向ではあまり広がらずコンパクトに育ちます。よく花をつけ、よく花を開くことが魅力ですが、夏場は葉が痛みやすいため注意が必要です。夏場の日差しの強い時間は、直射日光を避けるほうが良いでしょう。半日陰の場所がベストです。
鉢植えではなく、花壇に植える場合も半日陰の場所を選ぶようにすると、長期にわたり花の開花が楽しめます。寒さにも比較的強いコエビソウは、気温3度を目安にすると良いです。3度を下回る場合は室内に入れてあげるほうが良いでしょう。日当たりのよい暖かい場所に置いてあげてください。
暖かい地域であれば、外の日当たりのよい場所に置いておいても大丈夫です。寒さにより葉が落ちてしまうこともありますが、根っこが元気であればまた目を出してくれます。もし葉が落ちてしまったら、株の根元で切り戻しをするのも手です。切らずにそのままでも問題ありませんが、切ってしまった方がバランスよく新しい芽が出てきてくれます。
種付けや水やり、肥料について
水やりについて、春から秋にかけては土の表面が乾いてからたっぷり水を与えるようにします。与えすぎもあまりよくありません。常に土が湿っている状態は、根腐れを起こす原因となってしまいます。乾燥のしすぎも良くありません。コエビソウが必要な水分を摂取できずに、元気がなくなってしまいます。
適度に与えてあげてください。夏場の熱い時期は注意が必要です。非常に暑いときや、日照りにより土の乾燥が酷いときは1日に2回水を与えるようにしてください。水を与える時間帯は朝と夕方で、暑い昼間はコエビソウを痛めてしまうため避けるようにします。
庭の花壇に植えたものは、日照り続きで雨が降らず土が乾燥したときに与えるだけで十分です。冬場の寒い時期は、コエビソウの成長も緩やかになります。水を与える頻度を減らし、やや乾燥気味にします。土が乾いて数日たってから与えるぐらいで大丈夫です。
コエビソウに肥料を与える場合は、適度に与えます。あげなくても栽培は可能ですが、与えると花つきが良くなります。与えすぎると、今度は花つきが悪くなってしまうので注意が必要です。肥料は春から秋にかけての時期に与えます。液体肥料でも十分よく育ち、月に2回与えるようにします。
冬場はエネルギーを温存している時期です。この時期に肥料は与えません。花が終わった後にコエビソウは実をつけます。実の付け方はさく果で、実の中に複数の部屋があり、その中に種子が入っています。成熟すると身がはじけ、中から種が顔を覗かせるようになります。
増やし方や害虫について
コエビソウは実をつけ、種を残しますが、増やし方としては挿し木が一般的かつ容易です。挿し木を行う時期は4月から9月ごろに行います。枝を5から10センチほどの長さに切り、湿らせた土の上に挿します。土は赤玉土や川砂、バーミキュライトなどの清潔な土の上に挿します。
根は挿し木をして2、3週間で根が生えてきます。初めはあまり日に当てすぎない方が良いでしょう。半日陰の場所が良いです。挿し木した成長途中で、花をつけることがあります。花を切った方がコエビソウの生育には良いため、切ることをおすすめします。コエビソウは害虫の被害を受けにくく、
病気の心配もほとんどない植物でもあります。しかし生育場所、環境によっては虫が付くこともあります。ハダニ、アブラムシ、カイガラムシがコエビソウの主な害虫になります。早めに薬剤などで予防をするようにしておきましょう。ハダニは暖かく湿った場所を好みます。
カイガラムシは風通しの悪い場所を好む虫です。コエビソウは風通しの良い場所に置くようにし、多い茂った枝は剪定するようにしましょう。伸び放題の枝は湿気が中に溜まり、全体の見た目のバランスも良くありません。ハダニ対策としては、水やりのときに葉の裏にも水をかけてやると効果的です。
ハダニ、アブラムシは薬剤効果が見られるのに対し、カイガラムシは薬剤が効きにくい虫です。つかないように予め環境を整えてやることが重要です。もしカイガラムシが付いてしまった場合は、古い歯ブラシなどでこすり取ります。大抵はこのような深刻な事態にはならないため、気軽に生育を楽しめます。
コエビソウの歴史
コエビソウはメキシコを原産とする植物です。キツネノマゴ科キツネノマゴ属の植物で、常緑の多年草でもあります。低木ではありますが、木らしくない所も好まれる理由の一つです。キツネノマゴ科の植物は双子葉植物で、その多くが熱帯の地域を生息地としています。
ヨーロッパにも一部ありますが、主には中南米や東南アジアに多く自生しています。数は約230属4000種にも及びます。日本固有の植物ではキツネノマゴ、ハグロソウ、スズムシバナなどがこのキツネノマゴ科にあたります。暖かいところに多く生息するため、温室を必要とするものも中には存在しています。
園芸種としては、アンカンサス、ヤハズカズラやこのコエビソウなどが存在しています。メキシコにはコエビソウの他にも約60種が自生しています。日本に来たのは1931年頃と言われています。熱帯地域を主とするキツネノマゴ科の植物であることから、コエビソウも暑さに強く、
比較的寒さにも強い植物です。先端に稲穂のように垂れ下がった赤い苞をつけ、それがまるで小エビの尾のように見えることから日本ではコエビソウと呼ばれています。丈夫で、根さえ無事であれば元気に芽を出してくれます。コエビソウは長く楽しめる種でもあり、
うまく環境を管理することができれば一年中楽しむことができます。花言葉は「おてんば」「可憐な人」「思いがけない出会い」「友情」など活発なイメージの多い花です。ふよふよと揺れる赤い苞がよりそのイメージを連想させてくれます。
コエビソウの特徴
常緑の多年草であるところは、植物を楽しむ一つの魅力です。緑の葉をつけたまま一年を過ごせるため、特に初心者におすすめです。5月から11月ごろまで花をつけるため、非常に長い期間楽しめるのも特徴です。双子葉類のため、しっかり地面の下に根が伸びて本体を支えます。
この根が生きていれば、葉が落ちても新しい芽を出してくれます。丈夫なところも好まれています。葉はコロンと丸いたまご型をしており、向かい合って生えています。多い茂った葉の様子は見応えがあります。コエビソウの背丈は50から150センチほどにもなり、生育環境によって育ち方がかわります。
日向ではコンパクトに育ち、日陰ではツル状に茎が伸びるというおもしろい特徴を持っています。育て方を変え、比較してみるのもおもしろいかもしれません。花は赤く垂れた苞が特徴的です。苞の重なり方がまるで鱗のようなことも、小エビらしさを引き出しています。
揺れる様子が愛らしく、苞の奥には白い小さな唇型の花が隠れています。一目見ただけでは白い花の様子は見ることはできません。奥を覗くと、真珠を抱えているかのような、白い花の様子が見られます。苞と周りの緑がうまく溶けていく色合いもきれいです。
苞の色は赤の他にも黄色、白色などがあり、中には斑点のあるものもあります。バリエガタという品種が葉に斑点のできる種、苞が黄緑色から黄色になる品種はイエロー・クイーンといいます。様々な種を試してみるのも良いでしょう。
観葉植物の育て方など色々な植物の育て方に興味がある方は下記の記事も凄く参考になります♪
タイトル:ブバルディアの育て方
タイトル:ヒポエステスの育て方
-

-
カシワバアジサイの育て方
カシワバアジサイは古くからアジサイ類の仲間として広く親しまれてきました。日本でも奈良時代後期の万葉集にアジサイのことが詠...
-

-
アンズの育て方
アンズはヒマラヤ西部からフェルガナ盆地にかけてを生息地としている、バラ科サクラ属の落葉小高木です。英名ではアプリコットと...
-

-
シコンノボタンの育て方
シコンノボタンは野牡丹の一種です。野牡丹の生息地は、熱帯や亜熱帯で、比較的暖かい地域が原産です。日本にも自生しているもの...
-

-
ヤマホタルブクロの育て方
キキョウ目キキョウ科キキョウ亜科ホタルブクロ属の植物で、花の色は紫色や白い色のようです。学名はカンパニュラ・プンクタータ...
-

-
モモバギキョウの育て方
この花の特徴としては、キキョウ科、ホタルブクロ属となっています。園芸においては山野草、草花としての利用が多くなります。形...
-

-
ヒナガヤツリの育て方
ヒナガヤツリは、カヤツリグサ科カヤツリグサ属の植物です。ヒナガヤツリの原産地は北アメリカですが、主な生息地はオーストラリ...
-

-
エゾギク(アスター)の育て方
中国や朝鮮が原産の”アスター”。和名で「エゾギク(蝦夷菊)」と呼ばれている花になります。半耐寒性一年草で、草の高さは3c...
-

-
ローズマリーの育て方
その歴史は古く、古代エジプト時代の墓からローズマリーの枝が発見されているように、人間との関わりは非常に古くからとされてい...
-

-
エリンジウムの育て方
エリンジウムはセリ科のヒゴタイサイコ属の植物です。同じヒゴタイサイコ属の植物にはE.maritimum やオオバコエンド...
-

-
ミニメロンの育て方
メロン自体の歴史は古く、古代エジプトや古代ギリシャでも栽培されていたことが知られています。メロンは暖かい地域で栽培するこ...




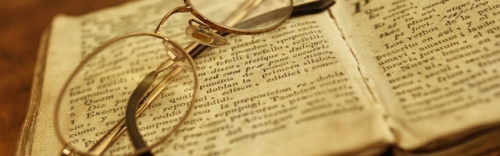





コエビソウはメキシコを原産とする植物です。キツネノマゴ科キツネノマゴ属の植物で、常緑の多年草でもあります。低木ではありますが、木らしくない所も好まれる理由の一つです。