ヨモギの育て方

育てる環境について
この植物は暑さや寒さに大変強い植物になります。その為、育て方も比較的簡単です。野山に雑草として生えている場合もあるくらい生命力が大変強い植物になります。地植えやプランターなどどんなところでも栽培する事が可能です。生育温度は15℃~25℃くらいと幅広い温度に適しているので、どこでも生育することが出来ます。
太陽の下でどんどん成長するので、出来るだけ日当たりの良い場所で育てましょう。また出来れば風通しの良い場所で育てていきましょう。土質も選ばず、どんな場所でも成長することが出来ます。誰でも簡単に栽培することが出来る植物です。あまり寒すぎる場所では適しませんが、日本全国色々な場所で育てる事が出来る生命力溢れる植物です。
良く道端などでも生えているのを見る事が出来るように、ちょっとした場所があれば勝手に成長していく事が出来るくらい強い植物です。栽培方法も本当に簡単なので、初心者でもどんどん増やす事が出来ます。ほとんど手をかけなくても成長することが出来る植物です。逆に増えすぎてしまう場合があるので、
他の植物が周りに生えている場合は注意が必要です。若葉は、早春に草丈が5~6cmになった頃に収穫して利用することが出来ます。もぐさとして利用する場合は、夏頃までそのまま成長させ1mぐらいになったら茎を切り取り乾燥させて使用します。場所を選ばず成長することが出来る植物なので、手間もいりませんしそのまま置いておいても比較的育ちます。
種付けや水やり、肥料について
ヨモギを育てる場合、山野や道端に生えている苗を取ってきてプランターなどに、移植する方法がもっとも簡単です。植えつけに適している時期は4月または9月頃です。何株も植える際は株間を20cmほどとって植えていきましょう。地植えの場合は、植えつけた後にしっかり根が付くまでの2週間程度しっかり水やりをしていきましょう。
その後はそのまま放置しても雨水などで十分育つでしょう。ただあまりにも土が乾燥している場合は水をあげるようにしましょう。プランターで栽培している場合は、土の表面が乾いてきたらたっぷりと水を与えるようにしましょう。どんな土質でも育てる事が出来ますが心配であれば植えつけの2週間ぐらい前に、1㎡につき堆肥と腐葉土を各4~5L、
苦土石灰を100gほど混ぜて土づくりをしておきましょう。プランターで栽培する場合は、赤玉土7、腐葉土3の割合で混ぜた用土に、苦土石灰を用土10Lにつき10gほど混ぜたものが良いでしょう。しかし、どんなところでも生える事が出来る植物なので、基本的には特に手入れをしなくてもしっかり成長してくれます。
それほど気を使う必要がないので、容易に栽培することが出来るでしょう。土の表面が乾燥した時だけ水をあげて、後は様子をみておきましょう。あまり水やりや肥料について深く考えすぎることはありません。面倒くさがり屋の人でも簡単に育てる事が出来るので、ヨモギを育ててみるのも良いでしょう。
増やし方や害虫について
実生または株分けで簡単に殖やすことができます。夏から秋に結実したら茎ごと刈り取ってしまい、袋をかぶせて日陰につるしておけば、自然に種子が落ちてきます。種を蒔く場合は3月または9月に行うと良いでしょう。庭などにばらまきして軽く覆土し、芽が出てきたらいくつか間引きながら育ていくと良いでしょう。
また、株分けの方法も良いでしょう。大きくなった株を2~3等分して植えるだけで大丈夫です。増やし方も簡単で、庭などで栽培する場合何もしなくてもどんどん増えていきます。害虫は春先や秋口にアブラムシが大量発生することがあります。草もちなどの材料にする場合、口に入るものですから収穫期は薬剤の使用は出来るだけ避けた方が良いでしょう。
出来るだけ数が少ないうちに処理して置くと良いでしょう。そのまま放置してしまうとアブラムシがどんどん増えてしまい茎にびっしりと大量に付いてしまうので、そうなる前に早めに見つけるようにしましょう。ヨモギは大変育てやすく、手間も少なくて済むので簡単です。環境が適している場所であれば知らないうちにどんどん増えていってしまうので、
増えすぎに注意する必要があります。育てたい場合でも、ちょっと野山にいけば生えているのでその苗を利用すれば育てる事が出来ます。また、花粉が飛ぶので花粉症の人は気をつけた方が良いでしょう。鉢植えなどで育てる場合は、根がどんどん成長して窮屈になってしまう場合があるのでその際は植え替えしながら育てていきましょう。
ヨモギの歴史
ヨモギは北アジア原産の植物です。日本では本州~九州まで幅広く生息地を広げている植物です。キク科の野草で日本へは江戸時代に入ってきました。ヨモギは草もちやお灸の材料として昔から人々に利用されてきました。また、古くから食用だけでなく、それ以上に生薬としても利用されています。
漢方薬としては”艾葉(ガイヨウ)”と呼ばれており、万能薬として重宝されてきました。他にヨモギは邪気を払い、長寿を約束すると昔から人々に信じられてきました。その為、地方によっては、桃の節句にヨモギ入りの草もちをみんなで食べたり、端午の節句の前日に、菖蒲と一緒に束ね、軒にさす習俗も見られる地域もあります。
その為、日本人にとっては昔から大変馴染みのある植物になります。和名である”ヨモギ”は、よく燃える草「善燃義」から来ています。同じ属の植物は約250種が分布しており、日本ではおよそ30種が海岸から高山まで色々な場所に生えています。独特の香りがあるので、ハーブとしても利用される便利な植物です。
家庭菜園などでも簡単に育てる事が出来る植物なので、誰でも一度は目にした事があるのではないでしょうか。野山などにもよく生えている植物になります。食用として利用する場合は3月から5月頃の春先で、若い芽を利用します。草もちにすると大変香りが豊かで独特の風味で大変おいしいお餅になります。昔から色々な方法で利用し、人々の身近にある植物だったんですね。
ヨモギの特徴
ヨモギは春に芽を出して50cm~1m程の高さまで成長します。夏から秋にかけて黄色い花粉を付けた小さな花を咲かせます。ヨモギと一般に呼ばれているのは、ヨモギ属の”アルテミシア・プリンケプス”です。この花は花粉が風で運ばれて受粉する為、花粉がこぼれやすいように下向きに咲いています。地下茎を伸ばして旺盛に繁殖します。
繁殖力の強い植物になります。葉は楕円形で羽状に深く裂けており、互い違いに生えています。葉の裏面は白っぽい毛で覆われており、葉を手で揉むとヨモギ独特の良い香りがします。開花時期は8月から10月にかけて、小さな紫色の花をつけますが、あまり目立たないので気付かない人も多くいます。
ヨモギに花が咲くのと初めて知った人もいるかもしれませんが、そのくらいあまり印象に残らない小さな花を咲かせます。地下茎が横に伸びて群生するのが特徴です。茎はよく枝分かれをし、毛が生えています。またヨモギ自体様々な効能を持っています。香りのもとであるシネオールにはリラックス効果があるので香りを嗅ぐと心を落ち着ける事が出来ます。
また、体を温める効果や便秘解消効果、皮膚を健康に保つ効果などもあるので、昔から人々に便利に利用されてきた植物になります。道端などで良く見かける植物なので、そんなに良い効果があるものだとは知らない人も多いでしょう。しかし、実際はたくさんの効能があり、人々の間で有効活用されてきた植物なんです。
-

-
ヒイラギナンテンの育て方
ヒイラギナンテンの原産地は中国や台湾で、東アジアや東南アジアを主な生息地としています。北アメリカや中央アメリカに自生する...
-

-
アグロステンマの育て方
アグロステンマは原産地が地中海沿岸で、日本に渡来したのは1877年のことでした。渡来した当初は切花として利用されていたの...
-

-
クリサンセマム・パルドーサムの育て方
クリサンセマム・パルドーサム(ノースポール)は、キク科フランスギク属に分類される半耐寒性多年草です。ただし、高温多湿に極...
-

-
ラナンキュラスの育て方
ラナンキュラスの原産地は地中海東部沿岸やアフリカ北東部、アジア南西部など北半球に広くあり、十字軍がヨーロッパに持ち帰り改...
-

-
チグリジア(ティグリディア)の育て方
チグリジアは別名ティグリディアとも呼ばれるユリに似た植物ですが実際にはアヤメ科の仲間になっています。チグジリアの仲間アヤ...
-

-
クンシランの育て方
クンシランはヒガンバナ科クンシラン属で、属名はAmaryllidaceae Clivia miniata Regelとい...
-

-
ムベの育て方
植物の種類としては、キンポウゲ目、アケビ科となります。園芸をする上でどのように分類されているかですが、まずは庭木であった...
-

-
カボチャの育て方
カボチャは、日本国内の分類では「日本カボチャ」と「西洋カボチャ」と「ペポカボチャ」との3つがある野菜です。特に日本・西洋...
-

-
ブルーハイビスカスの育て方
ブルーハイビスカスは別名をアリオギネ・ヒューゲリーやライラック・ハイビスカスといいます。属名はギリシャ語の結合したや分割...
-

-
アメリカアゼナの育て方
アゼナ科アゼナ属で、従来種のアゼナよりも大きく、大型だが花や葉の姿形や生育地はほとんどが同じです。特徴はたくさんあります...




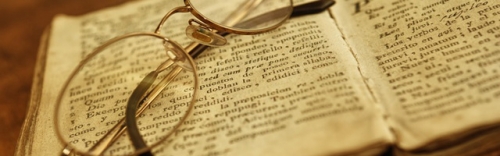




ヨモギは春に芽を出して50cm~1m程の高さまで成長します。夏から秋にかけて黄色い花粉を付けた小さな花を咲かせます。ヨモギと一般に呼ばれているのは、ヨモギ属の”アルテミシア・プリンケプス”です。この花は花粉が風で運ばれて受粉する為、花粉がこぼれやすいように下向きに咲いています。地下茎を伸ばして旺盛に繁殖します。