オレンジ類の育て方

オレンジ類の育てる環境について
オレンジ類の育て方のコツ としては、とにかくお日様の暖かな明 るい日差しがポイントになります。育てる環境において、日光が大好きなタイプですから、お日様の光は欠かせません。家庭の庭に植えて魅了と考えたときにも、植え付けの場所は、太陽の陽の光がよく当たる場所が良いです。
プランターや鉢で、ミニサイズからスタートというケースでも、プランターを置く場所は日光のよく当たるゾーンを選んで、毎日たっぷり、お日様の光を浴びせてあげることです。年間の平均気温も、割と暖かめな土地での栽培が可能な植物です。
日本国内においても、暖かい日差しのある場所では栽培が可能であり、一定の暖かな気温条件などがソロていれば、育てることができるものです。その土地の気温が低い場合には、熟期が遅れてしまうケースもあります。熱帯原産のものであり 、生育環境としては、
暖かい気候であり、多湿である気候が最適とされています。もちろん、それなりに雨量も必要となってきます。みずみずしく美味しい実をつけるためにも、ある程度の水分をキープできる土壌は必要です。保水力も持ちながら、風通しの良い通気性の良さも、環境には求められます。
この木の葉っぱは、できるだけ太陽の光に当ててあげることが大切です。葉っぱにたくさんの陽の光があたることで、 工業製が活発になります。そうすると、果実に甘味である糖も、たっぷりと蓄積されることになります。朝日を受けやすい方角も良いとされています。
種付けや水やり、肥料について
オレンジ類の植えつけや植え替えをするのに良い時期は、新芽も芽吹いてくる3月から、フレッ シュな風も心地よくなる4月中旬にかけ てになります。目的を改めて確認しておくと、根詰まりを防ぐことが特に挙げられます。通気性をよくして、快適にすることも、大きな目標の一つと言えます。
生育の状態を見ながら、プランターのサイズも見ながらになります。ペーストしては、2年間から3年間に1回のペースで行うとよいでしょう。太陽の光をたっぷりと浴びて成長しますから、水分補給も大切です。水やりは、土の表面が白く乾いていないかどうかをチェックしましょう。
白っぽく乾いてきたと気がついたら、たっぷりの水を与えてあげます。プランターの場合ならば、そこの穴から水が流れてくるレベルで、たくさんの水をあげることです。家庭の庭に植えてある場合、土書室ですとか、品種によっても多少の差はあるものの、
土が乾いた状態 を見つけたら、水やりをして潤いを与えてあげるこtです。特に真夏ともなると、日照りがヒートアップしてきますから、人間も帽子をかぶるなり対策をして、木に水をたっぷりとあげることです。真夏は特に、水やりはこまめに、
たっぷりとすることが大事になってきます。適度な肥料を与えることも大切なことです。庭に植えている場合なら、まずは3月くらいに、速効性化成肥料や機質肥料元肥として、土に施すようにします。速効性化成肥料の追肥は、そのあとの時期の、6月と11月に行うと良いです。
増やし方や害虫について
オレンジ類の害虫ですが、ミカンハモグリガやアゲハの幼虫、カミキリムシなどやアブラムシが、メインの害虫となって活躍します。ミカンハモグリガにおいては、 夏芽や秋芽に害をもたらします。その ため幼木をできる限り早めに成長させるためにも、防除を行うことは必須となります。
害虫の他にも、病気にも気をつけたいところです。潰瘍病などの病気には、注意が必要と言えます。果実であったり、枝や葉っぱに発生するものです。ここには害虫である、ミカンハモグリガが絡んでいます。この害虫の食害痕であったり、風が原因となってこすれ、
傷口となりかんせんするものです。早めに気がついて対処することですが、何もケアしないと葉っぱが落ちてきます。オレンジ類の増やし方ですが、増やしたい時にはつぎ木です。種を蒔き成長したカラタチが台木になるのが一般的です。切りつぎや芽つぎをして、苗木をつくるようにします。
植えてあるものにつぎ木をしようと考えるときには、時期にも注意を することです。適切な時期としては、4月の下旬から5月の上旬にかけてであり、腹つぎやはぎつぎを行います。時期的に、3月から4月にかけては、剪定も必要になってきます。
4月は中旬くらいまでに、剪定を済ませておくと良いでしょう。この時期時期も既に元気ですが、その先の時期も気候はいいですし、お日様の光はサンサンと降り注ぎますから、成長もグングンと進みます。そのため、この時点で一旦、剪定をしておくことは大切なポイントになります。
オレンジ類の歴史
インドのアッサム地方が生息地のオレンジ類は、中国からポルトガルに渡ったのは15世紀から16世紀はじめのことでした。地中海沿岸諸国へわたり、広がっていきました。あめりかにわたったのは、さらにあとで、19世紀に入ってからのことです。
明治の時代になって、やっと日本国内にも導入されています。アメリカのオレンジを手がける有名なブランドも、1980年代から栽培をスタートさせています。バレンシアオレンジという名称を聞いたことがあると思いますが、原産はスペインのバレンシアという認識が強くあります。
しかし実際にはスペインではなく、別の場所ではないか、という説tが強くあります。誕生したのはポルトガルであり、大西洋のアゾレス島を通過して米国へと渡っ たとも言われています。そして、スペインのバレンシア地方には、このオレンジと非常に似ている果実の栽培があったために、
そういったネーミングで呼ばれるようになった、といった話もあります。ネーブルオレンジは、冬シーズンから春先にかけて流通も活発になる、スイートなオレンジです。これは19世紀の頃、ブラジル後において、オレンジの芽条変異により誕生したと言われています。
そのあとにはアメリカへ渡ることとなり、フルーツとして多くの人たちに愛される人気の柑橘類となりました。現代の日本においては、カリフォルニア産の輸入が多く見られます。輸入だけではなく、日本国内でも栽培されていて、和歌山県や愛媛県、静岡県や広島県が、国内においてのメイン産地となります。
オレンジ類の特徴
オレンジ類は種類が豊富であること、みずみずしいフレッシュな果実が魅力的なのも特徴です。酸味が強めの果実もありあすが、品種改良の会もあって今では、甘みのある柑橘系果実も多くなっています。柑橘系は、薬剤をあまり使わないで育てることができるのも、特徴的と言えるでしょう。
そのため、家庭で栽培をするのにも向いている果樹でもあります。ミカン属の果樹であるオレンジ類は、耐寒性に関しては、若干弱いところがあります。しかし最近の機構としても、温暖化が関係しているために、栽培できる地域が昔よりも、はるかに広がりを見せています。
スイートオレンジでは、バレンシアやネーブルが代表選手と言えるでしょう。生でデザート感覚で食べるのには、スイートオ レンジは爽やかな甘 さもあってピッタリです。サワーオレンジは酸味が強めの特徴がありますが、こちらはマーマーレードや酢に適しており、利用されてきたものです。
日本のダイダイは、日本人には馴染みあるものです。インド原産で中国においてできた品種群とされており、日本へはかなり古い時代に伝えられています。お正月の飾りで目にする、鮮やかなオレンジカラーのダイダイは、1樹にあたり、
新旧代々の実がなることに由来しています。オレンジるおいは、基本的に形状は高い木になります。1.5mくらいから3mと、幅はありますが背の高い気です。育てるのであれば、日光を好むという体質を理解して、よく陽のあたる場所で育ててあげることです。
果樹の育て方など色々な植物の育て方に興味がある方は下記の記事も凄く参考になります♪
タイトル:クランベリーの育て方
タイトル:グアバの育て方
タイトル:キンカン類の育て方
-

-
家庭菜園で野菜を育てると収穫の喜びを味わう事ができます
毎日何気ない一日を過ごしていると、何かを始めてみたくなる事は誰でも経験する事です。そんな時にお勧めな事として、自宅で家庭...
-

-
自宅で植物を育てよう
部屋に植物があると生きたインテリアにもなり、その緑や花の華やかな色は日頃の疲れやストレスへの癒やしにもなります。ただ、生...
-

-
ワックスフラワーの育て方
花についてはフトモモ科、チャメラウキウム属になります。園芸上の分類としては庭木であったり花木としてになります。草丈に関し...
-

-
オオアラセイトウの育て方
オオアラセイトウは別名ショカツサイとも言われる中国原産のアブラナ科の植物です。紫色が美しい小花はその昔三国志で有名な軍師...
-

-
鉢植え乾燥地帯原産地「パキラ」の栽培方法について
鉢植え「パキラ」は東急ハンズ等で購入できる乾燥地地帯である中東が原産地の鑑賞植物です。高さが5cm以下の小型の植物で、手...
-

-
イングリッシュ ラベンダーの育て方
イングリッシュ ラベンダーは、シソ科のラベンダー属、半耐寒性の小低木の植物です。ハーブの女王としてゆるぎない地位を確立し...
-

-
レウイシア(岩花火)の育て方
スベリヒユ科であるレウイシアと呼ばれる植物は、原産が北アメリカであり学名はLewisiacotyledonで、この学名は...
-

-
サントリナの育て方
種類はキク科になります。除虫菊と同じ仲間なので、そのことからも虫をあまり寄せ付けないのかもしれません。草丈は大きいものだ...
-

-
エレムルスの育て方
花の特徴では、ユリ科に該当します。花が咲く時期としては4月から7月になります。咲き方としては1年を通して咲く多年草になり...
-

-
サボテンの育て方のコツとは
生活の中に緑があるのは目に優しいですし、空気を綺麗にしてくれるので健康にも良いものなのです。空気清浄機のように電気代がか...




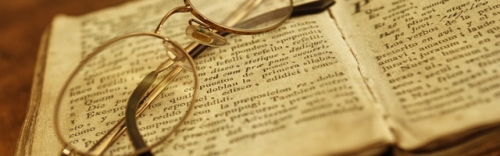





インドのアッサム地方が生息地のオレンジ類は、中国からポルトガルに渡ったのは15世紀から16世紀はじめのことでした。地中海沿岸諸国へわたり、広がっていきました。あめりかにわたったのは、さらにあとで、19世紀に入ってからのことです。