ストロベリーキャンドルの育て方

ストロベリーキャンドルの種付け
種付けする場合は、ストロベリーキャンドルは暑さに弱いので、蒔く時期は秋のみになります。土は土質を選ばない植物なので市販されている花と野菜の土で十分対応できます。自分で土を用意する場合は赤玉土と、腐葉土、バーライトを混ぜたものを準備します。花壇で栽培する場合は完熟腐葉土、完熟牛ふん堆肥を混ぜ合わせ、柔らかい土になるようにしましょう。
他にも、種を濡らしたキッチンペーパーで包み、フードバックに入れ、こたつで発芽させる方法もあります。この場合、発芽したら早めに鉢などの移し替えるようにしましょう。苗から育てる場合は、春から育てるのが一番適しています。暑さに弱いので、春の暖かくなる少し前に植えると良いでしょう。優しく根をほぐしてから植えるようにします。
ストロベリーキャンドルは横に増える性質があるので、苗と苗の間は20~30センチほど間隔を空けるようにします。マメ科の植物は、移植を嫌うとされているので、種付けした後は、移動させないようにします。寒い時期は土を這って成長しますが、暖かくなってくると、上に向かって成長をはじめます。
ストロベリーキャンドルの育て方
ストロベリーキャンドルを上手に成長させる育て方は、植え付けが終わった直後や苗の段階では土が乾いた時にたっぷりと水をあたえます。特に鉢植えの場合は乾燥しやすいので注意して観察します。一方でストロベリーキャンドルは加湿には弱いので、しっかり土が乾く前に水をあげないようにします。一度根付いてしまえば、乾燥にも強くなります。
この事からも育て方が簡単なのがわかりますが、更にマメ科植物の特徴でもある根粒菌が根に住み着いていて、肥料の要素の一部でもある窒素分を合成することができます。この特徴からあまり肥料をあげすぎると枯れてしまう原因にもなります。肥料を与えていない状態で、下のほうにある葉が黄色く変色してきた場合は薄めた液体肥料を与えます。
その他は特に肥料は必要ありません。病害虫が付く事はほとんどありませんし、付いた場合もアブラムシ程度なので植物用の殺虫剤を使用すれば問題ありません。ストロベリーキャンドルを置いておく場所は、日当たりが良い場所を好む植物なので、太陽の光が当たる場所で育てます。比較的明るい日陰でも栽培できますが極端に花のつきが悪くなります。
寒さには強いとされていますが、-2℃以下になる様な地域で栽培する場合は室内の日がよく当たる場所に移動させて管理し、育てます。霜よけやマルチングを行う事で、春の芽生えを良好にする事ができます。高温多湿の日本では、夏には枯れてしまうとされていますが、元々は多年草なので夏の間涼しいところで風通しもよくし、蒸れないように管理する事で、夏を越すことができれば次の年も花をさかせてくれます。
種を取らない場合は、花が咲き終わったら茎を切り落とす様にします。こうする事で、茎の消耗を押さえる事ができるので長く花を楽しむ事ができます。夏に枯れてしまう植物ですが次の年も楽しむもう一つの方法として花が咲き終わった後にできるだけ種を採取し、保存した後、秋に蒔いて育て直す方法もあります。種ができた状態のまま、花穂が雨に濡れてしまうとそのまま発芽してしまう事もあるのでなるべく早く切り落とすか種を取るようにします。
増やし方としては、秋頃に箱や浅鉢に種を蒔いて間引きをしながら苗を育てていきます。ある程度の大きさに成長したら、庭や鉢に植えつけるようにします。他にも、小鉢に仮り植えをしてから暖かくなる春頃に植え付けを行ってもよいでしょう。しかしある程度冬の寒さにも当てないと花がさかないで屋外で育てるようにします。苗が小さいうちは簡単な霜よけを取り付けます。
栽培する上で大切なポイント
育てる環境は日当たりの良い場所を好むとされていますが、夏の直射日光は強すぎて枯れてしまう原因にもなるので、注意しましょう。花壇に植える場合は霜に当たりやすいので、対策をきちんと行うようにします。寒さには強いので冷たい空気に触れさせる事で春以降の開花がよくなります。
咲き終わった後花穂が黒くなる事で汚く見えてしまうので、こまめに摘み取るようにすると見た目も良くなり、更に次々と花をさかせます。増やしたい場合には収穫した種を種付けするようにします。収穫した後の種は陰干しをしてしっかりと乾燥させましょう。その後容器に入れて、冷蔵庫の野菜室で保存するようにします。
土は水はけのよいものを準備します。春に種を蒔いた場合、葉はよく育ちますが、花を咲かせる事なく夏には枯れてしまう事が多いので寒冷地意外は秋に種を蒔きます。背が伸びる植物なのであまり大きく育てたくない場合には、根が育つ環境を制限するために、地植えではなく、鉢などに植えて育てると良いでしょう。寒冷地とそうではない地域では、育て方は同じですが種を蒔く時期に違いが出てきます。
ストロベリーキャンドルの歴史
ストロベリーキャンドルは、ヨーロッパ・西アジアが原産の植物で、自生していました。一年草とされ、蜜を取るためや肥料として、ヨーロッパでは扱われてきました。その為元々は牧草として導入された植物で、観賞用に美しものが選ばれました。
春になると茎を伸ばし、アカツメクサや、シロツメクサなどと同じ仲間で戦端に小さな花が集まり、イチゴのように真っ赤な細長い花を咲かせます。この姿からストロベリーキャンドルと名付けられましたが、現在では白花の品種も見られます。
日本には明治時代に原産国と同様に、牧草として移入し、現在では野生化しています。日本での生息地は、庭や草地など全国に広がっています。また、別名では赤い花が咲くクローバーと言う意味を持つ、ベニバナツメクサや、クリムソンクローバーなどとも呼ばれています。花言葉は「素朴なかわいさ」です。葉が四つある事から十字架に似ているとされ、幸運のシンボルとしても知られています。
ストロベリーキャンドルの特徴
ストロベリーキャンドルは丈夫ですが、暑さには弱いとされています。簡単に育てることができるので、初心者向けとされています。冬に寒さにも強く、秋に植えて翌年の春に花を咲かせるか、または春に苗を植えてることで、春から初夏にかけて花を楽しむことができます。多湿にも弱い植物なので、夏になると枯れてしまいます。
赤い花はとても目立ち、人目を引くので、寄せ植えや花壇に植えて楽しむ方が多く、最初の花の開花期間が終わった後に短く刈り込んでおく事で、今まで隠れていた2番花を楽しむ事もできます。その姿はキャッツテールという植物にも似ていますが、開花時期が夏~秋にかけてなど違いがあり、葉の形も異なっています。海外では多年草と言われていますが、日本では一年草扱いになっています。
また、切花としても流通しており、水揚げを行う事で、長く楽しむ事ができます。他にも、ハーブとして利用されている品種もあります。ストロベリーキャンドルはクローバーと同じ様に、空気中の窒素を土に取り込むことができるので、レンゲの様に肥料代わりに植える事ができます。属している科はマメ科です。
ストロベリーキャンドルを毎年育てたい場合は、種が出来たときにそれを保存し、秋に蒔くことができます。草丈は20センチ~60センチになり、種から栽培した時に開花をする期間は4月~6月、鉢で販売されているものの開花期間は2~4月頃です。
-

-
アボカドの種を観葉植物として育てる方法。
節約好きな主婦の間で、食べ終わったアボカドの種を観葉植物として育てるというチャレンジが密かなブームとなっているのをご存知...
-

-
ソレイロリアの育て方
特徴としては、イラクサ科の植物とされています。常緑多年性の草になります。草の高さとしてはそれ程高くなりません。5センチぐ...
-

-
なたまめの育て方
中国では古くから漢方と用いられてきました。中国の歴史的な著書には「なたまめは腎を益し、元を補う」とかかれています。人とい...
-

-
ノースポールとハナナの育て方
クリサンセマムは可愛いキク属の花です。クリオスに金という意味が、アンセマムには花という意味があります。クリサンセマムと呼...
-

-
ノウゼンカズラの育て方
ノウゼンカズラの歴史は古く、中国の中・南部が原産の生息地です。日本に入ってきたのは平安時代で、この頃には薬用植物として使...
-

-
サルスベリの育て方
サルスベリは、木登り上手のサルですら、すべって登ることができないほど、樹皮がツルツルとなめらかなことからつけられた名前ら...
-

-
レモンバームの育て方
レモンバームとはメリッサとも呼ばれるハーブの一種です。南ヨーロッパが原産で、地中海近くが生息地とされています。レモンバー...
-

-
スズメノエンドウの育て方
生息地は日本となっていますが、マメ科のソラマメ属に分類しています。後援などに雑草のようにその姿が見られ、古くから周りの草...
-

-
オクラの育て方について
夏になれば栄養満点のオクラの栽培方法のコツです。オクラは北海道など一部の地域を除きかなり育てやすい野菜の一つです。スーパ...
-

-
リパリスの育て方
特徴としては、被子植物になります。ラン目、ラン科、クモキリソウ属に該当します。ランの種類の一つとされ、多年草としても人気...




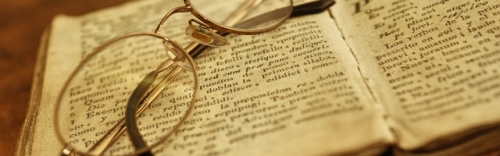





ストロベリーキャンドルは、ヨーロッパ・西アジアが原産の植物で、自生していました。一年草とされ、蜜を取るためや肥料として、ヨーロッパでは扱われてきました。その為元々は牧草として導入された植物で、観賞用に美しものが選ばれました。