イトラッキョウの育て方

育てる環境について
イトラッキョウは暑さ寒さによく耐える、育て方の簡単な植物です。自生している物同様に、陽当たりと風通しの良い場所で栽培すると上手く育ちます。土は根腐れが起きにくい水はけの良い物を選び、過湿を抑止するように十分気を配ると病気になりにくくなります。
夏期は強い日差しを避ける為に遮光ネット等を使って乾燥を防ぐ必要がありますが、あまりやり過ぎると細く弱弱しい形で育ち、花の数も少なくなるものです。遮光の程度は直射日光の半分か、やや弱い程度にすると適切な光量になります。また、冬期は寒気や寒風を避けやすい場所を選んで栽培するのが大切です。
長期の栽培をする場合は、特に鉢植えで育てるなら2年に1度は植え替えをします。イトラッキョウは根が張り易い植物ですから、鉢植えで育てると、やがて根が鉢一杯に広がってしまうからです。根が張り過ぎると根の生長が阻害されるだけでなく、
水や肥料をあげても鉢の下部まで水分や養分が浸透しにくくなります。より大きな鉢に植え替えをして根を成長させやすい環境を整えてあげれば、根の成長が促進されます。また、水分や栄養も吸収しやすくなり、葉や茎がよく育つものです。植え替えをせずに放っておくと、
葉が枯れたり色づきが悪くなったりするので注意します。イトラッキョウは多年草ですから、一度植えれば長く可憐な花として楽しむ頃ができるものです。暑さや寒さにも強い丈夫な植物ですから、育てる環境さえしっかり整えれば、手もかからず花を楽しめるでしょう。
種付けや水やり、肥料について
イトラッキョウの種付けは、早春の時期に行うと上手く育ちます。種付けのコツは、種を発芽しやすい状態で播種する事です。既にイトラッキョウを育てていて、初めて種を採取するという場合は、さやが黒くなったら採種して、すぐに播種すると発芽しやすくなるものです。
株分けをする場合は、花が枯れた後か早春かに様子を見て行うと上手くいきます。水やりは時期によってあげ方が違うので、注意が必要です。まず、播種や株分けの直後から晩秋の開花までは、土が乾いたのを見計らって水を与えます。水分を十分に与えると蕾も枯れず、育ちが良いものです。
次に、花の見頃の11月は気温が下がり、イトラッキョウが休眠に移行する時期に入っていきます。移行時期からは様子を見ながら徐々に水やりの頻度を減らしていくのが適切な水やりの方法です。それまで通りのペースで水やりをすると、過湿になって根腐れ等の病気が発生する原因になります。
病気予防の為にも、水やりのペース配分は計画的に行うのが大切です。最後に、休眠の時期になったら、土が乾いても我慢して、少し待ってから水をあげるように調整します。土が乾いているのを見ても、慌てて水をあげる事が無いように注意するべきです。
施肥のタイミングは初夏と仲秋の時期を選んで少量だけ行うと良いでしょう。肥料が無くても花が咲く植物ですが、控え目に施肥する事で生育が良く、花も多く成るものです。あまり多く施肥をせず控え目に行えば害虫の発生も抑止できますので、肥料の調整は慎重に行います。
増やし方や害虫について
イトラッキョウは採種と株分けのいずれでも増やす事ができます。採種は、さやが黒く変色した時が良い採種のタイミングです。さやが開くまで待って自然に種が落ちるまで待つこともできますが、種が熟したらすぐに播く方が発芽が良好です。株分けは花が咲き終わった後か、早春の時期を選んで行うと上手くいきます。
増やすのを急がないのなら、植え替えの時に株分けも一緒に行うと、手間がかからないものです。イトラッキョウの株分けは、事前に特別な道具を用意する必要もなく、手作業で簡単に作業ができます。植え替えの際は、球根を浅目に植えた方が上手く栽培できるものです。
多年草であり、種や株の母体は次の年も育ち続ける為、簡単に繁殖させやすいと言えます。ただし、全ての花を綺麗に咲かせるには、害虫の被害を避ける対策が必要です。イトラッキョウにつく害虫は、ネギコガとネギアブラムシの2つに気を付けます。
ネギコガは5月から10月頃、特に梅雨明けの暑くなってきた時期に多く発生するガの一種です。イトラッキョウの場合は餌となる葉が少ない為、数は多く発生しませんが、食害により葉が枯死したり白斑が生じたりして見栄えが悪くなります。ネギアブラムシはネギにのみ発生する黒いアブラムシです。
成長が早く繁殖力が高い為、一度発生すると急速に増える恐れがあります。発生すると葉が変色したり育ちにくくなったりしますが、特に被害が大きいと枯死の危険もあるので注意が必要です。いずれも薬剤を使った防除の他、防虫ネットや寒冷紗を利用した成虫の飛来防止により対策をすれば、被害を防ぎやすくなります。
イトラッキョウの歴史
イトラッキョウは日本原産の植物で、生息地が長崎県の平戸島に限られている貴重な植物です。準絶滅危惧種に指定されている貴重な固有種であり、なぜ平戸島にのみ自生するのかは今だ謎が残ります。平戸島以外の場所では自生していない為に、かつては人にほとんど知られていない植物でした。
しかし、その愛らしい見た目から、植物の研究者や野草の愛好家には古くから好まれてきた植物です。また、野生に自生しているものを民家の庭に移植した例もあり、やはり古くから地元の人々の目を楽しませてきた植物でもあります。
現在は群生地へのトレッキング・ツアーも催されているように、イトラッキョウは平戸島で観光資源の1つです。イトラッキョウの知名度が向上したきっかけは、植物写真家の富成忠夫氏から著書の中で「夢みるような雰囲気の花」と紹介された事でした。
イトラッキョウの存在が一般に広く知られるにつれて、植物研究家や野草愛好家、地元の方々以外にも、イトラッキョウの良さをに気が付く方が増えます。しかし、知名度が高まるにつれてイトラッキョウを採取する人が増えていき、群生地である礫岩での乱獲の被害が目立つようになりました。
一時その数が大きく減った事もありましたが、現在は礫岩周辺が国指定の天然記念物と特別保護区とに指定されていて、トラッキョウを含む全ての植物が採取禁止となった事から、乱獲が防がれるようになりました。また、人々の保護活動も実を結んだ事から、生息数を取り戻しています。
イトラッキョウの特徴
イトラッキョウは淡いピンク色の小さな花と、か細い葉という繊細な見た目の植物です。平戸島南部の佐志岳や、同じく西岸にある「礫岩(つぶていわ)」と呼ばれる断崖が群生地となっています。イトラッキョウは咲き方によって見た目の印象が大きく違う植物です。
沢山の花が咲いてブーケのようになっているものや、それぞれの花が均等に分かれている均整の取れたものがある他にも、輪の様になったユニークなものが見られます。花の色は個体によってある程度の違いがありますが、中でも白い花の色をした物は、
近年になって「オトメラッキョウ」と呼称されるようになっています。イトラッキョウの学名はAlllium Virgunculae(アリウム・ヴィルグンクラエ)で、種小名のヴィルグンクラエはラテン語で少女を意味する言葉です。見た目や学名のイメージからか弱い印象を受けがちですが、意外と生命力や繁殖力が強い植物となっています。
暑さや寒さに強く、比較的簡単に栽培できる植物できますが、全ての花を綺麗に咲かせるには害虫の食害を予防する工夫が必要です。しかし、対策は難しくありませんので、初心者が植物栽培の基本を学んでいくにも適していると言えます。
花の色は個体によって違いがあり、栽培の際は1株毎に微妙な色の違いを楽しめます。多年草として長期間栽培できる植物であり、増やすのも簡単ですから、1株手に入れれば花畑を作ったり、鉢植えを並べたりするのもやり易いでしょう。
花の育て方など色々な植物の育て方に興味がある方は下記の記事も凄く参考になります♪
タイトル:ウツボグサの育て方
-

-
コメツガ(米栂)の育て方
コメツガは、昔から庭の木としても利用されてきましたが、マツ科のツガ属ということで、マツの系統の植物ということになります。...
-

-
ディネマ・ポリブルボンの育て方
ディネマ・ポリブルボンは、中南アメリカ原産の小型のランです。主な生息地は、メキシコやグアテマラ、キューバやジャマイカで、...
-

-
レダマ(スパニッシュブルーム)の育て方
レダマ(スパニッシュブルーム)は、マメ科の低木になります。主に、南ヨーロッパとカナリア諸島が原産地になります。世界各地の...
-

-
コレオプシスの育て方
コレオプシスはアメリカ大陸、熱帯アフリカにおよそ120種類が分布するキク科の植物です。園芸用としては北アメリカ原産種が主...
-

-
ユズ(実)の育て方
ユズの実の特徴として、成長して実をつけるまでの時間の長さが挙げられます。桃栗八年とはよく聞くことですが、ゆずは16年くら...
-

-
クテナンテの育て方
クテナンテは熱帯アメリカ原産の植物で、葉の色や模様などが特徴的な種類が多いことから観葉植物として栽培されています。熱帯ア...
-

-
アスパラガスとスイゼンジナの栽培方法
まずはアスパラガスの育て方を説明します。保健野菜で有名なアスパラガスには、缶詰用のホワイトと生食用のグリーンとの二種類が...
-

-
メキャベツの育て方
キャベツを小さくしたような形の”メキャベツ”。キャベツと同じアブナ科になります。キャベツの芽と勘違いする人もいますが、メ...
-

-
ラナンキュラスの育て方
ラナンキュラスの原産地は地中海東部沿岸やアフリカ北東部、アジア南西部など北半球に広くあり、十字軍がヨーロッパに持ち帰り改...
-

-
ヤマブドウの育て方
ヤマブドウは低木落葉樹です。日本では、古くからエビカズラと呼ばれてきました。古くから存在している日本原産のブドウです。日...




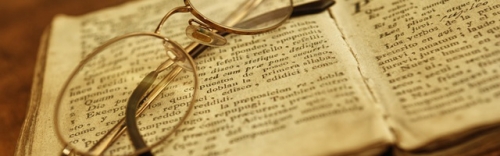





イトラッキョウは日本原産の植物で、生息地が長崎県の平戸島に限られている貴重な植物です。準絶滅危惧種に指定されている貴重な固有種であり、なぜ平戸島にのみ自生するのかは今だ謎が残ります。