カボチャの育て方

カボチャの育てる環境について
カボチャを育てる際は、まず始める時期の選択が大事です。カボチャは丈夫な野菜ですが、霜の被害で簡単に枯れてしまいます。特に、春になって「暖かくなった」と油断した時に発生しやすい遅霜に注意が必要です。遅霜の被害を避けるには、気象庁のホームページ等で最新の情報収集を行い、
栽培時期を選ぶと良いでしょう。土壌選びには、陽当たりの良い場所を選びます。また、水はけの良い土を使うと過湿が抑えられて病気を避けやすくなるものです。どうしても水はけの悪い土を使わなければいけない場合は、高畝を作る等の対策で過湿を抑えられます。
栽培場所の周囲も、事前に整えれば後の栽培が楽です。例えば、事前に種付けする周囲の雑草を除去する方法があります。雑草が無くなれば風通しが良くなって過湿と害虫が避けられると共に、敷き藁や整枝等の作業がしやすくなって一石二鳥です。
他にもフェンスや垣根を使った空間利用や、壁やネットを利用してグリーンカーテンを作る方法等がありますので、工夫次第で見た目や実用を兼ねた栽培ができるでしょう。生育初期は苗が弱い時期なので、気を配って保護する事が大切です。例えば、苗が低い内は風や害虫の被害にも弱い状態が続きます。
寒冷紗やビニール袋で苗の周りを囲う「あんどん」を作れば、風に倒れにくくなり、害虫による食害も防ぎやすくなるでしょう。収穫前には保管場所として、直射日光の当たらない風通しの良い場所を確保しておくと便利です。2週間から3週間程置いておけば、追熟されて美味しさが増します。
カボチャの種付けや水やり、肥料について
種付けは、育て方により行う時期が異なります。苗から育てる場合は4月から6月の間で行いますが、種から育てる場合は若干遅めで、5月から6月の間に行っても構いません。種付けを行う準備として、苗から育てる場合は、植える10日から1週間ほど前から、
種付け予定地にマルチを被せて土を温めておくと生育が良くなります。種から育てる場合は、播種の前日に種を1日中水に漬けて水を吸わせておきます。種付けをする時は予め育苗ポットに土を入れておき、必ず尖った方を下向きに植えましょう。ポット1つにつき2つか3つの種を播種するのが適切です。
1cmか2cm程度の土をかけて水やりをすると上手く発芽するでしょう。栽培中の水は土が乾き次第十分に行いますが、あまり与えすぎると根が弱くなり、実を大きくする時期に弱ってしまうので注意が必要です。水やりを行う時は、葉っぱにもかけると病気予防になります。
ただし、花にかけると花が萎れる事がありますので、水やりの時は花を避けるように注意します。肥料をやる時は「蔓ぼけ」に注意します。特に、最初の内に多くの肥料を与えると蔓ばかり伸びて実が付きにくくなるものです。
追肥は1番最初の実が拳大になった時に行うのが良いタイミングとなります。ただし、1番最初の実は小ぶりで見栄えも悪くなりがちなので、取り除く方が別の実が良く育つものです。以降は次の実が成った時、その次が成った時に肥料を足していくと、適度な追肥になります。
カボチャの増やし方や害虫について
カボチャは1株毎の結実が4個から5個と少なく、蜂任せの自然受粉では実が育ちきらない事もあります。種取りをして増やしたいのであれば、受粉のチャンスを逃さず人工授粉をするのが良い方法です。人工授粉をするには、雄花と雌花の両方が同時に咲いている必要がありますが、
油断していると雄花と雌花の開花タイミングがずれる事もあるものです。小まめに様子を見て、両方の花が開花した時を見計らって人工授粉を行います。種取りを行う手順は、カボチャを追熟させるまでは食用と同じです。追熟が終わったら実を割って、中の種を取り出します。
綿を丁寧に取り除いたら、種の選別を行いましょう。ボウルやバケツに水を張って種を入れると、良い種は水に浮かび、悪い種は底に沈みます。良い種だけを集めて乾燥させれば完成です。直射日光の当たらない風通しの良い場所で保管すれば、来年の播種に使えます。
害虫はウリバエとアブラムシに注意するべきです。ウリバエは栽培場所の周囲に雑草が繁茂していると発生しやすいので、雑草除去を丁寧に行って風通しを良くするのが有効な対策になります。また、ウリバエは反射光が苦手な虫ですから、
日光をよく反射するシルバーカラーのマルチを利用すれば、成虫の飛来を予防しやすくなります。シルバーマルチの利用はアブラムシ対策にも有効です。アブラムシの防除は薬剤も有効な方法となっています。また、寒冷紗で覆う事も良い対策の1つとして利用できるものです。
カボチャの歴史
カボチャは、日本国内の分類では「日本カボチャ」と「西洋カボチャ」と「ペポカボチャ」との3つがある野菜です。特に日本・西洋カボチャは日本の食卓で長く親しまれてきた歴史があります。原産地には様々な説がありますが、いずれもアメリカ大陸を原産とし、
それぞれ別々の生息地があったとする説が有力です。日本カボチャは昭和40年頃までは日本で生産・消費されるカボチャの主流でした。そのルーツをたどると、原産地は中米に行きつきます。近年、中米メキシコの南部ミトラ遺跡近くにある「Guila Naquitz(ギラ・ナキチス)」洞窟から、
最大で1万年前まで時代を遡れる種が見つかっています。また、現在日本で主流となっている西洋カボチャは南米が原産地です。ペルー北部のアンデス高地にある「Ñanchoc(ニャンチョーク)」谷の遺跡から、紀元前9200年の種が発見されています。
どちらの種類のカボチャも古い歴史を持ちますが、日本に初めて伝来したのは16世紀の事です。当時渡来したのは日本カボチャで、ポルトガルの船によって伝えられました。船は現在の大分県にたどり着いたとされ、伝来時の様子にも諸説があります。
例えば、江戸時代後期に農学者の佐藤信淵が著した「草木六部耕種法」の17巻には、東披塞亜(カンボジア)で産した野菜なのでカンボジアとも呼ばれるとする説や、スイカが渡来する100年前にポルトガル船が現在の大分県に来航し、時の大名であった大友宗麟に
献上した物の内の1つだったという説が記載されています。一方、西洋カボチャは明治時代にアメリカから伝来しました。1863年に北海道開拓使が本格的な導入と栽培を開始し、比較的寒冷な気候に適した種であった為、
当初は北海道を中心に東北でも栽培されていました。現在の様に日本の主流に転換したのは、戦後の品種改良で栽培可能な地域が広がり、日本人の食の洋風化が進んだ昭和40年以降です。
カボチャの特徴
カボチャは様々な栽培方法に適していて、病気や害虫にも強い特徴があります。比較的簡単に作れる野菜ですから、野菜栽培の初心者が挑戦する最初の野菜としても適している物です。連作もできますから、毎年繰り返して作れます。栽培用にやや広く空間を取る必要はありますが、
1つ植えれば4個から5個のカボチャが収穫を見込める、広さに見合った収穫量を持つ野菜です。物によっては狭い空間で栽培できますので、ベランダの片隅やプランターといった限られた空間でも栽培に挑戦できます。蔓が長く伸びる特徴を利用したガーデニングにも応用できますので、
計画的に栽培すれば野菜作りとガーデニングの両方を楽しむ事ができるでしょう。丈夫さと病害虫の少なさから手間もかかりません。しかし、整枝や人工授粉、玉直し等のようにカボチャならではの作業があるので、育てるのが面白い野菜と言えます。
野菜としては、日本カボチャは香りが良く、煮崩れしにくくて甘味も控えめの特徴があります。出汁を活かした煮物と相性が良く、食感は粘り気があり、和食作りに使うのに適していると言えます。西洋カボチャはホクホクした食感と強い甘味が特徴です。
様々な料理に適する活用範囲の広さがあり、比較的栄養が豊富な点も良い特徴となっています。長期保存したい場合は、まず直射日光の当たらない風通しの良い場所で1週間ほど保管すると良いものです。冷蔵庫へ入れても痛みにくく、新鮮さが長持ちします。
-

-
ブルーファンフラワーの育て方
ブルーファンフラワーはクサトベラ科スカエボラ属で、別名はファンフラワーやスカエボラ、和名は末広草といいます。末広草と名付...
-

-
ヒビスクス・アケトセラの育て方
ヒビスクス・アケトセラが日本に入ってきた年代は詳しく知られていないのですが、本来自生しているものは周種類であるとされてい...
-

-
バーゼリアの育て方
バーゼリアのいくつかの特徴を挙げていきます。植物としては、常緑低木に分類されます。開花時期としては、春頃です。4月から5...
-

-
ボリジの育て方
この花については、シソ目、ムラサキ科、ルリジサ科に属するとされています。一年草なので1年で枯れてしまいます。高さとしては...
-

-
簡単な人参の栽培の仕方について
野菜作りなどの趣味の範囲でも、人参の栽培は簡単に作る事ができます。ベランダなどでのプランター栽培でも作る事ができるのでお...
-

-
オクナ(ミッキーマウスツリー)の育て方
南アフリカ一帯に分布する樹木で、正式名称をオクナセルラタと呼び、ミッキーマウスツリーとして現在では親しまれている植物の特...
-

-
パイナップルの育て方
パイナップルは日本でもよく目にする果物ですが、原産地はブラジルで、代表的な熱帯果樹の一つです。先住民によって果物として栽...
-

-
アサギリソウの育て方
アサギリソウは、ロシアのサハラン・日本が原産国とされ、生息地は北陸から北の日本海沿岸から北海等、南千島などの高山や海岸で...
-

-
グミの仲間の育て方
グミの仲間はアジア、ヨーロッパ、北アメリカなどを原産地としており、幅広い地域を生息地にしています。約60種類ほどが存在し...
-

-
エスキナンサスの育て方
エスキナンサスとは、イワタバコ科の観葉植物です。半つる性で赤い花をつけるこの植物は、レイアウトをすることで、南国風のエキ...




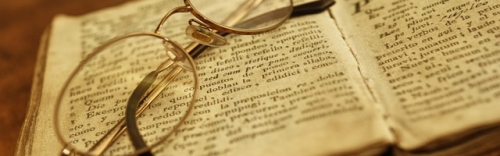




カボチャは、日本国内の分類では「日本カボチャ」と「西洋カボチャ」と「ペポカボチャ」との3つがある野菜です。特に日本・西洋カボチャは日本の食卓で長く親しまれてきた歴史があります。