オカトラノオの育て方

オカトラノオの育てる環境について
オカトラノオはもともと中国などのアジア地域が原産の植物なので、育て方に関しては、湿気を含んだ空気の中で育てることが一番大切で、乾燥する場所で育てる場合には水やりの方法などに注意が必要です。基本的には地中に根と茎の部分が埋もれているので、
ある程度の乾燥などに耐えることができるのですが、花の部分や葉の部分に関して直射日光や夏の暑い気候から守らなければなりません。オカトラノオに関しては野山で自生している場合が多いので、これらの場所の環境を参考にすることで植物を栽培することができるのですが、
日本の気候は基本的にオカトラノオにあっているので、直射日光や乾燥などに気をつけることで、庭で栽培することも十分に可能な植物です。花の咲く時期は春から初夏にかけてなのですが、それ以外の季節には地中で生育している植物なので、
なるべく日陰の場所である程度の湿気を含んでいる土地での栽培に適している植物です。オカトラノオは一般的には森や林の中で自生していることが多い植物なので、育てる環境に関しては日本国内の場合ならば、あまり難しく考える必要はありません。しかし乾燥することを嫌う種類なので、
雨の降らない時期や気温が上昇している場合には水を与えることが必要になる場合があります。しっかりと育てることができていると翌年の春には発芽をして葉をつけ始めて美しい白い花をたくさんつけていきます。サクラソウ科の植物は多年草や一年草が多いので、何度も繰り返し楽しむことができます。
種付けや水やり、肥料について
オカトラノオは自生している場合が多いことから種付けなどをしないで森に自生しているものをそのまま栽培することが多くなっているのですが、順調に生育させることによって初夏の時期になると地下に球根状の種を作るのでそれが次の年になるともう一度白い花をたくさん咲かせることになります。
水やりに関しては基本的には乾燥しない程度にすることが重要なのですが、根と茎が地中深く潜り込んでいる植物なので、あまりたくさんの水を与える必要はありません。しかし花をつけている時期に関しては乾燥や暑さに弱いので、直射日光が当たらないように気をつけたり、
乾燥をしないように適度な水やりが必要になります。花が咲かなければ次の年の根茎ができないので、以上に出てきている花や葉に関しては湿度を一定に保って、夏の高温などに注意をして育てる必要があります。一般的には日本の広い範囲で自生している植物なので、
日本の気候に順応できるているので、毎日の水やりなどの心配がないので、初心者や忙しい人でも安心して育てることができる植物なのですが、サクラソウのように育てる場合には湿地のような土地を再現する必要があります。基本的には川辺や森の中などの、
湿気の多い場所を好む性質があるので、直射日光が当たらない日陰の場所で冬の終わりに肥料を与えることで、春の気温上昇とともに地上に葉が出てきて、そこから花がつき始めて虎のしっぽのように下の方に向かって多くの花をつけていきます。
増やし方や害虫について
増やし方に関しては花ができた時にしっかりと管理をすることによって、実をつけるので地上に出てきてからの環境を大切にする必要があるのですが、基本的には日本の風土にあっている植物なので自生しているものを家の庭に植えておくと自然に増えていくことがあります。
しかし低湿地帯などを好んでいるので、都市部での栽培に関しては湿気の調節などが必要になる場合があるのですが、河原などに自生しているものはそのままの状態で群生しているので、庭で栽培する場合にも一般的な肥料などを春の前に与えることで自然に増えていきます。
害虫に関してはあまり心配がないとされているのですが、動物たちが群生地に入ることで荒らされてしまう恐れがあります。またサクラソウ科の植物は都市化された環境に弱いので、栽培をして増やしていく場合には広い範囲で湿地のような環境を作り出す必要があります。
現在では自生しているサクラソウ科の植物に関してはゴルフ場や工場などの建設によって、生育環境が悪化していて、それによって群生している地域が少しずつなくなっています。現在ではボランティアなどの手によってサクラソウなどの自生地を守る運動がされているのですが、
そのためには湿地帯や森のような日が当たらなくて涼しい場所が必要になるので、自宅で栽培する場合にもなるべく夏の暑い日差しなどが当たらない湿気の多い場所で栽培をしなければ増やしていくことが難しいとされています。
オカトラノオの歴史
オカトラノオはサクラソウ科の多年草で、その歴史としては中国を生息地としていたこの種類の植物が朝鮮半島を経由して日本に入ってきたと考えられています。日本では北海道から九州までの地域の日当たりの良い場所ならば生育することができるので、
多くの山野で見ることができる一般的な植物です。サクラソウ科の仲間はほとんどの場合は一年草と多年草なので、江戸時代の頃から荒川の原野などに自生しているものを栽培することから始められてきて、交配を繰り返しているうちに様々な種類のサクラソウ科の植物が造られてきました。
また文化元年からは品種の数が増えてきたことから品評会などが開かれるようになったので、愛好家が増えて日本のいたるところで見られる植物となっていきました。またサクラソウに関しては番付などが残されていて、現在見られる種類のうちその半数以上が江戸時代に品種改良されて作られたものです。
オカトラノオのようなサクラソウ科の植物は戦後になると盛んに育てられるようになり、ヨーロッパなどでも平成に入ってから園芸品種として栽培されるようになりました。またアメリカなどでは国際シンポジウムなどが行われて、そこで紹介されることで、
日本のサクラソウ文化が本格的に世界に知られるようになっています。現在ではイギリスやアメリカなどでも愛好家が増えているので、多くに品種が世界中で作られています。またオカトラノオなどもサクラソウとの類似点が多いので様々な形で栽培されています。
オカトラノオの特徴
オカトラノオの特徴はその白い花で、小さな花が集まることで一つの植物を形作っています。花の付き方が非常に珍しいのが特徴で先端に向かって細くなっているので、それが虎のしっぽに見えることからオカトラノオと呼ばれるようになりました。
サクラソウ科の植物の特徴としては一般的な林の中や原野の中に生えていて、種類によっては群生していることがあるので、景観んが非常に美しくなっている場合があります。地中に根茎があって、これが春になると発芽をすることで葉を出して、
それから高さが15センチから40センチくらいまで直立していきます。花の数は5から10個程度とされているのですが、オカトラノオなどの場合には小さな花がたくさんのできるので、10個以上になる場合もあります。葉の形は基本的には楕円形となっていて縁には切れ込みが合って少しギザギザしているのが特徴です。
花は桜の木に咲いているものと同様に花びらが5個に深く切れ込んでいて、それぞれの花びらには切れ込みが入っていて、中にはハート型に見えるものもあります。花が咲いたあとには地面に新しい根茎を作り出して、梅雨明け時期になると地面の中に入り込んでしまって、
休眠状態になります。これは夏の暑さから植物を守るための防御反応で、暑さと乾燥に弱いというオカトラノオなどのサクラソウ科の植物のほとんどはこのようにして種を守ります。サクラソウ科の植物は日本の気候に順応できる植物なので、多くの山野で見ることができます。
花の育て方など色々な植物の育て方に興味がある方は下記の記事も参考になります♪
タイトル:アナガリスの育て方
タイトル:オリエンタルポピーの育て方
-

-
ユーフォルビアの育て方
ユーフォルビア、別名、ユーフォルビアダイヤモンドフロストは、トウダイグサ科ユーフォルビア属の植物です。生息地は世界の熱帯...
-

-
ネクタリンの育て方
ネクタリンの語源はギリシャ神話に出てくる神々の酒であるネクターに由来していると言われています。芳しい香りと柔らかくてみず...
-

-
シラタマノキの育て方
シラタマノキは学名をGaultheriamiquelianaといい、ツツジ科のシラタマノキ属になります。漢字にすると「白...
-

-
サルピグロッシスの育て方
サルピグロッシスはナス科サルピグロッシス属(サルメンバナ属)の一年草または多年草です。その名前はギリシャ語のsalpin...
-

-
クリ(栗)の育て方
クリの歴史は非常に古いものであり、縄文時代の遺跡である三内丸山遺跡からも数多くの栗が出土しています。そのため有史以前から...
-

-
シノブ、トキワシノブの育て方
これはシダ植物と言われる植物になります。一般的な種子植物とは異なり種を作って増えるタイプではありません。胞子があり、それ...
-

-
オカヒジキの育て方
オカヒジキの原産地は日本や中国、シベリア、ヨーロッパ南西部です。「ヒジキ」と言いますが海藻ではなく海辺の砂地などを生息地...
-

-
フクシアの育て方
フクシアという植物はアカバナ科の低木ですが、アカバナ科の多くは多年草でフクシアの他にもツキミソウ、マツヨイグサなどが挙げ...
-

-
家庭菜園で甘くておいしいトマトを作る方法
家庭菜園を始める際、どんな野菜を作りたいかと聞けば、トマトと答える人は多いようです。トマトは見た目もかわいく、野菜なのに...
-

-
風知草の育て方
風知草はイネ科ウラハグサ属の植物です。別名をウラハグサ、またカゼグサとも言います。ウラハグサ属の植物は風知草ただ一種です...




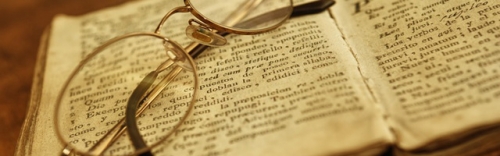





オカトラノオはサクラソウ科の多年草で、その歴史としては中国を生息地としていたこの種類の植物が朝鮮半島を経由して日本に入ってきたと考えられています。