スズメノエンドウの育て方

育てる環境について
スズメノエンドウの育て方の環境としてはとくに決まり事はありません。比較的どのような所でも育つことができるということで、とても強い植物となっています。したがって雑草のようにさまざまなところで見かけることができます。雨が多くて根腐れをするというような心配もあまりありません。土があり、日当たりが良ければどこでも育つことができるようになっています。
したがって家庭で育てているという人は少なくなっています。家庭で育てるというようなときには鉢などに入れて育てることができます。このときには培養土を使いますが、周りに花を咲かせるような植物を一緒においておくと、この部分にひげが巻き付くという可能性があります。したがって周りにはあまり何もないようなところで育てるのが理想です。
庭先に植えるというよりは、鉢などで独立した形で植えるのが理想です。しかし寒い時期には生息するということがなく、春の暖かい時期に小さな白紫色の花を3個から5個集中させて咲いている姿をたくさん見かけることができます。日当たりの良い平地や荒れ地に生息をするという傾向があります。
比較的どこでも見かけることができる植物となっていて、実を付けます。秋になって熟してくるとその色が黒くなってきます。本州から九州にまで生息が確認されているということで、見かけたことがあるという人がほとんどとなっています。春にたくさんの花を咲かせます。1つの果実の中に2つの種子しか作らないようになっています。
種付けや水やり、肥料について
自然環境に生息をしているということで種付けや水やりや肥料はとくに必要はありません。種は自然に成長をしたときに、土に落ちるようになっています。できた実が土の中に入り再び春になる頃に花を咲かせます。またスズメノエンドウは他の植物にからみつくという特徴から、他の植物を介して種を運ぶというようなこともあります。
植物にはたくさんの虫がよってきますが、この虫によって種が運ばれることもあります。したがってさまざまなところでスズメノエンドウの姿を見かけることができます。日当たりの良い草地を好むとくことで、あまり日当たりの良くないような所では生息をしません。栽培するというときには日当たりの良いところにおくようにします。
野草として生息しているので、根っこごと持ち帰って育てることができます。このときには鉢の中に培養土を入れてところで栽培をするようにします。こうすることで他の植物に巻き付くというような心配がありません。鉢を日当たりの良いところに置き、水やりをします。
土が乾燥してきたら水やりをすればいいのですが、寒さに弱いということや暑さに弱いということがありません。したがって育てる中でとくに気をつけなければいけないというようなことはありません。肥料もとくに必要はありません。培養土だけで十分に育てることができます。放っておいてもしっかりと育つので、スズメノエンドウは初心者にとっては非常に向いている植物といえます。
増やし方や害虫について
増やし方としては実をたくさん作るように心がけます。木の実が種となって次の年にも花を咲かせるようになっています。一つの果実の中に2つの種子しかできないので、これを残しておきます。道ばたや土手や草原などにたくさん生息しているということで、害虫などの被害の心配もありません。
したがって育てているときにとくに対策をしなければいけないということもありません。秋に発芽するようになっていますが、地表面下が10センチメートル前後でも出芽するという特徴があります。発芽は不斉一で長期間にわたっています。しかし年を越して春になってからが生育が旺盛な時期になります。
そして4月から6月にかけて開花するようになっています。その跡見ができて熟すと種子をはじき飛ばして広がります。夏にはかれるようになっていますが、それまでに種子を降ろさないように刈り取るということが大切です。こうすることでまた次のシーズンに花や実を楽しむことができます。基本的に蜜腺は花の中にあります。
このようにして花を育てることができますが、野草ということであまり育てる人は少なくなっています。知らないうちに種が飛んできて家の敷地内に生息しているということもたくさんあります。繁殖力が非常に強いということではありませんが、あまりにも増えすぎたときには少し抜いておくようにします。知らないうちに他の植物に巻き付いているということもあるので、適度な量を保つようにします。
スズメノエンドウの歴史
スズメノエンドウは古くから日本に生息している植物です。その生息地も広くなっており、本州から琉球までとなっています。またこのほかにはユーラシア大陸などの暖かく湿ったところにも広く生息しています。少し荒れたところに生息するという特徴があります。この名前はヤハズエンドウと比べると少し小さいということで、雀と名付けられたとされています。
生息地は日本となっていますが、マメ科のソラマメ属に分類しています。後援などに雑草のようにその姿が見られ、古くから周りの草や木に巻き付いている形で生息をしています。花の実がカラスノエンドウに似ており、それより小さいということでこの名前が付いていますが、薄い紫色の小さな花がたくさん咲きます。
とくに観賞用や庭先に植える植物として使われていたということはありませんが、毎日目にするということで、親しみやすい植物となっています。原産地はオリエントから地中海にかけての地方となります。この地方で古代の麦作りや濃厚が始まる問いにはエンドウなどと一緒に栽培されて、作物として利用されていたという歴史もあります。
その後現在に至るまでに栽培植物としての利用がほとんどなくなり、雑草として多くのところでその姿を見かけます。したがって若い芽や若い豆果は食用にすることができます。熟した豆の部分も炒って食用にすることができます。茎の部分には巻きひげがあるのが特徴で、近くの物にからみついている姿をよく見かけます。
スズメノエンドウの特徴
スズメノエンドウは開花時期が4月から6月となっています。花の色は白くて小さいのが特徴です。日本では本州から沖縄にかけて分布しています。生息地はとくに決まったところはなく、道ばたや草地でたくさんその姿を見ることができます。植物のタイプとしては越年草となります。栽培をして成長をするとその高さが30センチメートルから50センチメートルになります。
花の部分の特徴は、長い柄の先に長さが3ミリメートルから4ミリメートルのちょうちょのような形の花を、3輪から7輪程度付けます。花の色は白が主流で、淡い紫色を帯びているというのが大きな特徴です。葉はどのようになっているのかというと、6から7対の小さな葉からできている、羽状複葉になります。
これは鳥の羽のように左右に小さな葉がいくつか並んで1枚の葉が構成されているという状態です。そしてこれが互い違いに見えます。葉の先端部分には小さな葉の変化した巻きひげを見ることができます。小さな葉の形は幅の狭い卵形となっています。その先はへこんでおり、縁にぎざぎざはありません。
花が咲いた後には実ができますが、この実は楕円形の豆果になっています。ここには短い毛が生えており、2個の種子が入っています。カラスノエンドウよりも少し乾燥したところで生息をします。固い荒れたところでも生えるという傾向があります。葉の先端が巻きひげ状になっているのは、野エンドウの仲間の特徴となっています。
-

-
マーガレットの育て方
マーガレットは、大西洋に浮かぶカナリア諸島が原産で、もともとの生息地です。17世紀は、ヨーロッパにおいて色々な花の改良が...
-

-
プルモナリアの育て方
プルモナリアはムラサキ科プルモナリア属に属し、多年草です。園芸ではプルモナリアと呼ばれていますが、ハーブティーなどにも使...
-

-
ゴンゴラの育て方
花の特徴としては、ラン科になります。園芸分類はランで、多年草として咲くことになります。草の丈としては30センチ位から50...
-

-
ビギナー向けの育てやすい植物
カラフルな花を観賞するだけではなく、現在では多くの方が育て方・栽培法を専門誌やサイトなどから得て植物を育てていらっしゃい...
-

-
チオノドクサの育て方
チオノドクサという植物は東地中海クレタ島やトルコの高山が原産で、現在ではヨーロッパの山々を生息地とする高山植物の一種です...
-

-
初心者でも簡単な観葉植物について
最近は趣味として、ガーデニングなどを楽しんでいる方がどんどん増えています。自宅の庭に色とりどりの花を咲かせたり、ベランダ...
-

-
タチツボスミレの育て方
タチツボスミレに代表されるスミレの歴史は大変古く、日本でも最古の歌集万葉集にスミレが詠まれて登場するというほど、日本人に...
-

-
キャットテールの育て方
キャットテールは別名をアカリファといい、主にインドが原産地で、熱帯や亜熱帯地方を生息地としている植物でおよそ300種類か...
-

-
ラミウムの育て方
ラミウムは、シソ科、オドリコソウ属(ラミウム属)になります。和名は、オドリコソウ(踊子草) と呼ばれています。ラミウムは...
-

-
アローカリアの育て方
アローカリアは日本においては南洋杉と言う呼ばれ方をしています。その言葉の示すとおり南から来た杉の木であると言えます。日本...




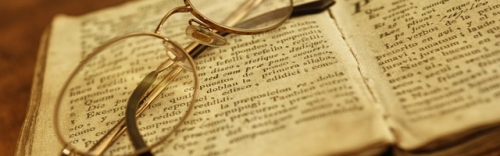





生息地は日本となっていますが、マメ科のソラマメ属に分類しています。後援などに雑草のようにその姿が見られ、古くから周りの草や木に巻き付いている形で生息をしています。花の実がカラスノエンドウに似ており、それより小さいということでこの名前が付いていますが、薄い紫色の小さな花がたくさん咲きます。