ビフレナリアの育て方

育てる環境について
育て方としてどのような環境に置くようにするかですが、日当たりの良い所にします。特に花が咲くとき、開花時期においては日光に十分当てる必要があります。と言っても直射日光は夏などは避けなければいけません。そのことから明るい日陰などに置くことがあります。管理としてはそちらのほうが楽です。移動をさせる必要がないからです。
でも楽をすればその分花も応えてくれません。季節によって良い環境に置くことでより花もつきやすくなります。真夏などにおいては半日陰などにしますが、それ以外の季節においては十分日光が当たるように日当たりに置くようにするのがよいでしょう。特に春などは日当たりに置きます。春先の種類においては冬から春の日当たりが重要になります。
このときに十分当てていないと花芽ができないとされます。どれくらい日当たりに当てるかといえば、葉っぱやバルブが黄色っぽくなるくらいまで日当たりに当てたほうが良いとされます。これはいわゆる葉焼けに近い状態ですが、それくらい当てないと花つきが良くならないとされています。
冬に直射日光、春と秋は直射日光と柔らかい日差しが半々、夏は明るい日陰と季節に応じて移動させます。冬は最低12度程度まで耐えるとされます。安心なのは15度です。温度不足があると花が咲く前に花芽が落ちたりと残念な咲き方になることがありあす。自宅内で管理をするときには冷暖房の風が当たらないように気を配る必要があります。
種付けや水やり、肥料について
栽培の時の用土としてはミズゴケを使う方法があります。植木鉢は通気性を考えて素焼きの植木鉢を利用します。この種類についてはミズゴケの他にはランの専用の土とも言われるバークを使うことができます。中粒タイプで、プラスチックの鉢を使って育てることができます。バークはミズゴケに比べると乾燥しやすいとされていて、水の管理としては難しくなるとされています。
バークを利用するときには水の調整が必要になります。水やりとしては、春の芽が伸びてくる頃から秋までについては、たっぷり目に与えるようにしていきます。用土の表面が乾いてきたときに与えるようにします。ミズゴケを使っているときはそれなりに水分を保持していますが、バークの場合は乾燥が早いので冬以外の季節においては水分量をチェックしながら水を与えるようにします。
冬は休眠期になります。全く水が不要にはなりませんが、あまり水を吸わなくなるので、自ずと水分もそれ程必要としなくなります。乾燥気味に育てるつもりで行うのが良いとされます。冬に用土を湿り気味にすると、春に花芽が出にくくなる傾向があるとされています。更には根腐れの状態になることがあります。
花芽が出てくるまでは乾燥気味に水やりをするのがいいでしょう。肥料は新芽が伸び始めたときに与えます。株元に有機質の固形タイプのものを置くようにします。液体肥料については週に1回与えます。液体肥料については秋ごろまで与えますが、それ以降は与えません。
増やし方や害虫について
増やす方としては株分けを行います。植え替えをするときにバルブの状態を見ておきます。植え替えにおいては2年に1回ぐらいの頻度で行うことがあります。バルブを切り分けることによって行いますが、一株あたりバルブが3つ以上つくように切り分けるようにします。適期としては春頃、4月ぐらいに行うと良いとされています。
植え付けなどと同じ時期に行うことで、その後の管理スケジュールなども立てやすくなります。ただし植え替えに関しては慎重に行う必要があるとされています。それは、この花についてはあまり植え替えを好まないともされています。根をいじられるのを好まないタイプになります。
鉢からバルブがはみ出すような場合においてはさすがに植え替えをしないと株が傷むことになるので行う必要がありますが、それ以外であれば無理に行うのは良くありません。行うときにおいても根を慎重に扱うようにするのを忘れないようにします。少しぐらいと考えてしまいますが、そこから問題が発生してしまうこともあります。
根に関しては地中深くにどんどん伸びていくわけではなく、浅い位置において這うように伸びていきます。これは着生種だからということもあるのでしょう。そのことから通気性の良い浅めの植木鉢を利用するのが良いとされています。鉢の底には軽石などを詰めておくと良いとされています。病気としては低温高湿度の状態で黒斑病の場合があります。葉の裏にカイガラムシが付いた時はこすり落とします。
ビフレナリアの歴史
花を購入するところとしては花屋さんがあります。多くの場合は切り花を購入できます。育てる花を購入したい場合は園芸店に行くと良いとされます。こちらにおいても花はおいていますが、花束のような花は少なく、野菜の苗なども買えるようになっています。園芸店といいますと見つけにくいかもしれませんが、ホームセンターであれば比較的身近にあるかもしれません。
ホームセンターの園芸コーナーは比較的幅広い園芸のために必要なものを揃えることができます。しかしこの園芸店でもなかなか買えない花があります。それはランの種類です。ランに関しては世界的においても貴重で栽培などはそれ程容易ではありません。そのために非常に高いタイプもあります。そういうこともあってかランの専門店があります。
そちらにいけば花束としてのラン、贈答用の蘭のほか、栽培をするためのランもあります。ビフレナリアと呼ばれる花がありそちらを育てたいと考えることがあるかもしれませんが、こちらについてはランの中でもあまり流通しないタイプとされています。一般の園芸店などでは探すことができない場合があり、
ラン専門店でないと買えないことがあるようです。名前の由来としてはビは数字の2を表すとされます。そしてフレヌムに関しては手綱を意味するとされています。2つの手綱となりますが、これは花粉の形がそのような形をしているからとされています。種の小名については収集家の名前がついています。
ビフレナリアの特徴
花についてはラン科になります。園芸上の分類もランになります。ランについては多くは多年草です。しかし育て方が難しいのでずっと育て続けるのは難しいこともあります。原産地は南アメリカのブラジルになります。草の丈としては50センチぐらいになります。花が咲く時期は幅が広いですが春から初夏にかけてになります。
花の色としては白や紫ですが、一色で咲くよりも両方が混ざったような花になると言ったほうがいいかもしれません。耐暑性についてはそれなりにあります。耐寒性はあまりなく寒さに弱い花とされています。常緑性になります。寒さには弱いですが、洋ランの種類の中では比較的冬越えがしやすいタイプとされています。
最低温度としては12度ぐらいですから、暖地などであればなんとか昼間は外でも管理が可能です。夜は室内に取り込んだほうが無難でしょう。この花については、生息地としてはブラジルの南部になります。約12種類あるはなになります。樹木などに根を張り付かせる着生種の一つになります。
ランといいますと土から出る部分においてバルブと言われる膨らんだ部分を持つことがありますが、その部分が特徴的になっています。通常は丸いタイプが多いですが、この花の場合は角張った形をしています。このバルブの上部に葉っぱを付けます。バルブから花茎を伸ばしてその花茎から1輪から数輪の花を咲かせるようになります。花茎はあまり伸びないので、バルブから直接咲いているようにも見えます。
-

-
ピメレアの育て方
ピメレアは育てるのに、簡単で丈夫な植物になりますが、どうしても夏場は気をつけてあげないといけないです。夏場は高温になって...
-

-
タコノキの育て方
タコノキの生息地と原産はユーラシア大陸、アフリカ大陸、オセアニア周辺の島などで、温暖な地域に広く分布しています。現在は5...
-

-
ヒアシンスの育て方
ヒアシンスは16世紀前半にヨーロッパにもたされ、イタリアで栽培されていた歴史がありますが、ヨーロッパにも伝わった16世紀...
-

-
サザンカの育て方
サザンカは、元々日本に自生している植物です。ツバキとは種が異なりますが、属のレベルではツバキと同じですから、近縁種だと言...
-

-
きゅうりの育て方
インド北部のヒマラヤ山麓がきゅうりの原産地や生息地で、現在から約3000年以上前には栽培されていたのです。その後シルクロ...
-

-
ゴメザの育て方
ブラジル原産のラン科の植物です。属名がなんども変えられた歴史を持っています。最初はSigmatostalix(シグマトス...
-

-
グンネラの育て方
グンネラの科名は、グンネラ科 / 属名は、グンネラ属で、和名は、オニブキ(鬼蕗)となります。グンネラ属グンネラは南半球に...
-

-
ラッカセイの育て方
ラッカセイは、マメ科になります。和名は、ラッカセイ(落花生)、その他の名前は、ピーナッツと呼ばれています。ラッカセイは植...
-

-
ハボタンの育て方
ハボタンは日本で改良されて誕生したもので、海外から伝わってきたものではありません。江戸時代の前期に食用のケールがつたえら...
-

-
カリンの育て方
カリンは昔から咳止めの効果があると言われてきており、現在ではのど飴に利用されていたりします。かつてはカリン酒等に利用され...




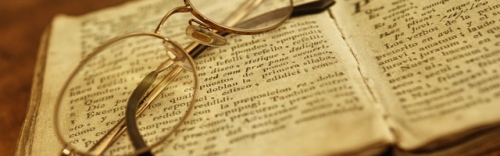




花についてはラン科になります。園芸上の分類もランになります。ランについては多くは多年草です。しかし育て方が難しいのでずっと育て続けるのは難しいこともあります。原産地は南アメリカのブラジルになります。草の丈としては50センチぐらいになります。花が咲く時期は幅が広いですが春から初夏にかけてになります。