アグラオネマ(Agleonema)の育て方

アグラオネマの主な種類
栽培種として園芸店やホームセンターなどに出回りやすい種類としては、シルバークイーン(細葉でパステルグリーンに濃いグリーンの斑が入る)、シルバーキング(シルバークイーンに比べてややごつい感じの斑)
グリーンサン(グリーンの細葉で葉脈はイエローグリーン、茎は白)、スノーホワイト(グリーンの太葉で葉脈と茎が白)、レガシー(白っぽいグリーンの太葉にグリーンの斑が入り、濃いピンクの葉脈で、葉裏も濃いピンク)、二ティードゥーム(スノーホワイトよりやや葉色が明るく、葉脈はパステルグリーン)
カーティシー(グリーンの葉に白い筋が入る)、バレンタイン(葉脈と縁がグリーンで、葉のほとんどが淡いピンク)、アンヤマニー(バレンタインのピンクの部分が真紅)、オーロラ(グリーンのやや細葉で、中央の葉脈と縁が赤)、ペッナムヌン(明るいイエローグリーンの細葉でグリーンの斑が入る)などがあります。
マニアに大人気の原種はピクタム(pictum)という種類で、大きく分けてバイカラーと呼ばれる緑色の葉に1色の斑が入るものと、取りカラーと呼ばれる緑色に2色の斑が入るものがあり、斑の入り方のバランスの良い株は1株数万円で売買されます。
アグラオネマの育て方
栽培種のアグラオネマは前述のアクアテラリウム、鉢植え、ハイドロカルチャーなどで育てることができます。鉢植えの場合は市販の観葉植物の土、ハンギングバスケット用の土、球根用の土などが使えます。アグラオネマの育て方で注意しなければならないのは、温度と湿度と水遣りです。
シルバークイーン、シルバーキング、スノーホワイト、グリーンサン、二ティドゥーム、カーティシーはアグラオネマの中では比較的冬越しが容易です。原種と、それ以外の栽培種の栽培がどうも上手くいかないという方は、室内用温室や水槽などを利用して、年間を通じて20度を下回らないようにしてみてください。
必要なのは空気の温度なので、鉢の下にシートヒーターを置いて土を直接暖めると枯れてしまうため、注意が必要です。また、高温多湿の環境では、弱めのファンなどを利用して空気が滞らないようにしますが、アグラオネマに直接その風を当てないで、囲んである中に弱い空気の流れがあるようにします。
置き場所ですが、暖かい季節は半日陰の屋外で育てるという説がありますが、川の側でもない限り、たいていは乾いた日が続いたときに空中湿度が不足して枯れます。屋外が熱帯雨林並みの湿度でないようなら、止めたほうが無難です。5月~11月であれば、明るい窓辺に置くのがベストです。
ガラスは紫外線を減らすので、レースのカーテン越しにこだわる必要はありません。人間も植物も、引きこもっていると体調を崩しやすくなります。アグラオネマにも同じことが言えます。
週末など、週に1回程度、15~20分カンカン照りではない程度の日向に置いて、葉を優しい日ざしに当てます。栽培種のアグラオネマの場合、30分強い日差しに当てると葉焼けして枯れますが、ずっと室内では徒長してだんだん弱々しい姿になっていきます。
冬越しは、年間温度を一定にしたほうが良い種類はそのままで、シルバークイーン、シルバーキング、スノーホワイト、グリーンサン、二ティドゥーム、カーティシーについては、鉢を2重にして、間に梱包用のプチプチビニールを入れて巻きます。
晴れた日の日中は窓辺で構いませんが、曇りや雨、雪の日と午後5時以降と、なんとなく元気がなくなってきたように見える場合は、部屋のなるべく中央で、床からなるべく高い位置に置きます。湿度は20度以上を必要とする種類なら、アクアテラリウムか加湿器の側に置くのがベストです。
それ以外の種類は、最低でも朝夕2回は霧吹きします。水遣りは春~秋なら鉢土の表面が乾いてから1~2日後、冬は7~10日に1回、鉢底から水が出るまで与えます。このとき、受け皿に水を溜めておかないように気をつけます。肥料は緩効性の肥料を用法どおりに与えます。
アグラオネマの増やし方
アグラオネマは水芭蕉を小さくしたような、あるいはスパティフィラムを小さくしたような花が咲きます。種付けする場合は数鉢用意しておいた方がいいですが、種付け以外の増やし方の方がずっと簡単です。土の中から子株が出てきた場合は、ある程度しっかりしてから株分けします。
また、アグラオネマは先端が成長して新しい葉が展開すると、下の方の古い葉が黄色くなっていって枯れる場合が多いので、茎の下の方が棒状になってしまったら、茎にせっせと霧吹きします。すると節から新しい葉が出てくるので、気温が20度以上になったら、その葉を残してそれより上の棒状の茎の節を切って挿し木します。
棒状の茎の節にミズゴケを巻いて乾かさないようにしておくと発根するので、その下で切って鉢に移すこともできますが、その方法だと元の鉢から新しい葉が出にくい場合がありますので、状況を見て、増やし方を決めましょう。
アグラオネマの歴史
アグラオネマはアジア原産の熱帯雨林が生息地のサトイモ科の多年草です。インドから東南アジア、中国南部にかけて約50種類が生息しており、特にタイからは栽培種、生息地で現地の人が掘りあげてくる野生種、実生種などが日本に輸入されており。
美しく多様な葉の模様が一般家庭からマニアにいたるまで、幅広く愛されている観葉植物です。種類によって耐寒性に差があり、また木立性ではないものの、高さ1メートル以上になる大柄な種類から、丈が伸びず地を這っているような感じの種類まで、多種多様です。野生種の中には現在でも品種が特定出来ないものも稀にあります。
アグラオネマは古くから観葉植物マニアの間では知られていましたが、一般の人々にまで広くその名前を一躍有名にしたのは、1994年製作のフランス・アメリカ合作映画でリュックベンソン監督の映画「レオン」が人気を博してからです。
主人公の孤独な殺し屋・レオンが、「根が地面についていない(地植えでは無いから)のが自分と同じだ」と言って、唯一の友として大切にして、こまごまと手入れをしていた一鉢の観葉植物がこのアグラオネマで、その中の「カーティシー」という種類だといわれています。
「レオン」を見て、観葉植物に興味を持った人や、アグラオネマに見せられて栽培を始めた人もたくさんいます。また、生息地が高温多湿であるということで、熱帯魚愛好家がアクアテラリウムに取り入れたり、カメレオンなどの爬虫類愛好家がケージ内に設置する例も近年では多々見られます。
アグラオネマの特徴
アグラオネマの生息地である熱帯雨林は年間を通して気温が高く、降雨量も多いところです。気温が高く雨が多いため、湿度も年間を通して高い状態です。また、雨林の低層でも地域によっては日光が届きますが、ほとんどの場合、雨雲や高い木々に遮られてしまうため、強い日差しが届いて射し続けることはありません。
また、熱帯雨林というと落ち葉が積もったフカフカで栄養豊富な土壌を想像しがちですが、実際には養分のある柔らかい土は地表からほんの数センチまでで、その下は赤い粘土質の土や岩盤です。
落ち葉は気温が高いために微生物による分解が早く、またシロアリが巣に持ち運んでしまい、わずかな養分は雨で流れてしまうので、痩せた酸性の土壌となっています。アグラオネマの栽培が盛んなタイも熱帯性の気候ですが、栽培地ではやはり年間を通じて気温が20度を下回ることは少なく、降水量は多い。
観葉植物の育て方など色々な植物を育てることに興味がある方は下記の記事も凄く参考になります♪
タイトル:スパティフィラムの育て方
タイトル:ベンジャミンの育て方
-

-
ペペロミア(Peperomia ssp.)の育て方
ペペロミアの原産地はブラジル、ボリビア、エクアドルなどで、主な生息地は熱帯や亜熱帯です。約およそ1400種類もの種類が存...
-

-
ヘスペランサの育て方
ヘスペランサは白い花を持つ美しい植物でり、日本だけに留まらず多くの愛好家がいます。花の歴史も深く、大航海時代にまで遡る事...
-

-
ラセンイの育て方
”ラセンイ”は畳の原料である「イグサ」と同じ種類の植物になります。葉っぱが退化し、くるくるとらせん状にうねうねと曲がって...
-

-
コバイモの育て方
コバイモは本州中部から近畿地方の山地に多く自生している植物で、原産国としては日本であるとされているのですが、その生息地は...
-

-
シランの育て方
シランという植物は、ラン科シラン属の宿根草のことを言います。宿根草は多年生の中でも生育に適していないシーズンには地上部分...
-

-
ヒベルティアの育て方
ディレニア科ヒベルティア属は、害虫被害に遭いにくい植物です。原産地をオーストラリアとするヒベルティアという花は、種類にも...
-

-
植物の栽培、育て方のコツ。
植物を育てるのは生き物を飼うのよりはだいぶ気楽にできます。動かないので当然といえますが、それでもナマモノである以上手を抜...
-

-
ナスタチウム(キンレンカ、金蓮花)の栽培
ナスタチウム(キンレンカ、金蓮花)は、南米原産のノウゼンハレン科のつる性の一年生です。開花時期は5月から10月過ぎる頃ま...
-

-
トリフォリウムの育て方
トリフォリウムは分類上はシロツメクサやクローバーの仲間であり北半球だけで300種類ほどが分布しています。日本においてはシ...
-

-
ヒペリカムの育て方
ヒペリカムの原産地は中国で、中央アジアや地中海沿岸を主な生息地としています。もともとは中国大陸の草地や山の中に自生してい...




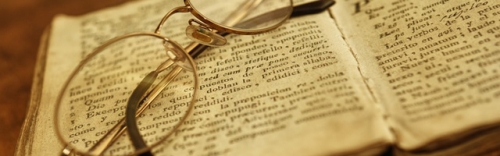





アグラオネマはアジア原産の熱帯雨林が生息地のサトイモ科の多年草です。インドから東南アジア、中国南部にかけて約50種類が生息しており、特にタイからは栽培種、生息地で現地の人が掘りあげてくる野生種、実生種などが日本に輸入されており。