キンモクセイの育て方

キンモクセイの水やりと肥料
地植えしたものは一度根付いてしまえば、降雨だけで十分です。特にひどい日照りにならない限りは水をやる必要はありません。鉢植えしたものは土が乾いたらしっかりと水をやるようにします。肥料は、地植えしたものは2月ころに骨粉や鶏糞、リン酸など多く含んだものを与えます。
油カスなどの多いものを与えすぎると、枝葉は茂りますが、花付が悪くなります。鉢植えしたものは、5月と初夏に同じ肥料を与えます。肥料が少なすぎると、花付きに影響を及ぼします。
キンモクセイの用土・管理場所
日当たりの良い場所で、水はけは良く肥えた土が適しています。日当たりが悪い場所に植えてしまうと、冬でも葉が落ちない常緑樹なのに落葉しはじめます。また、キンモクセイは排気ガスなどの大気汚染に敏感で空気の悪い場所ですと、花芽が付かなくなったり、花が咲いても香りが弱くなることがあります。
葉の表面が汚れるために、このような現象が起こることがあります。そのような場合は、ときどき葉の表面を洗い流してあげるといいです。梅雨時期に、たくさんの雨が降ると花付が良くなることがあるのは、葉の表面を洗い流す効果があるからです。
キンモクセイは日陰でも育ちますが、花付きがよくないので大気汚染などに影響されない日当たりが良い場所になります。
キンモクセイの植え替え・ふやし方
植え付けは新芽の出る4~5月が最適です。鉢に植える場合は、8号以上の鉢を使って植えます。地植えの場合は、一度植えつけてしまえば植え替える必要はありませんが、鉢植えの場合は、鉢に根が回ってしまったら、一回り大きな鉢に植え替えます。
増やし方ですが、キンモクセイはオスの木しか日本にはありませんので、種付け方法はできません。増やすには、さし木の方法をとります。6月~7月の梅雨時期が、作業の最適な時期になります。
今年伸びた新しい枝を、10~15cm位切り取って水に2,3時間挿して充分に水揚げをした後に、水はけの良い土に挿して乾かさないように管理します。新しい枝の切り口は、斜めにカットすることと、乾かさないのがコツです。
ギンモクセイの場合は、木が大きくなると実をつけることがあります。キンモクセイは病害虫が少ないですが、風通しが悪いとカイガラムシやハダニが発生することがあります。見つけ次第、適応薬剤を散布して駆除します。
キンモクセイの剪定
植え付け後、そのまま放置の状態で栽培すると、7~8mくらいになります。育て方に関係なく自然と樹形が整う木なので、広い庭などであればそのままの状態にしておくと、かなりの大木になります。
一般的な庭の場合、上に伸びすぎてしまうと下枝が寂しくなってしまい、目隠しにはなりません。そのようにならないためにも、上部を抑えて、庭とのバランスをとった剪定をしなくてはなりません。選定の時期ですが、花の直後か翌年の花に影響の少ない2~3月頃がおすすめです。
なぜこの時期がおすすめなのかと言いますと、春から秋が生育期になります。葉が多く茂る時期なので、おもいっきり剪定したくなりますが、花を楽しみたい場合は注意が必要となります。花は、その年の春~夏に伸びた枝に花を付けるので、この春~夏に剪定をしてしまうと、花が楽しめません。
なので、花が咲き終わった直後か、翌年の花に影響の少ない2~3月頃が剪定のお勧め時期と言う事になります。また、キンモクセイは刈り込みに強い木なので、ただ小さくしたいと思う場合は厳冬期を避ければいつでも剪定して大丈夫です。ただし、葉がほとんどなくなるような剪定をしてしまうと、枝枯れを招くので禁物です。
焦らず毎年少しずつ剪定して、小さくするといいです。剪定のイメージ、楕円形や球形、円筒形に刈り込んだ状態ですが、外側だけ刈り込んでも鬱蒼とし感じは取り除かれません。外側だけではなく、内側の枝も刈り込まないといけません。このように剪定するには、刈り込みバサミで好みの形に切るだけです。下枝は生えにくいので、根元から生えている小枝は切らず大切にします。
その手順は、
①刈り込みバサミで木の表面を刈り込んで、好きな形に作ります。
②木の表面に達していなし枝(楕円形などを作るのに貢献していない枝)を、木バサミで元から切っていきます。このようにしていくと、お庭のキンモクセイも好みの形に整えられます。
また、花を楽しみたいのに花が付かない場合は、幹を途中で切って枝を横に伸ばすようにします。そうすると、小枝が増えてきて、花が付くようになります。他にも、切ったところが「棒」のように見える剪定は花付が悪くなりますので、木バサミなどで葉が残る剪定がいいです。
キンモクセイは、花は9月~11月頃に香りの強い黄色の花を咲かせる木です。ジンチョウゲ、クチナシとともに「三香木」として数えられています。小さな黄色の花を咲かせるキンモクセイは、秋の花の代名詞で街路樹などで見かける木です。
そのキンモクセイの花言葉は、「謙虚」「謙遜」です。その香りのすばらしさに比べて、花が小さく控えめなところからきています。花の由来は、黄色の花を金色に見立てたところからきているので、「金木犀」となります。原産地の中国では「桂花」と呼ばれ「雅な花」という意味を持ちます。
キンモクセイの歴史
キンモクセイはギンモクセイの亜種で江戸時代に中国から伝わってきました。九州には自生するウスギモクセイが変異した説もあり、来歴ははっきりしていません。キンモクセイは雄雌異株(オスとメスがある)のうちオスしか日本にはないため、日本ではキンモクセイの結実は見られません。中国ではキンモクセイのことを「桂花」と呼び、この花を白ワインに付けたお酒が「桂花陳酒」です。
キンモクセイの特徴
中国原産の樹高5m以上にもなる常緑性樹木です。生息地は、中国の桂林地方になるキンモクセイは、秋に小さなオレンジ色の小花をかたまって咲かせ、強く香ります。また、ギンモクセイは白い花で、甘く香ります。両種とも寒さに弱いので、関東地方以西の地域で栽培に適しています。
キンモクセイはクチナシと並んで芳香をもった庭木として親しまれていて、花が散る様は金色の絨毯のようにみえます。またキンモクセイの香りは長い間トイレの芳香剤として使用されていました。それは、昔、水洗トイレではなかったので匂っていたため、トイレの脇に植えられたことが多かったことから、長い間トイレ用の芳香剤として使用されていました。
日当たりを好む植物ですので、日光が足りないと葉が落ちることがあります。また、排気ガスには弱く、大気汚染の強い地域などに植えると、花が咲かなかったり、咲いても香りが弱かったりしますので、植える場所も重要です。
キンモクセイは成長が遅い木ですので、強く刈り込むと枯れてしまうことがありますので、毎年少しずつ刈り込んで樹形を整えていきます。春に延びた新しい新芽に8月上旬に花芽が形成され、秋に花が咲きます。
つまり、新芽が出る4月から開花するまでの期間に剪定をすると、花芽まで切り落とすことになりますが、それ以外の季節ならばいつでも剪定しても大丈夫です。ある研究結果で、キンモクセイの香りをかぐと体重増加が抑えられる効果があると言われています。
また、香りの主成分はβ-イオノン、リナロール、v-デカラクトン、リナロールオキシドなどで、このうち、v-デカラクトンはモンシロチョウなどで忌避作用があることが分かっています。キンモクセイのの香り成分を付けた腕に蚊を近づけても、全く刺されなかった。という実験結果もあります。
キンモクセイの花は、中華料理で色々と使われています。お茶は、桂花茶で、お酒は桂花陳酒です。また、花を砂糖とハチミツに漬けこんだものもあります。
庭木の育て方や色々な植物の育て方に興味がある方は下記の記事も参考になります♪
タイトル:ボケの育て方
タイトル:ハナミズキの育て方
-

-
フォックスフェイスの育て方
フォックスフェイスはブラジル原産のナス属の植物とされ、ナス属は世界の熱帯から温帯にかけて1700種ほどが分布しています。...
-

-
植物の栽培育て方のコツを教えます。
最近はインテリアグリーンとして植物を栽培するかたが増えてきました。部屋のインテリアの一部として飾るのはもちろん、植物の成...
-

-
ミツマタの育て方
ミツマタ(三椏)は、中国原産で、冬に葉を落とすジンチョウゲ科の落葉性の低木です。枝が三つ叉に分かれるところから「ミツマタ...
-

-
チューリップの栽培の仕方
チューリップはユリ科の植物で品種には早生系、早生八重、晩生系など色々な種類があり、その種類によって草丈や開花期が異なりま...
-

-
初心者でも栽培しやすいえんどう豆の育て方について説明します。
えんどう豆の栽培は、マメ科なので前回マメを育てた場所での栽培は避けた方が無難です。しかし、えんどう豆は日当たりが良く水は...
-

-
モンステラ(Monstera spp.)の育て方
モンステラはサトイモ科に属するつる性の植物です。アメリカの熱帯地域を原産とし、約30種の品種が分布しています。深いジャン...
-

-
主婦の間で密かなブームとなっている栽培方法
現在、主婦の間で密かなブームとなっているのが、お金のかからない種取り栽培です。これは、スーパーで買ってきた野菜や果物のタ...
-

-
ラベンダーの育て方
ラベンダーはシソ科の植物で、精油などにもよく使われています。実はこのラベンダーの精油はなんと古代ローマ時代から使われてい...
-

-
ニワトコの仲間の育て方
ニワトコの仲間は、ヨーロッパや中国や朝鮮にもありますが、日本でも、寒い北国を除く、ほとんどを原産地として、分布している、...
-

-
ミツバの育て方
ミツバは、日本を含む東アジアが原産地の、せり科の自生植物です。生息地は、日本原産のものでは、全国の産地の日陰に育ちますが...





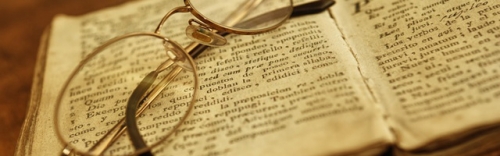





キンモクセイはギンモクセイの亜種で江戸時代に中国から伝わってきました。九州には自生するウスギモクセイが変異した説もあり、来歴ははっきりしていません。キンモクセイは雄雌異株(オスとメスがある)のうちオスしか日本にはないため、日本ではキンモクセイの結実は見られません。中国ではキンモクセイのことを「桂花」と呼び、この花を白ワインに付けたお酒が「桂花陳酒」です。