アルブカの育て方

育てる環境について
この植物を栽培するにあたってはどのような環境にするのが良いかです。生息地は南アフリカなので暖かくて日差しのあるところが良さそうです。まず第一には日当たりが良く、風通しの良い所になります。寒さにはそれ程強くありませんから、冬などには移動しやすいところがいいでしょう。軒下などであれば霜が降りたとしても影響しません。
また雨が降ったからといって直接当たるようなことはありません。鉢植えのときに行うと良いこととしては土に埋めることがあります。そのまま地植えの場合は場合によっては根がやられてしまうことがありますが、植木鉢に植えた上でそれを土に埋めると寒さに対する保護をすることが出来るようになります。
寒さに弱いと言っても一般的な暖地であれば十分冬越が出来る耐寒性を持っています。最低温度としてはマイナス5度位まで耐えることが出来るようです。北海道や東北などだと厳しいこともありますが、太平洋側なら夜に0度になることも少ないですからなんとか冬越できるでしょう。あまりに寒いと室内に取り込む必要が出てきますが、
そうなると日光に当てられなくなります。日光に当てられないとある現象が見られなくなるとされています。この植物の特徴である葉っぱの部分がくるくるとまく様子が見られません。期待はずれに感じる人もいるでしょう。寒いところにおいては自宅の中でも日差しがしっかりと当たる所に置くことによって、くるくる巻く様子が確認できるでしょう。
種付けや水やり、肥料について
育て方として植え付けについてはどのように行っていくかですが、まず芽が出る直前に行うようにすることがあります。8月下旬から9月中旬頃に植え付けを行います。真夏に植え替えをすることも可能で、その時には8月下旬までは水を与えないようにする必要があります。この植物に関しては夏に休眠をすることになりますが、
掘りあげて保管するタイプではありません。鉢に植えたまま夏を越させます。植木鉢についてはどのよなサイズが良いかですが、4号鉢ぐらいであれば1球にします。これは球根が大きく成長することがあるからです。あまりたくさん植えると球根同士がぶつかり合ってしまう場合があります。
球根が大きな場合、複数植えようとするときはもう少し大きなタイプの植木鉢を利用します。過湿状態をあまり好みません。用土はそれに合った配合にしておきます。鹿沼土とボラ土を5割ずつ混ぜた土などが良いようです。よく育てたいために腐葉土を混ぜたいところですが、あまり有機質の土を使わないほうが良い場合があります。
球根を植える位置については、球根の頭がやや見えるかどうかぐらいのところにします。朝埋めが基本の植物です。水やりは他の植物とは別と考えて行います。6月頃から枯れ始めますから水を減らし始めます。夏場はほとんど与えません。土の中で休眠です。9月で芽が伸び出したら徐々に水を増やし始めます。冬場などは1週間に1回ほどで、春は2日に1回ほどに数を増やします。
増やし方や害虫について
増やす方法としては、球根を分給する方法が知られています。夏場に植え替えをすることになるので、そのときに球根の様子を見ましょう。あまり小さいと行えませんが、小さい球根が見えてきたらそれをチェックしておきます。次の年に大きくなっていればそれを外して使える場合があります。球根の形としてはネギに似た形です。
それ程大きくはありませんが、それは植えるときで、将来的に成長してくると大きくなることもあります。種まきをしても増やすことができます。花が終わった後に種を取ることができればそれを保存しておきます。種まきの時期は9月から11月頃が適期になります。発芽温度としては8度位から25度位と結構幅広いのであまり意識して温度を聞いすることはないでしょう。
暑すぎるのは良くないので、10月以降に行ったほうが安全でしょう。種をまく時の用土としては、鹿沼土、ボラ土、赤玉土などを利用します。これらの良い所は水はけの良いことです。この時には少し肥料を混ぜておくと良いとされています。何度も与えるわけではないので、元肥に少しいれておいて、
長期間にわたって効くようにしておきます。種子から芽が出るのは日陰で置いておくと10日ほどで出てくる事が多いです。芽が出てくればそれ以降は日光に当てるようにします。種子から育てると球根までが時間がかかるため花もしばらく掛かりそうと考えがちですが、1年半近くで咲かせることが出来る場合があります。
アルブカの歴史
野草の中でわらびと呼ばれるものがあります。特徴としては先のほうが少し丸まった状態で成長していきます。通常の植物はどんどん伸びていく時はまっすぐ上に行くか、匍匐するように横に伸びていく、何かにつたって鶴のように伸びていくのでしょう。わらびに関しては最初はなんとか自分で上に行きますが、
そのうち上に行く気力がなくなったのか曲がってしまってそのまま渦を巻いたようになります。それでも特徴的に成長するので面白い植物になるかもしれません。そんなわらびに少し似た性質を持っている植物としてアルブカと呼ばれるものがあります。あくまでも伸びた状態が一時的にわらびに似ているだけなので、同じ種類などではありません。
でも一瞬見た時にはとても植物には見えないかもしれません。人工的に作られた緑の紐を土に植えているようにも見えます。それくらいあまり見かけない光景を見ることができます。こちらについては南アフリカを原産とする植物になります。種の小名にヴィスコサがありますが、これについてはラテン語で粘着性のあるの意味になります。
実際に少しベタベタつくような感覚がありますから、そのところから付けられてのかもしれません。その他にもいくつかの種類があることが知られています。よく知られているのがナマクエンシスと呼ばれる種類になり、こちらが代表的な品種になります。ピラリスと呼ばれる種類もあり、雰囲気としてはナマクエンシスとよく似ています。
アルブカの特徴
この植物に関しては多肉植物として知られています。一般的な花とはかなり異なるように感じていましたが、比較的身近な花の科に属します。ユリ科となりますから、ユリの仲間になります。茎の状態だけを見ると観賞用の葉っぱ、植物ですが、実際に花が咲くと当初とはかなり異なる様子になり、まさにユリ科の植物といえるような花が咲きますから問題はないでしょう。
球根として植えることになりますから、育てたい場合は球根を入手する必要があります。問題としてはあまりお店では出回らないことです。発芽したときに非常に珍しい育ち方をすることから人気がありますが、出まわらないのは残念です。発芽した時にはしばらくはまっすぐ伸びますが程なくくるくると丸まっていきます。
丸まり方は種類によって多少異なります。わらびのように丸まることもありますし、螺旋階段のように丸まっていくこともあります。最初の方は少し変わっているように見えますが、螺旋状に育っていても大きくなると普通の花の草のように見えてくるから不思議です。最初はまるまる茎ですが、成長するにつれてしっかりと直立して、
最終的には茎の上部に花をつけます。茎から細い枝が出てきて、そこにつぼみを付けてそこから開きます。枝が非常に細いので、つぼみの状態から下を向いています。花が咲いても下向きになります。花の中央部分が筒状になっていて、その周りにその色と同じ色の花びらが3枚ほど囲むようについています。
-

-
ヤマシャクヤクの育て方
ヤマシャクヤクは、ボタン科、ボタン属になります。ボタン、シャクヤク、ユリといいますとどれも女性に例えられる事がある花です...
-

-
オリヅルランの育て方
オリヅルランはユリ科オリヅルラン属の常緑多年草で、初心者にも手軽に育てられるため観葉植物として高い人気を誇っています。生...
-

-
ウスベニアオイの育て方
ウスベニアオイは、アオイ科の多年草で成長すると2mほどの高さにもなる植物で、直立した円柱形の茎に手のひらのような形をした...
-

-
クガイソウの育て方
クガイソウは、日本でも古くから知られていた植物で、昔の植物の書物にも載せてあるくらいですから、相当有名な薬草だったという...
-

-
メキャベツの育て方
キャベツを小さくしたような形の”メキャベツ”。キャベツと同じアブナ科になります。キャベツの芽と勘違いする人もいますが、メ...
-

-
アフェランドラ・スクアロサ‘ダニア’(Aphelandra ...
アフェランドラという植物は、熱帯や亜熱帯地域が生息地で、亜熱帯アメリカが主な原産地でその他にもブラジルなどに生息していま...
-

-
セイロンベンケイの育て方
セイロンベンケイというのは、ベンケイソウ科リュウキュウベンケイ属の植物で別名トウロウソウと呼ばれることがあります。ベンケ...
-

-
モラエアの育て方
アヤメ科モラエア属であるこの花は球根から育つ多年草の小球根類です。まだまだ謎の多い種類で植物学者や植物マニアの人達が研究...
-

-
ライスフラワーの育て方
ライスフラワーの特徴として、種類としてはキク科、ヘリクリサム属になります。常緑低木です。草丈としては30センチぐらいから...
-

-
カラジウムの育て方
カラジウム/学名・Caladium/和名・ハイモ、カラジューム/サトイモ科・ハイモ属(カラジウム属)カラジウムは、涼しげ...




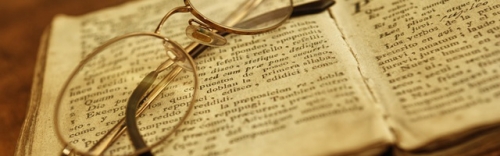





この植物に関しては多肉植物として知られています。一般的な花とはかなり異なるように感じていましたが、比較的身近な花の科に属します。ユリ科となりますから、ユリの仲間になります。茎の状態だけを見ると観賞用の葉っぱ、植物ですが、実際に花が咲くと当初とはかなり異なる様子になり、まさにユリ科の植物といえるような花が咲きますから問題はないでしょう。