パンジーゼラニウムの育て方

育てる環境について
パンジーゼラニウムの育て方で注意したいのは、水と湿気です。その土地の気候に応じて、室内で栽培するか、屋外で栽培するかを判断すると良いでしょう。高温多湿な気候の日本では、屋外で栽培していると傷みやすく、夏を越せないこともあります。
しかしエアコンで空調管理されている環境ならば、過剰な湿気の心配がありません。日当たりの良い室内の窓辺ならば、葉が光合成を行いますので、しっかりと栄養分を作り出せますし、花も美しく咲き揃います。屋外で栽培するのならば、軒下のように雨避けのできる環境が理想的です。
風通しが良い環境ならば、多少の雨に濡れてしまっても乾燥しますが、真夏のように高温になってしまうと、蒸された状態になるため注意が必要です。雨に濡れて、葉が溶けて腐ってしまうと、他の健全な葉にも影響してきますので、葉が溶けているの見かけたら迅速に摘出するように心がけましょう。
パンジーゼラニウムはゼラニウムとしての害虫忌避効果を備えています。乾燥気味に栽培していれば、害虫が寄り付きにくく、衛生的に生育できます。しかし葉が腐ったまま放置してしまっていると、小さな虫が繁殖してしまい、本来の良い芳香よりも、
強い悪臭を放ち始めてしまうこともありますので、日頃から手入れを欠かさないようにしましょう。室内で栽培しているのならば、天気が良い日に窓を開けて、鉢やプランターに風を当てるようにしましょう。株全体に風を当てることで、健康状態が良好になります。
種付けや水やり、肥料について
パンジーゼラニウムへの水やりは、細心の注意が必要です。土の表面が乾燥していないのであれば、水やりは行わないほうが安全です。水やりを行うときは、必ず土に水をかけるようにします。葉に水が掛からないようするのがポイントです。できれば茎や株元にも水が掛からないように、
あくまでも土そのものに対して水やりを行います。花が咲いたあとに種子を収穫することができますが、採取した種子は濡らさないように保存します。涼しい場所で保存した種子は、春になってから蒔きましょう。肥料は液体肥料が安全です。液体肥料は土に浸透して、
土の表面が乾燥しますので、健全に生育させやすいからです。もちろん緩やかに効くタイプの化成肥料も宵のですが、その場合は植え付け時に土の中に混ぜてしまっておくのが安全です。植え付け時、あるいは植え替え時のタイミングであれば、土の中に混ぜ合わせることが用意です。
夏が過ぎて秋から冬へと涼しくなる季節ならば、追肥として、株元に粒状の緩効性の化成肥料を置いておくのも良いのですが、肥料を与えすぎると根腐れの原因になることを覚えておきましょう。水やりの頻度が少なくても良いため、粒状の緩効性の化成肥料を、
置いておいてもなかなか溶けませんので、春から夏にかけては決して土の表面には置かないようにします。化成肥料の栄養分や、水やり直後の水分を求めて、夏は虫が寄ってきてしまうことがあります。夏を越すときは、乾燥しがちに土の表面を維持することが大切です。
増やし方や害虫について
パンジーゼラニウムを増やすときは、挿し芽が良いでしょう。挿し芽とは挿し木と同じ要領で行えます。伸びた茎を切り、土に挿します。挿す土は、雑菌が少ないほうが発根しやすいですし、病気になって枯れてしまうという心配がありません。栄養分の多い腐葉土よりも、
赤玉土や鹿沼土のほうが挿し芽は成功しやすいです。挿し芽で成功し、ある程度まで成長してから、腐葉土などの栄養分の多い培養土に植え替えます。挿し芽のまま栽培し続けるよりも、植え替えを行うことで、花を長く楽しめるようになります。ただし植え替えは、
年に一度だけに留めておくほうが無難です。パンジーゼラニウムの株は、植え替えには弱いからです。挿し芽で成長したものを植え替えるときも、最初の土をつけたままの状態で、根に直接触れずに済むように移植するのがポイントです。花が咲き終わったら花ガラを摘み取りましょう。
花ガラを放置しておくと、カイガラムシや小バエが繁殖してしまうことがあるからです。カイガラムシを放置していると、茎と葉が病気になりやすいです。ただし乾燥気味に土を維持していれば、土が菌に汚染されにくいので、しっかりと花ガラを摘み取り、
枯葉も適切に除去するように心がけていれば、安心して栽培できます。水やりの頻度が少なくて良いので、虫にとって好都合な水分が少ない土壌を維持できますので、害虫対策は比較的に容易なのが嬉しいポイントです。わりばしを使用すると、小さな花ガラ摘みは容易に作業できます。
パンジーゼラニウムの歴史
パンジーゼラニウムはフロウソウ科のテンジクアオイ属の植物です。品種改良によって、南アフリカ原産のトリコロル種とオウァーレ種を種間交雑種させたハーブです。別名はスプレンディッドゼラニウムです。スプレンディッドとは、華麗なという意味の言葉です。
華麗で美しく、まるでパンジーのような花が咲くゼラニウムという意味です。ただし品種改良によって、葉の形が野生種のゼラニウムとは大きく異なっています。南アフリカ原産の野生種は、17世紀以降のヨーロッパで人気となり、さまざまな交配による品種改良が盛んに行われてきました。
現在手は広く世界に生息地がありますが、基本的にはヨーロッパのイギリスとフランスが多く知られています。パンジーゼラニウムは、ゼラニウムと比較して耐寒性と耐暑性が弱いハーブです。しかし株いっぱいに花が咲きますので、野生種のゼラニウムや、
芳香性を高めたゼラニウムと比較すると、花の観賞用として重宝されるようになったハーブです。高温多湿な気候のアジアと比較すると、ヨーロッパは乾燥しやすく寒冷ですから、越冬に注意すれば容易に栽培できます。室内暖房が整備されているヨーロッパでは、
越冬されやすいため、好んで栽培されるようになりました。現在は、エアコンの普及によって温度と湿度の管理が行いやすくなりましたので、ヨーロッパ以外の地域でも栽培されるようになりました。日本では夏の高温多湿に弱いため、育て方には注意が必要です。
パンジーゼラニウムの特徴
パンジーゼラニウムの最大の特徴は、ゼラニウムの仲間でありながらも、ゼラニウムとは大きく異なる花と葉の形状です。花はパンジーに似ていることでも分かるように、名前の由来にもなっています。パンジーよりも小さめの花が咲き、ひとつの株にたくさん花をつけます。
茎が横方向へと伸びて分岐し、新芽が伸びて増えていくため、どんどん広がっていきます。下垂性ではないものの、ハンギングバスケットで栽培していると、横方向に伸びた茎と葉の重さで、自然に下へと下がっていきます。一株だけでも花をたくさん観賞できるのもポイントです。
葉は楕円形をしており、灰色がかった白い毛で覆われています。そのため常緑性の葉でありながらも、全体的に灰色がかった色彩に見えますので、落ち着いて感じられます。花の壮麗さと調和して、エレガントさを発揮しています。全体的に白い毛に覆われている葉は美しく、
パンジーのような花を、よりいっそう際立たせています。その一方で、葉を全体的に覆っている白い毛は水に弱く、葉を濡らしてしまうと傷んでしまうことが多々あるため、なるべく雨に当たらないように、屋外で栽培するのであれば軒下などに設置すると良いでしょう。
ヨーロッパは気候が乾燥しやすく、雨が降ってもからりと乾きやすいので問題ないのですが、日本は湿度が高いので雨に濡れてしまうと乾きにくく、傷みやすいです。窓辺に飾ると、とてもお洒落に感じられる雰囲気になります。
花の育て方など色々な植物の育て方に興味がある方は下記の記事も凄く参考になります♪
タイトル:センテッドゼラニウムの育て方
タイトル:ウチョウランの育て方
タイトル:アヤメの育て方
タイトル:ヒナゲシの育て方
-

-
テコフィレアの育て方
南米にはたくさんの野生生物が生息しているとされています。そのなかでテコフィレアという植物があります。テコフィレアは、テコ...
-

-
シラタマノキの育て方
シラタマノキは学名をGaultheriamiquelianaといい、ツツジ科のシラタマノキ属になります。漢字にすると「白...
-

-
ネギとミツバの栽培方法
ネギは中央アジア原産のユリ科の多年草で、白ネギ(長ネギ)と青ネギ(葉ネギ)・ワケギに大きく分かれており、古くから薬味とし...
-

-
セイヨウヒイラギの育て方
クリスマスなどによく見られるかわいらしい赤い実を多くつけるセイヨウヒイラギの花言葉は「神を信じます」「将来の見通し」「不...
-

-
アズマギクの育て方
アズマギクは東北地方、関東地方、中部地方を原産とする日本固有の植物です。キク科ムカシヨモギ属の植物で、植物の中でも最も進...
-

-
アジサイの育て方
アジサイは日本原産のアジサイ科の花のことをいいます。その名前の由来は「藍色が集まった」を意味している「集真藍」によるもの...
-

-
モモイロユキヤナギの育て方
花が散ると地面に砕いた米をまいたようになるので、コゴメヤナギとも呼ばれています。古来はこの花が岩のあるところを好み生える...
-

-
ペラルゴニウムの育て方
和名においてアオイと入っていますがアオイの仲間ではありません。フクロソウ科、テンジクアオイ属とされています。よく知られて...
-

-
かぼちゃの育て方
生息地はインドのネイル河沿岸やペルー、南アジアやアンゴラなど様々な説があったのですが、ここ数年の間に研究が進められ、中南...
-

-
ラムズイヤーの育て方
この植物は被子植物になります。双子葉植物綱になります。キク亜綱、シソ目、シソ科、イヌゴマ属となります。園芸上の分類として...




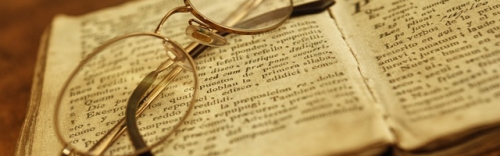





パンジーゼラニウムはフロウソウ科のテンジクアオイ属の植物です。品種改良によって、南アフリカ原産のトリコロル種とオウァーレ種を種間交雑種させたハーブです。別名はスプレンディッドゼラニウムです。スプレンディッドとは、華麗なという意味の言葉です。