ラケナリアの育て方

育てる環境について
栽培における環境ですが、生息地が南アフリカとのこともあり、暑さに強く寒さに弱い花と言えます。しかし花が咲くのは真冬ですから、管理の方法や環境の選び方が大事になりそうです。生育期においては十分日光を当てるようにします。この花の生育期としては、秋ごろから始まります。夏は休眠しているので土の中に球根がある状態です。
その後花が咲き、春頃になると徐々に散っていきます。夏の強い日差しを経験しませんから、置くときは常に日差しに向けるようにしても問題なさそうです。寒さには弱く、霜の当たるところでは栽培することはできません。そのため、通常は庭植えしないとされています。霜の発生しないようなところではベランダなどにおいて越冬させることも可能です。
通常は11月頃に室内に入れて管理をしていきます。室内でも窓際に置きます。日当たりが大事になります。暖かさが必要とのことで冬に暖房器具の近くに置くようなことがあるようです。また、暖房の空気が知らない間に直撃していたなどのこともあります。暖かすぎる環境はあまり良くありません。そうなると茎が弱々しく伸びてしまうことがあります。
適温としては10度から18度ぐらいとされています。5月頃に花が終わると休眠の準備に入ります。梅雨の前には入ることが多くなります。この時には植木鉢ごと涼しい日陰においておくようにします。南の地域と関東などでは育て方が異なるので、屋内か室内かを考える必要があります。
種付けや水やり、肥料について
育て方として良い用土としては、水はけと水持ちの両方を兼ね備えた土にします。赤玉土を5割、ピートモス3割、パーミキュライトを2割などにすると適度な土になります。更に通気性を考慮することがあります。もちろん栄養もあったほうが育ちは良くなります。赤玉土を6割、腐葉土を4割にすることがあります。
水やりは過湿を注意しながら管理していくことになります。あまり水分が多い状態だと球根が腐ってしまうことがあります。では乾燥に対してはどうかですが、乾燥に対しては比較的よく耐える植物です。表面が乾いたときに与えるタイミングでも大丈夫とされています。水やりの頻度に関しては季節によって微妙に変化させるようにします。
春頃に花が終わってくると葉が黄色くなってきます。これは休眠のサインになりますから、徐々に水やりの回数を減らすようにしていきます。完全に休眠に入る夏においては水分を一切与える必要はありません。夏に水分を与えない珍しい植物ですが、水のかからないところで管理しなければいけません。
秋に萌芽してきたら水やりを開始し始めます。肥料については植えつける際に入れるようにします。ゆっくりと効くタイプの肥料を混ぜ込みます。追肥に関しては開花のときに行います。液体肥料を2千倍ぐらいに薄めたものを2週間に1回与えます。最初や花が咲いた時以外においてはそれ程肥料を必要としません。球根の状態によっても異なるので、肥料の量を調整します。
増やし方や害虫について
増やし方として取ることが出来るのが球根を分ける方法です。親の球根の回りに自然に子珠が増えます。里芋は親芋に子芋がたくさんついた状態になりますが、まさに子芋のようについてきたら親球から子球を外して貯蔵をしておいて、秋ごろに植えつけるようにします。植え付けの方法としては秋咲きの場合は9月ごろに行います。
そして冬から春に咲くタイプになると10月頃に植え付けを行うようにします。5号の植木鉢であれば小さな球根であれば5つぐらい植えることが可能になります。大きい球根で3つぐらいを植えることができます。この時の植え方としては、球根が隠れるくらいの浅植えです。しっかりと埋めてしまう方法ではありません。
芽が出るまでは日陰で管理するようにします。水やりについてはあまりしないですが、極端に乾かさないようにすればいいでしょう。発芽し始めたら十分に日光に当てながら育てるようにします。植え替えを頻繁にしたほうが良いとされています。それは球根が腐りやすいためです。水の与え方を少し間違えるとそこから腐らせてしまいます。
また、土の状態や球根の状態を確かめるためにも毎年植え替えるぐらいだときれいな花を咲かせ続けることが出来るかもしれません。病気や害虫に関してはあまり付きませんが、根腐れには十分気をつけるようにします。花が終わったあとには花がら摘みを行うようにします。花の茎の先端まで小花が咲いたら、茎を付け根から切り取ります。
ラケナリアの歴史
花をプレゼントするときに、カーネーションなら母の日の定番の花になります。その他お祝いなどではきれいなバラの花などを贈るのも定番として知られています。お店においてはコチョウランなどを贈ることがあるかもしれません。花束として贈ることもあれば、少し育てた状態であったり、鉢植えなどの状態で贈ったりすることもあるでしょう。
その時には花言葉などがぴったり合うものを贈るようなことがあります。ラケナリアと呼ばれる花があります。花束として使うよりも植木鉢などで育てることが多い花です。この花については、花言葉としては変化を意味することが多く設定されています。変化、移り気、そのほか継続するなどもあります。
誕生花としても設定されていて、冬に咲くことが多いことから主に冬の日に多く設定されています。1月12日や1月18日などに設定されているようです。原産としては南アフリカのケープ地方とされています。アフリカ南部ですから比較的暖かいところといえるでしょう。日本にはいつ頃渡来してきた花かですが、昭和の初期頃に渡来してきたとされています。
南アフリカといいますと非常に遠いように感じ、昔には伝わっていないと考えてしまうことがありますが、実際のところは明治や大正などにもどんどん入ってきています。しかしこの花については昭和ですから少し遅れての渡来になります。咲く時期に特徴があることから人気がある花としても知られるようになっています。
ラケナリアの特徴
特徴としてはまずは分類があります。キジカクシ科とされることがあります。その他ユリ科、ヒアシンス科とされることもあります。この花の別名としてはアフリカヒアシンスと呼ばれます。ヒアシンスに似ていることからそのようについたのかもしれません。園芸上の分類としては草花で、球根で育つタイプになります。
咲き方としては多年草になります。草丈としては15センチから30センチとそれ程高く育つ花ではありません。花が咲くじいは主に10月下旬から5月上旬とされています。晩秋から冬、そして春の終わりぐらいまで非常に長く楽しめるようになっています。しかしある程度の差はあります。花の色が豊富です。鮮やかな色が多いと言えそうです。
白、赤、オレンジなどから、紫や青色などの涼しげな色まであります。複数の色が混ざっているタイプもあります。この花は耐暑性は高いとされています。多年草ですが、実際は夏は休眠状態に入ります。活動をしないので、それ程暑さなどの影響を受けません。寒い時期にかけて咲く花になりますが、耐寒性としては少し弱いとされています。
落葉性なので、毎年花がついたり散ったりします。花の付き方としては花茎が1本から数本出てきて、その周りに釣鐘型の花が穂状に付きます。花茎がこの花の高さとなります。花は上向きではなく横向きに付きます。花については基本的には横に水平に花びらが伸びるタイプが多いですが、斜め下に垂れ下がるように咲くタイプもあります。
-

-
緑のカーテンを育てよう
ツルを伸ばし、何かに巻き付く性質を持つ植物で作る自然のカーテンのことを「緑のカーテン」と言います。直射日光を遮ることがで...
-

-
エスキナンサスの育て方
エスキナンサスとは、イワタバコ科の観葉植物です。半つる性で赤い花をつけるこの植物は、レイアウトをすることで、南国風のエキ...
-

-
コバイモの育て方
コバイモは本州中部から近畿地方の山地に多く自生している植物で、原産国としては日本であるとされているのですが、その生息地は...
-

-
ウスベニヒゴスミレの育て方
ウスベニヒゴスミレはガーデニングでも適した植物と言われていて、専門家も性質も強く園芸的にも優れていると太鼓判を押している...
-

-
クリサンセマム・パルドーサムの育て方
クリサンセマム・パルドーサム(ノースポール)は、キク科フランスギク属に分類される半耐寒性多年草です。ただし、高温多湿に極...
-

-
ニワゼキショウの育て方
特徴としては、被子植物、単子葉類の植物となります。キジカクシ目、アヤメ科になります。花の季節としては5月から6月とされま...
-

-
キリンソウの育て方
キリンソウとは、ベンケイソウ科に属している多年草のことです。生息地は、シベリア東部や中国、朝鮮半島などが挙げられます。タ...
-

-
ミツバツツジの育て方
枝先に3枚のひし形の葉をつける落葉する種類を、一般的なミツバツツジの種類と呼んでいます。紫色の野趣あふれる花を咲かせます...
-

-
ニガナの育て方
ニガナはキク科の多年草で、原産地及び生息地は日本や東アジア一帯ということで、広く分布している植物でもあります。日本でも道...
-

-
シバザクラ(芝桜)の育て方
シバザクラは北米を原産とするハナシノブ科の多年草です。春先にサクラによく似た可愛らしい花を咲かせますが、サクラのような大...




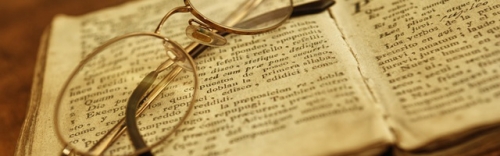





特徴としてはまずは分類があります。キジカクシ科とされることがあります。その他ユリ科、ヒアシンス科とされることもあります。この花の別名としてはアフリカヒアシンスと呼ばれます。ヒアシンスに似ていることからそのようについたのかもしれません。