ニゲラの育て方

ニゲラの育てる環境について
南ヨーロッパ原産の耐寒性の一年草なので、水はけの良い日向が適しています。気候としては、やや乾燥気味の場所が適しています。用土には水はけと通気性の良いものを使います。保水力が適度にあると水やりの手間が省けて便利です。市販の草花用の培養土を使うか、
もしくは自分で小粒赤玉土:腐葉土:軽石=5:3:2の割合で作った混合土を使うと良いです。暗くしないと発芽しない暗光性の種子のため、種をまいた後はしっかり覆土するようにします。覆土が十分でないといつまでも発芽しないので、足りないようであれば再度覆土するようにしましょう。
ニゲラは移植を嫌う植物なので、なるべく移植をしないで済むような工夫を施すと成功率が高くなります。セルトレーやジフィーセブンなどの園芸用品を使えば、根を切らないで育苗することが可能です。暖かい地域には秋に植え付けを行います。心配ならば霜よけをしておけば良いです。
植え付けた後は剪定や切り戻し、花がら摘みなどの作業がほとんど不要なので、育て方は比較的優しいです。ニゲラをアレンジして育てる場合には、自然風の花壇に植え付けてあげると良いです。変わった形の花ですが、どことなく野性味のある姿をしているので、
自然風の花壇に植えてあげるとよく映えます。かえって整然とした花壇に植えてしまうと面白みがなくなるので、少々荒れた感じの花壇に植えてあげると良いでしょう。
敵地ならば、放任しても育ってくれます。
ニゲラの種付けや水やり、肥料について
種まきは9月上旬〜10月下旬にかけて行います。直まきか、もしくはポットまきにします。ポットまきで秋に蒔いた場合には、10月上旬〜11月下旬に大きくなると生育不良になる可能性があるので、花壇やコンテナに移植するようにします。大きさを見分けるには、土の硬さで見分けます。
しっかりと育っていると根が張って土が崩れてきませんが、まだ小さい段階だと土がポロポロと崩れてきます。まだ崩れてくるようであれば、移植には早いので引き続き鉢で育てるようにします。だいたい3月中旬〜4月下旬にかけて植え替えると丁度良いでしょう。
花壇に直まきする場合にはもっと楽です。苗の生育状況を見なくても勝手に育ってくれるからです。水やりをするときには、鉢植えの場合には土が乾いたらあげるようにします。なるべくたっぷり目に与えて構いませんが、過湿状態だと根が軟弱になったり、
根腐れを起こすことがあるので調整します。庭植えの場合には、根が張った後は特別水やりの必要はありません。カラカラに乾燥したとき以外は降雨に任せてOKです。肥料は用土の元肥として、緩行性の化成肥料を与えます。ポットで生育するときには、
緩行性の化成肥料か、もしくは液体肥料を定期的に追肥として与えてあげれば良いです。花壇植えの場合には元肥は与えますが、追肥はしなくても大丈夫です。肥料が多すぎるとかえって植物全体が軟弱に育ってしまうことがあるので、庭植えでは追肥は与えないようにしましょう。
ニゲラの増やし方や害虫について
増やし方は種まきで増やします。9月上旬〜10月下旬に直まき、もしくはポットにまきます。暗くないと発芽しにくい暗光性の植物なので、たっぷりと覆土するようにします。
害虫はアブラムシがつくことがあります。特に多いのは春〜秋にかけてで、
茎や葉っぱに体調3mmほどのアブラムシが群生してしまうことがあります。群生してしまうと駆除が厄介なので、少数でも見つけたらすぐに潰すようにします。少数のうちは捕殺すれば済みますが、それよりも増えてしまった場合には駆除用の薬剤を散布するようにします。
アブラムシが発生しやすいのは、風通しが悪いときと窒素が多すぎるときです。窒素はリン、カリ、と並ぶ植物の成長に必要な3大栄養素の一つですが、多すぎると葉っぱが大きくなりすぎたり、アブラムシがつく原因になります。庭に直植えの場合には元肥だけで追肥は基本的にはしませんが、
ポット植えだと追肥で窒素過多になってアブラムシがついてしまうことがあるので、十分ん注意しましょう。アブラムシの発生を防ぐためには、風通しの良い場所を選び、肥料による窒素過多に陥らないように管理してあげるのがポイントです。
根が張ってしっかりと植え付け作業が完了すれば、その後はあまり手をかけなくても育ちます。花がら摘みをしなくても風通しの良いところに置いてあげれば湿度を調整出来ます。病気もこれといって大きな心配がないので、アブラムシにだけ注意しておきましょう。
ニゲラの歴史
地中海沿岸から西アジアが原産の一年草の植物です。ニゲラの仲間はおよそ15種類がこの場所を生息地としています。この中でもニゲラという名前で普及しているのはクロタネソウ(ニゲラ・ダマスケナ)という品種です。ダマスケナは南ヨーロッパに広く分布しており、
秋に種をまいて、翌春に花を楽しむ一年草として扱われます。日本に入ってきたのは江戸時代の末期と言われています。現在では露地栽培、鉢植え、ドライフラワー、などとして利用、加工されています。品種改良された種類もあり、花が原種よりも濃いものや、
八重咲きで草丈が低いもの、大輪の花を咲かせるもの、などの園芸品種があります。ニゲラの名前の由来は、ラテン語のニガー(黒い)が由来です。これは、ニゲラの種が黒いことからつけられたとされています。英語名では「霧の恋人」という意味でlove-in-a-mist(ラブ・イン・ア・ミスト)や
「茂みの中の悪魔」という意味でdevil-in-a-bush(デビル・イン・ア・ブッシュ)などと呼ばれることもあります。前者の「霧の恋人」というのは、ニゲラが細かい苞片に包まれていることからきています。後者の「茂みの中の悪魔」は、
果実のときに先端にツノ状の突起が出てくることからきらイメージです。日本ではもっぱら観賞用としてのイメージが強いですが、インドではスパイスとして種が使われることもあります。そのほか、種に含まれているアルカロイドや揮発性の油を使い、薬に使うこともあります。
ニゲラの特徴
和名は黒種草(クロタネソウ)で、キンポウゲ科クロタネソウ属の草花です。花のように見えるのは萼片と呼ばれる場所で、花弁ではありません。萼片の色は白、青、薄紅色などで、苞の糸状の葉っぱが花を包み込むようにして咲きます。花弁は進化の過程で退化しており、
目立ちませんが、品種改良された八重咲きの種では花弁も萼片のように発達しています。市場に出回っているのは南ヨーロッパ原産のクロタネソウ(Nigella-demascena)という品種が多いです。秋に蒔くと4月下旬〜7月上旬にかけて花を咲かせてくれます。
一年草なので枯れてしまいますが、花壇や切り花にも使われます。5月の誕生花でもあり、花としては珍しい青色が特徴のため、贈答用としても使われます。花が終わると果実が大きく発達します。この時期に素早く収穫し風通しの良い日陰で乾燥させておけば、
ドライフラワーとして使うことも出来ます。果実の中に含まれている種は香り付けとして使うことも可能です。バニラのような香りがします。ちなみに、インドではカレーのスパイスとしてニゲラの種が使われることもありますが、これはニゲラ・サティば(Nigella-sativa)と呼ばれる品種で、
ブラッククミンと呼ばれています。日本ではほとんど栽培されていないので、手に入りにくいです。ニゲラは暑さにはあまり強くありませんが、耐寒性が強く開花期が長いので、初心者でも比較的育てやすいです。
花の育て方など色々な植物の育て方に興味がある方は下記の記事も凄く参考になります♪
タイトル:フヨウの育て方
タイトル:ヒメヒオウギの育て方
-

-
ハベナリアの育て方
ハベナリアはラン科の植物で、草丈は15cmから60cmほどになります。洋ランの中でもその品種が非常に多い植物でもあります...
-

-
ディケロステンマの育て方
ディケロステンマは原産が北アメリカ西海岸のワシントン州西部からカリフォルニア州中部に分布しています。別名をブローディア・...
-

-
アストランティア・マヨールの育て方
アストランティア・マヨールは、中央・西部ヨーロッパが原産のセリ科の宿根草で、生息地は主にヨーロッパからアジアの西部にかけ...
-

-
スターフルーツの育て方
スターフルーツは南インド等の熱帯アジアを原産としているフルーツです。主に東南アジアで栽培されている他、中国南部や南アメリ...
-

-
ポテンティラの育て方
この花の科名としてはバラ科になります。キジムシロ属、ポテンティラ属ともされています。あまり高くまで成長することはなく、低...
-

-
金時草の育て方
金時草は学名Gynura bicolorと呼ばれています。金時草の名前の由来は、葉の裏面の色が金時芋のように美しい赤紫色...
-

-
アスパラガスとスイゼンジナの栽培方法
まずはアスパラガスの育て方を説明します。保健野菜で有名なアスパラガスには、缶詰用のホワイトと生食用のグリーンとの二種類が...
-

-
ポーチュラカリアの育て方
特徴としてどういった種類に属するかですが、カナボウノキ科であったりスベリヒユ科とされています。木の大きさとしては植木鉢な...
-

-
あじさいの育て方
あじさいといえば知らない人はいないほど、梅雨の時期に見られる代表的な花です。紫陽花科(ユキノシタ)科の植物で6月から7月...
-

-
ギンバイカ(マートル)の育て方
ギンバイカはフトモモ科ギンバイカ属の低木常緑樹です。ギンバイカは和名になり、漢字では「銀梅花」と書きます。これは開ききる...




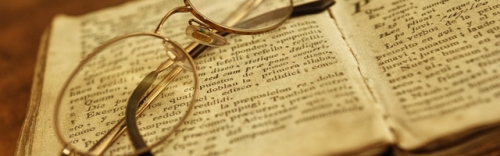





地中海沿岸から西アジアが原産の一年草の植物です。ニゲラの仲間はおよそ15種類がこの場所を生息地としています。この中でもニゲラという名前で普及しているのはクロタネソウ(ニゲラ・ダマスケナ)という品種です。