クランベリーの育て方

クランベリーの育てる環境について
育てる時の栽培環境ですが、これは庭に植える場合でも、室内で鉢植えのする場合でも、共通のコツがあります。太陽の光は大事ですが、バランスを大切にした日照を心がけることです。午前中のうちは、出来るっ限りお日様の光がポカポカと当たる場所にあることが望ましいいです。
そして午後になったら、今度は明るさはあるものの、木陰のゾーンとなるような場所が良いです。太陽は1日をかけて移動していきます。庭に植えるときには、そんな太陽の動きにも着目して、ちょうどよさそうな場所に植えてあげることです。
鉢植えで室内沖する場合も、午前はよく陽に当たる場所において、午後からは明るくて日陰という場所になるような、ナイスなスペースに置くことです。 基本的に耐寒性には強く、耐暑性には弱いという特徴があります。程よい温かさは必要ですが、寒過ぎは向いていません。
寒すごるのは向いていないものの、涼しいい環境は好きなshく物です。強い西日には、少し弱いという面もあります。半日は日陰で過ごすのが、植物としても快適な過ごし方です。涼しくて快適な、風通しのよい、おひさまのある場所での栽培がよいでしょう。
関東以北の環境が比較的向いている植物ではありますが、九州などでも栽培することはできます。庭に植えたり、プランターで育てたりと、かなり広く楽しむことができるものです。自家結実性をもちますから、1本だけの木であっても、ちゃんと実をつけることができます。
種付けや水やり、肥料について
植えつけや植え替 えをしたいと思ったら、時期は2月の中旬から3月の中旬が、ベストなシーズンになります。植え替えを行うことには、それなりの理由があります。まずは、なんといっても根詰まりを防止するためです。もう一つは、健康的にスクスクと育つように、通気性をよくするためにも行うことです。
生育の状態もよく観察をしながら、使用する鉢の大きさなどとも相談します。そのうえで、2年に1回くらいのペースで行うことが大事です。鉢植えの用土ですが、水ゴケであったり、鹿沼土などの等量配合土、酸度未調整のピートモスなどを用いて植え付けを行います。
プランターや鉢だけではなく、庭に植えているものに対しても、用土は関心を持ちたいところです。鹿沼土であったり、酸度未調整の水ゴケやピートモスを使 用するのが良いでしょう。状態としては、水はけをよくしておくことも大切になります。水はけは良いながら、それでいて水もちも良いという、
育つのにも適切な状態の環境を整えてあげることです。植え付けの時には、できるだけベストな状態を作って、快適に成長できるように見守ってあげましょう。国内で趣味レベルでの栽培は、庭や鉢で控えめに楽しめるものです。しかし海外に行くと、クランベリー農家なるものが存在します。
ウェイダーズスタイルというのを聞いたことがあるかもしれないですが、そのスタイルは、彼らの誇りでもあります。クランベリー農家の栽培環境は、壮大なものです。水やりは、土の乾きを見てあげましょう。肥料は、庭植えの場合は、速効性化成肥料か有機質肥料を、2月くらいに施しましょう。
増やし方や害虫について
育て方として気になってくるのは害虫ですが、素晴らしいことにクランベリーには、これといってトラブルを引き起こすような害虫はないというナイスポイントがあります。通常は、何かしらの病気や害虫に悩みますから、そういった心配が不要になります。
クランベリーの増やし方としては、挿し木するのも簡単です。増やし方として株を考えたとき、時期は2月の中旬 から下旬にかけての期間で、株分けをするとよいでしょう。そのあと、3月になってからか、梅雨のシーズンに、さし芽で徐々に増やしていくこともできます。
その年に芽吹いた新しい目の部位を、少しだけカットしておきます。この時真っ直ぐではなく、少し斜めに切っておくと良いです。水揚げのために水に1時間くらいつけておきます。プランターの場合、さし木ようの土も販売しています。栄養豊富な用土に挿すと良いです。用土に挿したら水をあげます。
挿し木は、誰でも作業しやすい方法です。種では増やすのが大変な品種ですとか、観葉植物やハーブにも用いられる方法です。クランベリーは、土が基本です。挿し木自体は、土以外に挿す方法もあります。水挿しや茎挿し、葉挿しなどもあります。
葉挿 しというのは、葉っぱを挿して増やしていくやり方です。水挿しの場合は、観葉植物のポトスなどで、よく使われる方法です。水を良い状態にキープするのがコツになります。植物の挿し木をする時には、土はできるだけ新しい、栄養分も豊富な土を使うことです。
クランベリーの歴史
クランベリーという洒落たネーミングは、可愛らしい花びらの形状を見て、鶴の頭部と同じようなイメージであることから付けられたものです。鶴は英語ではクランといいます。アメリカであっても、先住民部族によって違いがあるものの、昔はクランベリーと呼ばれる以外にも、
様々な呼び方をされていたものです。アトカとかイビミ、サッサマネシなど、いろんな呼び方で愛されていました。北米大陸を原産とするクランベリーは、そのあたりの地域を生息地とし、海外の特にアメリカではなじみの深いものとして、古くから愛されてきました。
日本においては、それほど馴染みはないものの、目にすれば形状のキュートさに、心も温かくなるような印象です。北米 大陸での栽培としては、やわらかな砂質がある湿地帯で成長します。これは、ボクという砂質です。
つる性でトゲも持つ植物というのは、まるで地面をはっているかのように伸びていくもので、この植物も同様に地面を這うように伸びます。しかし、ただ伸びるだけではなく、真っ赤な実を、たわわに付けてのことですから、目を引くこと間違いなしの光景です。長い歴史の中で、この美しい状態は、
湿地のルビーとも呼ばれるようになりました。アメリカ先住民は昔、食用としても使用していましたし、染料にも使っていました。今とは意識が異なる点といえば、昔は医薬品として使われていたということです。航海中はビタミンC不足になるため、100年間にわたり、壊血病予防として利用をされたものです。
クランベリーの特徴
北米三大フルーツでもあるクランベリーは、鮮やかな小さな実が特徴的です。鑑賞してもキュートなものですが、その可愛らしい果実には、栄養成分も豊富です。ポリフェノールやキナ酸、プロアントシアニジンなどの、高い栄養素を成分として含んでいるのも特徴です。
尿路感染症であったり、むくみなども改善するとして、効果が期待されるものです。女性にとっては嬉しいことに、美肌効果もあると言われています。健康効果にも優れていて、生活習慣病も予防する作用もあり、歯周病予防の効果まで発揮するという優れた果実です。
美意識が高い女性にとって、関心が高くなる栄養成分を持っていますが、むくみにも効果があるのは、女性にとって気になるポイントです 。プロアントシアニジンという成分が含まれており、この成分は腎臓の機能を、より活発にしてくれるものです。
肝臓がスムーズの活動しますから、むくみ解消にも役立つことになります。体の中に溜まった不要な水を、外へと排泄させるのが腎臓の働きです。プロアントシアニジンの成分は、腎臓機能を健やかな状態で維持する作用があります。むくみの原因は血行の悪さもありますが、そんな滞りも解消させてくれます。
足にむくみが出がちな女性には、知っておいて損はない情報でしょう。クランベリーは、ツツジ科であり、つる性の果樹ですから、お気に入りの鉢に植えて、部屋に置いても良いインテリアのような感じになります。実をつける時期になったら、毎日見るのも楽しみになってきます。
果樹の育て方など色々な植物の育て方に興味がある方は下記の記事も凄く参考になります♪
タイトル:グーズベリーの育て方
-

-
植物の育て方はある三つを守れば枯れない?
植物を育ててみたいけれども育て方が分からないから枯らしてしまうかもと悩んでいる方、植物は水の量、どのくらいあげればいいの...
-

-
カラジウムの育て方
カラジウム/学名・Caladium/和名・ハイモ、カラジューム/サトイモ科・ハイモ属(カラジウム属)カラジウムは、涼しげ...
-

-
クロウエアの育て方
クロウエアはオーストラリア島南部原産の、ミカン科クロウエア属の常緑小低木です。クロウエアの名は、イギリスの植物学者・園芸...
-

-
シクノチェスの育て方
シクノチェスはラン科の植物で独特の花を咲かせることから世界中で人気となっている品種で、15000種以上の品種があるとされ...
-

-
サクラソウの育て方
サクラソウとは、サクラソウ科サクラソウ属(プリムラ属)の植物で、学名をPrimula sieboldiiといいます。日本...
-

-
ゴンゴラの育て方
花の特徴としては、ラン科になります。園芸分類はランで、多年草として咲くことになります。草の丈としては30センチ位から50...
-

-
フリーセアの育て方
フリーセアとは、ブラジル等、熱帯アメリカ原産の、パイナップル科の植物です。有名な生息地はブラジルですが、この他、中央アメ...
-

-
コリゼマの育て方
オーストラリア原産の”コリゼマ”。まだ日本に入ってきて間もない植物になります。花の色がとても鮮やかなオレンジ色をしており...
-

-
ミヤマホタルカズラの育て方
ミヤマホタルカズラはヨーロッパの南西部、フランス西部からスペイン、ポルトガルなどを生息地とする常緑低木です。もともと日本...
-

-
栽培植物の上手な育て方
お部屋の片隅にある花瓶に一輪の花が挿してあります。たったこれだけのさりげない光景なのに、どんなに心を癒してくれるでしょう...




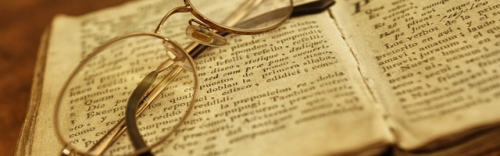





クランベリーという洒落たネーミングは、可愛らしい花びらの形状を見て、鶴の頭部と同じようなイメージであることから付けられたものです。鶴は英語ではクランといいます。