プルネラの育て方

プルネラの育て方
プルネラは初夏から夏にかけての時期に紫色や白、赤紫色、ピンク色などのたくさんの花を咲かせ、大変見ごたえのある花です。暑さや寒さにはとても強い植物で、冬になると霜にあたって地上部分は枯れますが、春にはしっかり芽吹いて毎年花を咲かせる多年草です。
大変丈夫で育てやすいのが特徴ですが、夏の湿気の多い気候には弱く、蒸れて枯れてしまうことがあります。そのため夏は水やりを控えるようにして、過湿を避けるようにすることがとても大切です。しっかりと過湿を避けるようにすれば、十分夏越しが可能な植物です。
梅雨の時期や秋の長雨の時期には、軒下においておくのもおすすめです。ただし、土の質や育成環境などによっては、長雨にあたってしまうと必ず枯れてしまったり全滅してしまうとは限りません。湿気の多い環境で蒸れると葉が黒く変色してしまい、コバエがたかるようになります。
鉢植えにする育て方の場合は土が乾燥していたら水を与えるようにします。あくまでも土の表面部分が乾燥して白くなってから水を与える程度で十分で、乾燥気味の育て方をするのが向いています。栽培に関しては水をやり過ぎないことが重要です。
庭植えにして栽培するときには植え付けた直後の1週間ほどの間はしっかりと水を与えるようにしますが、その後は自然に雨が降って水分が与えられるだけで大丈夫です。土が乾燥しているようであれば、ごくたまに水をあげるようにします。
春になって芽が動き出すころから開花する前と、秋になったら、窒素、リン酸、カリなどが等量の配合肥料などを少量施肥するようにします。ただし肥料が多すぎると株の姿が乱れてしまうので、肥料の与えすぎには注意するようにします。庭植えなどの場合は特に施肥の必要はありません。
盆栽のように小さく小ぢんまりと栽培する場合には肥料は特に与えなくても大丈夫です。花が終わってきたら花を摘むようにします。種付け用に種を取ろうとすると、次の花が咲きづらくなるし、花を摘むことによって脇芽が出てきて株自体が大きくなってしまいます。
プルネラの増やし方
種付けでも増やすことができますが、一般的には春か秋に市場に出回っている苗を購入し植え付けをします。用土は市販されている花と野菜用の土で植え付けを行うようにします。赤玉土が6割、腐葉土が3割、パーライトを1割混ぜたものを自分で作ってみてもよいのですが、この割合のものが販売されているので、購入したほうが便利で簡単です。
植えつける場所の土に粒状の肥料を混ぜ込んでから苗を植えるのがおすすめです。また、プルネラは挿し木でも簡単に増やすことができます。気に入った花色が咲いたら挿し木で増やしてみることもできます。挿し木の時期は初夏のころと、初秋から秋にかけての季節に行うようにします。
茎を2節ごとに切りそろえ、切り口を30分間ほど水につけてから、挿し木用の用土にさします。この時に切り口に植物成長調整剤をまぶしておくようにすると、発根が促進されます。約4週間ほどでポットへ植え替え、ポットに根がいっぱいに広がったら、花壇や好みの鉢などに植え付けるようにします。
種付けでも増やすことは可能なのですが、7月から8月にかけて種を取り、種付け時期としては桜の花が開花するころから行うようにします。順調に成長すれば2年目には開花します。栽培は日当たりで管理するようにします。日当たりの悪い場所で日光が不足すると花付きが悪くなり、成長にも影響します。
一年を通して日当たりの良い風通しの良い、できればある程度開けた場所に植える育て方をするのが理想です。夏は明るい日陰でも大丈夫ですが、水はけの良い土を好むので、庭植えにする場合でも、雨が降った後に水たまりになるような場所でなければ、乾燥しがちな場所であっても十分に生育します。
鉢植えの場合は毎年植え替えを行うようにします。植え替えの時期は2月から3月の芽が出る少し前の時期か、あるいは6月から10月上旬に行うようにします。植え替えと同時に株分けで増やすこともできますが、その際にはあまり小さく分けず、一株を2個から3個に分割するようにします。
プルネラの栽培で注意したい病気と害虫
水はけの悪い土に植え付けると立枯れ病にかかる心配があります。立ち枯れ病になると日中はしおれるようになります。病気が進行すると下葉から黄色く変色してしまい、やがて株全体が立ち枯れを起こしてしまいます。病原菌は前年の被害植物や土の中で胞子や菌糸の状態のまま越年し、茎の部分から侵入します。
病原菌は土壌で繁殖するので、生育中に発生した場合には株を抜き取って処分するようにします。また、土が長時間湿ったままの状態にならないよう、水の与え具合をコントロールすることが大切です。プルネラはバッタの食害があるので、見つけ次第捕殺するようにします。また、ハダニが付くことがありますが、重症化してしまうのはごく稀です。
プルネラの歴史
北アメリカやヨーロッパなどに自生するシソ科の植物で、別名西洋ウツボグサと呼ばれています。日本でもプルネラの仲間でウツボグサと呼ばれる種類が自生しており、西洋ウツボグサに比べると、草の丈が高いのが特徴で、見た目はヒョロヒョロした印象を受けます。
この名前のウツボは海の中に生息するウツボではなく、弓矢を入れるかごの事です。時代劇などで弓を引く人が背中に背負って弓矢を入れている入れ物の形が、プルネラの花の形と似ていることからウツボグサと呼ばれるようになりました。
暑さにも寒さにも強く、花壇やグラウンドカバーとして栽培されています。ヨーロッパから中国東北部から朝鮮半島の小アジアの草原などが原産地で、そのほかにもミヤマウツボグサ、オオバナウツボグサ、タイリンウツボグサ、ヤクシマウツボグサ、ヒメウツボグサ、紅花姫ウツボグサ、キクバウツボグサなどの名称で呼ばれる種類があります。
ウツボグサの基準亜種がプルネラ・ブルガリスと呼ばれる種類で、生息地はヨーロッパから西アジア、中央アジア、中国と北アフリカの温帯地域、や亜高山帯に広く分布しており、花はやや小さめで直径が1.3センチメートルほどです。日本のウツボグサ同様に、白い花やピンクなどの色変わり品種や斑入りの品種などがあります。
プルネラの特徴
海岸近くから高原の日当たりの良い草原や道端などが生息地として見られ、根元は少し這うように育ちますが、上部はまっすぐに立ち上り、株立ちになって、茎の先端部分に花をつけます。花穂の大きさは3センチから5センチ程度で、整然と並んだ蕚の姿が、松ぼっくりに似ているような形になるのが特徴です。
花一輪の寿命は2日から3日ほどとそれほど長くありません。花の色は通常は紫色が多いのですが、白や薄いピンク色の花なども見られます。楕円形の短い柄のある葉が対になって付きます。ランナーを出して増える特徴がありますが、あまりたくさん出ることはありません。
プルネラは初夏から夏に多くの花を咲かせます。丈夫で花壇や法面を覆うように育つので、グランドカバープランツとしての役割も果たします。株は毎年大きくなり、一年で直径が30センチメートルから40センチメートルほどを覆うように育ちます。
翌年にはさらにその倍くらいの大きさに生長し、いっぱいに花が付くと夏の暑さを忘れさせてくれるような見事な花畑になり、見る人をとてもさわやかで心地よい気分にさせてくれます。
-

-
オンシジウム育て方
オンシジウムの一種で特にランは熱帯地域で種類も多くさまざまな形のものが見られることが知られています。それらを洋蘭と呼び、...
-

-
マンリョウの育て方
江戸時代より日本で育種され、改良も重ねられた植物を古典園芸植物と称しますが、マンリョウもこのような古典園芸植物です。 ...
-

-
トマトの育て方について
自宅の庭に花が咲く植物を植えてキレイなフラワーガーデンを作るというのも一つの方法ですが、日常的に使う野菜を栽培することが...
-

-
センニチコウの育て方
熱帯アメリカが生息地の原産で、日本には江戸時代に渡来しました。江戸時代の初期に渡来して、江戸時代に書かれた書物にもその名...
-

-
ウツボグサの育て方
中国北部〜朝鮮半島、日本列島が原産のシソ科の植物です。紫色の小さな花がポツポツと咲くのが特徴です。漢方医学では「夏枯草」...
-

-
エゾギク(アスター)の育て方
中国や朝鮮が原産の”アスター”。和名で「エゾギク(蝦夷菊)」と呼ばれている花になります。半耐寒性一年草で、草の高さは3c...
-

-
ランタナの育て方
一つの花の中にとても多くの色を持つランタナは、とても人気の高い植物で多くの家の庭先で見かける可愛らしい花です。ランタナ(...
-

-
オオバハブソウの育て方
オオバハブソウはオオバノハブソウとも言われ、古くから薬用として珍重されてきた薬草です。江戸時代に渡来した当時は、ムカデ・...
-

-
チリアヤメの育て方
チリアヤメ(チリ菖蒲/知里菖蒲 Herbertia lahue=Herbertia amoena=Alophia amo...
-

-
植物の栽培とこの育て方とこの種まきのやり方
趣味としてガーデニング等をしている方々は大勢いますが、野菜等の栽培をしたり、この育て方やこの種まき等の知識を身につけるこ...




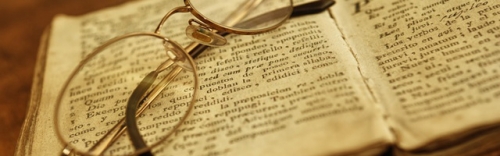





北アメリカやヨーロッパなどに自生するシソ科の植物で、別名西洋ウツボグサと呼ばれています。日本でもプルネラの仲間でウツボグサと呼ばれる種類が自生しており、西洋ウツボグサに比べると、草の丈が高いのが特徴で、見た目はヒョロヒョロした印象を受けます。