ハナカイドウの育て方

育てる環境について
日当たりの良い場所を好み、日当たりが悪くなると花をつけないことがありますから注意が必要です。強い西日は嫌います。できるだけ日当たりが良いような場所を選んで植えましょう。ハナカイドウの花を楽しむためには日当たりが最も重要です。植え付ける場所を間違えると、
ずっと花が咲きません。もしも花が咲かないと思ったのなら、別の場所に植え替えると、その場所で花を咲かせることもありますが、木にとってはあまり良いものではありませんから注意が必要です。これは木のそれぞれの部分についても言えることでです。
たとえば、木の下の枝には光が当たりにくいことがあります。このような場合にも花をつけなくなることがあります。木の全体に光が当たるような場所を選ぶとともに、剪定をするときには上の方を小さくするようにして、下の方にも光が当たるようにすると良いです。
半日くらい日陰になるような場所であっても育ちはしますが、花をつけないことがあります。一日中光の当たる場所を選びましょう。冬の寒さについてはかなり強いですから、防寒にはあまり木を配らなくて良いです。土壌としては水はけの良い肥沃な土壌を好みますから、
植え付けるときにはたっぷりと肥料を与えるとともに、追肥を行っていきます。地植えをすることが多いようですが、鉢植えで栽培することもできます。鉢植えをするときにも基本的には同じで、水はけの良い土壌で肥料が十分にある土壌を用意すれば良いです。
種付けや水やり、肥料について
落葉している時期に植え付けを行うのが基本です。日本の多くの地域では2月頃が最も適しています。ただ、寒い地域であれば、この時期には地面が凍っていたり、あるいは雪に覆われていたりすることが多いですから、このような地域には春に植え付けると良いです。
苗木は接ぎ木をしていることが多いですから、ついである部分を確認します。たいていは根元の部分にあります。長い苗木は半分くらいに切って植え付けます。そして、ついである部分が埋まるくらいまで土をかぶせます。少し大きく成長しているものも、枝を半分くらいに切ります。
植え付けは浅めにするほうが良いです。根の上部が土よりも上にくるくらいが良いです。浅いですから根が張るまでは倒れやすいです。倒れそうだと思ったら支柱を立てると良いです。植え付けた後にはたっぷりと水を与えます。地植えの場合には、その後は水やりをする必要はありません。
残暑などで暑さが続き、雨がなかなか降らない日が続いた場合には水をやった方が良いですが、それ以外は水やりをする必要はありません。鉢植えの場合には土の表面が乾いてから水やりをすれば良いです。肥料は植え付けの際に混ぜておくのが基本です。
肥沃な土地を好みますから、多めに与えておくと良いです。追肥は年2回くらい与えます。2月と8月とが適してます。一般的な化成肥料とともに、骨粉を加えておくと放つ気が良くなります。鉢植えにするときには、花が咲いた後にも肥料を与えると良いでしょう。
増やし方や害虫について
ハナカイドウは接ぎ木で増やすのが基本です。挿し木はほぼ無理です。接ぎ木で増やす場合には台座となる木が必要となります。カイドウの接ぎ木に用いるのはズミです。ズミはリンゴの接ぎ木をする台座として用いられることもありますから、入手しやすいです。
接ぎ木に適した時期は3月ごろです。なお、実ができた場合には種で育てることができる場合がありますが、種で育てると異なるものができる場合があります。接ぎ木で増やせば確実に同じものを増やすことができます。これは、接ぎ木はクローンのようなものだからです。
人間でも親と子は似ていても全く同じではないように、種で増やすと異なるものが現れることもあります。良い花をつける木を増やすためには、やはり接ぎ木が適しています。ハナカイドウは病気にかかりやすいですし、害虫もつきやすいです。病気としてはうどんこ病などが代表的なものです。
害虫としてはアブラムシやテッポウムシ、ナシグンバイなどがあります。これらの被害に遭わないようにするためには、定期的に薬剤を散布するべきでしょう。こうすることによって害虫が発生するのを防げます。害虫は春から秋にかけて発生します。
病気に対する予防法は風通しを良くすることです。特に、木の内部の風通しを良くするために、透かすようにして剪定をしていくと良いです。透かして剪定するのには時間がかかりますが、枝が混み合ってきたと思ったのなら、その次の冬には時間をかけて剪定しましょう。
ハナカイドウの歴史
ハナカイドウは、原産は中国です。「カイドウ」と呼ばれることもあります。中国では華やかな花を咲かせると言うことから、古くから栽培されていました。これが日本へ渡ってきたのは江戸時代の頃です。この時期に日本に渡ってきて「海棠」と表記されることになります。
棠とは、梨を意味する感じです。海を渡ってきた梨ということことから「海棠」と表記されるようになりました。「カイドウ」という言葉は、この「海棠」をそのまま読んだことから来ています。発音ではなくて、意味から呼び方が決まったのです。
では、元々の生息地の中国ではどのように呼ばれていたのでしょうか。唐の時代には睡花と呼ばれるようになります。玄宗皇帝が楊貴妃を呼んだときに、楊貴妃を海棠の花にたとえたことから、このようにいわれるようになったそうです。中国ではかなり古くから愛されていて、
詩や絵画にも用いられることが多いです。日本ではと言うと、やはり日本でも詩や絵画にも用いられています。与謝蕪村や正岡子規、夏目漱石などが取り上げています。ピンク色の花を咲かせるものが多いですが、品種改良も進んで色々なものがあります。日本でも愛されている植物ですから、
品種改良が行われてきました。近縁種としてミカイドウやノカイドウなどがあり、これらは花の色などが異なります。カイドウには色々な種類がありますが、ハナカイドウが最も有名で、一般的にカイドウと言われたときにはハナカイドウを指すことが多く、だいたい同じ意味で用いられています。
ハナカイドウの特徴
ハナカイドウはピンク色の花を咲かせる樹木です。高さは5メートルから8メートルくらいになります。江戸時代から日本で栽培されていて、日本の気候にはかなりなじんでいます。ですから、育て方はそれほど難しくはありません。開花期は4月から5月くらいで、
桜の花が散るとカイドウの花が咲きますから、桜とともに植えて花を楽しむといった方法もあります。花の大きさは3センチから5センチくらいのものが多いです。花は完全に開花するのではなくて、おしべとめしべを包むような形で、開ききらない状態で咲きます。
一重咲きのものから八重咲きのものまでありますから、好みによって良いものを選びましょう。花の色はピンクが基本ですが、白に近いものもありますし、濃い紅色のものもあります。また、最初は濃いピンク色で、徐々に白くなっていくものなどもあります。
品種によって多少の違いはありますが、だいたいはピンク色です。樹形を整えることは必要で、手入れとしては剪定が必要になります。自然な形に剪定をすることもありますが、少し変わった形の樹形を好む人もいます。剪定は11月から2月くらいの寒い時期に行うのが一般的で、
芽を残しておきさえすれば特に難しくはありません。花が咲くと、その後は結実して実を作ることがあります。赤い実をつけ、これは食用にすることもできますが、実をつけることはあまり多くはありません。実の大きさは2センチくらいで、リンゴのような形をしています。
庭木の育て方など色々な植物の育て方に興味がある方は下記の記事も凄く参考になります♪
タイトル:ヒトツバタゴの育て方
-

-
サンセベリア(Sansevieria)の育て方
サンセベリアの原産地は、アフリカ、南アジア、マダガスカルなどです。熱帯の乾燥した地域を好んで生息地としており、約60種類...
-

-
プリムラ・ポリアンサの育て方
プリムラ・ポリアンサは、ヨーロッパを原産でクリンザクラとも呼ばれています。17世紀には、プリムラの野生種から幾つかの品種...
-

-
長ねぎの育て方
長ねぎの他、一般的なねぎの原産地は中国西部あるいはシベリア南部のアルタイル地方を生息地にしていたのではないかといわれてい...
-

-
チゴユリの育て方
チゴユリはチゴユリ属の多年草で生息地としては、東アジアの日本・中国・朝鮮などが挙げられます。チゴユリ属というのは、イヌサ...
-

-
エレモフィラの育て方
エレモフィラと言う植物は比較的最近になってもたらされた植物として知られています。オーストラリアを生息地としている植物であ...
-

-
ハナトラノオ(カクトラノオ)の育て方
種類としては、シソ目、シソ科に属します。多年草の草花で、草丈としては40センチから高くても1メートルぐらいとされています...
-

-
カロライナジャスミンの育て方
カロライナジャスミンは、北アメリカの南部から、グアテマラが原産の、つるで伸びていく植物です。ジャスミンといえば、ジャスミ...
-

-
植物の栽培に必要な土と水と光
植物の栽培に必要なのは、土と水と光です。一部の水の中や乾燥している場所で育つ植物以外は、基本的にこれらによって育っていき...
-

-
ワダンの育て方
この植物は花から見てもわかりますが、キク科アゼトウナ属でキク科ということですが、キク科の野草は黄色い色や白が多くて、特に...
-

-
アセロラの育て方
アセロラの原産国は西インド諸島や中央アメリカなど温かい熱帯気候の地域です。別名「西インドチェリー」とも呼ばれています。そ...




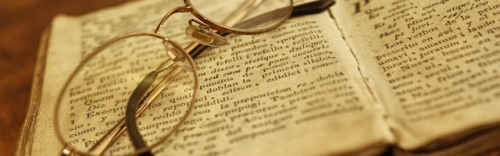





ハナカイドウは、原産は中国です。「カイドウ」と呼ばれることもあります。中国では華やかな花を咲かせると言うことから、古くから栽培されていました。これが日本へ渡ってきたのは江戸時代の頃です。