ダイコンの育て方

ダイコンの育てる環境について
日本の各地で栽培されているダイコンですが、栽培されているのは日本だけではなくヨーロッパや中国などでも行われており、消化力や殺菌効果などが有る事からも注目されている野菜でもあるのです。中でも、消化力については大根を超える野菜は無いとも言われており、
大根に含まれるジアスターゼはアミラーゼとも呼ばれる消化酵素であり、胸やけ、胃もたれ、二日良いなどに効果を持つとされています。しかし、ジアスターゼは消化酵素であり、加熱する事で壊れることからも、大根おろしやサラダと言った生食で、
食べることでこれらの効果を得ることが出来ると言われています。家庭菜園などでもダイコンを栽培する事が可能であり、辛味のある大根を作りたい場合は白首大根、甘みを持つ大根を作りたい場合は青首大根と言った具合に、ダイコンの種類を選んで栽培が出来る楽しみも有ります。
育てる環境と言うのは、生育適温について17度から20度を好み、生育適温に合ったタイミングを見て種まきを行うのがコツです。葉から栄養を吸収する事からも、日当たりが良く水はけが良い場所を選んで種まきをします。尚、大根は春まきと秋まきの2度が可能となりますが、
季節に合ったダイコンの品種を選ぶ事が大切です。また、ダイコンは長い根を持つのが特徴でもあり、深耕・精耕を心がけることが大切で、土を深く掘り、丹念に耕してあげてダイコンが真っ直ぐ成長できる環境を作り上げてあげる必要が有ります。
ダイコンの種付けや水やり、肥料について
17度から20度と言った冷涼を好むダイコンですが、10度以下になってしまうと、花芽分化が起きてしまい、これによりダイコンの根の肥大が止まってしまいます。そのため、生育適温に合う時期に栽培出来るように種をまいてあげるのがコツです。
尚、種をまく時期は中間期においては3月の下旬頃から5月の初旬(春まき)、8月の下旬頃から9月の中旬頃(秋まき)となり、寒冷地などでは4月の下旬頃から5月の下旬(春まき)、7月の中旬頃から8月の上旬頃(秋まき)、
暖地では3月の中旬頃から4月の下旬頃(春まき)、9月の初旬頃から中旬頃’(秋まき)となり、地域により種薪を行うタイミングや春まきと秋まきでは異なるので注意が必要です。尚、ダイコンは直根性の野菜であり、直まきが基本となります。
花芽分化になる前に根を十分に肥大させることが必要であり、種まき時期を厳守する事が成長を促すダイコン栽培の秘訣でもあるのです。種まきを行う2週間前までに、1㎡あたり100~150gの苦土石灰をまいてから土を掘り返しながら耕してあげます。
また、種まきを行う1週間前には1㎡あたり2kgの完熟牛ふん堆肥、120gの粒状肥料をまいてあげて、土を砕くようにしながら混ぜ合わせ、土の状態はふかふか、通気性を持つ土壌に仕上げておきます。
これから1週間経過したら、幅60cmの畝を立てあげて、土の表面を平らにしてから株間30cm程度の間隔を取り、深さ1cm程の穴をあけて、その穴に4~5粒の種をまき、覆土をした後に水やりをたっぷり与えてます。
ダイコンの増やし方や害虫について
種まきをしたとは、種が発芽するまでの間は土が乾燥しないように管理を行う事が大切で、その都度水をあげて乾燥を防いであげます。また、発芽した後もたっぷりと水をあげて土が乾燥をしないように管理をしていく事が大きな大根を作るコツであり、育て方のコツでもあるのです。
発芽をして本葉が1~2枚になった時に、生育の良いものだけを残し、1か所につき3本を間引いていきます。間引終えたら、株元部分に寄せ土を行うことで、倒れるのを防止ることが出来ます。更に、本葉が3~4枚になった時に2本、本葉が6~7枚になった時に1本立ちを行っておきます。
因みに、間引きを行った菜と言うのは、根を摘み取ってあげてから食材としても利用する事が出来ます。本葉の枚数が5~6枚になった時点で、液体肥料を500倍に薄めたものなどを利用して、水やりの代わりとして施してあげます。尚、これ以降は2週間に1度の割合で追肥を施していきます。
収穫は大根の種類により異なりますが、青首大根などの場合は土から出ている首部分が6㎝から7㎝ほどのサイズになった時、早生品種などの場合では種まきをしてから55日から60日、晩生品種では90日から100日が目安となります。年間を通じて様々な害虫が葉を襲ってきますが、
主な害虫としてはアオムシやコナガ、アブラムシなどであり、これらの害虫が発生したら速やかに殺虫剤を散布して防除しておきます。また、害虫は日中だけではなく夜間にも襲ってきますので、夜間活動を行うヨトウムシなどについても注意が必要です。
ダイコンの歴史
大根は冬になると鍋料理の具材やおろしなどをして食べたり、収穫後に干してたくわんなどの漬物にするなど色々な調理方法が在ります。ブリとダイコンを煮込んだブリ大根、おでんの具材として大根を入れたりと、レシピが数多く在る野菜でもあり、青首になっているものなどは甘いが高く、
先端になるほど辛味を持ち、大根おろしなどで食べる人が多い食材です。この大根の歴史と言うのは紀元前2500年前と言われており、古い時代から食されていた野菜でもあるのです。紀元前2500年と言う時代は今からかなり前の話になるわけですが、エジプトではピラミッドを建設していた時代でもあり、
労働者はピラミッドの建設を行う際には多くの労力が必要となります。身体全体を使っての労働は、現代社会においては中々ない物でもあり、エジプトにおいてピラミッド建設に携わる労働者の貴重な食材としてダイコンは利用されていたと言います。
疲れを取る作用を持つことからも労働者のための食材として利用されていたのですが、ダイコンは後にヨーロッパやアジア諸国へと広まり、日本においては中国から伝わったと言われています。因みに、中国の料理の中ではあまりダイコンを食材とした料理は有りませんが、
大根と豚バラの中華煮や白菜と大根の中華煮などのように、豚肉などを利用した料理や根菜を利用した料理などで利用されており、中国から日本への伝来により今日のダイコンは存在していると言う事なのです。
ダイコンの特徴
日本におけるダイコンは中国から広まったと言いますが、これは最古の歴史書とも言われている古事記の中に記載されている、仁徳天皇の恋歌の一節に在るように、女性の腕を例えたと言う、大根根白の白腕として登場しており、この時代には既に日本の中でダイコンが栽培されていたと言われています。
また、室町時代に入ると一般的に生産が行われており、日本の中では様々地域で色々な品種のダイコンが栽培されているのです。尚、大根と言うのは、キャベツやブロッコリーなどの野菜と同じくアブラナ科の野菜であり、原産国と言うのは地中海地方、中東などになります。
現在の生息地は日本の中では全国的なものとなっていますが、栽培されている地域により青首大根、白首大根、桜島大根、聖護院大根、二十日大根、守口大根と言ったブランド品としてのダイコンも存在しています。因みに、大根の種類と言うのは、日本国内だけでも100種類以上あると言われていますが、
比較的良く見かけるのが青首大根や白首大根などであり、葉に近い部分が緑色になっているのが青首大根であり、緑色の部分が多く在るのが特徴です。また、青首大根は全体的に甘味が在るのが特徴で、生食でも食べることが出来る種類になります。
これに対し、白首大根は全体的に辛味が強いのが特徴で、辛味の度合いについては青首大根の倍以上であり、根に近い場所ほどその辛味は強く殺菌効果なども高いと言われているのです。因みに、大根と言うのは細長い形をしているのが特徴ですが、桜島大根のように丸い形をしている種類も有ります。
野菜の育て方など色々な植物の育て方に興味がある方は下記の記事も凄く参考になります♪
タイトル:ニラの育て方
タイトル:玉レタスの育て方
-

-
ハクサンイチゲの育て方
花の高さは約15センチから30センチで、上記でも述べたように大群落をつくります。その姿は絨毯を敷き詰めたようで圧巻です。...
-

-
ウェストリンギアの育て方
シソ科・ウエストリンギア属に分類され、別名にオーストラリアンローズマリーの名前を持つ低木がウェストリンギアです。別名にあ...
-

-
ユキヤナギの育て方について
広い公園や河沿いの遊歩道にユキヤナギが植えられているケースが多いです。ユキヤナギの開花期はだいたい4月頃です。
-

-
ヒメサユリの育て方
ヒメサユリは高山植物として愛好家も多い日本固有の品種ですが、楚々として咲くユリは日本だけでなく世界中で古くから愛されてき...
-

-
ユキヤナギの育て方
古くから花壇や公園によく植えられているユキヤナギは、関東地方以西の本州や、四国、九州など広範囲に生息しています。生息地は...
-

-
ミズナ(キョウナ)の育て方
ミズナは関西では”ミズナ”、京都では”キョウナ”と呼ばれる山菜です。原産地は京都になり日本固有の野菜になります。ビタミン...
-

-
ユーコミスの育て方
この花はユリ科に属します。その他にキジカクシ科に属するとの考えもあります。更にヒアシンス科としていることもあります。園芸...
-

-
ペチュニアの育て方
ペチュニアは花がタバコの花に似ているためブラジルのグアラニ語で タバコを意味するの「ペチュン」という言葉が花の名前の由来...
-

-
レティクラツム・オウァリウムの育て方
この花についてはキツネノマゴ科、プセウデランテムム属となります。園芸上の分類としては熱帯植物です。また暖かいところに生息...
-

-
アメリカネズコ(ベイスギ)の育て方
特徴としては、裸子植物になります。マツ綱、マツ目、ヒノキ科です。属はスギではなくクロベ属、ネズコ属と言われることもありま...




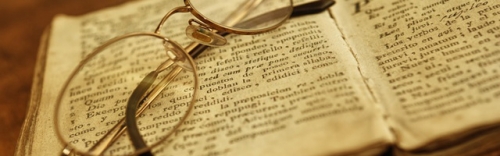





大根は冬になると鍋料理の具材やおろしなどをして食べたり、収穫後に干してたくわんなどの漬物にするなど色々な調理方法が在ります。