センニンソウの育て方

育てる環境について
元々の生息地が、日当たりの良いところなので、育てる環境でも、日光がよく当たる場所を選びます。あまり日が当たらないと、茎が萎えてしまったり、他のものに巻き付くのに重要な葉柄がうまく巻き付かない、巻き付く前に弱ってしまうことがあります。可能な限り、日当たりの良い場所を選びましょう。
また、風通しの良い場所を選ぶことも重要ですが、あまり風が強すぎでも傷んでしまうため、適度な風通りの良さを確保する必要があります。また、真夏の直射日光は、いくら日当たりを好むと言っても、全体を炒めてしまうことがあるため、真夏には北向きの場所に置いたり、遮光ネットなどを用いて、遮光することをオススメします。
遮光は、50%以下に抑えれば問題ありませんが、適宜、調整して、育成を見守りながら適切な遮光度合いを探し出します。面倒な場合は、北向きの庭に置いて風通しと、真っ暗な影の中に入らないようにします。センニンソウそのものの育てる環境もさることながら、その他の育成方法なども、一般的には、クレマチスの育成環境と同じと考えて問題ありません。
インターネットや園芸雑誌、書物などですと、クレマチスと分類され、掲載されていることが多いです。もし、何か栽培上の問題などある場合には、クレマチスで検索すると適切な情報にたどり着くことができます。この際に注意したいのは、クレマチスには、開花の時期により、その種類が分類されるため、何かしらの時期に絡むものは、センニンソウに似ているサイクルのものを選びます。
種付けや水やり、肥料について
比較的、丈夫な種として知られていますが、乾燥を防ぐための水やりは欠かせません。鉢植えで育てる場合には、表面が乾いた段階で、水をたっぷり与えます。目安としては、鉢の下から、水が溢れ出てくる程度です。土壌は有機質を含んだ肥えた土を選び、水はけのよいものにしましょう。腐葉土などが有効です。
肥料は、真夏を避けた時期に、緩効性肥料を1ヶ月くらいのサイクルで与えます。液体肥料は、数ヶ月に1度与える程度で構いません。冬の時期には。寒肥を与えます。1年の成長を決める上で重要ですので、寒肥の実施はオススメです。根の部分に30cm程度の穴を掘り、そこに有機物がたっぷりはいった肥料を与えます。
寒肥用の肥料は、園芸店などから普通に購入することができますので、自作するのが面倒な方は、購入して使用してください。冬の時期には、成長が止まりますが、春頃、再度成長をしていく上で必要な土壌内の肥料の多寡は、この寒肥の有無により異なります。寒い時期の作業で、すぐに効果が見られるものではないのですが、手間を惜しまないことで、春以降の元気な成長を下支えします。
寒肥が重要なように、植え付けの際にも、土に多めの有機物を含ませ、栄養たっぷりにしておくことも重要です。さほど大きな成長はしないのですが、肥料食いの植物として知られているため、植え始めから、育つまで、一貫して、肥料や土壌の栄養分にはこまめに気を使って、成長を阻害しないように配慮します。
増やし方や害虫について
増やし方の方法としては、挿し木とつる伏せがあります。一般の樹木と違い、枝部分ではなく、挿し木として切り取る年と同じ年のつる(もっとも新しいもの)を切り取り、挿し木をします。2ヶ月程度で、音が出てきますので、音が出てきたら、鉢あげしてください。その間、水切れには注意する他、日当たりにも注意をしてください。
育ち具合を見て、肥料も与えることを検討します。挿し木用の土を購入するのもひとつの手です。一方で、つる伏せには、挿し木よりも楽に作業ができます。つる伏せ前の一番元気なつるを選び、隣においた鉢に、5cm程度の深さに、選んだつるを1から2節程度植えます。
約2ヶ月から3ヶ月程度で発根しますが、この状態で親から切り離しはしないようにし、つる伏せをした状態で、1年位放置し、十分に滋養分が新しい苗まで行き渡った段階で切り離しします。つる伏せの場合には、新しい鉢で、つるが曲がらないようにしっかりと固定してください。病害虫としては、アブラムシ、コガネムシ、ヨトウムシ、ナメクジ、アオムシ、ハダニなどがあります。
これらの虫は、葉を食べてしまうため、葉に食べられたような形跡が確認され次第、適切に駆除などの措置を講じてください。ただし、挿し木やつる布施にしろ、または害虫の駆除にしても、注意深く行わないと、有毒の葉のせいで、手がかぶれてしまう恐れがあります。あまり葉の部分に触らないようにする他、不安であればゴム手袋などをはめ作業し、触った部分を自分だけではなく、他人も触らないように袋に入れるなどして廃棄してください。
センニンソウの歴史
中国に伝わる薬草について書かれた書物で、1560年に創刊した、李時珍著の本草綱目には、石草類一十九種の15種目にあり、扁桃腺などの風邪の症状に効くとされており、「仙草は味甘く、寒性で、煮て茶として飲用、清涼にて乾きを癒し、暑気を払い、疲労を取り、老若みな適す」と書かれています。
中国では、ゼリー状にしたものを、コーヒーゼリーのように飲み物の中に入れ提供してくれるお店もあります。北地不生と記載されていることから、北部では取れないため、北京よりも、台湾などの地域でみることができます。日本でも扁桃腺治療に古くから用いられていて、民間療法として知られますが、
中国の飲料に用いるような乾燥を経た後の漢方薬化(実際には、根の部分を生薬化したものを、和威霊仙として漢方薬とします)をせずに、生の葉をすりつぶし、短時間(30分から1時間程度)片手に絆創膏のようなもので皮膚に接触し、毒性が強い状態の生の葉により、意図的に皮膚にかぶれ(水疱瘡のようなもの)を作り、そのまま放置します。
なぜ、これだけの過程で扁桃腺の腫れに効くのかは未だ解明されていませんし、皮膚に跡が残ることもあります。通常は、一般の耳鼻咽喉科の医師の判断を必ず仰いでください。民間療法を信じやってみたいというようなオプション程度と考えるのが妥当です。
しかし、この民間療法を用いることにより、扁桃腺の外科手術を勧められていた患者が回復した例もあり、且つメディアでの報道もあったことから知られるようになりました。また、毒性が強いため、生の葉や根をそのまま飲用することは絶対に避けます。
センニンソウの特徴
センニンソウの特徴は、扁桃腺治療などに用いられる薬草としての役割も多いのですが、仙人の由来ともなった、仙人のヒゲのようなものは、花ではなく、果実に生えた白い毛のことです。薬草と聞くと聞こえは良いですが、一般的に皮膚に触れるとかぶれる毒性があるので、触らないようにします。4枚の花弁のようなものが、花のように見えますが、実際には、この4枚は萼片(がくへん)で、花弁の周りの部分です。
実際の花弁も白く複数咲きます。また、センニンソウは、つる植物のため、1mほど伸びるつるが、伸びる過程で、次々と他の木々などに巻き付いて成長していくの特徴的です。センニンソウは、キンポウゲ科センニンソウ属に属しており、この属は世界でもよく見られます。世界では300種類程度存在し、北半球を中心に、中国、ヨーロッパとユーラシア大陸を超え、アメリカまで続く、広範囲に生息しています。
また、南半球のニュージーランドでも確認されています。日本国内では、20種類以上が確認されています。その中で、日本が原産地のもととして、センニンソウがあります。日本各地で見ることができ、主に日当たりの良い山間部に見られます。特定の地域に根づいたもので、同じ名前を冠するものもあります。
紀伊半島や九州にあるものを、キイセンニンソウ、屋久島から沖縄に棲息するものをヤンバルセンニンソウと言います。名前が異なるように、特徴もそれぞれ異なる箇所があります。広範囲で生息していることからも、環境に適応力があるとされ、育て方はさほど難しくはありません。
-

-
柑橘類(交雑品種)の育て方
柑橘類は遡ること3000万年という、はるか昔の頃から、インド東北部を生息地として存在していたものです。中国においては、4...
-

-
初心者からはじめるミニ盆栽の育て方
少し前に流行ったミニ盆栽。若者にもひそかに人気があります。盆栽はなんといっても風格があります。3000円くらいから1万円...
-

-
キアノティスの育て方
キアノティスは熱帯アジアと熱帯アフリカを生息地とする植物です。原産の地域では高さが10センチから40センチくらいになりま...
-

-
モラエアの育て方
アヤメ科モラエア属であるこの花は球根から育つ多年草の小球根類です。まだまだ謎の多い種類で植物学者や植物マニアの人達が研究...
-

-
ゴーヤの栽培こでまりの育て方あさがおのの種まき
種物屋さんに行くといろいろ知識の豊富な方がいらっしゃいますのでわからない時はまずはそういう専門家に相談してみます。そうし...
-

-
苺の種まきや苺の育て方や苺の栽培について
冬になると、苺がスーパーなどで店頭に並ぶため、苺の種まきは夏に行っていると思う人も居るかも知れませんが、ハウス栽培でなけ...
-

-
アリッサムの育て方
アリッサムはミヤマナズナ属のアブラナ科の植物で、日本で一般的にアリッサムと呼ばれているものはニワナズナなので、かつてはミ...
-

-
ウツギの育て方
ウツギは、ユキノシタ科の植物です。生息地は北海道から九州、奄美大島までの日本の山野や、中国原産のものもあります。落葉性の...
-

-
シュンギクの育て方
キク科シュンギク属に分類されるシュンギクは、20cmから60cmの草丈となる一年草植物であり、春には花径3cmから4cm...
-

-
ピーマンの育て方
現在は家庭の食卓にも馴染み深いピーマンですが、実はナス科の植物だということはご存知でしたか? ピーマンは熱帯アメリカ原産...




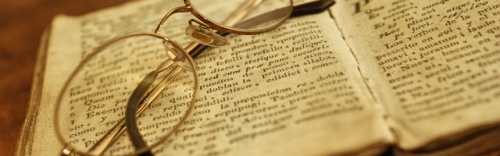





センニンソウの特徴は、扁桃腺治療などに用いられる薬草としての役割も多いのですが、仙人の由来ともなった、仙人のヒゲのようなものは、花ではなく、果実に生えた白い毛のことです。薬草と聞くと聞こえは良いですが、一般的に皮膚に触れるとかぶれる毒性があるので、触らないようにします。