サキシフラガ(高山性)の育て方

育てる環境について
春時期に開花となり成長をし、夏場は葉が茂る状態となり、秋になると葉が繁り、そして冬場は常緑であり休眠となります。サキシフラガは雨を嫌うため、夏場などの時期には雨に当たらないような環境で育ててあげることが大切ですし、水やりについてもそれほど頻繁に行う必要が有りません。
また、雨が嫌いな植物であることからも、庭植えではなく鉢植えの方が管理がし易いと言う利点も有ります。鹿沼土や火山レキと言った水はけの良い用土を利用して育てる環境づくりをしてあげます。春先には化成肥料を置き肥してあげ、春先は夏場とは異なりたっぷりと水をあげるようにします。
特に表土が乾燥したら水を与え、一定の湿気を作り出す事で綺麗な花を咲かせてくれます。花の色は色々な種類が有り、赤色やピンク色、白色、黄色、杏子色と言った色の花を咲かせる種類が存在しています。原産地は欧州アルプスや東欧、ヒマラヤと言った地域であり、
これらの共通点は高山であり、サキシフラガは高山性の植物です。本来は高山に生息しているため、平地などでの栽培は、気圧や環境などに順応不可となるので栽培は出来ませんでしたが、品種を改良するなどして園芸用としての植物も多く出回っています。
日本の中で栽培が可能な種類も僅かではあるのですが有りますので、家の中などで栽培をする事で色々な色の花を咲かせてくれるサキシフラガの栽培は可能になります。尚、育て方のポイントとしては日当たりが良い場所を選ぶ事、鉢植えなどの場合は水はけが良い用土を選ぶ事、高温多湿にしない事などが挙げられます。
種付けや水やり、肥料について
サキシフラガはマット状に丸い形をした葉が広がって、春になると5cmほどの小さな花をつける高山性の植物です。花茎を伸ばして円錐花序を出して、花径が1㎝ていどの小さな5枚の花びらをつけるのが特徴です。花の色は色々なものがあり、斑が入っている品種も有ります(サキシフラガ・パニクラタと言う品種)。
尚、比較的栽培の難易度が高めであり、初心者向きとは言えませんが、鉢植えで上手に管理をしてあげれば毎年綺麗な花を咲かせますし、株を大きくしていく事で株わけが出来て増やせるなどのメリットも有ります。日当たりが良く、しかも風の通りの良い場所に鉢を置いて管理をしてあげます。
サキシフラガは雨や高温多湿を嫌うため、室内で管理をしたり、屋根や雨よけが出来る戸外での管理が中心となります。午前中に太陽の光があたり、午後は日陰になる場所などは最適ですが、夏場などの太陽の日差しが強い時などは、
葉が焼けやすい事からも遮光を50%ほど行う必要が有ります。種まきは4月中旬から6月にかけて行い、4月中旬から6月と9月下旬から11月上旬頃に肥料を与えます。これは春と秋の成長期に月に2度ほどの肥料を与えると言う事であり、夏場は肥料は不要です。
1日1度の割合で水やりをしますが、春と秋冬の時期は朝に行い、夏場は気温が下がる夕方以降に行う事で鉢の温度をあげずに済みます。また、雨が多い時期などは雨に出来る限り当たらないように管理をする事がサキシフラガの栽培のコツです。
増やし方や害虫について
サキシフラガは夏場を過ぎると株や根が傷みますし、用土についても同じことが言えるため、1年に1度の割合で植え替えを行うと良いと言います。植え替えを行うタイミングは9月下旬から10月上旬で、この時期に植え替えを行う事で、根が伸びて株の復活が早まります。
また、株が大きくなっていれば増やす事も出来ます。株分けによる増やし方は、この植え替えの時期に行うのが最適で、茎や根をなるべく多くつけて分けてあげるのがコツです。尚、株を抜いた時に傷んでいる芽や根が有る場合はそれらを綺麗に取り除き、用土を株本まで入れてあげます。
また、表面や目砂ようにやや細かめの石を敷いておくと多湿を防止出来るのでお勧めです。株分け以外にも、挿し芽による増やし方や種まきなどが有ります。挿し芽の場合は、春時期に株元の芽を茎が付いた状態で切って行いますが、挿し芽における活着率のポイントは1本でも根が付いている状態で行う事です。
サキシフラガの害虫にはアブラムシやナメクジ、ヨトウムシ、ネジラミと言ったものが発生します。これらはその都度防除する事が大切ですが、アブラムシは花に発生し、ナメクジやヨトウムシは新芽につきます。また、ネジラミは根につく害虫であり、それぞれを食害する被害を受けるので注意が必要です。
また、高温多湿を嫌いますが、この状態で起きるのが根腐れや軟腐病です。高温多湿により、芽の一部分が茶色く枯れくるので解りますが、このような病気にならないようにするためにも管理をきちんと行う事がポイントとなります。
サキシフラガ(高山性)の歴史
サキシフラガは、ユキノシタ科ユキノシタ属に分類される高山性の植物です。また、流通名はホシツヅリ、別名をカブシア、ジェンキンシアとも呼ばれており、欧州アルプスを初め東欧やヒマラヤなどが生息地で、ヨーロッパが原産となります。
多年草の山野草であり、欧州アルプスやヒマラヤなどの山々に咲く高山性の植物であり、花の色には赤色、ピンク色、白色、黄色、杏子色など様々な色を咲かせる品種が有ります。3月下旬から5月上旬が開花時期となりますが、高山などを生息地としている事からも高山性の植物と言う事になるのですが、
高山性の植物は都会の中ではそのままの状態では栽培が出来ませんし、育て方においてもコツが必要になります。最近は品種が改良されたりする植物も増えており、本来標高が高い場所でしか生息が出来ない植物も、品種などが改良されたことで都会の中で栽培が出来るようになるものも増えており、
サキシフラガにおいても栽培における難易度は高いものの、それでも栽培が可能になる種類も有ります。因みに、サキシフラガの仲間と言うのは全世界に、400種類以上有ると言われていますが、これらの大半は北半球の産地に生息しているものであり、
日本に自生しているユキノシタ、ダイモンジソウなどもサキシフラガの仲間でもあるのです。尚、品種が改良されたものなども有りますが、最近はアルパイン・プランツとして園芸化が行われたと言うサキシフラガもあり、このような品種であれば都会の中でもコツさえつかめば栽培が出来ると言われているのです。
サキシフラガ(高山性)の特徴
サキシフラガはユキノシタ科の植物であり、日本国内に自生しているユキノシタと同じ仲間の高山性の植物です。花の色は様々であり、流通されているものとしては、赤色やピンク色、白色、黄色、杏子色などが有ると言われています。小さな花が咲く種類でもあり、その花の大きさは5センチから10センチになります。
葉は縮こまった感じになる丸い葉であり、葉の形にも魅力が有ります。因みに、ユキノシタ科の植物には「サキシフラガ・ケベンネンシス」と言う品種も有ります。これは同じ仲間の高山性の植物なのですが、この花はフランス南部が原産であり、サキシフラガとは原産や生息地は異なります。
自生しているものは品種改良が行われたものよりも一回り小さい花を咲かせるのが特徴ですが、高山に咲く花であることからもハイキングや登山などをしなければ見ることが出来ない植物です。サキシフラガについてもヨーロッパアルプスなどの高山に咲く植物を園芸用に品種が改良されたり、
交配種として流通させることにより、高山ではない環境の中でも栽培が可能になっており、本来は高山地帯に行かなければ目にすることが出来なかった植物を自宅の家の中や花壇などで栽培出来るなどの魅力が有ります。
因みに、サキシフラガは高温多湿に弱いと言われており、栽培にはコツが必要であること、日本国内で生産されている品種は数が少ないなどの特徴が有りますが、園芸専門店や通販サイトなどを利用して苗木の入手が可能になります。
花の育て方など色々な植物の育て方に興味がある方は下記の記事も凄く参考になります♪
タイトル:バイカウツギの育て方
タイトル:サンビタリアの育て方
-

-
シロダモの育て方
現在に至るまでに木材としても広く利用されています。クスノキ科のシロダモ属に分類されています。原産や分布地は本州や四国や九...
-

-
イチゴノキの育て方
マドリードの旧市街の中心地には、「プエルタ・デル・ソル」(太陽の門)と呼ばれている広場が有ります。この広場はスペイン全土...
-

-
プリムラ・ポリアンサの育て方
プリムラ・ポリアンサは、ヨーロッパを原産でクリンザクラとも呼ばれています。17世紀には、プリムラの野生種から幾つかの品種...
-

-
クサノオウの育て方
クサノオウは古くから日本に生息している山野草です。聞き慣れない植物ですが、黄色い花を咲かせるヤマブキソウに似ています。ク...
-

-
パンジーゼラニウムの育て方
パンジーゼラニウムはフロウソウ科のテンジクアオイ属の植物です。品種改良によって、南アフリカ原産のトリコロル種とオウァーレ...
-

-
ラナンキュラスの育て方
ラナンキュラスの原産地は地中海東部沿岸やアフリカ北東部、アジア南西部など北半球に広くあり、十字軍がヨーロッパに持ち帰り改...
-

-
サルビア(一年性)の育て方
サルビアの正式名称はサルビア・スプレンデンスであり、ブラジルが原産です。生息地として、日本国内でもよく見られる花です。多...
-

-
スターフルーツの育て方
スターフルーツは南インド等の熱帯アジアを原産としているフルーツです。主に東南アジアで栽培されている他、中国南部や南アメリ...
-

-
風知草の育て方
風知草はイネ科ウラハグサ属の植物です。別名をウラハグサ、またカゼグサとも言います。ウラハグサ属の植物は風知草ただ一種です...
-

-
ガーベラの育て方について
ガーベラは、キク科の花であり、毎年花を咲かせる多年草です。園芸では、鉢花や切り花などに広く利用され、多数の園芸品種が存在...




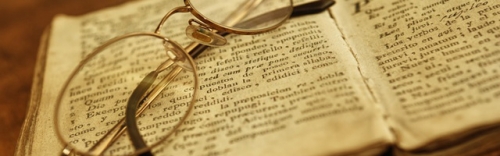





サキシフラガは、ユキノシタ科ユキノシタ属に分類される高山性の植物です。また、流通名はホシツヅリ、別名をカブシア、ジェンキンシアとも呼ばれており、欧州アルプスを初め東欧やヒマラヤなどが生息地で、ヨーロッパが原産となります。