ゲットウの育て方

育てる環境について
ゲットウは琉球列島以南の、亜熱帯地方に郡生する植物ですので、基本的に温暖な気候を好みます。ショウガ科で根をしっかり張ることから、畑の土が川から海へと流れ込んで海の生物に影響を与えるのを防ぐという役割を果たすことでも知られています。川岸の護岸にも有用と考えられており、コンクリートの護岸工事が主流になる以前は、ゲットウを始めとする植物の力との循環で土壌流失防止を行っていました。
今でも赤土流出防止対策として植えらることがあります。沖縄の土は、基本的には降雨によって浸食のおきやすいマージとよばれる土の場所が多く、雨によって流された赤土は沿岸海域を汚染し易いと言われています。これによって珊瑚礁や漁獲量に悪影響を及ぼすことがあります。それだけではなく観光イメージを損なってしまう点についても憂慮されています。
沖縄には赤土流出を防ぐ植物はいくつも存在していますが、例えば石垣島においてはゲットウが一番良く使われています。これは地表面を保護する効果や、株による土止めの効果が大きいというのが理由のとされています。他にも作物を風害潮害から守ったり、防風防潮林としての効果も大きいという面も期待されているのでしょう。また月桃には防虫効果もあります。
ほとんどの葉に虫食いの跡はほとんど見られないため、畑などでは防虫がわりに野菜の近くに植えたり、葉のエキスを搾って無農薬栽培用の防虫剤として使われることが多いです。また家庭においても、台所やゴキブリの居る場所に月桃の葉を置くとゴキブリが居なくなると昔から重宝されています。面白いところでは、米軍の機密文書を虫食いから守るために、月桃紙が使用されているそうです。
種付けや水やり、肥料について
月桃の栽培は非常に簡単です。肥沃で排水のよい土壌を好みます。沖縄地方であれば、わざわざ栽培する必要もないかもしれませんが、沖縄県内外でも、鉢植えの苗を育てて楽しむことが可能です。育て方としては、まず土として赤だま土(小粒)を入れたガーデン板やトレイに種蒔いて3センチくらいの大きさになるまで育てます。その後、個別にポットに植え変えていきます。
成長する大きさに合わせて鉢を大きくしていくようにしましょう。花が咲くようになるのは2年目以降ですが、寒い地方の場合、もっとかかるかもしれません。その葉自体も見た目が良いことから、観葉植物として楽しむことができます。この場合、例えば根のまわりの土を落としてミズゴケだけで、こけ玉にしてもとても元気よく育っていきますので、
お部屋のちょっとしたインテリアにも良い感じです。冬場は室内に置きますが、このときには日当たりよりも温度と湿度が高くなる場所を選んで置くようにしてください。時々、日に当ててやるくらいでいいでしょう。水やりについては、一般的な植物と同じく、土が乾いたら水をやるという程度で十分です。水を好むと言われていますが、実際のところは乾燥気味である方が好みです。
逆に水を与え過ぎることで、根腐れを起こして枯れてしまわないように注意してください。水を控える代わりに葉水してあげるのも良いでしょう。空気中の湿度が高い状態を好むため、霧吹きで葉っぱや茎に水を吹きかけて水分を補給することができます。できればこれは年間を通して行うと良いでしょう。肥料は生育期2週間に1回程度液肥か、緩効性肥料を2ヶ月に1回程度で十分です。また肥料を与え無くても枯れることはありません。
増やし方や害虫について
ゲットウを育てていると、子ができて増えてくるので、株分けして簡単に増やす事ができます。タイミングとしては、植え替えするのと一緒に行うのが良いです。このときに鉢を大きくしたくない場合は、株分けすれば良いでしょう。鉢植えにしていると花が咲き辛いという場合は庭植えしてみるのも良いでしょう。軒下であれば少々霜が降りる地域でも育てることは可能です。
この場合、植え替えは春に行いますが、これは出来るだけ毎年行うようにしましょう。また用土は観葉植物の土を利用すると良いです。ゲットウの耐寒温度は5度程度で、霜に当たると枯れてしまいますが、完全に根まで枯死していなければ、翌年の春にはまた芽吹いてくるでしょう。基本的にゲットウは病害虫に侵されにくい植物です。
鉢植え等で虫が発生するという場合の原因の多くは、鉢土の使われた用土に含まれている腐葉土などによるもので、腐葉土自体に虫の卵が含まれていたり、有機質の分解物に虫が引き寄せられている場合がほとんどです。コケが生えるという場合もありますが、この場合、鉢内が過湿になっている場合が多いようです。
過湿の状態だと、有機質が分解し易くなってしまう為です。このような場合には、水を控えたり、鉢自体を風通しの良い場所に移動して、鉢土を少し乾かし気味に管理するのが良い方法です。ただし、ゲットウの根は乾燥し過ぎた状態が苦手なので、水を与えるタイミングはしっかり管理してあげることが大切です。
ゲットウの歴史
ゲットウは沖縄から九州南部を生息地としている植物で、海外では、台湾、中国、インドなどにも分布しています。沖縄に生息している月桃には2つの種類があり、沖縄の原種である月桃と、とタイリン月桃と呼ばれる亜種が生息しています。この花の房が三日月状であること、花の粒が桃のように見えることから「月桃」名前が付けられたとされている話が有名ですが、
実際のところは、これは観光向けに作られたストーリーであるようです。諸説あるものの中で現在もっとも有力なものとしては、ゲットウは台湾の現地語で「ゲータオ」と発音するので、この音に「月桃」の文字を当て字というものとも言われています。また沖縄では月桃のことを「サンニン」と呼んでいますが、これは外観が良く似ている別の植物の生薬名、砂仁(しゃじん)が訛ったものだと言われています。
月桃は沖縄のあちこちに咲いており、その香りも良いため、昔から各家庭で大いに利用されてきました。沖縄では代表的な「ぬちぐすい」の植物です。これを直訳すると「ぬち」は「命」で、「ぐすい」は「薬」という意味になります。それほど大切なものでありながら、沖縄においては、
あまりにも身近にあるために、まるで雑草のように見られる傾向もあり、その有難さや役割に気づいていないという面もあるようです。またその薬効は、インドの伝承医学アーユルヴェーダでは主に根茎を使うことが残されており、大変古い時代から知られていたことを伺い知ることができます。
ゲットウの特徴
ゲットウの特徴ですが、南国の植物でショウガ科に属し、葉は生姜の葉と同じ形をしています。葉の幅約15センチ程度、長さが40から60センチの楕円形です。色は濃緑色で光沢があって、夏になると長さ4センチ程度に垂れ下がって、まるで堤灯のような形の花をつけます。果実はおおよそ2センチくらいの球卵形をしています。
実の中に灰色の種子ができ、これが成長していきます。初夏頃になると白く可憐な花が咲き、7月頃には蘭に似ている黄色の美しい花を咲かせます。花のつぼみは白いふっくらして、はちきれんばかりのみずみずしさを備えています。先端がほんのりピンク色に色づくため、桃を連想させることから、月桃と命名されたという話もあります。
初秋になると、赤茶色の可憐な実を実らせることが特徴です。ゲットウ自体の高さは2~3メートル程ですが、台湾原産の品種においては高さが4メートル以上にもなる場合もあります。ゲットウは生活シーンの様々なところで役立てることができる優れた植物でもあります。そのよい香りと殺菌効果を生かし化粧品等にも活用されることもあり、また防腐・防虫の効果もあって、
昔から食材を包むのに使われてきました。沖縄地方においては、旧暦12月8日になると月桃の葉で包んだムーチーと呼ばれる餅が作られます。これは沖縄県で食される菓子の一種で、「餅」の沖縄方言でもあり、葉で巻くことから「カーサ(葉)ムーチー」とも呼ばれています。その作り方は、まず餅粉をこね、白砂糖や黒砂糖で味付けをして、月桃の葉で巻き、これを蒸して完成となります。健康・長寿の祈願のため縁起物として食されています。
-

-
センノウの育て方
センノウは鎌倉時代の末か室町時代の初めごろ、中国から渡来したと言われている多年草です。中国名は「剪紅紗花」と書き、センコ...
-

-
ツルニチニチソウの育て方
夾竹桃(きょうちくとう)科に属しているツルニチニチソウは、学名を「Vinca major」「Vinca」といい、ツルニチ...
-

-
コブシの育て方
早春に白い花を咲かせるコブシは日本原産です。野山に広く自生していたことから、古くから日本人の生活になじみ深い植物でもあり...
-

-
シンビジウムの育て方
ランはヒマラヤから中国、日本、オーストラリア、南米など広範囲に分布していますが、その中でもシンビジウムは約50種ほどある...
-

-
アピオスの育て方
アピオスは食材で、北アメリカは北西部が原産地のマメ科のつる性植物で肥大した根茎を食べます。アピオスは芋でありながらマメ科...
-

-
お洒落なハーブの育て方
お洒落なハーブを自分で育てることが素敵だと思いませんか?最近はお家でハーブを育てている人が多くなっています。ハーブと聞く...
-

-
シシトウの育て方
程よい辛味があり、あらゆる料理に使用されて人気のあるシシトウですが、その正式名称はシシトウガラシ(獅子唐辛子)であり、そ...
-

-
プルーンの育て方
プルーンは、スモモの近縁種であり、水溶性の食物繊維を多く含む果実であり、中心部分には大きな種が入っているのが特徴です。
-

-
ホメリアの育て方
ホメリアは庭植えの場合に関しては、数年植えっぱなしでもそのままの状態で育つことができます。毎年球根を掘り上げるよりも、花...
-

-
ピメレアの育て方
ピメレアは育てるのに、簡単で丈夫な植物になりますが、どうしても夏場は気をつけてあげないといけないです。夏場は高温になって...




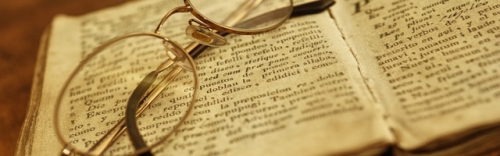





ゲットウの特徴ですが、南国の植物でショウガ科に属し、葉は生姜の葉と同じ形をしています。葉の幅約15センチ程度、長さが40から60センチの楕円形です。色は濃緑色で光沢があって、夏になると長さ4センチ程度に垂れ下がって、まるで堤灯のような形の花をつけます。