アナガリスの育て方

育てる環境について
スペインやポルトガルといった土地が乾燥している場所が原産地であるアナガリスを育てる環境としては、日当たりと水はけが良い場所が最も適しています。また、用土としては、荒れ地や痩せた土地で育ってきた植物らしく、水はけのよい、やや砂質の土が最適でしょう。
春は日当たりのよい場所を選んで育てましょう。そして、梅雨から夏にかけては長雨にさらさないよう注意しながら育てます。またアナガリスは高温多湿は苦手なので、風通しのよい、半日陰の場所を常に用意してあげましょう。さらにこの時期は、アナガリスの生長が盛んになり、
活発に枝分かれするようになるので、枝の隙間は蒸れやすくなっています。植物に変調が起こっていないか、常に気をつけましょう。日本の気候では最も種まきに適している時期とされている秋は、春と同様、日当たりのよい場所で育てます。
この時期には、夏前に切り落とした枝も、ふたたびよく生えてきます。そして冬ですが、アナガリスは霜にあたっても生きられるので、よほどの寒冷地でない限りは屋外で冬を越すことが可能です。それでも気になるという場合は、ベランダや軒下、屋根の下など、
比較的寒さをしのげる場所に移動させると良いでしょう。また、花壇で育てている場合は霜よけをしておくと、より安心です。しかし、何より大切なことは、アナガリスを湿度から遠ざけることです。夏を無事越すことができれば、比較的簡単に冬を越すことができるでしょう。
種付けや水やり、肥料について
アナガリスの栽培方法として、箱まきやポットまきという種まき方法が特に適しています。発芽に光が必要である好光性なので、覆土をする必要はありません。発芽するまでは土を乾かさないように注意しましょう。鉢植えで育てる用土を自分で作る場合は、
小粒の赤玉土を6の割合、そして腐葉土を4の割合で作ると良いでしょう。さらに水はけを良くするためにパーライトを少量混ぜるとさらに良くなります。そして、花壇で育てる場合には酸性土壌を嫌う植物の特性に配慮して、石灰とマグネシウムを混ぜた苦土石灰に水はけを良くする腐葉土、
さらに堆肥を混ぜこんだ用土を使用しましょう。水やりは土が乾燥したときに、たっぷり与える程度で充分です。土が乾燥した状態を好みますので、土が湿っている時に水を与えることはアナガリスの生長には逆効果です。また痩せた土地で育つ植物なので、
肥料も多く与える必要はありません。鉢植えの場合は効き目が穏やかで長く効く、緩効性の化成肥料などを置き肥すれば充分です。また、鉢植えの場合には用土に混ぜ込んだ堆肥だけでも、ある程度の効果は見られるので、その後に1回ほど速効性のある化成肥料などを追加すれば充分でしょう。
それでも生長の様子が気になる場合は、開花時期のみ液体の肥料を与えましょう。肥料を多く与えすぎてしまうと、花付きが悪くなるほか、茎伸びすぎたり、葉もひょろひょろとひ弱な状態で育ってしまうので、お勧めできません。
増やし方や害虫について
アナガリスの増やし方は、全部で4通りです。ひとつ目は種蒔き、二つ目は挿し木、そして三つ目は挿し芽、そして最後は株わけです。ます種まきに関しては、花が咲いた後に種を採ることができます。採った種は、秋に蒔くのが最適とされていますが、3月から4月にかけて蒔くことも可能です。
また、挿し木は比較的簡単にアナガリスを増やす方法とされています。挿し木に適した時期は気温が20~25度になり、日もだんだんと長くなる梅雨から初夏にかけての時期なので5月から6月頃に行うことをお勧めします。夏になり、気温が高くなると蒸散作用が盛んになってしまい、
植物がよわるおそれがあるので涼しい場所に置くようにしましょう。根を出すまではある程度の光も必要なので、明るい日陰が最適です。これは、さし芽でもまったく同じことが言えます。そして、株分けで増やす場合には、植え替えもかねて3月から4月頃に行うのが良いでしょう。
植え替えの際には、植物の環境を一新してあげることも大切です。土を新しく用意したり、古い根を整えると、より健康に育ちます。最後に、アナガリスにつきやすい害虫といえばアブラムシです。アブラムシを防ぐために、
あらかじめオルトラン粒剤を撒いておきましょう。オルトラン粒剤は手軽に使用できて、草花の害虫を退治することができます。根元や葉に散布するほか、植え穴にまくという使い方も可能です。それでもアブラムシが見つかった場合は、見つけ次第早急に駆除しましょう。
アナガリスの歴史
ギリシア語で「楽しむ」や「笑う」を意味する言葉、「アナゲラオ」が名前の由来といわれているアナガリスは、スペインやポルトガルを原産地に持つサクラソウ科・アナガリス属の花です。かつてのヨーロッパでは薬草として重宝されており、精神病の薬として使用されていたことから、
この名がついたと考えられています。和名では「ルリハコベ」と言い、日本では九州、四国、紀伊半島を生息地としています。その他の地域では熱帯アジアでも見ることができ、また中国では「海緑」と言う名で、毒ヘビや狂犬に噛まれたときの傷にも使われていました。
アナガリスは全部で3種類あり、ひとつは「ルリハコベ」が属する「アルベンシス」。この種類は花の色が多岐にわたり、青紫、赤などが見られます。二つ目は「モネリー」。この種類は、地中海沿岸やヨーロッパ西部など比較的広い地域に分布しています。
そして、最後は「テネラ」です。こちらは花の色がピンク色となっています。アナガリスの花が咲く時期は5月から7月とされていますが、寒さにも比較的強く、マイナス5度の環境でも霜に耐えて生き延びることができます。これまでの歴史の中で、痩せた土地でも自生してきた強い植物なので、
様々な環境に適応することができるのです。一方で、肥料を与えすぎてしまうと、上手く花が咲かない一面もあります。種をまくのは、9月下旬から10月上旬が適しており、耐寒性があるので冬越しも可能です。まだまだ多くは出回っていない花ですが、こうした頑健さから、世界中で植物を愛する人たちからの需要は、非常に高いです。
アナガリスの特徴
アナガリスの特徴のひとつは、初期の生育は比較的緩やかであるということです。そして、茎がまっすぐ伸びずに斜め上に向かって伸びる、あるいは這うようにして伸びることも特徴と言えます。そのため、本葉が4枚ぐらいになり、鉢やプランターに株を植えるときは
20~30センチほど間隔を開けると良いでしょう。こうした特徴から、ハンギング植えやコンテナ植えといった育て方が向いています。咲いたその日のうちにしぼんでしまいますが、その花は目が覚めるような美しい青色をしており、その真ん中には黄色のおしべが花の美しさを際立たせ、
さらに、そのおしべを囲むようにしてピンク色の彩りが見られます。アナガリスのこうした華やかさはガーデニングのアクセントとして、欠かせない存在となってきています。最近では、主流である青色のほかにもピンクや赤、オレンジといった色も見られるようになってきています。
また、花は一斉に咲くので、開花時の見ごたえは抜群です。育て方の難易度としては、中級者レベルと言えます。アナガリスは比較的頑健な植物と言えど、多湿には比較的弱く、日本の湿度の高い気候の中での管理が初心者には難しいと考えられるためです。
特に、真夏の管理は難しく、夏前に伸びた枝を切り落とし手入れをしたうえで、風通しのよい場所を常に選び、花をこまめに移動させる必要があります。こうした気候と植物との兼ね合いをいかに上手に行うかが、アナガリスを長持ちさせる秘訣です。
花の育て方など色々な植物の育て方に興味がある方は下記の記事も凄く参考になります♪
タイトル:オーリキュラの育て方
タイトル:イワカガミダマシの育て方
-

-
ナツメ(実)の育て方
この植物は繁殖している地域も、日本中何処ででも見られますので、その点でも栽培では、初心者に適していますが、味の方も食べる...
-

-
ヤツデの育て方
ヤツデは学名がファツシア・ジャポニカということでジャポニカとありますから、日本固有の種類ということがわかりますが、ウコギ...
-

-
セントーレアの育て方
セントーレアの歴史は、古くやギリシャ時代にまでさかのぼります。今現在、一般的に使われているセントーレアという属名は、ギリ...
-

-
セイヨウムラサキの育て方
セイヨウムラサキの特徴について書いていきます。日本を本来の生息地とするムラサキと比較してみると、茎に特徴があります。茎が...
-

-
ワダンの育て方
この植物は花から見てもわかりますが、キク科アゼトウナ属でキク科ということですが、キク科の野草は黄色い色や白が多くて、特に...
-

-
アシダンセラの育て方
花の特徴としてはアヤメ科になります。草の大きさとしては60センチぐらいから90センチぐらいになります。花が開花するのは秋...
-

-
ヤマジノホトトギスの育て方
ヤマジノホトトギスはユリ科の植物です。そのため、ユリのように花被片があり、ヤマジノホトトギスの場合は6つの花被片がありま...
-

-
ポンテデリアの育て方
ポンテデリアの生息地は主にアメリカとなります。原産地は北米南部となっていますが、北アメリカから南アメリカの淡水の湿地など...
-

-
キンバイソウの育て方
キンポウゲ科キンバイソウ属に属する多年草で、その土地にしか生えていない固有の種類です。過去どのような形で進化してきたのか...
-

-
緑のカーテンの育て方
緑のカーテンの特徴としては、つる性の植物であることです。主に育てるところとしては窓の外から壁などにはわせるように育てるこ...




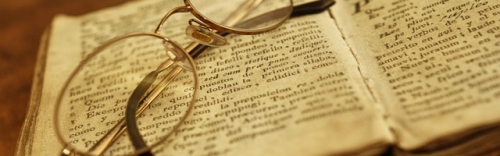





ギリシア語で「楽しむ」や「笑う」を意味する言葉、「アナゲラオ」が名前の由来といわれているアナガリスは、スペインやポルトガルを原産地に持つサクラソウ科・アナガリス属の花です。