パイナップルの育て方

育てる環境について
パイナップルは熱帯の植物ですので、基本的に日光がよく当たる場所を好みます。暑さに強く、強い日差しでも大丈夫ですので、どこに植えるにしても日光のよく当たる場所を選びましょう。ただし、鉢植えにしたものを真夏にコンクリートなどの上に直置きしていると、
土よりもはるかに高い温度になってさすがに弱ってしまうことがありますので、鉢の底にレンガなどを敷いて隙間を作り、風を通して温度を調整しましょう。また、強い風が吹く場所では鋭利な形をしている葉がこすれて、表面に傷がついてしまいます。
特に観賞用として育てている場合には、見た目が悪くなってしまいますので気を付けましょう。暑さには強い反面、寒さには弱いため、4~10月は屋外やベランダなどで育てるのがよいですが、それ以降は屋内に取り込みます。冬場でも10~13度はある場所が理想的で、
屋内でもこの気温を維持できれば生長します。5度くらいまで気温が下がっても耐えることはできますが、生育は鈍ります。用土は清潔なものを使用して、自分で配合するときには鹿沼土7に対して腐葉土3程度を使用しましょう。
水はけがよければ、ある程度養分の少ないところでもきちんと成長します。また、時期によっては下の方の葉が枯れてくることがありますが、これを放置しておくと見た目もあまりきれいではありませんし、湿度の高い時期にはカビが発生することもありますので、こまめに取り除くようにしましょう。
種付けや水やり、肥料について
パイナップルは生息地が恵まれた土壌ではないこともあって、育て方がそれほど難しくありません。植え付けや植え替えは、5~6月に行います。植え替えは子株が多くなってしまったときに、株分けを兼ねて行うようにします。パイナップルはもともとやせた土地でも十分に成長する植物ですので、
自宅で栽培するときにも土はそれほど条件が厳しくありません。ただ、どちらかといえば酸性で水はけのよいものの方が育ちやすいです。また、成長するにつれて葉が大きく外側に張り出してきますので、鉢植えにするときには大きめの鉢やプランターを利用したほうがよいでしょう。
実の重みもありますので、サイズが小さいものは強風で倒れてしまうこともあります。水やりは、冬場には土を乾燥気味にしておくことで根腐れを防ぎますが、ある程度気温があるときには日当たりのよい場所に設置しましょう。水をやりすぎると根腐れを起こすこともありますので、
土が乾いてから水やりをするのが基本で、果実がなっているときにはしっかり与えるようにしましょう。肥料は、5~9月にかけてチッ素、リン酸、カリウムを等倍で与えたり、リン酸がやや多めの化成肥料を規定量、置き肥します。 葉からも水分や栄養素を吸収しますので、
液肥を葉面全体に散布するのも効果的です。植えつけてから2~4年くらいで身が付きますが、一度開花すると同じ茎には花が付きませんので、新たに伸びている芽などを新しい苗として育てます。
増やし方や害虫について
パイナップルを増やす方法は、挿し木によります。一度開花した茎には花がつかないことから、基本的にはこまめに行う必要があります。挿し木は5~7月に、果実の上部にあるクラウンを挿し木することで容易に苗を増やすことができます。力がいる作業に見えますが、
軍手をはめて傷がつかないようにして、しっかりと回転させながら引っ張ると簡単に分離させることができます。分離したクラウンは鹿沼土などの用土にさしますが、それほど管理に気を付ける必要もありません。さし床は半日陰で用土をやや乾かし気味にし、
水やりはそれほど頻繁に行わず、葉を湿らせる程度で湿度を保ちます。パイナップルの栽培で気を付けるような病気は特にありません。害虫にも基本的に強いですが、乾燥した室内ではカイガラムシがつくことがありますので、見つけたらブラシなどで払い落としましょう。
パイナップルに含まれるシュウ酸カルシウムの針状の結晶と、システインというたんぱく質分解酵素には、いずれもこちらが特に何もしなくても害虫から果物を守る、高い殺虫効果が確認されています。そのため、近年ではキウイやパイナップルの成分から、
害虫に強い作物を作り出したり、安全性の高い農薬の開発などができないかが研究されています。このように、非常に育てやすい植物ですので、興味のある人はまずは鉢物の小ぶりなものから育て始めてはいかがでしょうか。生命力が強いため、初心者にもおすすめです。
パイナップルの歴史
パイナップルは日本でもよく目にする果物ですが、原産地はブラジルで、代表的な熱帯果樹の一つです。先住民によって果物として栽培化され、15世紀末にヨーロッパ人が新大陸に到着した時には、すでに各地で栽培されていました。
コロンブスが西インド諸島でこの果樹を発見してからは急速にほかの大陸にも伝わり、1513年にはスペインに、その後インド航路に乗って、アフリカやアジアの熱帯地方にも広められました。1558年にはフィリピンへ、1599年にはジャワへ、1605年にはマカオへと伝わり、1650年ころには台湾に導入されています。
日本には1800年代に伝わったといわれており、主に沖縄で生育してます。沖縄では1888年に小笠原から輸入されたものが広まったといわれていますが、1927年には主力栽培品種であるスムースカイエン種が導入され、石垣島では1930年に台湾から運び込まれた苗をもとに、
台湾から栽培農家が移住して、本格的に生産が始まりました。生産を開始してから数年後には缶詰工場が建設されて県外への出荷も行われましたが、第二次世界大戦によって一時は壊滅的な打撃を受けます。その後、1952年に栽培を再開してからは生産量が急増し、
経済を支えるほどに成長しました。しかしその後、パイナップル産業の中でも主力商品の一つであった缶詰の輸入が自由化されたことにより、現在では最盛期であった頃よりは生産量が少なくなっています。
パイナップルの特徴
パイナップルは、観葉植物として栽培されているアナナスの仲間ですが、食用の果実がよく知られています。代表的な熱帯果樹の一つであり、南国ではよく見かけるだけでなく、日本でも沖縄などで栽培されています。葉は地下茎から生えており剣のような形で硬く、
ふちにとげがあるものとないものがあります。花は苗を植えて1年~1年半ほどで株の中心から花穂が現れ、花軸は60~100㎝近くまで成長します。先端部分に円筒形の花序がつき、およそ150の花が咲きます。花弁は肉質で、全体的に白っぽいですが、先端部分は薄紫色です。
開花後は半年程度で結実します。パイナップルは熱帯のやせた酸性土壌や乾燥している環境でも育つ強い品種であることも大きな特徴ですが、苗を植え付けて1年半から2年程度で収穫できるという成長の早さも大きな魅力となっています。日本では沖縄などで生産されていますが、
海外に目を向けてみてもタイやフィリピン、ブラジルなどで生産されており、これらの商品が日本に輸入されているため、海外のパイナップルも比較的簡単に購入できます。たんぱく質を分解する働きがあり、肉を柔らかくしたいときなどに用いられているほか、
新鮮な果実は甘みがありビタミンも豊富ですので、日本国内でも好んで食べられています。地植えのものを見かけることが多いですが、鉢植えでも結実するため、近年では自宅用に果実のなっている鉢物も流通しており、注目されています。
-

-
そら豆の育て方
そら豆は祖先種ももともとの生息地も、まだはっきりしていません。 原産地についてはエジプト説、ペルシャ説、カスピ海南部説な...
-

-
ハエトリグサの育て方
ハエトリグサは北アメリカを原産とするモウセンゴケ科・ディオネア属の食虫植物です。開いた貝殻のような形の葉が印象的で、その...
-

-
プリムラ・シネンシスの育て方
プリムラ・シネンシスは日本では寒桜と呼ばれていますが、もともとは中国の中南部が原産です。そのため、英語ではChinese...
-

-
月見草の育て方
月見草とは、アカバナ科マツヨイグサ属に属する多年草のことをいいます。原産地はメキシコで、江戸時代には日本にも渡来し、鑑賞...
-

-
セダムの育て方
セダムとは、ベンケイソウ科マンネングサ属(マンネングサぞく、学名: Sedum)に属する植物の総称で、園芸の世界では、学...
-

-
ジギタリスの育て方
ジギタリスの原産地は、ヨーロッパ、北東アフリカから西アジアです。およそ19種類の仲間があります。毒性があり、食用ではない...
-

-
なすびの栽培やナスの育て方やその種まきについて
夏野菜の中でもひときわ濃い紫が特徴なのがなすびです。日の光をたくさん浴びて、油炒めにとても合う野菜ですが、家庭でも育てる...
-

-
エキザカムの育て方
エキザカムはリンドウ科の植物で、別名でベニヒメリンドウ、エクサクムと呼ばれることもあります。 属名の Exacum は、...
-

-
カリフォルニア・デージーの育て方
科名はキク科であり、学名はライアであり、別名にライア・エレガンスという名を持つのがカリフォルニア・デージーであり、その名...
-

-
ヤマブキの育て方
春の花が咲き終わる頃になると、濃い黄色の小花をたくさん咲かせ、自然な樹形を保ちやすく、和風な作りの庭などにもよく利用され...




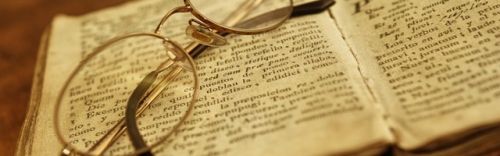





パイナップルは日本でもよく目にする果物ですが、原産地はブラジルで、代表的な熱帯果樹の一つです。先住民によって果物として栽培化され、15世紀末にヨーロッパ人が新大陸に到着した時には、すでに各地で栽培されていました。