ラミウムの育て方

育てる環境について
ラミウムを育てる際に、気をつけなくてはいけないことは、先ほども述べました通り、高温多湿に気をつけるということです。ですので、梅雨時期から夏場にかけては、特に注意をしてあげなくてはいけません。真夏の直射日光は、葉焼けの原因を作ってしまう可能性がありますので、できる限り太陽が当たらないように配慮してあげましょう。
また、雨が当たりすぎてしまいますと、それが原因で葉が腐ってしまう可能性があります。ですので、あまり雨が当たらないような所を選んで育ててあげると良いでしょう。ラミウムは、きちんと育てることができれば、花茎がしっかりと立ち上がって、桃色や黄色、また、白色や紫色といった、様々な花を咲かせることができます。
開花時期は大変美しくなりますので、是非環境には気を使って、綺麗な花を咲かせてあげるようにしましょう。そして、ラミウムには、様々な原種や園芸品種があります。育てる際には、是非、そのような色が良いのか、また、どういった花が良いのかというのを事前に調べてから、苗を購入することをおすすめ致します。
明るい半日陰か、水はけの良い土壌を選んで育ててあげれば、年中楽しむことができます。特に夏場に関しましては、育てる際に注意が必要になりますが、寒さには強い花になりますので、どうしても難しいということであれば、秋先から苗を購入して育てると良いでしょう。きちんとした環境を準備してあげて、良い花をつけるように、配慮してあげましょう。
種付けや水やり、肥料について
ラミウムの栽培方法で、気をつけなくてはいけない事とは、一体なんなのでしょうか。それは、なんと言いましても、水やりや肥料になります。特に、気をつけなくてはいけないのが、夏場になります。基本的に水やりに関しましては、土の表面が乾き始めてきましたら、たっぷりと水をあげるようにします。
ですが、真夏に関しましては、生育が衰えてくる時期になりますので、特に過湿にならないように、土の乾き具合をきちんと見ながら水やりをする必要があります。どうせ暑くなるし、乾くのも早いからといって、水をたくさんあげすぎてしまいますと、それが原因で枯らせてしまう可能性がありますので、気をつけましょう。
そして、肥料に関しましては、植え付けをする際にきちんと用意してあげる必要があります。元肥としておすすめするのが、緩効性化成肥料を用土にしっかりと混ぜるという事です。そして、追肥に関しましては、鉢植えでラミウムを育てる時のみ、用意をします。生育が旺盛な、春と秋に、液体肥料を与えてあげるようにしましょう。もしもラミウムを、鉢植えで育てたいという事であれば、
水はけと通気性が良い鉢を選んであげるようにしましょう。また、適度に保水性のある土を選んであげる事で、しっかりと育つ事ができますので、大変おすすめです。ラミウムは、比較的簡単に育てる事ができる花という事で、ガーデニング初心者に人気のある花になります。ですが、育て方を間違えてしまいますと、簡単に枯れてしまいますので、簡単だからといって、適当に育てないようにしましょう。
増やし方や害虫について
ラミウムを増やしたいという事であれば、春と秋をおすすめ致します。株分けをするか、さし芽をする事で、増やす事ができます。花が咲いた後に、旺盛にほふく枝を伸ばしてきます。ですので、その成長を狙って、さし芽用土などにさせば、たくさん増やす事が出来るでしょう。
そして、開花時期を超えて、花が咲いた後は、花穂の付け根あたりで切るようにしましょう。少し面倒ではありますが、この花がら摘みをきちんと行う事で、美しさを保つ事ができますよ。また、成長をしていく段階で、どうしても避けて通れないのが、害虫対策になります。特に病気は斑点病に気をつけてあげましょう。
斑点病とは、下の葉に褐色の斑点が現れてくる症状です。そのまま何もしないで、放置してしまいますと、次第に葉が枯れあがってきてしまいます。そう致しますと、株が弱ってしまいますので、注意が必要です。空中湿度が非常に高く、風通しが悪いと、斑点病になってしまう可能性がありますので、できる限り風通しが良い所で育ててあげるようにしましょう。もしも、斑点病になってしまったら、早く対処をしてあげてください。
傷んでしまった葉を取り除く事で、対処する事ができますよ。また、害虫で気をつけなくてはいけないのが、ナメクジになります。水を与えすぎる事で、発生する可能性がありますので、注意が必要です。ラミウムの生息地は、高温多湿に気をつければ、どこにでも生えております。ガーデニング初心者でも、比較的簡単に育てることができますので、大変おすすめですよ。
ラミウムの歴史
ラミウムは、日本に自生するホトケノザやオドリコソウの仲間になります。ですが、最もガーデニングに利用されるのが、紫色です。地面を這うようにして生える枝は、長くても1メートルくらいになります。ですので、ガーデニングで育てる際には、きちんと管理を行うようにしましょう。主に、グラウンドカバーやハンギングバスケットに多く利用されますので、是非、育てる際には、利用してみることをおすすめ致します。
ラミウムの原産地は、主にヨーロッパやアフリカ北部、そしてアジアの温帯地域になります。そして、開花時期は5月から6月になるのですが、立ち上がった茎の先に、まるでサルビアのような華穂を伸ばして、華を咲かせます。多年草になりますので、葉に関しましては、年中鑑賞をすることができます。
ですが、やはり美しいのは、花をつける5月から6月にかけてになりますので、是非、開花時期を逃さないようにしましょう。また、寒さにとても強く、そして、日陰でも育つという特徴があります。ですので、比較的誰にでも育てることができるといったメリットがあります。ガーデニング初心者の人でも、
十分に育てる事ができる花になりますので、是非、何かを育ててみたいと思っている人は、ラミウムから始めてみるのも良いでしょう。ガーデニングは、大変楽しいものではありますが、きちんとした準備も必要になります。育てるのが比較的簡単な花であったとしても、しっかりと準備をしてから育てるようにしましょう。
ラミウムの特徴
ラミウムの特徴は、なんと言いましても、地面を這うように枝が這うということです。特に、長くなりますと1メートルくらいになりますので、グラウンドカバーなどに利用するのに、大変最適です。秋か春になりますと、花屋さんで苗が売られるようになります。非常に育てやすく、初心者の人でもガーデニングに最適な花になりますので、是非、育ててみることをおすすめ致します。
また、植え付ける際には、できる限り直射日光を避けるようにしてあげましょう。特に、真夏の直射日光は当たりすぎてしまいますと、枯れてしまう原因を作ってしまいます。たとえ育てやすい花だとしても、きちんと環境に配慮してあげなくてはいけません。グラウンドカバーとして最適なラミウムも、真夏の直射日光のせいで、
葉焼けをしてしまっては、美しさも台無しですよね。ですので、育てるのであれば、あまり直射日光の当たらないような、半日陰の場所を選んであげましょう。また、高温多湿を嫌う花になりますので、梅雨時期から夏場に関しては、最も注意して育ててあげる必要があります。
用土が過湿にならないように、気をつけなくてはいけないといった点からも、できる限り簡単に育てたいということであれば、秋先を狙って育てると良いでしょう。ラミウムは、先ほども述べました通り、寒さに関しましては大変強い花になります。ですので、春先から育てるよりも、秋先から育てたほうが、きちんと成長する可能性が高いですよ。
-

-
コメツガ(米栂)の育て方
コメツガは、昔から庭の木としても利用されてきましたが、マツ科のツガ属ということで、マツの系統の植物ということになります。...
-

-
マクワウリの育て方
マクワウリと言えば、お盆のお供えには欠かせない野菜です。メロンの仲間で、中国や日本で古くから栽培されるようになりました。...
-

-
エラチオール・ベゴニアの育て方
エラチオール・ベゴニアは、日本でもポピュラーな園芸植物のひとつで、鉢植えにして室内で楽しむ植物としても高い人気を誇ります...
-

-
パキラの育て方について
大鉢仕立てにすることもできれば、手のひらサイズのミニ観葉に仕立てることもできるので、いろいろな場所で目にすることができま...
-

-
ジニア・リネアリス(ホソバヒャクニチソウ)の育て方
ジニア・リネアリス(ホソバヒャクニチソウ)は和名を細葉百日草といい、原産地はメキシコを中心とした南北アメリカです。リネア...
-

-
ソラマメの栽培~ソラマメの種まきからソラマメの育て方
ソラマメの種まきは関東を標準にしますと10月下旬から11月上旬になります。地域によって種まきの適期は異なるので種袋で確認...
-

-
ノビルの育て方
原産地や生息地の中国では漢方薬としても利用されていて、すりおろして痒み止めやかぶれ等の付け薬にしているということでした。...
-

-
ひまわりの栽培やヒマワリの育て方やその種まきについて
夏になると太陽の方向を向いて元気に咲くひまわりが目につきます。このひまわりを自分で育てることができます。ひまわりの栽培方...
-

-
グリフィニアの育て方
原産国がブラジル連邦共和国原産の”グリフィニア”はヒガンバナ科の植物です。和名”ミニブルーアマリリス”とも呼ばれており、...
-

-
アラマンダの育て方
アラマンダはキョウチクトウ科 Apocynaceaeのアリアケカズラ属 Allamanda Linn. の植物です。原産...




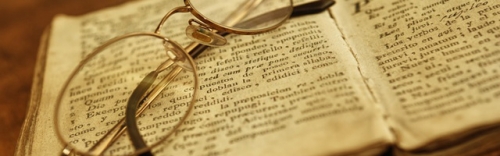





ラミウムは、シソ科、オドリコソウ属(ラミウム属)になります。和名は、オドリコソウ(踊子草) と呼ばれています。ラミウムは、日本に自生するホトケノザやオドリコソウの仲間になります。ですが、最もガーデニングに利用されるのが、紫色です。地面を這うようにして生える枝は、長くても1メートルくらいになります。