シダルセアの育て方

育てる環境について
シダルセアを栽培しようと考えたら、空気の乾燥具合も配慮してあげるとよいでしょう。育て方のポイントとしても、気候的に乾いた感じがあるかどうかを、まずは考えてあげると良いです。乾いた機構が苦手な植物も多い中、カリフォルニア原産の元気なシダルセアは、日あたりが良好であり、
尚且つ乾いている気候が好きな植物です。耐暑性や耐寒性を合わせ持ってはいるものの、乾いた中での環境が好みであるため、水分が過剰すぎる環境は得意な方ではありません。雨が長く降り続くような地域であったり、高温でありながら湿気がやけに多い環境などは、
シダルセアにとっては、以ての外なのです。湿気が多くて、蒸れて仕方ないような環境は、かなり弱いです。そのため、育てるときには、水はけの良さも条件となります。扱いにくそうにも感じますが、冷涼地ではスクスクと元気に栽培しやすいといった特徴もあります。
太陽の日差しも眩しい夏の時期にも、シダルセアは咲き続けてくれますから、それに伴い株も増えていきます。ただ、夜の気温が高くなると、成長自体にストップがかかります。そして、半休眠状態になっていきます。環境は、お日様の光がよく当たる場所であり、
排水も良いという場所を探して植えてあげることです。日常的には、高温多湿にならないように配慮してあげると良いです。高温多湿状態には、とても弱いという弱点を持っていますから、上手にカバーしてあげると、植物にとっても優しいです。
種付けや水やり、肥料について
植え替えや植え付けですが、5月から6月位になたら、ポットな円植え付けをすると良いです。ポット苗ではない場合は、3月から4月の時期か、そのあとは9月の終わりくらいから11月までのあいだに、植え替え作業をすると良い時期になります。庭に植えるときには、
水はけがよくて、日あたりも良好というナイスポジションを見つけて、植え付け作業を行いましょう。植える時の土には、腐葉土も一緒によく混ぜます。しっかりと根っこが張るまでは、乾燥しないように気をつけます。鉢植えの場合、1年に1回くらい、必要であれば株分けして、
植え替え作業をします。シダルセアの育て方で気をつけたいのは、日々の水遣り作業です。多くの植物の場合、栽培するにあたって、こまめに水やりをしてあげるものが多いです。植物としても、毎日のように水やりを希望するタイプもあります。シダルセアは、乾いた機構を好む植物であり、
過剰な水分や湿気には、とても弱いという面を持っています。そのため、庭に植えた場合は、しっかりと根さえ張ってしまえば、水やりをする必要は、ほとんどありません。水はけの良い場所を選んで植えますから、植物にとっても快適な環境です。
プランターや鉢植えについては、用土の様子を見ながら、乾いたら適度に水やりをします。肥料を上げる時期は、春の時期と秋のシーズンです。春は成長期になりますし、秋は気温も下がってきて、肥料をあげるタイミングになります。夏は高温多湿の時期なので、できるだけ肥料が残らないようにしておきましょう。
増やし方や害虫について
シダルセアを栽培するときには、害虫にも気をつけて育てたいものです。発生しやすい害虫としては、ハマキムシの存在があります。ハマキムシが出てくると、葉っぱをまいてしまったり、つづり合わせたりと、何かと食害を加えてしまいます。葉っぱが食害されることにより、
見た目にも美しさが損なわれることになります。ハマキムシにはいくつもの種類がいて、コカクモンハマキとチャハマキは、メインとなって植物を攻撃します。どの種類も1年のうちで1回の登場ではなく、4回から5回は発生するというツワモノです。
まいた葉っぱの中で幼虫の状態のまま冬を越します。そんな恵まれた環境ですから、温度が少し高めであれば、冬の時期でも活動を始めます。対策としては、葉っぱの中に害虫を見つけたら、被害を受けた葉っぱごと、プチッと摘み取りましょう。
薬剤を使用する場合には、オルトラン水和剤を使用するか、スミチオン乳剤を散布するなどの方法があります。スミチオン乳剤は、たっぷりと使うことで、退治になります。シダルセアの増やし方としては、株分けすることもできますし、タネまきしても良いでしょう。
株分けに敵下敷きとしては、暖かくなってくる春の時期か、行楽にも良い時期の秋の季節です。春は3月から4月にかけてで、秋は10月から11月にかけて作業を行います。品種にもよりますが、増やすのにタネまきでできるものもあります。タネまきであれば、4月から5月に作業をします。
シダルセアの歴史
シダルセアは、北アメリカ中部、北アメリカ西部が原産国です。耐寒性はある方で、乾燥気味である気候の地域を生息地として選びます。アオイ科のシダルセア属で、耐寒性多年草です。アオイのような花の、といった意味も持っているものです。双子葉植物の一つがアオイ科で、1500 種程があります。
分類でいうと、75属とも言われています。アオイ科は、観賞用もあります火、食用の植物もあります。観賞用では、タチアオイやフヨウ、ムクゲやハイビスカスなどがあり、大きめのサイズの鮮やかな花を付けるのも特徴的です。食用の種類になると、白い花を付けるオクラも、
日本人にとっては身近な食材として感じられるものです。また、これ以外にも繊維として用いられる、ケナフであったり、ワタなどもあります。アオイ科は、主に熱帯を子息地としており、全世界に分布しています。日本国内では、固有は4種類であり、9属あります。
低い木であったり、草本などがあります。種類は多いですが、見た目の印象で言えば、サイズは大柄であり、花の中でも派手なくらいの華やかさを持っているタイプです。そのなかでシダルセアは、派手さとは少し離れている、どちらかというと可憐さも持っている花です。
茎のラインもほっそりとしていて、スラッとしたスタイルであるため、華奢な印象もあります。花は大柄で咲くというものではなく、色味も薄めの控えめな花びらが、多数咲き誇ります。細身ですが、花が咲き乱れると、ボリュームが出てきます。
シダルセアの特徴
シダルセアの花は、フリルのような花びらで、淡いカラーのピンクの花びらが特徴的です。茎は細くて、華奢な印象であり、小枝も多いです。花の質としては、まるで薄い紙のような質感が特徴的です。たくさんの花をつけて風に揺れるさまは、とてもソフトな風情を、見る者に感じさせてくれる花です。
1輪で見たときには花の時期は短いものの、まとめて植えるとぼシュー無冠が出てきます。切花にすると水揚げがよくて、飾るのにも向いている花です。 シダルセアの分類は、アオイ科シダルセア属の耐寒性多年草になります。草丈としては、約80cmくらいであり、
開花を迎える時期は、太陽の光もサンサンと降り注ぐ、真夏の7月から8月にかけてのシーズンになります。耐寒性に対しては強いほうです。日照という面においては、日向でも良いですし、明るい日陰の方が適しているケースもあります。
水やりは過剰にならないように、適湿が好ましいです。施肥は、暖かさと新緑が訪れる春のシーズンと、紅葉も美しく山を飾るようになる秋のシーズンです。油粕肥料や有機液肥を、生育時、だいたい2週間に1回くらいのペースで施します。
植え込み用土としては、オリジナルの園芸培養土などで良いでしょう。開花した花は、切花に使うのも良いですし、ボーダー・ガーデンにもむいています。栽培をする環境については、日向はもちろんのこと、明るい日陰であり、水もちがよくて、水はけも良い土壌が向いています。
-

-
マツカゼソウの育て方
松風草は、一般的には、マツカゼソウと表記され、ミカン科マツカゼソウ属に属しており、東アジアに生息するマツカゼソウの品種と...
-

-
エンドウの育て方
古代エジプトの王の墓から発見されたというエンドウは、地中海地方と中国が原産地や生息地とされています。日本には10世紀のこ...
-

-
ファレノプシス(コチョウラン)の育て方
学名はファレノプシスですが、和名をコチョウランとも言い、日本でランと言えば、胡蝶蘭を思い浮かべるくらい有名で、人気がある...
-

-
チングルマの育て方
チングルマは高山に咲く高山植物の一つです。白い花弁の中心には、黄色い色をした無数の雌蕊や雄蕊を持つ花で、登山をしていると...
-

-
シモツケソウの育て方
シモツケソウは日本原産の固有種で、本州の関東地方から九州にかけてが生息地となっています。山地や亜高山の草地、林の縁などに...
-

-
イキシオリリオンの育て方
花については被子植物、単子葉類になります。クサスギカズラ目とされることがあります。ヒガンバナ科に属するとされることもあり...
-

-
アスパラガスとスイゼンジナの栽培方法
まずはアスパラガスの育て方を説明します。保健野菜で有名なアスパラガスには、缶詰用のホワイトと生食用のグリーンとの二種類が...
-

-
ペペロミア(Peperomia ssp.)の育て方
ペペロミアの原産地はブラジル、ボリビア、エクアドルなどで、主な生息地は熱帯や亜熱帯です。約およそ1400種類もの種類が存...
-

-
モクビャッコウの育て方
日本では、神の島「久高島」の浜辺に群生していることで知られています。また日本では古くから南西諸島や硫黄島などに自生が見ら...
-

-
ビギナー向けの育てやすい植物
カラフルな花を観賞するだけではなく、現在では多くの方が育て方・栽培法を専門誌やサイトなどから得て植物を育てていらっしゃい...




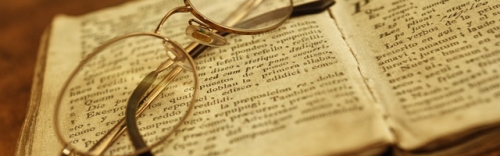





シダルセアは、北アメリカ中部、北アメリカ西部が原産国です。耐寒性はある方で、乾燥気味である気候の地域を生息地として選びます。アオイ科のシダルセア属で、耐寒性多年草です。