球根ベゴニアの育て方

育てる環境について
球根ベゴニアはもともと日本の風土では育ちにくく、庭上には向いていませんので、家庭で育てるときには鉢植えにします。冬に休眠しますが、凍ると球根が傷んで花が咲かなくなってしまいますので、凍らない温度で管理をしましょう。早春に目が出てきたら、室内の明るい窓辺に置いて、
日の光に当てます。戸外で栽培するときには5月からにして、雨には当てないようにしましょう。梅雨明け以降は、風通しの良い半日陰においてできるだけ涼しい環境を保ちますが、真夏などは戸外では夏越しができなくなる恐れがありますので、
クーラーの効いた室内に日中は取り込むようにするとよいでしょう。クーラーがかかっていないときには、閉め切った室内では高温多湿になりますので風通しのよい場所に移しておきましょう。用土は水はけと通気性に富み、適度な保水性のある土が適しています。
例えば、赤玉土小粒5、腐葉土3、日向土2などの配合で作成した用土を利用するとよいでしょう。また、草花用培養土に日向土を2割程度混ぜてもよいでしょう。咲き終わった花がらは、そのままにしていると養分を失ってしまいますので付け根のところで折り取ります。
また、スタンドタイプの球根ベゴニアは太い茎が倒れやすいため、支柱を立てて支えたほうがよいでしょう。この時、球根を突き刺さないように気を付けて、花がつかない側に立てると見た目もきれいですし安定します。ハンギングタイプには支柱は必要ありません。
種付けや水やり、肥料について
種付け時期は、3月中旬から4月上旬です。この時期に5号鉢に1球を目安として、球根の上部が土から出るように、浅く植えつけます。球根がたくさんある場合には、育苗箱などに仮植えして、芽が出てきたものから順次鉢上げするとよいでしょう。
真冬の寒さで球根が凍ると花を咲かせなくなりますので、植え付け時期までは適温の場所に保管しておいて、時期になると順次植えていきます。水やりは、生育期には土の表面がよく乾いたら、たっぷりと与えるようにします。しかし、高温期になり株が弱ってきたら、水やりの量を控えめにしましょう。
秋は地上部が枯れ始めたら水やりを控えめにし、完全に枯れて球根だけになったら停止します。球根ベゴニアは育て方が難しいといわれていますが、特にこの水やりのバランスや気温調節、球根の管理など、神経を使わなければならないポイントが多いことも曽田出るのが難しいといわれているゆえんです。
また、球根ベゴニアの季節開花は初夏ですが、真夏までの期間が短くなりますので、開花している期間がわずかになります。早春に入手した球根を冷蔵庫の野菜室に入れて秋まで貯蔵し、秋に植え付けることにより、長期的な開花を実現する方法もあります。
肥料は、元肥として緩効性化成肥料を用土に混ぜます。生育が旺盛なときは、緩効性の化成肥料を置き肥するか、液体肥料を定期的に施すと立派な花を咲かせるようになります。元肥は植え付け時期と同じですが、追肥は4月上旬から6月中にかけて行います。
増やし方や害虫について
球根ベゴニアは、育てることが難しいだけでなく、増やすという行為自体もほぼ困難です。この花は球根が増えませんので、特に家庭で育てるときに球根を分割して繁殖させるということができません。中でも、茎の太いタイプは見た目にはしっかりしているように思えますが、
一度の開花で球根が養分を吸収されてしまいますので、次につなげる力がほとんど残されていません。茎が細く、しっかりして国内でもある程度適応できる品種は挿し木によって増やすことができますが、ほとんどの品種は腐りやすくなっており、挿し木をしても根付くことがありません。
挿し木をするときには、水はけのよい用土や水にさすと根が生えてきます。この花で多く見られる病気は、灰色かび病やうどんこ病です。灰色かび病は梅雨時期や低温期によく見られ、うどんこ病は気温が20度程度のときによく発生しますので、夏以外の時期は葉や花の状態をこまめにチェックしましょう。
害虫としては、ハダニやアザミウマなどがよく発生します。ハダニは葉の裏についていることが多いため、こまめにチェックするとよいでしょう。アザミウマは花粉を食べに来ますので、花をよく観察すると見つけられます。状態がひどくなると、
花弁が委縮したりかすり状の傷が入りますので、早めに対策を講じておきましょう。害虫対策としては、鉢植えよりも地植えにしたほうがよい場合もあります。ただし、その場合にはセンチュウ類の被害にあう可能性もありますので、薬剤などを用いて防除しなければなりません。
球根ベゴニアの歴史
ベゴニアの原種は、オーストラリア大陸を除いたほぼ世界中の熱帯や亜熱帯地域に分布しています。ベゴニア自体は日本でも原種が存在しており、多くは西表島から石垣島にかけてにみられます。ただ、暑い場所で生息するというわけではなく、
実際には木陰や高地などの涼しく寒暖の差が少ないところに自生していることが多いです。原種は2000を超えるといわれており、さらに交配種はその数倍存在しますので、一口にベゴニアといってもかなりの数になります。球根ベゴニアとは交配種の一種であり、
もともとはアンデス山脈に自生していた球根性のベゴニアが原産です。生息地はペルーやボリビアなどのアンデス高山地帯に幅広く分布していましたが、そのベゴニアを交配によって改良したものであるため、基本的に半耐寒性で暑さに対してはかなり弱く、
フランスやイギリス、ドイツなどでは家庭用の観賞植物として種子や球根が販売されています。日本のように四季がはっきりしており、夏場の暑さが強い地域では自然に育てることは難しく、専用の温室で育てられているものがほとんどです。
そのため、もともとはヨーロッパを中心として花壇や鉢植えなどで楽しまれていましたが、近年ではベゴニアガーデンが各地にオープンしたことにより、比較的気軽に大輪のベゴニアを楽しめるようになっています。北朝鮮の指導者である金正日は真っ赤なベゴニアを好んでおり、自身の名前を付けた品種を作らせています。
球根ベゴニアの特徴
球根ベゴニアはその名の通り、球根を持ったベゴニアです。直径3~4cmの不整形の塊茎をもち、茎は太さがあり、20~30cmの高さで直立するスタンドタイプと、ペンデュラとよばれる柔らかい茎がしだれ状に垂れ下がるハンギングタイプがあります。
ハンギングタイプは花が小輪で花弁が細く、一重から半八重の花が咲きますが、こちらの品種は比較的暑さに強いため、家庭でも育てやすくなっています。一方、スタンドタイプは大輪の豪華な花を咲かせるものも多く、ボタンやツバキのような華やかさがあり、花径15㎝程度のものもみられます。
観光施設や植物園でも人気があり、専用のベゴニア園が作られているところも多いです。色合いも豊富で、赤や朱色、黄色、ピンク、白、赤紫など幅広い上、絞りや覆輪のものもあり、ベゴニアだけで植えられていても、鮮やかな眺めを楽しめます。
球根ベゴニアは暑さに弱いものがほとんどですので、球根がついていても一年草と認識しておいたほうがよいでしょう。茎や葉は汁が多く、毛は生えていません。葉はベゴニア特有の形状をしており、光沢があります。日照に関係なく咲くため、
初夏から秋まで長い間美しい花を咲かせています。一般的には春植えの球根として3月頃に出回っていますが、4~6月頃には花つきの株も出回っており、よりスピーディーに花を咲かせます。秋ごろには地上部が枯れて休眠しますが、球根が増えないので増やすことは困難です。
花の育て方など色々な植物の育て方に興味がある方は下記の記事も凄く参考になります♪
タイトル:木立ち性ベゴニアの育て方
タイトル:根茎性ベゴニアの育て方
タイトル:シュウカイドウの育て方
タイトル:クレオメの育て方
タイトル:グラジオラス(夏咲き)の育て方
タイトル:雲間草の育て方
-

-
ローズゼラニウムの育て方
ローズゼラニウムの特徴は、やはりバラのような甘い香りです。クセのある甘ったるさではなく、ミントが混ざったようないわゆるグ...
-

-
ワケギの育て方
原産地については西アジアから地中海東部であるいう説やユーラシア南部を生息地とする説もあればアフリカやヨーロッパが原産地で...
-

-
カランコエの育て方
乾燥に強い性質のある多肉植物で、育てるのに手間がかからず、鮮やかな色の花だけではなく、美しい葉そして面白い株の姿を鑑賞す...
-

-
アルストロメリアの育て方
アルストロメリアは、南米原産の単子葉植物の属の一つで、アルストロメリア属、または別名をユリズイセン属とします。
-

-
リョウブの育て方
両部の特徴においては、まずは種類があります。ツツジ目、リョウブ科になります。落葉小高木になります。若葉に関しては古くから...
-

-
ウグイスカグラの育て方
ウグイスカグラは、落葉性の低木です。スイカズラ科スイカズラ属の植物ですが、カズラではありません。名前の語感がカズラと似て...
-

-
植物のことについて知ることは大事
誰でも一度は植物を育てたり、栽培したことはあるものです。しかし、育て方や栽培方法を良く知らなかったために枯れてしまったり...
-

-
ニンジンの育て方
ニンジンはセリ科の一種であり、この名前の由来は朝鮮人参に形が似ていることからつけられたものですが、朝鮮人参はウコギ科の植...
-

-
観葉植物を育ててみよう
初めての人でも比較的簡単に栽培することが出来る観葉植物の育て方について記述していきます。まず、観葉植物と一口に言っても、...
-

-
ノコンギクの育て方
ノコンギクの歴史としまして、伝統的にはこの種には長らく「Aster ageratoides Turcz. subsp. ...




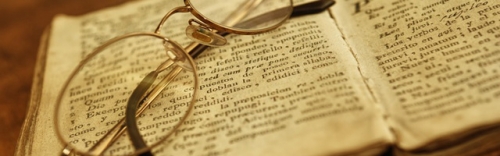





ベゴニアの原種は、オーストラリア大陸を除いたほぼ世界中の熱帯や亜熱帯地域に分布しています。ベゴニア自体は日本でも原種が存在しており、多くは西表島から石垣島にかけてにみられます。