マイヅルソウの育て方

育てる環境について
栽培をしようとする場合の環境です。育て方として必要になるのはどういったところでしょうか。北は北海道、更に上のロシアでも咲いているとされています。日本の南限としては屋久島になっています。ちょっとした特徴として、北に行くほど姿が大きくなり、南に行くほど小さくなる傾向があります。これについては花の特性と何らかの関係があると考えられます。
それを意識した環境を用意しなければいけないでしょう。季節ごとに色々と場所を移しながら育てるのが良さそうです。まずは秋から春です。この時期は日向を中心にして育てます。この花は寒さに強く暑さに弱い性質があります。秋から冬場、春の初めなどの寒い時期でも特に外に置いておいても問題はありません。
この時にしっかりと日差しが当たるところで育てるようにします。そしてその後にどうするかです。春の間ぐらいならそれ程気温も上がりませんが、4月から5月などになってくると夏のような暑さの日も出てきます。このようになってくるとかなり花の方も弱りやすくなります。日当たりを避けて日陰に置くようにします。
日差しがあるのと日陰ではかなり温度が異なりますから、この移動だけで花の様子も大きく変わります。春以降秋になって気温が低くなるぐらいまでは日陰に置いておきます。10月ぐらいになってくれば落ち着いてきますから日向に出せるようになってきます。庭植えの場合には落葉樹の下に植え、夏場の日差しが遮られるようにします。
種付けや水やり、肥料について
種付けを行うについて土はどうするかです。水はけと水持ちを良くするような配合が必要なので、自分で行うようにするのがいいでしょう。硬質の鹿沼土、軽石、赤玉土を等量に混ぜます。その中にヤシ柄チップを混ぜます。こうすることで水はけと水持ちを良くするような土を作ることができます。
乾きやすい植木鉢を利用している時には土の構成も少し変化させるようにします。軽石の量を減らして赤玉土の量を増やすようにすれば、水持ちの良さをアップさせることができます。こうすることで良い割合の土を作ることができます。水やりはどのようなことに気をつけないといけないかですが、表土が乾いた時に与えるようにします。
高山によく生える植物なので必ずしも水が大量に必要なわけでは無いですが、成長を促すにあたっては水分が必要になってきます。ですから水分量については細かい管理が必要になると言えます。葉っぱのでている時においては乾燥は禁物になるのでそのことを忘れないようにしなければいけません。
鉢植えにおいては、砂床に埋めておく、二重鉢にするなどの方法をすることでできるだけ乾燥を防ぐようにします。この花については休眠をします。通常休眠中には水などを与えないようにするのが一般的ですが、この花に関しては休眠中も乾かさないようにしたほうが良いとされています。植木鉢であっても、地面に埋めておく形にしておけば水分を切らさないので水分不足に陥ることがなくなります。
増やし方や害虫について
植え替えでは、毎年か1年おきに行います。時期としては2月から3月ぐらいです。この時期を過ぎると徐々に休眠から目を覚ます状態になります。休眠状態の時に行うと良いとされています。芽の上2センチから3センチにおいて土をかぶせるようにします。増やす時としては株分けを行う方法を取ります。植え替えなどをするときに地下茎を見てみましょう。
絡み合っているとそれをほぐすだけで傷んでしまうことがあります。大きくなった株を利用してそれを分けて行います。ハサミを使って切り分けますが、いつも使っているはさみでも十分熱湯などで消毒をしてから使うようにします。そうしないとそこから傷んでしまう場合があります。
デリケートな部分を持っている花ですから、気をつけるようにしないといけないでしょう。病気に関してはあまり気にすることはありませんが、害虫はつくことがあるので気をつけます。新芽や若い葉、つぼみにつくことが多いのがアブラムシであったりナメクジです。夏に気温が上がりだすとハダニが発生してきます。
これらの害虫においては、この花だけにつくわけではありません。この花だけ防除した、別の花だけ防除したとしてもその後に別の花から移ってきてしまうことがあります。防除が必要な花においてはきちんと対策を取りながら管理をするようにします。花の見た目で植える位置などを決めることがありますが、つきやすい害虫ごとに分けると、対策がしやすくなります。
マイヅルソウの歴史
日本のおとぎ話においてはいろいろな動物が出てきます。それらの動物は日本に昔からいたりするのでしょう。鳥においては自由に移動することができますから比較的いろいろなところからやってくることがあります。北のほうからであったり、南の方からやってくることもあります。それらの鳥に似ているからと何かの名前が付けられることもあります。
ある草花についてはある動物の名前が付けられています。それはマイヅルソウと呼ばれる草花です。原産地としては生息地が非常に広くにわたっているため特定のところがわかりません。ユーラシア大陸の北東部としてロシア、朝鮮半島、日本などが言われています。その他北アメリカの北西部にも分布するとされています。
日本においては、北海道から九州の主に山地帯の上部、亜高山帯などに群生することがあるとされています。ではなぜこのような名前が付けられたかですが、葉の模様が特徴的だからとのことです。この様子が舞う鶴に似ているからこのように付けられたとされています。
鶴といいますと日本においては広く知られている鳥で、長寿の象徴ともなっています。その鶴の名前が付けられているのですから、この草花においても何らかの意味深い物があるのかもしれません。この花に似ている花としてヒメマイヅルソウと呼ばれる花があります。種類などにおいては同じになるようですが、全く同じではないので区別されるようになりました。間違えないようにしないといけません。
マイヅルソウの特徴
こちらの草花の特徴としてクサスギカズラ目、クサスギカズラ科、スズラン亜科となっています。見た目は確かにスズランに似ています。花の形も特徴的になっています。形態としては多年草ですから、毎年花を見せてくれそうです。草丈は小さいものになると3センチほどです。一方で大きなものになると20センチを超えてくるものもあります。
花が咲くのは、日本においては4月から5月にかけてです。春の中でもある程度暖かさが落ち着いてきた頃に咲く花と言えそうです。とはいえ高山部分で咲く花なので、必ずしも暖かい時期を好んで咲くわけでは無いかもしれません。花の色は白っぽくなります。高山に咲くことから、耐寒性としては極めて強いとされています。
一方で耐暑性についてはあまり強くない花とされています。高山や高原などの他湿原においても見られることがあるようです。葉っぱに関しては、一つの茎において2枚から3枚つけることが多くなります。花が咲かない場合には花の代わりなのかどうかわかりませんが大きめの葉っぱがつくことがあります。
葉っぱは縦に長いタイプではなく、幅がひろいタイプになっています。葉っぱの付き方、生え方も少し特徴があり、少しくぼみをもたせたような形で伸びていきます。くぼみの部分に水分がたまるのではないかと感じるくらいのくぼみができています。この葉っぱについてははっきりした柄がついているのも特徴になります。花はスズランのような小さな花が付きます。
-

-
アガベ(観葉植物)の育て方
アガベとは、別名・リュウゼツラン(竜舌蘭)とも呼ばれ、リュウゼツラン科リュウゼツラン属の単子葉植物の総称のことで、100...
-

-
トウガラシの育て方
トウガラシの原産地や生息地は中南米で、メキシコでは数千年前から食用として栽培や利用されていたのです。このことから中南米や...
-

-
オクラとツルレイシの作り方
オクラは別名アメリカネリといい、アフリカ原産の暑さに強い野菜でクリーム色の大きな美しい花の後にできる若さや食用にしてます...
-

-
スネールフラワーの育て方
スネールフラワーの原産地や生息地は中央アメリカから南アメリカの熱帯地域です。ベネズエラであるというのがよく言われているこ...
-

-
ゼブリナの育て方
ゼブリナは、ツユクサ科トラデスカンチア属で学名はTradescantia zebrinaです。別名はシマムラサキツユクサ...
-

-
プテロスティリスの育て方
プテロスティリスは、オーストラリアの南東部が主な生息地であり、ニュージーランドやニューカレドニア、パプアニューギニアと言...
-

-
イポメアの育て方
ヒルガオ科サツマイモ属の植物です。一般的にはサツマイモの名前で知られています。原産地には諸説あり、アフリカ、アジア、メキ...
-

-
簡単な人参の栽培の仕方について
野菜作りなどの趣味の範囲でも、人参の栽培は簡単に作る事ができます。ベランダなどでのプランター栽培でも作る事ができるのでお...
-

-
モヤシの育て方
原産地は歴史的には古代中国ですが、実際は多分世界中で作られていて、生息地も昔から今に至るまで世界中ということになります。...
-

-
オヤマリンドウの育て方
オヤマリンドウの特徴は名前の由来にもなっておりますように、ある程度標高の高い亜高山や高山に咲くことが大きな特徴です。そし...




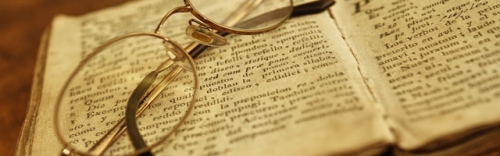





こちらの草花の特徴としてクサスギカズラ目、クサスギカズラ科、スズラン亜科となっています。見た目は確かにスズランに似ています。花の形も特徴的になっています。形態としては多年草ですから、毎年花を見せてくれそうです。