シシトウの育て方

シシトウの育てる環境について
シシトウの生育気温は23~28℃と高めです。種からも育てられますが時間がかかってしまうので、初心者の方はあらかじめ苗を購入して植えられる方がお勧めです。本葉が10〜15枚程度ついており、一番花が開花した苗を選ぶのがコツです。
多湿を嫌い、浅く根をはる性質がありますので、植え付けるプランターなどは大きくて深めのものを用意しましょう。水はけの良いようづの植え付けますが、市販の培養土をしようすれば大丈夫です。自分で作る場合、赤玉土6:腐葉土3:バーミキュライト1を混ぜあわせたものを使用するようにします。
酸性の用土に弱いので、植え付けをする2週間前までには用土に石灰を施し、化成肥料で元肥を与えておきましょう。しっかりと土を耕しておくのもポイントです。プランターで育てる場合、ナス科の植物は連作障害を起こすことがありますので必ず新しい用土を使うように注意しましょう。
畑で育てる場合はしっかりと土を耕した後、幅約1メートル、高さ10〜20センチほどの畝を作っておきましょう。畝と畝の間は約50センチほど空けるようにします。植え付けをするのは午前中が向いています。株と株の間はプランターならば20センチ、畑ならば30センチほど空けて植えます。
あらかじめポットより一回りほど大きな穴を掘って、そこに丁寧に植えつけるようにしましょう。浅植えをした後は周りを軽く手で抑えてたっぷりと水を与えておきましょう。その際に仮支柱を立てておくことをお勧めします。
種付けや水やり、肥料について
浅植えで育てるため、水切れには注意するようにします。用土が乾かないようにたっぷりと水を与えるようにします。水が不足すると、せっかくの実が辛くなってしまうこともあります。夏場は特に乾きやすいので朝と夕方に2回ずつほど水やりをしましょう。
昼間に水やりをすると日差しで水分が沸騰してしまうことがありますので、必ず涼しいうちに行います。株が30センチほどになると下の方からワキ芽が出てることがありますが、栄養の分散を防ぐためにも小さい内に摘み取っておきます。プランターで育てている場合は主枝1本と側枝2本の3本仕立て、
畑で育てている場合4本仕立てくらいが理想的です。ワキ芽をとると風で倒れやすくなりますので必ず支柱で支えてあげるようにしましょう。シシトウはよく実をつけるので肥料は必ず与えるようにしましょう。これも甘みのある実をつけるポイントです。
生育期間中には月に一度くらい有機肥料を与え、土に混ぜてあげましょう。液体肥料を週に一度くらい与えるのもよいでしょう。窒素分が多いと株が育ちすぎてしまうので、収穫期には窒素分が少なめの肥料を使うようにします。開花後2週間ほどで実がつくようになってきます。
5〜7センチ程度のものをヘタからハサミ等で切り取って収穫します。収穫が遅れてしまうと赤くなって辛味が増してきますし、そのままにしておくと株が弱ってきますので早めに収穫してしまいましょう。収穫したシシトウは新聞紙で包んでポリ袋などに入れ、冷蔵庫の野菜室で保存しておくと4〜5日ほどは保ちます。
シシトウの増やし方や害虫について
シシトウは種で育てることも出来ますが、その場合は植えつけるまでに70日以上掛かってしまいますので、ポット苗などで育ててあるものを購入することが一般的です。連作を嫌いますので、必ず新しい用土を使用することが重要です。基本的には病気にも強い植物ですが、
まれに斑点病やうどんこ病などにかかることがあります。乾燥していると発生しやすくなりますので、加湿をしてあげることによって予防することも出来ます。発生した葉はこまめに取り除き、他の葉に伝染してしまうことを防ぎましょう。園芸店などには専用の薬剤が、
販売されていますので、散布してあげるようにします。また、アブラムシやハダニが発生することもあります。アブラムシが発生するとモザイク病などの病気を引き起こす原因になりますので、見つけたらすぐに駆除するようにしましょう。アブラムシ専用の駆除剤を、
使用するのもの効果的ですが、野菜に薬剤を散布することに抵抗のある方も少なくないでしょう。その場合は牛乳を霧吹きなどでスプレーしてあげると窒息してしまいますのでお勧めです。木酢液なども効果的ですので、まずはこちらの方法で試してみるとよいでしょう。
ハダニは乾燥しがちになると発生しやすくなります。定期的に株の上からもしっかりと水を掛けて加湿してあげると予防になります。ハダニは葉の裏側に発生することが多いので、表面だけでなく、葉の裏側にも霧吹きなどで定期的に葉水を与えてあげるとより効果的です。
シシトウの歴史
程よい辛味があり、あらゆる料理に使用されて人気のあるシシトウですが、その正式名称はシシトウガラシ(獅子唐辛子)であり、それが省略されてシシトウと呼ばれるようになりました。実の形が獅子の頭に似ていることからその名が付けられたと言われています。
シシトウは中央アメリカから南アフリカを原産とするナス科の植物です。唐辛子の仲間ですが、唐辛子ほどの辛味はありません。15世紀、コロンブスによってスペインに運ばれ、その後ヨーロッパで辛味の少ない品種への改良が進みました。日本に入ってきたのは江戸時代で、
ポルトガル人によって持ち込まれ、栽培されていました。その頃入ってきたのは辛味のあるトウガラシでしたが、明治時代には欧米から辛味を抑えた品種が入ってきました。今のように一般的に栽培されるようになってきたのは第二次世界大戦後になります。
植物分類学によるとピーマンと同種とされており、殆ど区別がつきません。元々熱帯地域を生息地としていただけあって高温に強いため、日本の厳しい夏も元気に乗り切ってくれる植物です。育て方も簡単で、秋口まで実を収穫することができるので長く楽しめます。
野菜と言ったら畑を耕したりと大変なイメージがありますが、シシトウはプランターや鉢でも育てられるので、お家に庭や畑がない方でもベランダなどで栽培することが可能です。病気や害虫にも強いので、家庭菜園の初心者の方にもうってつけの野菜と言ってもよいでしょう。
シシトウの特徴
シシトウは緑の実を食するのが一般的ですが、実はこれは未成熟の実です。トウガラシ同様、成熟すると赤くなります。シシトウはビタミンCとカロチンといった栄養分を豊富に含んでおり、免疫力を高めて疲労回復をはかってくれますので夏バテに効果的です。
風邪の予防や、血圧上昇にも効果があります。ビタミンCは加熱すると殆どなくなってしまうのですが、シシトウに含まれるビタミンCは加熱しても減りにくいため、美容にも効果的だと言われています。抗酸化作用もありますので、アンチエイジングにもピッタリです。
また、カプサイシンの成分も含まれていますので、脂肪燃焼や血行促進の効果もあり、ダイエット中の方にもお勧めの夏野菜です。まれに辛味の強いものが存在しますが、それは受粉時に単為結果を起こしてしまっていたり、生育過程において株が何らかのストレスを感じたりすると起こと言われています。
見た目では辛味のあるものを見分けるのは難しいですが、黒みがかったものや、いびつな形のものは辛い傾向にあるようです。また、辛味が強い実には種が少ないので触ってみることによってある程度判断することは出来ます。様々な調理法で食されるシシトウですが、
油との相性がよく、ビタミンB6やβカロテンなどは特に油と一緒に摂ると吸収が良くなりますのでお勧めです。天ぷらなどにして食する場合は、破裂してしまうことがありますので、あらかじめ楊枝などで小さく穴を開けて調理するとよいでしょう。
野菜の育て方など色々な植物の育て方に興味がある方は下記の記事も凄く参考になります♪
タイトル:ハバネロの育て方
タイトル:ショウガの育て方
-

-
ホヤ(サクララン)の育て方
花の名前からラン科、さくらの科であるバラ科のように考えている人もいるかもしれませんが、どちらにも該当しない花になります。...
-

-
エゾエンゴサクの育て方
エゾエンゴサクとは北海道や本州の北部の日本海側の比較的湿った原野や山地に古くから生息してきたという歴史があります。生息地...
-

-
ナンテンハギの育て方
ナンテンハギはマメ科でありますが、他のマメ科の植物がツルを使って他の植物に頼ることで立つ植物であるのに対して、そうしたツ...
-

-
ハナズオウの育て方
ハナズオウはジャケツイバラ科ハナズオウ属に分類される落葉低木です。ジャケツイバラ科はマメ科に似ているため、マメ科ジャケツ...
-

-
コンボルブルスの育て方
コンボルブルスは地中海の沿岸を中心とした地域で200種くらいが自生しているとされていて、品種によって一年草や多年草、低木...
-

-
チャイブの育て方
チャイブは5000年ほど前から中国で食用として利用されたことが記録として残っています。料理としてのレシピも紀元前1000...
-

-
カンパニュラの仲間の育て方
カンパニュラはラテン語で「釣鐘」を意味しています。和名もツリガネソウだったり、英名がベルフラワーだったりすることから、ど...
-

-
ラグラスの育て方
ラグラスは、ふさふさした穂がかわいらしく、野兎のしっぽの意味を持つ名前で、イネ科の植物です。原産地は地中海沿岸で、秋まき...
-

-
スリナムチェリーの育て方
スリナムチェリーはフトモモ科の常緑の低木でこの樹木の歴史は非常に古くブラジルの先住民族が赤い実を意味するスリナムチェリー...
-

-
キュウリの育て方
どうせガーデニングをするのであれば、収穫の楽しみを味わうことができる植物も植えたいと希望する人が少なくありません。キレイ...




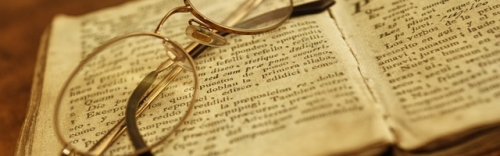





程よい辛味があり、あらゆる料理に使用されて人気のあるシシトウですが、その正式名称はシシトウガラシ(獅子唐辛子)であり、それが省略されてシシトウと呼ばれるようになりました。