マスタード(カラシナ)の育て方

育てる環境について
栽培をするにあたっては育て方をどうするようにしたらよいかです。生息地としては元々は中央アジア付近とのことで乾燥したところで育つような雰囲気があります。栽培適地として言われているのが日当たりの良い場所で、冷涼な気候を好むとされています。あまり夏に暑くなるようなところは好ましくない事がわかります。
土壌におけるペーハーとしては6.0前後とされていますから、それを守るように土の管理をするようにすると育てやすくなるかもしれません。発芽温度としてはどれくらいかですが、6度から35度までとされています。冷涼なところを好むとされていますが、35度ぐらいの暑さのところでも特に弱ってしまうなどのことはないようです。
それとは別の発芽温度として15度から25度ぐらいとあります。夏にこれくらいの温度となると、北海道、本州では東北、信州などの高原などに限られてくるかもしれません。生育をするのに適温とされるのが15度から20度となっています。発芽をしたとしてもその後にどんどん成長してくれなくては意味がありません。
30度を超えるところだと何とか発芽をすることができてもその後に生育することができないかもしれません。観賞用として育てることもあるでしょうが、なんといっても食べるために育てる人も多いでしょう。草丈が20センチ以上になった頃がちょうど食べごろとされます。これくらいになった時に収穫をすると、いい味の状態になるでしょう。
種付けや水やり、肥料について
どのような用土を利用しながら行うかですが、比較的いろいろな土壌でも良いとされています。ポイントとして押さえたいのが保水力と弱酸性の土壌になります。よく言われるのは水はけの良さですから、それについては特に問題視されていない条件になっています。種まきの時期としては、通常は秋まきをするとされています。
秋に発芽して越冬、翌年に枯れるパターンで成長します。涼しいところにおいてはどのような育て方が出来るかといえば春まきにすることができます。春と秋の2回収穫することができれば、当然量も増やすことができます。気象条件が異なると必ずしも春と秋で同じ量になるわけではないですし、
味の雰囲気なども異なってくるので必ずしも2倍になるわけは無いですが、たくさん収穫できれば栽培するしがいが出てくるでしょう。何かのやりがいを持って行うことが出来るのはいいことです。収穫に関しては種まきから1箇月から2箇月ぐらいに出来るとされます。ですから比較的成長も早いです。
肥料についてはどのように与えていくかですが、種をまいている間はだいたい追肥を行っていきます。美味しくしていくためには必要になってくるでしょう。秋から冬、冬から夏ぐらいまで行い続けることが多くなります。真冬において行われることとしてはビニールトンネルの利用があります。気温の調節をしないといけない場合があります。涼しいところは冬に寒くなることがありますから、対応が必要です。
増やし方や害虫について
野菜の栽培をする時、最初は食べることが出来るものが収穫できただけでもうれしいと感じがしてくるでしょう。とりあえずは第一回目の栽培を成功させるようにします。そして2回目、3回目に挑戦していくようにします。野菜に関しては収穫することによって実などを食べることがあります。そのために増やす方法としてはまずは種まきがあります。
種を販売しているところがありますから、そちらにおいて種を購入して、それをまくことによって増やすことができます。種についてはマスタードとして使うことができますが、これを使って種まきをすることができます。そうすればよりたくさん栽培することが可能になりそうです。
マスタードをつくろうとするとかなりの量を栽培しないといけないでしょうし、作ってしまえば増やすことができなくなります。増やすために使うのか、マスタードとして使うのかを分量管理をするようにした方がいいでしょう。作ったとしてもそれ程多くの量を作ることが出来るわけでは無いでしょうから、
あまり無理な計画を立てないようにすることもだいじになるでしょう。メインとしては葉っぱの部分を食べることにして、通常は種を次の年にまくように利用すればどんどん増やすことができます。病気であったり虫においてはあまりつきにくいとされています。香りが独特ですが、これを虫のほうがあまり好まないのかもしれません。そうすると多の植物の周りでも効果を得られそうです。
マスタード(カラシナ)の歴史
食べ物の中には主にそれを食べるためのものもあれば、薬味のようにして使うことによって生きてくるものもあります。果物の中ではレモンなどは直接食べることはほとんど無いですが、味付けなどに使うことはあります。わさびにおいてもあまり直接食べることはありません。お刺身などを食べるときの薬味として使います。
主な材料になることも薬味になるものもあります。ネギや大根などは薬味になることもあれば、メインで使われることもあります。シソも天ぷらにすることもあれば、香りづけにすることもあります。どちらかと言えばシソの様な使われ方をするものとしてマスタードがあります。別の名称としてはカラシナと呼ばれることもあります。
よく粒マスタードと言われる商品がありますが、これはその種を潰すことによって作られ事になります。メインの辛子は粒を利用することになりますが、ではその葉っぱに関してはどうかですが、食べることができます。これが種の辛子のようにぴりっとした辛味があって美味しいとされています。
この植物の原産としては中央アジアとされています。地中海沿岸から伝わってくるときに自然交雑によって生じたのでしょう。日本に渡来してくるのはかなり古いとされています。文献によると弥生時代にはすでに存在したとされています。わさびといいますと日本的で辛子は洋風なイメージがあります。でもこちらについても古くから日本にあり、利用されていたことがわかります。
マスタード(カラシナ)の特徴
特徴として、フウチョウソウ目、アブラナ科、アブラナ属となっています。確かに葉っぱを見るとアブラナ、菜の花と同じような形をしています。越年草としても知られています。高さとしては1メートルから1.5メートルほどの高さになり、春にはアブラナのような花を咲かせるとされています。
種の利用がよくされることで知らえていますが、葉っぱの部分においてもよく利用されています。また、茎の部分についても炒めたり、漬物にしたりして調理する例が全国にあります。品種としてはどのようなものがあるかですが、黄からし菜があります。こちらについては葉が通常のものよりも大きく、辛味が強いタイプになっています。
種子を辛子の原料として使うことが多くなります。葉からし菜葉濃い緑色の大葉でさやわかな辛味になっています。花や茎を朝漬けで楽しむことが出来る野菜になります。つまりは野沢菜や高菜などと同じような使い方をすることが出来る葉物の野菜として使われることが多くなっています。
この植物の花についてはアブラナの花と同じような黄色であったり白っぽい花になります。花が咲ききる前のつぼみの状態などの時に葉と一緒に料理などをすることが多くなるようです。この葉自体に味がついていて人気のある食材です。葉っぱとしては全体的にシワがあり、縁もまっすぐではありません。葉脈の方はよく見えますが、真ん中に一本通っているものがはっきり見えるぐらいで後はあまりわかりません。
-

-
コノフィツムの育て方
コノフィツムは、アフリカ南部(南アフリカ・ナミビア南部)が原産の生息地の多肉植物です。また、ハマミズナ科コノフィツム属に...
-

-
タンポポの育て方
道端などで春先に良くみかける”タンポポ”。キク科タンポポ属の総称になります。地中海沿岸・中央アジア原産になり、日本には外...
-

-
コレオプシスの育て方
コレオプシスはアメリカ大陸、熱帯アフリカにおよそ120種類が分布するキク科の植物です。園芸用としては北アメリカ原産種が主...
-

-
カンパニュラの育て方について
カンパニュラは、釣り鐘のような形の大ぶりの花をたくさん咲かせるキキョウ科の植物です。草丈が1m近くまで伸びる高性タイプの...
-

-
スイスチャードの育て方
スイスチャードという野菜はまだあまり耳慣れないという人が多いかもしれません。スイスチャードはアカザ科で、地中海沿岸が原産...
-

-
イキシアの育て方
イキシアはアヤメ科の植物で、原産地は南アフリカになります。また、別名として「ヤリズイセン(槍水仙)」、「コーン・リリー」...
-

-
ネズミモチ(プリベット)の育て方
ネズミモチ(鼠黐・Ligustrum japonicum)は、モクセイ科イボタノキ属の樹木です。 生長すると樹高が4~7...
-

-
観葉植物としても人気があるイチゴの育て方
イチゴは収穫が多く病気や虫に強いので、家庭菜園で人気です。イチゴの中でも比較的葉が多いワイルドストロベリーは観葉植物とし...
-

-
セイロンベンケイの育て方
セイロンベンケイというのは、ベンケイソウ科リュウキュウベンケイ属の植物で別名トウロウソウと呼ばれることがあります。ベンケ...
-

-
へらおおばこの育て方
へらおおばこは我が国に在来しているプラントのオオバコの仲間であり、またオオバコに似ているとされていますが、へらおおばこは...




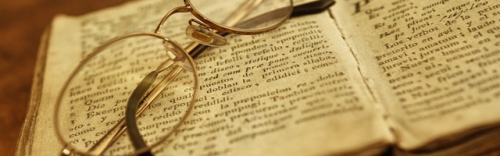





特徴として、フウチョウソウ目、アブラナ科、アブラナ属となっています。確かに葉っぱを見るとアブラナ、菜の花と同じような形をしています。越年草としても知られています。高さとしては1メートルから1.5メートルほどの高さになり、春にはアブラナのような花を咲かせるとされています。