ネフロレピスの育て方

ネフロレピスの植え方
基本的に真冬以外であれば植えつけは可能ですが、最も適している時期は5月から9月頃です。株を買って来たら、水はけのよい養分の豊富な土に肥料を混ぜて植えつけをしましょう。一般に売られている観葉植物用の用土で構いませんが、赤玉土を全体の半分の割合に、腐葉土や軽石などを適度に混ぜたようなものが栽培に適しているでしょう。
ネフロレピスを美しく見せてくれるのは小~中の鉢植えや釣り鉢ですが、大きな鉢に植えても豪華な印象になるので人目を引くものにすることができます。ただ、大きな鉢植えは根が詰まったり株が蒸れたりしやすくなってしまい、植え替えをする時に作業が困難になってしまうことが多いです。
ですので、育てるのに慣れていないうちは小さめのものから挑戦すると失敗が少ないでしょう。成長するにしたがい、鉢の周囲にそってぐるりと円形に葉を伸ばし始めますので、広くスペースを取った場所に置いてやることが成長を妨げず、見栄えの点でも優れています。
植え替えと、増やし方
鉢の底から根が伸びてきたり、新しい芽が出にくくなったりしてくると、根詰まりを起こしている可能性があるので植え替えをしてやる必要があります。シダ類の植物は成長スピードが速くよく育つので、少なくとも1年に1回ほどは植え替えの作業が必要です。
植え替えをする際は根鉢の下3分の1くらいを切り落とし、伸びた葉もチェックをして傷んでいるところは切っておきます。植えつけた時と同じくらいのサイズの鉢に同じ土を用意して植え替えましょう。ネフロレピスはシダの仲間の植物なので、種を付けて増えるものではありません。
そのため増やす時には株分けという方法を使いますので、種や果実を付ける植物を種付けする場合とはすこしやり方に違いがありますが、難しいものではありません。植え替えの際に作業してしまうと手間がないでしょう。株分けに適している時期は5月から6月です。
鉢から根鉢を抜いて3分の1を切り落とした状態で3~4等分にざっくりと根を手で割り開いて小さな株に分け、傷んだ部分は根の部分から切り落として処分します。元の大きさの鉢と、栽培していたものと同じ成分の土を用意してそこに植えつければ完了です。植え替えて一か月ほどは直接日の当たらない場所に置いておきましょう。
根の部分から子株と呼ばれる小さな株が伸びている場合は、それを切り取って植え替えることで増やすこともできます。その場合は3.5号サイズの小さな鉢に植えてやり、日陰に置いて新芽が出てくるまで育てます。新しい葉が出てきたら大きめの鉢に移し替えて肥料を追加するとその後の育成が良好になります。
基本的な育て方と日常の管理方法
ネフロレピスは水分を好み、強すぎる日差しと乾燥を嫌います。この点をよく掴んでおけば、植物を育てる時に最も苦戦する冬の時期にも特別なことをする必要はなく、室内に置いておくだけでどんどん育ってくれる初心者にも育てやすい植物です。シダは元来は大きな木の根元などに生えているものですから、直射日光のような強すぎる光を好みません。
日なたにおいておくと葉が焼けてしまい、せっかくの美しい葉もしなだれて元気がなくなってしまいます。かといって暗すぎる場所に置いても土の水分がこもって根腐れを起こしてしまうので、基本的には日が直接当たらない室内や日陰に置いておくのが良いでしょう。
ネフロレピスは庭植えをすることもできますが、室内で育てることを考えて改良された経緯もある品種ですので、お部屋の中にグリーンが欲しいという方はぜひ室内での育成にもチャレンジしてみましょう。水やりや湿度管理については、ネフロレピスが乾燥を嫌う植物であることを覚えて置けば自ずと弱らせないような管理をすることが出来ます。
春から秋にかけては気温が上がり、水分が蒸発しやすくなるとともにネフロレピスが水を吸う力も強くなります。土への水やりは勿論、霧吹きなどで葉に水分を行きわたらせてあげることも行いましょう。春や秋はこれを毎日、夏場は1日に2回水やりを行います。気温が下がる冬場には、水やりを頻繁にしすぎないように注意します。
気温が低くなると水分の蒸発量が減り、植物自体の活動も弱くなるので土が蒸れて根っこが傷みやすくなってしまいます。冬場の水やりは土を触ってみて、乾いているなと感じたら行う程度に留めますが、湿度を一定に保つためにも葉への霧吹きを行うことは続けたほうが良いでしょう。
ネフロレピスは肥料を好む植物です。春から秋にかけての芽が出る季節には緩効性の肥料を2か月に1回ほど使って育成を促進します。即効性の液体肥料を10日に1度ほど与えることも良いでしょう。病気や害虫はほとんどありませんが、春から秋にかけての暖かい季節にカイガラムシやナメクジが発生することがあります。
見つけたら取り除くようにしていれば大きな被害はありません。病気についても春から秋にかけて炭そ病が発生することがあり、葉の色が黄色く変わったりチリチリとすることがあります。その場合は変色した部分を根元から切り落として病気が広がらないようにしましょう。
ネフロレピスの歴史
ネフロレピスはシダの仲間に属する植物で、亜熱帯地方や熱帯地域を主な生息地として世界中に分布しています。中米を原産とし、現地では幻の鳥として著名なケツァールの尾と呼ばれています。日本では紀伊半島や伊豆半島にタマシダと呼ばれるものが自生していますが、鑑賞用として多く出回っているのはネフロレピス(セイヨウタマシダ)です。
シダは世界最古の植物で、約4億年のものと考えられる化石からも出土したことがあります。気の遠くなるような年月を経て非常に多くの種類に分かれていき、観賞用のものが人の手によって作られるに至りました。ネフロレピスだけでも現在では約40もの種類がありますが、一般的に園芸用として人気の高いのはボストンファーンという種類のものです。
ネフロレピスはもっとも美しいシダのひとつと考えられ、観葉植物として近年とてもポピュラーになっています。19世紀のロンドンは産業革命後の工業の発展で空がいつもどんよりと灰色に曇ってしまうほどだったので、緑を生活に取り入れるガーデニングブームが広がり、それにともなって丈夫なシダの仲間であるネフロレピスの品種改良が盛んになったという伝承があります。
ネフロレピスの特徴
ネフロレピスは常緑の植物で、成長するに従って羽のように茎を伸ばし、そこに美しく波打った葉を隙間なく付けます。距離を置いて見た時に、鉢から噴水のような姿で葉がしなやかに垂れ下がっているのがとても優雅なので、通常の鉢植えのほかに釣り鉢をして飾るスタイルが人気です。
品種は非常に多様ですが、どれも40~50cmくらいに成長することが多く、葉の一つ一つも弱いので壁や他の鉢植えに接することのないような広いスペースが必要になってきます。湿度の高い地域を原産とする植物なのでもともと乾燥には弱く、高湿度の環境下に適しています。
寒さには非常に強く、室内に置いておけば冬の間も枯れる心配はほぼありませんが、暖房機などの乾燥には弱く、屋外に置いても冬場の乾燥によって枯れてしまうケースがあるようです。人類よりも長い歴史を生き抜いてきた植物というだけあり、虫もつきにくく丈夫で手がかからないので、室内で育てる植物としては最適なものです。
なお、直射日光を嫌うので日陰でも育ちます。西または東向きの窓の近くで管理すると育てやすくなりますし、半日陰になるようなバルコニーなどに置いてやると風通しも良くなり蒸れも防げるでしょう。
観葉植物の育て方など色々な植物の育て方に興味がある方は下記の記事も凄く参考になります♪
タイトル:アスプレニウムの育て方
タイトル:コロカシアの育て方
-

-
マルバストラムの育て方
特徴としてどのような属性になっているかです。名前としてはアオイに似ているとなっていますが、種類としては同じと考えられます...
-

-
ミニメロンの育て方
メロン自体の歴史は古く、古代エジプトや古代ギリシャでも栽培されていたことが知られています。メロンは暖かい地域で栽培するこ...
-

-
モモバギキョウの育て方
この花の特徴としては、キキョウ科、ホタルブクロ属となっています。園芸においては山野草、草花としての利用が多くなります。形...
-

-
コルムネアの育て方
コルムネア属の植物は熱帯アメリカに自生していて、熱帯雨林に生えている樹木の幹の部分や露出している岩の部分などに付着しなが...
-

-
スモモの育て方
スモモにはいくつかの種類があり、日本、ヨーロッパ、アメリカの3つに分類されます。ヨーロッパではカスピ海沿岸が生息地だった...
-

-
イングリッシュ ラベンダーの育て方
イングリッシュ ラベンダーは、シソ科のラベンダー属、半耐寒性の小低木の植物です。ハーブの女王としてゆるぎない地位を確立し...
-

-
小松菜の栽培に挑戦してみよう。
今回は、小松菜の育て方について説明していきます。プラナ科である小松菜は、土壌を選ばず寒さや暑さにも強いので、とても作りや...
-

-
ニゲラの育て方
地中海沿岸から西アジアが原産の一年草の植物です。ニゲラの仲間はおよそ15種類がこの場所を生息地としています。この中でもニ...
-

-
ヤーコンの育て方
特徴としてはまずはキク類、真正キク類、キク目、キク科、キク亜科、メナモミ連、スマランサス属となっています。キクの仲間であ...
-

-
アルテルナンテラ‘千日小坊’の育て方
園芸店や生花店などでは千日小坊という常緑多年草が売られています。これはペルーやエクアドルといった中米原産の植物です。アル...




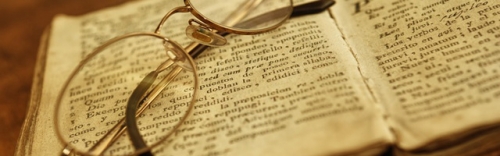





ネフロレピスはシダの仲間に属する植物で、亜熱帯地方や熱帯地域を主な生息地として世界中に分布しています。中米を原産とし、現地では幻の鳥として著名なケツァールの尾と呼ばれています。日本では紀伊半島や伊豆半島にタマシダと呼ばれるものが自生していますが、鑑賞用として多く出回っているのはネフロレピス(セイヨウタマシダ)です。