オダマキの育て方

育てる環境について
この花は、手間いらずといっても良いほど、種が飛んで行けばどこでも芽を出して育つ花でもあります。草木を育てるのが得意でない人でも、簡単に花を咲かせることができる物と言っても良いほど、育て方は楽です。ただ、この花を育てる環境としては、涼しいところであること、そして水はけがよく乾燥した土の所を好みます。
種を植える時期は、2月ごろから3月上旬あたりが良いでしょう。また、植え付けや植え替えと言った時期もこの時期が適しています。また、肥料を与えるのは鉢植えでも庭植えでも3月から9月ごろまですることです。開花期は早いと4月半ばからしますが、大体が5月から6月ごろとなっています。
此花は、原産地は北米大陸、ユーラシアとされ、草丈も30センチから50センチに伸びます。耐寒性にも強く、そして耐暑性にも普通に育つ草花でもあります。季節が過ぎて秋から冬になると、葉は落ちていきます。根っこの部分だけが残りますが、決して枯れていないので、そのままにしておきましょう。
また、日陰でも育つという強い草花でもありますので、初心者の人でも育てやすい植物となっています。冬には一葉や茎が枯れてしまいますが、根っこはしっかりと生きています。春にはれば、再び茎を伸ばしていき、花をつけていきます。葉が広がるので、花が開花したころはボリュームのある植木として、見栄えがします。変わり花もありますので、色と形を合わせて庭を飾れば、様々な花を楽しめます。
種付けや水やり、肥料について
オダマキは、基本的にはどこでも育つ花なので、種が自然に飛んでその地に根付いたら自然に芽が出てきます。とはいえ、やりキチンと育てたいものでしょう。ならば、種を付けた際には収穫をして、次の種まきの際に備えておきましょう。種付けは大体が2月ごろを目安にしてください。意外に水はけが良く、乾燥した土を好みますので、手間がかかりません。
ただし、芽が出て来たら定期的に水やりをしてください。春から夏にかけては、水もすぐに乾いてしまいますので、朝と夕方に上げるのがベストでしょう。生育期間は3月から6月です。夏になると生育が鈍りますが、秋ごろからは再び育ち始めます。肥料を与えるには、3月から9月ごろ、開花時期になれば液体肥料を10日に1回の割合で与えてください。
液体肥料の濃さは、普通の草花に与えるほどのものと同じで良いです。また、植え付けるのであれば、土にあらかじめ肥料である粒上のものを混ぜておきましょう。それから植え付けをしてください。用土を作るのであれば、赤玉の小粒かもしくは日向土の軽石のように軽くて硬く、白い用土で水はけを良くするようにしておきます。
そして、7の割合で腐葉土を混ぜたもの、あるいは市販で売られている山野草の土を利用してください。市販の土は、あらかじめ肥料も全て入っているので、そのまま使えます。また、鉢植えをするのであれば、3月か暑い日差しが過ぎて9月中ごろから10月ごろが良いでしょう。伸びすぎた根っこは切り、主根は傷つけないように植え替えてください。
増やし方や害虫について
この花は強い草花ですが、かかりやすい病気や害虫もまたあります。害虫はアブラムシにハダニ、ヨトウムシ、なめくじです。アブラムシとハダニは、植物の汁を吸ってしまう害虫で、放っておくとどんどんと増えていき、仕舞には植物を弱らせてしまうという物です。害虫を見たら、薬剤を散布して駆除することです。
また、ヨウトウムシは夜間に活動し、葉を食べつくしてしまいます。見つけずらい害虫なのも厄介です。同じくなめくじも葉を食べてしまいますので、見つけたら駆除をしてください。そして、オダマキの増やし方ですが、大概は種を収穫して時期が来たら植えると自然に芽を出して来ます。ただ、比較的に寿命は短く、3年から4年で老化してきます。
絶やしたくないのであれば、こまめに種まきをすること、そして株分けをしていくことです。種で増やすのであれば、保存してもできますが、種をすぐに巻く方法としてとりまきというものもあります。種の保存よりも、とりまきをした方が発芽も良く揃います。この場合は、5月から6月ごろに巻くことになりますが、
ただ夏の暑さで枯れてしまうこともありますので、注意が必要です。株分けで増やす場合は、冬を越して芽吹いた頃の3月ごろが良いでしょう。ただ、株分けすると機嫌を損ない、枯れてしまうちおう事もあります。また、この花は面白い事に自然交雑をしやすい品種でもあります。そのため、色んな種類のオダマキを育てる事ができるのも、この花の面白いところでしょう。
オダマキの歴史
関東では4月中ごろになると、色とりどりのオダマキが花を咲かせます。花屋でも多く見かけるこの花は、手間いらずでとても育てやすいとして多くの園芸を好む人から好かれる花でもあります。さらに、花の色が豊富にあることから、多くの園芸家が色んな色を集めて育てている人も多くいます。この花は、キンポウゲ科オダマキ属で、多年草です。
北半球の温帯地方を中心に、生息している花でもあります。この花の歴史は古く、園芸品種として栽培されるようになったのが明治以降になっています。西洋のものが入ってきた事により、日本でも栽培されるようになりました。日本の涼しい環境に生息地としているミヤマオダマキを園芸品種化としたものと推測されています。
原種から、現在の色とりどりの花へ作られました。そして、ちょっとした花の形が違うことで、コレクターしている人もいるほどです。愛らしくとても綺麗なこの花の名前の由来となるのは、麻糸をまく苧環の形に似ているからと言われています。確かに、花の名前でも特色のあるものだと言えましょう。
現在は日本原産ミヤマオダマキとヨーロッパ原産の西洋オダマキの2つのパターンのものと区別されています。日本原産のものは、花全体がとても丸い感じでもあり、色の幅も広くあります。ピンクかかったものは、変わり花としても人気です。方や、西洋の物は細身がかった花です。特に黄色の花があり、日本の花よりも少しだけ遅れて咲くようにも感じます。
オダマキの特徴
オダマキの花の特徴は、一つの茎に可憐な花をいくつも付けて咲くことと、そして其の葉がハート形をしています。葉っぱがハート形というのも、とても可愛らしいのですが、雑草でもこの形に似たものがあり、小さい芽が出てきた時には間違えてしまいます。この花は、30センチから50センチの茎の先端に3センチくらいの花を付けます。
特徴的なのが垂れて咲くので、花を良く見る際には下からのぞく事をしなければなりません。花弁、がく片とどちらも5枚あり、花弁の基部には距と呼ぶ袋のような突起があります。涼しい気候を好み、そして杯酢の良いところ、乾燥した土が好きです。さらに、園芸品種としては大きくわけて日本産と西洋産の2つに分かれるのですが、
日本のものと西洋のもの花を見比べると、日本の方が柔らかい曲線を描いたような花の形をしています。西洋のものは、細身で尖がった感じがあります。また、日本の原産のものは白や紫、桃色、黄色、黒、青、オレンジ、茶色といったさまざまな複色です。花の形でも変種に八重咲きするフローレ・プレノというものや、
同じ八重咲きするステラータは花の後ろにある突起した部分がない花です。さらにこの突起の距がないタイプで八重咲するクレマチスもあります。余談になるのですが花言葉は、おろか、必ず手に入れる、断固として勝つです。そして色別では紫色は、捨てられた恋人、勝利の決意で、赤色は素直です。白色は、あの方が気がかりになるという言葉になります。
-

-
アメリカノリノキ‘アナベル’の育て方
白いアジサイはアメリカノリノキ、別名セイヨウアジサイの園芸品種であるアナベルという品種です。アジサイの生息地は世界ではア...
-

-
レナンキュラスの育て方
レナンキュラスはキンポウゲ科・キンポウゲ属に分類され、Ranunculusasiaticsの学名を持ち、ヨーロッパを原産...
-

-
タカナ類の育て方
アブラナ科アブラナ属のタカナはからし菜の変種で原産、生息地は東南アジアと言われています。シルクロードを渡ってきたという説...
-

-
タイムの育て方
学名はThyme、分類はシソ科イブキジャコウソウ属に当たります。高さおよそ15センチメートルから40センチメートルほどに...
-

-
シペラスの育て方
シペラスは、カヤツリグサ科カヤツリグザ(シぺラス)属に分類される、常緑多年草(非耐寒性多年草)です。別名パピルス、カミヤ...
-

-
マユミの育て方
マユミはニシキギ科に属しますが、ニシキギという名称は、錦のような紅葉の美しさから名づけられたと言われています。秋になると...
-

-
初心者でも簡単な観葉植物について
最近は趣味として、ガーデニングなどを楽しんでいる方がどんどん増えています。自宅の庭に色とりどりの花を咲かせたり、ベランダ...
-

-
フウセンカズラの育て方
フウセンカズラは、熱帯地方原産の植物です。アメリカ南部、アフリカ、インド、東南アジアなどを生息地とし、湿気の多い雑木林や...
-

-
ジュズサンゴの育て方
花期は夏から秋頃になります。果実が見煮るのは9月から11月頃、ヤマゴボウ科の常緑多年草です。葉は互生し、長卵形をしており...
-

-
リョウブの育て方
両部の特徴においては、まずは種類があります。ツツジ目、リョウブ科になります。落葉小高木になります。若葉に関しては古くから...




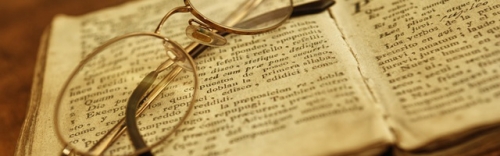





この花は、キンポウゲ科オダマキ属で、多年草です。北半球の温帯地方を中心に、生息している花でもあります。この花の歴史は古く、園芸品種として栽培されるようになったのが明治以降になっています。