ワタ(綿)の育て方

育てる環境について
用途としては、様々な織物製品として使われていて、吸収性が良いということから、タオルやローブやベッドのシーツなどにも、今でも利用されていますが、衣類としてもジーンズなどや作業着、また靴下や下着などでも使われています。一時アクリル繊維、ポリエステルなどに市場を奪われましたが、その後、やはり木綿が良いということで、回復して今に至っています。
今はそれぞれの良さで住み分けができているという状態でもあります。その他にも、漁網やコーヒーのフィルターなどやテント、火薬まで様々な用途に使われていますが、珍しいところでは、中国では以前、紙を作るのに使っていたということです。非常に様々な利用の仕方があるものですが、それだけ優れた植物でもあるということになります。
また医療用の脱脂綿でも利用されています。栽培での育て方と環境ということでは、気候が重要で、降霜のない長い季節が必要であり、600mmから1200mm程度の降水量も必要ということです。地域としては熱帯から亜熱帯の湿潤な地域ということになります。ですので当然ガーデニングや家庭菜園などで育てる場合にも、
同じような気候の地域や環境が必要になるということになります。このような歴史のある植物ですので、ガーデニングでも面白い植物ではないかということですが、試してみたい、育ててみたい植物ということも言えます。その歴史や衣類のことなどをイメージしながら実際に僅かでも収穫してみたいということになります。
種付けや水やり、肥料について
育てる場合に、気候的な問題もあり、本来は多年草ですが、日本の場合には冬が問題になります、もともと熱帯や亜熱帯の植物ですので、日本の気候では冬が寒いということで、ダメージが大きすぎて、多年草としては無理があるようです。ですので1年で種まきから収穫までで終わるということになります。非常に綿のできた時の見た目が特異で白さも目立ち、
何とも不思議な植物ですので、ガーデニングでも楽しめる植物ですから、挑戦してみるのも楽しいでしょう。パカっと口を開けたところに白いわたがあるということで、特に最初に収穫する時には、珍しくて面白いでしょう。そんな楽しみも味わえますが、具体的には、種まきは5月から6月頃で、開花は7月から8月頃ということになります。
肥料は5月から8月まで与え続けます。また関東ぐらいならばプランターや鉢植えなどで栽培できますので、観賞用としてマンションのベランダなどで育ててみるのも面白いでしょう。そして気温が高いほうが夏の生育が早いので、やはり熱帯、亜熱帯の植物ということですが、日本では東北地方までならば成長度合いはともかくできないことはない植物ということです。
またこの植物は面白いことに、共生菌という菌の力を借りて生育するということですが、この菌に感染し窒素を取り込めるようになることで成長していきます。その仕組も面白いのですが、それまで1ヶ月ほどかかるということです。また落果も多いということですが、そのこともあまり気にしないようにするとよいそうです。
増やし方や害虫について
また発芽後に、その共生菌が増えるまでの間は、葉も増えないので、そこは忍耐で見守っていくということですが、この時に成長が遅いということで、水をやり過ぎたりすると根腐れを起こして枯れてしまいますので、水分調整は慎重にします。与え過ぎないようにということです。
その反対に7月、8月は葉が急に増えるので、水分を必要としますから出来るだけ乾燥しないように水を与えることが必要になります。そのような特徴も植物では珍しいかもしれません。肥料は普通に与えますが、多すぎても花が咲かない場合があるので適度に与えるほうが良いようです。
鉢植えで販売しているものは、もともと土に肥料が混ぜてあるので、そのままで良いということですが、地植えの場合には2週間に1回ぐらいで良いようです。また土はアルカリ性の土壌を好み、酸性の土壌を嫌うので、石灰を撒いて中和させておくと良いとのことです。
またこの植物は根が傷つくと枯れてしまうので植え替えができないということですが、一本真っ直ぐに根が張るので、この根を大切にしておくということが必要になります。また種は他の植物と同じですが、一晩ぐらい水でふやかしておきます。また害虫としては、ナメクジが葉を食べるようですので、よく観察して、それらの害虫を駆除するようにします。
また台風などで倒れやすいので、短めにしておき支柱などで支えるか、鉢植えなどで室内に避難させるかすると良いということです。また実際に綿を収穫するのですが、量が少ないので、あまりそれで衣類を作るとかは期待しないほうが良いとのことでした。あくまでも観賞用ということです。
ワタ(綿)の歴史
日常生活でも衣食住は重要ですが、その中でも着るものは、まず絶対に必要な生活の必需品ということになります。これがないと、人間社会では生きていけないですし、また健康的にも生活がスムーズにいかなくなります。太古の昔から、まず身体を覆うものを用意しなければならないのが人間で、他の動物達は体毛で覆いながら生きていけましたが、
人間の場合には衣類が必要になってきたということになります。それで色々な衣類が生まれましたが、最初は動物などの毛皮などや、植物の葉っぱなどだったのでしょうが、そのうちに、植物から衣類を作り出す智慧が生まれてきたということですが、その代表的な植物がワタということになります。綿の種子は、非常に硬いのですが、
それが自然に破れて、中から柔らかい綿毛が現れるということになります。多分最初は、自然にあるそれらの綿毛を集めて、暖を取ったりしたのでしょうが、そのうちに、それらを利用して、衣類を作る智慧が生まれて、それが発展し、今に至るということになるのでしょう。歴史的な最古の証拠ということでは南米のメキシコで、そこが原産地ということになりますが、
インドにもあり、いくつかの地域が生息地となっていたということでしょう。栽培ということでは、このメキシコで8000年前に栽培されていたということですが、インドでも7000年前の有名なインダス文明で栽培の痕跡があるということです。このように非常に古い歴史があり、その頃から今に至るまで栽培されていたのがこの植物ということになります。
ワタ(綿)の特徴
その後インドでは、この植物の栽培が盛んになり、それは最近まで続いていたということですが、世界に広がったのは意外に遅く、アレクサンダー大王の頃ではまだ羊毛だけしか知られていなかったようです。ギリシャのこれらの古代の文明での話としては、ある王様の話として、インドには羊毛が生える木があると伝えられているという記述があるそうで、
それまでは羊毛しか知られていなかったということになります。面白い表現ですが、そのような状態が紀元前300年頃の様子だったということになります。その後紀元前後にアラブ人が木綿をイタリアなどに販売していたようで、実際にヨーロッパで栽培されたのは9世紀に入ってからということのようです。また中国には晩唐の頃ということですから、
900年頃ということで、その後朝鮮半島に1300年代後半に伝わったようです。日本には800年頃インド人が漂着して日本で栽培を始めたという話がありますが、それは失敗したようで、その後は長く中国や朝鮮からの輸入に頼っていたということです。ですので非常に貴重な製品だったということになります。その場所は愛知県だったようですが、
その後は16世紀の戦国時代に日本全国に広がり、今に至るということになります。特に江戸時代は盛んだったようで、時代劇でも木綿問屋が出てきますが、問屋まで出来るほどに広まったということです。このように非常に時間をかけて伝わった植物ということですが、日本まで広がるのに6000年ぐらいかかったということになります。
-

-
ケストルムの育て方
ケストルムはアメリカの熱帯地帯でよく見られる常緑樹でその中でも園芸用の品種として栽培されているのは10種類程度であるとさ...
-

-
ヒベルティアの育て方
ディレニア科ヒベルティア属は、害虫被害に遭いにくい植物です。原産地をオーストラリアとするヒベルティアという花は、種類にも...
-

-
デルフィニウムの育て方
デルフィニウムはキンポウゲ科の花で、5月から6月頃に様々な色の繊細で美しい花を咲かせます。背が高い茎に小さな花をたくさん...
-

-
トマトの栽培は驚く事ばかりでした
今年こそは、立派なトマトを作ろうと思いながら数年が過ぎようとしていた時、テレビ番組を見た事がきっかけで、自分でトマトを作...
-

-
ブッドレアの育て方
ブッドレアはイギリスのエセックス州の牧師であり、植物学者でもあったアダム・バドル氏の名からとられたものです。名付けたのは...
-

-
コブシの育て方
早春に白い花を咲かせるコブシは日本原産です。野山に広く自生していたことから、古くから日本人の生活になじみ深い植物でもあり...
-

-
ニンジンの上手な育て方について
ニンジンは、春まきと夏まきとがあるのですが、夏以降から育てるニンジンは、春に比べると害虫被害が少なく育てやすいので、初心...
-

-
サルビア・レウカンサの育て方
サルビア・レウカンサの原産地はメキシコや中央アメリカです。別名を「メキシカンブッシュセージ」「アメジストセージ」といい、...
-

-
オクナ(ミッキーマウスツリー)の育て方
南アフリカ一帯に分布する樹木で、正式名称をオクナセルラタと呼び、ミッキーマウスツリーとして現在では親しまれている植物の特...
-

-
ハツユキソウの育て方
ハツユキソウは背丈がおよそ1メートル程の高さに延び、その葉先に小さな花をつけます。白く色づく葉は花の回りにある唇型の葉で...




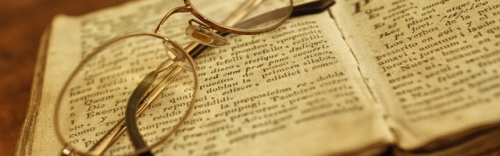





その後インドでは、この植物の栽培が盛んになり、それは最近まで続いていたということですが、世界に広がったのは意外に遅く、アレクサンダー大王の頃ではまだ羊毛だけしか知られていなかったようです。