モミジの育て方

モミジの育て方
この品種は半日陰から日向の水はけの良い場所を好みます。植え付けもそのような場所を選んで行いましょう。余りにも日当たりが悪いと幹の太さが十分にならず発育不良になってしまうケースがありますし、余りにも一日日が当たる場所だと葉が焼けてチリチリになってしまうことがあります。
カエデの根はたいへん太く、地中深くに入り込んで行くことが出来るのですが、細い根は地上にとどまる性質があるので水はけの悪い土地では根腐れしてしまうケースがあります。かなり大きくなる品種ですので植え付けする場所はよく考えて成長したあとの空間に余裕を持って植え付けましょう。
もしスペースが足りない場合には植え付けをしたあとに定期的に剪定をすることでコンパクトに保ちながら栽培していくことも可能です。鉢植えの場合でも通年戸外で管理しましょう。春や秋の成長期は十分に日光を当てて夏は半日陰、冬は寒風が当たらない場所で管理するようにします。
屋内で栽培していた品種や斑入りの品種を急に日光に当てると葉が焼けてチリチリになってしまうことがありますのでまず、半日陰で管理して徐々に光を当てるのが良いでしょう。植え付けと植え替えの時期は真冬の休眠期を避けて10月下旬または3月に行います。
植え付けるときには根鉢を崩して根の先を切り詰めることでくさった根を取り除くことができます。根鉢の大きさよりも大きな直径の穴を掘り、腐葉土や牛糞などを混ぜてから植え付けるようにします。用土は赤玉土4割に腐葉土を加えて、水はけと保水性を両立させるのが良いでしょう。
普段の管理の注意点
モミジを育てるにあたってはほかの植物にくべてかなり容易です。きちんと根付くことができれば夏の気温が高いときに乾燥しすぎてしまわないように注意する以外には水遣りの必要もありません。ただし夏の高温期は直射日光が葉に当たってチリチリになってしまう可能性もありますので、朝夕の日が当たらない時間に葉にも水をかけてやるのが良いでしょう。
鉢植えの場合には夏は朝夕二回、それ以外の季節は乾燥したら水やりをするようにします。庭植えの場合には肥料は寒肥をやる程度で良いでしょう。2月につぶ状のゆっくりと効果を出すタイプの肥料を株元にやります。また成長期の5月、充実期の10月につぶ状肥料をやると幹が太くなり丈夫な株となります。
カエデの栽培で大事なことは剪定です。カエデは自然な樹形が美しいので、庭植えの場合にはあまり積極的に剪定をしません。ただしスペースに余裕がなくコンパクトに育てたい時などは剪定を行います。落葉後なるべく早い時期に剪定をすれば葉の芽を切らずに済み成長を妨げることがありません。
枝を切った時の樹形をイメージしながら重なってしまい樹形が乱れる太い枝を付け根から取り除き、次に重なった細かい枝もカットします。最後に残った枝を長さを考えて好みのサイズにカットして終了です。この際に節のすぐ上できるようにすれば翌年新しい芽が出てくるのを妨げることがなく安心です。
モミジは種も可愛い植物で赤く色づいた種はくるくると回りながら地表に落ちて芽を出すことがあります。ただし園芸品種は通常接木で増やし、ナーサリーなどはこの方法で台木を使って増やします。一部のカエデは挿し木で増やすことができます。開花後の伸び始めた梢を10センチほど切り、水揚げをし、植物成長調整剤などをまぶして鹿沼土にさしておき、乾燥しないように注意して育てることで秋には発根します。
このように挿し木で増やして行くことが出来るだけではなく、山もみじなどは種で増やすことも可能です。種を乾燥させないように気をつけて鹿沼土などに置いておくと発根します。木になるまでには何年もかかりますが、種から育てたモミジとしてひとしおの愛着がわくことでしょう。
栽培してみたい品種
モミジはカエデの仲間で日本に古くから野生種がありましたので、日本の風土によく合い植える場所も選ばない育てやすい高木です。庭植えでも鉢植えでも育てられるのが特徴です。この植物の種付けは一般的には行わず、ある程度育っている木を購入して植え付けるようになります。
イロハモミジやウチワカエデなどが多く流通しているので入手しやすい品種です。好みの品種を選ぶときには葉の色付きのタイプや高さなどに注目して選ぶのが良いでしょう。葉の色だけでなく形や幹の色なども品種によって変わってきます。人気のある品種にオオモミジの立田川があります。
これは新芽が黄緑でその後、美しい緑になる人気品種です紅葉も美しいのが特徴です。また‘珊瑚閣はヨーロッパやアメリカでも人気の品種で枝が赤いのが特徴です。さらに北米原産のネグンドカエデ、エレガンスやフラミンゴも人気のあるカエデです。葉に斑が入り印象的な庭を演出してくれます。ただし成長してかなり大きくなるのである程度の広さのある庭が必要になってきます。
モミジの歴史
モミジは日本人に古くから愛されてきた植物です。色づいたこの植物を見に行くことを紅葉狩りといい、秋の風物詩として古くからたのしまれてきました。この植物は古くは日本を代表する古典である万葉集や源氏物語などにも登場しています。平安時代には貴族たちを中心として紅葉狩りが行われてきましたが、江戸時代になると庶民も多く紅葉狩りを楽しむようになり多くの方に親しまれるようになってきました。
その後、八代将軍徳川吉宗が飛鳥山に桜とともにたくさんのカエデを植え付けてその景色は壮観だったと言われています。下谷の正燈寺と並んでモミジの名所となり今でも親しまれています。明治時代になると旅行を兼ねて紅葉狩りに行く習慣が根付き与謝野晶子などは温泉旅行も兼ねて紅葉狩りに出かけた記録が残っています。
よく知られている百人一首にもこの植物をよんでいる歌があり日本人に好まれてきたことがわかります。ただし厳密に言うとこのモミジという植物はなく、カエデ類の中に分類されます。もともと秋になり葉が赤や黄色に色づくことをもみちと呼び、そこから色づいた葉のことをモミジというようになったということです。
モミジの特徴
モミジはカエデ属の植物ですが原産は広く約150種が北半球の温帯を中心に分布しています。温帯が生息地ではありますがかなり寒い地域にも分布しているので耐寒性があり容易に冬越しをします。常緑、落葉の品種の高木で日本にはイロハモミジ、ハウチワカエデ、ハナノキなど約20種類ものモミジが分布しています。
この仲間は赤や黄色などの紅葉の色はもちろん美しいのですが、それだけでなく赤ちゃんの手のひらのような可愛らしい形や樹皮なども美しいものが多く、四季を通じて鑑賞する楽しみがあります。特に日本に流通しているカエデは野生種を改良したものなので、日本の風土に合っており、育てやすい上に、庭木としても鉢植えとしてもどちらでも栽培することが出来るのが特徴です。
モミジとカエデの違いを疑問に思われる方がいますが、どちらも同じもので、紅葉したカエデをモミジと呼びます。もともと色づいた紅葉した葉は全てモミジと行っていたのです。この仲間にサトウカエデという品種があり、この樹液を煮詰めるとメイプルシロップとなります。昼と夜の寒暖差が激しい地域では光合成によって作られた糖分が分解されるので美しく紅葉します。そのため寒冷地の紅葉は、温暖な地域よりも美しく輝くのです。
庭木の育て方など色々な植物の育て方に興味がある方は下記の記事も凄く参考になります♪
タイトル:カエデ類の育て方
タイトル:センリョウの育て方
タイトル:キンモクセイの育て方
-

-
パイナップルの育て方
パイナップルは日本でもよく目にする果物ですが、原産地はブラジルで、代表的な熱帯果樹の一つです。先住民によって果物として栽...
-

-
ダボエシアの育て方
ダボエシアは学名でDaboeciacantabrica’bicolor’といいますが、分類で言うとツツジ科ダボエシカ属に...
-

-
スミレの育て方
スミレの原産国は、北アメリカ南部になります。種類が豊富であるため、生息地としても種類により、適した環境で花を咲かせていま...
-

-
部屋をいろどる観葉植物
私は5年ほど前から観葉植物を買いました。昔から興味はあったのですが、なかなか手が出せずにいたのですが、友人からおすすめさ...
-

-
植物の上手な育て方を知る
生活の中に植物を取り入れることで、とても豊な気持ちになれます。また、癒しの効果もあって、育てていく過程も楽しめます。キレ...
-

-
エスキナンサスの育て方
エスキナンサスとは、イワタバコ科の観葉植物です。半つる性で赤い花をつけるこの植物は、レイアウトをすることで、南国風のエキ...
-

-
サポナリアの育て方
サポナリアの科名は、ナデシコ科で属名は、シャボンソウ属(サポナリア属)となります。また、和名は、シャボンソウでその他の名...
-

-
ルドベキアの育て方
ルドベキアは北米を生息地としており、15種類ほどの自生種がある、アメリカを原産とする植物です。和名ではオオハンゴウソウ属...
-

-
ビワの育て方
ビワは中国原産のバラ科の常緑高木で、淡いオレンジ色の果実をつけます。肉厚で甘みのある果実は生のまま食べてもいいですし、お...
-

-
マンデビラの育て方
メキシコやアルゼンチンなどの中米から南米などが生息地のつる性の植物です。ディプラデニアという名前で呼ばれていたこともあり...




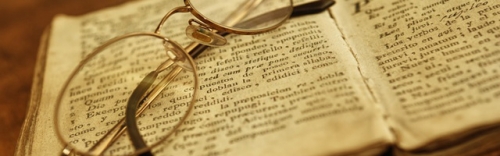





モミジは日本人に古くから愛されてきた植物です。色づいたこの植物を見に行くことを紅葉狩りといい、秋の風物詩として古くからたのしまれてきました。この植物は古くは日本を代表する古典である万葉集や源氏物語などにも登場しています。平安時代には貴族たちを中心として紅葉狩りが行われてきましたが、江戸時代になると庶民も多く紅葉狩りを楽しむようになり多くの方に親しまれるようになってきました。