オーブリエタの育て方

育てる環境について
オーブリエタを育てる環境については、文字通り湿度が問題ですので水はけと水の乾きの程よい土で育てる事が好ましいとされます。ただ、オーブリエタはヨーロッパ圏や西アジア圏では、日本で見られるタンポポの様に勝手に自生して勝手に花を咲かせるぐらいの、
現地生息地においては適応した強い生命力を誇る種ですので、日本の年がら年中高い湿度の問題をクリアできれば、多く花を咲かせる事も出来るかもしれません。ただ、湿度の調整などは菜園ハウスなどを作るレベルでもないと難しいですし、湿度とは少しでも隙間があれば入り込む性質のものなので、
湿度云々は無理をせず日本流の育て方に適したやり方をするのも必要であります。日本流の育て方は、春から夏入り前に栽培する事を前提としたプランを持った育て方です。おおよそ2月頃から畑や花壇の土の手入れを施しておき、3月頃に種を撒いて育てていく手法です。
これは春が程よく乾燥する時勢が多い環境を利用するパターンです。そして水やりは2日に1回程の頻度でよく、水を染みこませ過ぎない様にして育てていく事が必要です。ただし、梅雨の季節が近づいたり、長雨などに見舞われた場合には植木鉢などに移し変えて屋内に避難させておく必要もあります。
そうしないと湿度を含みすぎて、芽などがふやけて死んでしまう場合もあるからです。育てる環境においてはオーブリエタは日本では世話がかかる花でもあるという事を注意して認識し、育てる事が大切です。
種付けや水やり、肥料について
オーブリエタの種付けや水やりにおいては育てる環境について説明した通りですが、追記すべき部分もあります。オーブリエタの種付けの時期は冬明けの比較的乾燥した頃合いから土の手入れをする必要もある訳ですが、この土はなるべく固めで水を程よく太陽の陽射しで
乾燥していってくれるタイプのモノが好ましいです。これが意味するのはオーブリエタは固い土相手でも強く根を張る種である事から、水はけが悪い土では湿度にやられてしまう為に調整しないといけない部分であるという点に由来します。そして冬明けというのは
乾燥していて湿度が低いからこそ丁度いい時期でもあるというのがあります。水やりは二日に1度程度の頻度で良いと記載しましたが、朝霧などが多く、水っぽい朝などに見舞われた日などにおいては保留にして翌日に水を撒くというのも1つの選択肢になります。
そして肥料については、オーブリエタは湿度に弱いという点がある為、そこに気をつけた販売されている液体肥料や固形肥料を用いる事が大切です。特に、固形肥料などの場合においては水はけを悪くしてしまう土と一体化を前提としたタイプのものですと、
オーブリエにダメージを与えてしまいかねないので注意が必要です。液体肥料も水分性が高すぎる場合には水やりをせずに液体肥料だけを与えて、その代わりに少し時間をおいてから家庭菜園用のスプレーなどに水を入れて、軽く土の周りを湿らせるぐらいで充分になります。この場合ではジョウロなどは用いない少量の水やりとなります。
増やし方や害虫について
オーブリエタとは、日本ではなくヨーロッパや西アジア圏では自然と増える傾向にある為、育て方の中での「増やし方」とマニュアルというのはあまり存在しません。これも日本流に則ったやり方になる為、シンプルに家庭菜園で行う茎や根が隣のオーブリエタと
絡まってお互いが傷つけあう状態になるのを防ぐ植え分けを程よく施す必要もあります。ただ、基本的にオーブリエタは凄い勢いで近隣の合間の中であろうと葉っぱを生い茂らせるのでなるべく早期に植え分けをするのが好ましいです。加えて、
そんなある種の雑草魂と言える程に育つ勢いがあるので畑や家庭菜園の花壇などはなるべく広い土地が好ましく、もし植木鉢などで育てたいと考えている場合には種蒔きの時点で種は1つの植木鉢に1つか3つまでのレベルに抑える必要もあります。
そして3つ中2つか3つも芽が出たら、なるべく早く植え分けをしてあげると良いでしょう。オーブリエタに対する害虫とは、原産地、生息地においては比較的大きな問題とならないケースも多いのですが、日本では湿度が高い為に色々な害虫が存在する為、敵が多い問題があります。
ヨーロッパ圏などでは梅雨の時期などでぐらいしかカタツムリやナメクジというのは見られない国も存在するのですが、日本では一年を通して雨が降れば大量に自然発生してくる害虫でもあるので厄介です。何より日本では雨が降る事が多いので
湿度に弱いという部分でもダブルコンボになっていると言えます。その為、オーブリエタには塩などを撒いたりするのが好ましく、他の害虫対策としても防虫剤などを適度に使用する事が推奨されます。
オーブリエタの歴史
オーブリエタとは、アブラナ科オーブリエタ属に類する多年草です。多年草とは、毎年生息して育つ植物の事を言います。いわば土の栄養とのバランス能力があり、土の栄養を取り過ぎないので毎年自然と咲きやすい花です。学名はAubrieta deltoideaで、
英語名は3通りありLilacbuとRock cressにCommon aubrietaとなります。生息地に連なる原産地の歴史は、ヨーロッパの東南部から西アジアに分布して生息してきたと言われています。その歴史の生息はヨーロッパ圏から西アジア圏に広く分布してきた為、
広く長く知れ渡っていながらも1500年代以降に多くなってきた過去の研究者などの筆記研究資料などの情報は少なく、いつから生息していたのかという詳細は定かとはなっていません。ただ、フランスの植物画家のクロード・オーブリエの名前に因んで付けられた名前であるという説が強く残っており、
おおよそ16世紀後半から17世紀前半の辺りでは、この花の存在が明確に明らかになっているものと考えられています。そして日本に伝来したのは明治末期の頃と言われており、日本に伝来してからは和名で「ムラサキナズナ」という名前が付けられるようになりました。
その為、日本ではオーブリエタの名前はあまり知名度が高くなく、逆にムラサキナズナの知名度はそれなりにあるという和名・英名の知名度逆転現象が起きている花としても有名でもあります。
オーブリエタの特徴
オーブリエタの特徴は、多年草ですので毎年自ら咲き続けるぐらいの強さがある事です。これは雑草類に属する様な野良の花と類似しており、ヨーロッパ圏から西アジア圏にまで存在が確認されていたと言われている通り、花としては生命力の高さが伺える種でもあります。
花の形としての特徴は、四葉のクローバーを彷彿とさせる4つの葉で成り立った花であり、サイズは四葉のクローバーよりも大きく人の指一本を丸めたぐらいよりも大きい花を咲かせるのもいます。色は基本的にムラサキナズナというオーブリエタの日本の和名が存在する様に、
多くは紫色ですが、品種改良や交配の結果、現代では紫色だけではなく、ピンク色や、桃色混じりの白色、青紫色や淡青色などの色合いを咲かす様になりました。ですが、日本では多く普及していないのは日本は湿度が高く、尚且つ多湿な国柄でもあるからと言われています。
オーブリエタにとっての弱点とは湿度であり、日本の様に年がら年中ある程度の湿度がある国では育ちにくい為、家庭園芸などでもあまり多く普及していないのが実情です。しかし、その代わり湿度も高くないヨーロッパ圏や西アジア圏で広く分布して生息したという理由もあります。
加えてヨーロッパでは日本で言うタンポポの様な知名度で、春の造園の花や草花という高い知名度を持っており、親しまれているのでヨーロッパなどに春に旅行に行けばオーブリエタの姿を垣間見る事も出来る事となります。
-

-
シラネアオイの育て方
シラネアオイの原産地は、日本で日本固有の壱属一種の多年草の植物ですが、分類上の位置が二転三転してきた植物でもあります。昔...
-

-
ケストルムの育て方
ケストルムはアメリカの熱帯地帯でよく見られる常緑樹でその中でも園芸用の品種として栽培されているのは10種類程度であるとさ...
-

-
シダルセアの育て方
シダルセアは、北アメリカ中部、北アメリカ西部が原産国です。耐寒性はある方で、乾燥気味である気候の地域を生息地として選びま...
-

-
宿根アスターの育て方
アスターは、キク科の中でも約500種類の品種を有する大きな属です。宿根アスター属は、中国北部の冷涼な乾燥地帯を生息地とす...
-

-
ヘリオフィラの育て方
ヘリオフィラはアブラナ科の植物で小さな青い花を咲かせてくれます。つぎつぎと花を楽しむことができる植物になっています。南ア...
-

-
バラ(ピュア)の育て方
その特徴といえば、たくさんありますが、特徴を挙げるとすれば、その香りが最大の特徴ではないかと考えられます。もし、いくら花...
-

-
リンコスティリスの育て方
リンコスティリスはラン科の植物ですが、生息地は熱帯アジア地方に分布しています。主にインドやタイ、マレーシア、中国南部が原...
-

-
ゴマナの育て方
ゴマナは胡麻の菜と書きますが、胡麻の葉っぱに似ていることから、この名前がついたと言われていて、キク科ですので、花も菊に似...
-

-
チャービルの育て方
チャービルはロシア南部から西アジアが原産で、特に、コーカサス地方原産のものがローマによってヨーロッパに広く伝えられたと言...
-

-
ワイルドストロベリーの育て方
ワイルドストロベリーの特徴は野生の植物に見られる強さがあることです。踏まれても尚踏ん張って生きている雑草に例えることがで...




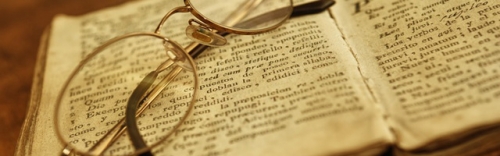





オーブリエタとは、アブラナ科オーブリエタ属に類する多年草です。多年草とは、毎年生息して育つ植物の事を言います。いわば土の栄養とのバランス能力があり、土の栄養を取り過ぎないので毎年自然と咲きやすい花です。