インパチエンスの育て方

インパチエンスの種付けの注意点
インパチエンスのタネをまく場合、タネが細かいため、種付けではいくつかの注意が必要です。まず平鉢などにまき、芽が出て大きくなってきたら移植をする方法をとります。また発芽をするためには、光が必要であるため、まいたあとは軽く押さえるだけにするか、土をかぶせる場合はタネが隠れる程度の薄めにすることが種付けの際の注意点となります。
水は上から勢いよくやると、細かいタネが流れてしまいますので注意が必要です。鉢底に受け皿を敷き、そこに水を入れて鉢底から水を吸わせる方法をとります。このあたりも種付けとしての注意点です。さらに芽が出てきたら水切れに注意をし、できるだけ日当たりのよい場所に置き、大切に育てます。
発芽の直後には、日当たりが不足すると、ひょろひょろとした弱い芽になるため、よく注意をし、日光を充分にあてることが大切です。いくつかの注意点をおさえておくと、インパチエンスの種付けについて自信をもって行うことが出来ます。
インパチエンスの栽培
インパチエンスの栽培を、季節に応じて理解をすることが大切です。まず種付けは、4月中旬から5月いっぱいです。また苗として植える場合は、5月中旬から7月上旬までの間が適しています。肥料は5月中旬から9月までのよい時期に、適宜与えることをします。花の開花期は、5月中旬から10月中旬くらいまでです。
長い時期、色とりどりの花を楽しむことが出来ますので、この植物を栽培し、育て方に注意を施すことは有意義なこととなります。よく成長をする成長期には、絶え間なく花を咲かせますので、花がら摘みを丹念に行います。そうすると長期間元気に花を咲かせ続けることが出来ます。したがって育て方として大切なことは、よく観察をし、花を楽しみながら花がらを摘んできれいな姿にしてやることです。
花のシーズンは暖かい時期が一般的ですが、気温が15℃以上あると、花が咲くことが可能なため、置いた環境や気候を考慮に入れながら、大切に育てていきます。梅雨の前後によく花を楽しむことが出来ますが、夏の終わりになると茎が伸びて姿が乱れてきます。その場合は、茎を半分くらいの高さに切ることによって、ワキから芽が出てきて茎が伸び、姿が整っていきます。こういった手入れも育て方として覚えておくとよいことです。
また、真夏の直射日光はインパチェンスには注意が必要です。葉が黄ばんで色が悪くなったり、色あせたり、生育に悪い影響を及ぼすため、真夏の時期には明るい日陰に避難させることが必要です。鉢植えの場合は置き場所を移動して、真夏の太陽から保護することが大切です。花壇に植える場合は、夏の日射し考えたうえで、よい場所に植えることを注意することが必要です。
寒さには弱く、気温が5℃を切るとインパチエンスは枯れてしまいます。したがって、一年草として理解しておくことが必要ですが、元来は毎年花をさかせる多年草であることから、乾燥気味に管理をし、気温を保てる工夫をした場合は冬を越すことも可能となります。温室等の環境が整っている場合は、こういった育て方で栽培をすると、一年中育つことも可能となります。
つきやすい病害虫など
インパチエンスには、アブラムシとハダニがつきやすくなります。アブラムシは、インパチエンスのつぼみや新芽、さらには茎につきやすく、汁を吸ってこの植物を弱らせていきます。またハダニは、高温で乾燥している時期に発生しやすく、主に葉の裏について、葉の養分を吸いとり、この植物を弱らせていきます。気がつかないでいると、枯らしてしまうこともあります。
病害虫による被害が確認された場合は、病害虫に適した薬剤を散布して駆除します。ホームセンターなどで、この種類の病害虫に効果のある薬剤を購入し、説明書のとおりに散布します。なるべく薬剤に頼りたくない人達には、ハダニの場合は葉にたっぷりの水をかけて湿度を充分に保つ努力をすることで、ある程度病害虫の発生を予防することが出来ます。
いずれにせよ、インパチエンスをよく観察し、病害虫等の被害は早めに解決することが大切なこととなります。インパチエンスをまめに育てていくと、この植物をこよなく愛することが出来るようになります。種付けから始まり、暖かい季節には、熱帯育ちのインパチエンスとよく付き合うことで、この植物を理解することが出来ます。
日本の季節は、日々変化していきます。さわやかな季節からじめじめとした梅雨の季節、さらに抜けるような青空の夏の到来、じりじりと照りつける太陽の真夏、そして涼風の吹く秋、霜の降りる冬への準備期間と、季節は巡っていきます。季節に応じて、インパチエンスがよい環境で育っていくように、手入れや管理をすることは人の仕事としてはりあいがあります。育てる人達にとっても、教えられることも多く、有意義な作業となります。
インパチエンスの歴史
暖かい時期に、色とりどりの美しい花を咲かせるインパチエンスは、熱帯や亜熱帯の地域が原産地です。アフリカやインドといった高温で多湿の地域が生息地として向いています。インパチエンスと呼ばれているのは、タンザニアやモザンビークなどのアフリカ東部原産の、アフリカホウセンカとその園芸品種です。
日本でも、昔からあるホウセンカはこの種類です。したがって、日本でもインパチエンスは、5月から11月頃の暖かい時期に、この花がよく咲いています。インパチエンスの名前は、ラテン語で、我慢できないという意味から来ています。これはこの花のタネが弾けるさまに由来しており、名前の由来を覚えておくと、この植物の姿を理解することにつながります。
この植物は、オランダで品種改良が何度か行われている歴史があります。またアメリカや日本でも気候にあった品種が開発、改良されています。したがって多くの種類を見かけることが出来ます。色の種類や花の付き方の種類など、豊富な種類の中から、気に入ったインパチエンスを選ぶことが出来るため、とても楽しめる植物として人気があります。
インパチエンスの特徴
この植物は、寒さに弱く、霜の降りる頃には枯れてしまうことが多いことが特徴です。したがって、一年草として考えることが必要です。放っておくと、野生化していつまでも生息していることもありますが、一般的には暖かい時期に元気な姿を見かける植物です。草丈は、20cm~60cmぐらいのものが多く、茎は太くて多汁質であり、よく枝分かれしています。葉は長さ5cm前後のタマゴ型であり、フチはぎざぎざとした形となっています。
葉の付け根の部分に、花を咲かせます。この植物の花の色は、緋色、淡紅をはじめとして、青紫、白、さらには紫、ピンク、サーモンピンクそしてオレンジや赤などがあります。品種によって各色に濃淡があり、豊富な色彩を確認することが出来ます。花びらに縁取りが入るピコティ咲きや白いすじふがくっきりと入るものもあります。花の種類も豊富です。花の大きさは径5cm~2cm程度です。
花の後ろには距と呼ばれる細長い管があることも特徴です。また名前の由来となっている、果実を指で触れるとパチンとはじけて中のタネが飛び散り、果皮は巻いた形となります。名前とその姿を観察することは、この植物の特徴を理解することにつながります。様々な特徴をもつインパチエンスは魅力のある植物です。
-

-
エゴポディウムの育て方
セリ科・エゴポディウム属の耐寒性多年草です。和名はイワミツバと呼ばれ、春先の葉の柔らかい部分は食用にもなります。エゴポデ...
-

-
ヒナガヤツリの育て方
ヒナガヤツリは、カヤツリグサ科カヤツリグサ属の植物です。ヒナガヤツリの原産地は北アメリカですが、主な生息地はオーストラリ...
-

-
ヤブレガサの育て方
葉っぱから見ると種類が想像しにくいですが、キク目、キク科、キク亜科となっていますからキクの仲間になります。通常は葉っぱの...
-

-
ツキヌキニンドウの育て方
ツキヌキニンドウはアメリカ原産のツル性の植物で、5月頃から10月頃までの春時期から秋口にかけて、細長く先端部分が開いた、...
-

-
フィロデンドロン・セロウム(Philodendoron bi...
フィロデンドロンとはギリシャ語で「木を好む」という意味を持つ言葉です。セロウムはサトイモ科に属するフィロデンドロン属の仲...
-

-
キウイフルーツの育て方
キウイフルーツは、中国にある長江中流地域の山岳地帯から揚子江流域を原産地とする植物です。1904年に中国からニュージーラ...
-

-
アオマムシグサの育て方
アオマムシグサという植物はマムシグサの一種です。マムシグサというのはサトイモ科テンナンショウ属の多年草です。「蛇の杓子」...
-

-
ヤブジラミの育て方
分類はセリ科でヤブジラミ属ですが、原産地及び生息地ということでは中国から朝鮮半島、台湾、日本言うことで東アジア一帯に生息...
-

-
リンドウの育て方
リンドウは、リンドウ科、リンドウ属になります。和名は、リンドウ(竜胆)、その他の名前は、ササリンドウ、疫病草(えやみぐさ...
-

-
ヒメオドリコソウの育て方
春先の3月から5月頃にかけて花を咲かせるヨーロッパ原産のシソ科の草花である”ヒメオドリコソウ”。学名をLamiumpur...




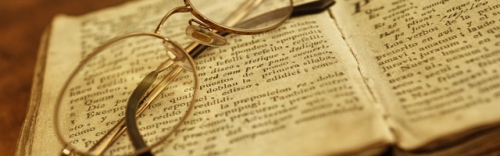





暖かい時期に、色とりどりの美しい花を咲かせるインパチエンスは、熱帯や亜熱帯の地域が原産地です。アフリカやインドといった高温で多湿の地域が生息地として向いています。インパチエンスと呼ばれているのは、タンザニアやモザンビークなどのアフリカ東部原産の、アフリカホウセンカとその園芸品種です。