カエデ類の育て方

カエデ類の育てる環境について
カエデ類は4月頃から5月上旬くらいが開花シーズンで、植え付けや植え替えをおこなうのは12月から3月下旬頃が適しています。育て方としては、日当りのよいところを選び通気性と水はけをよくしてあげてください。石灰岩質、花こう岩質の風化した土壌など肥沃な乾燥した場所を好みます。
日当りのよいところを好みますが、夏などの特に気温が高くなり暑くなるシーズンには直射日光を浴び続けることで葉が焼けて変色してしまうことがあります。鉢植えで栽培している場合には、夏の間は西日があたりにくいような半日陰に移動することがおすすめされています。
庭植えで育てている場合には、鉢植えのように移動することができないためそのままにしておくことが多いですが、根元部分にグランドカバーを植えるなどして蒸発を防ぐこともあります。また、最初から半日陰な場所に植えることもあります。
夏場の直射日光や乾燥によって葉が茶色くなってしまった場合には、8月下旬頃までは葉をむしってしまって対処することができます。この時期までにむしってしまった葉は9月頃に芽吹きますが、9月を過ぎてしまってからですと芽吹かないケースがありますので、
葉をむしるタイミングに注意してください。また、気温が高くなる時間帯に農薬散布などをおこなってしまうと葉が痛んでしまうことがありますので注意するようにしましょう。カエデ類は耐寒性がありますので冬の間は、特に対策を施す必要はありません。
カエデ類の種付けや水やり、肥料について
カエデの水やりは庭植えの場合には基本的にあまり必要ないのですが、比較的じめじめとした場所を好みます。自然の雨だけでは不十分で乾いてきた場合は水やりをしてください。特に鉢植えで育てているような場合は、完全に乾燥してしまわないように注意し、
土が乾ききってしまう前に水やりをおこないましょう。特に夏の暑いシーズンは乾燥しやすいですので、水不足になってしまわないようにしてあげてください。水やりをする際には葉っぱ部分にも水を掛けることがおすすめです。
乾燥に弱いですので水が切れてしまいますと葉が縮れてしまうことがあり、一旦縮れてしまった葉は元に戻ることができません。美しい紅葉を見るためにも夏場は葉の部分にも水を掛けて乾燥から守ってあげるようにしましょう。日射しの強くなる時間帯は避けて、
早朝や夕方など比較的涼しくなってくる時間帯に水やりをすることがおすすめです。水が不足してしまうと葉がしおれてしまいますので、朝夕にたっぷりと水をあげていきましょう。肥料をあげるタイミングは、植え付けや種付けをおこなう12月頃からですが、
鉢植えで育てる場合には2月頃まで、庭植えで育てていく場合には1月下旬頃までにあげるのが好ましいです。落葉した後すぐに肥料をあげるのですが、有機物と緩効性の化成肥料を混合したものを利用するとよいです。休眠時期に入っても吸水を早く始めるため肥料をあげることを忘れないようにしてあげてください。
カエデ類の増やし方や害虫について
園芸品種のカエデの増やし方には接ぎ木がおこなわれます。野生のカエデの場合には種まきの実生で増やしていきます。その他にも挿し木で増やしていく場合には、5月下旬頃から7月上旬頃には充実して硬くなりますのでこの枝を10センチメートルから15センチメートルほどにカットして用土に挿します。
カットする場合には先端部分に2、3枚ほどの葉を残しておいて、1時間程度水揚げをします。この時に植物用の成長剤を利用して切り口部分に塗っておくと効果的です。用土に挿す場合は、葉が触れる程度の間隔でおこなっていきます。カエデを育てる場合に注意したい病気にうどんこ病があります。
新梢は白色粉状の菌糸と分生子で覆われてしまいます。成熟している葉にはすす病が発生することがあります。すすかび斑点病は葉の部分に褐色の斑点が生じてしまいます。日当りや風通しをよくするように注意してあげてください。
枝や葉の被害として首垂細菌病がというものがあり、葉脈に沿って水浸状の病斑が生じてしまいます。この病気が新梢に発生してしまうと新葉が褐色腐敗をして垂れ下がってしまいます。害虫にはアブラムシやテッポウムシ、ミノムシ、コウモリガなどがあります。
新芽や若い葉にはアブラムシが発生することがあります。ヒロヘリアオイラガと呼ばれている幼虫は葉に害をもたらし、モミジワタカイガラムシは枝幹に寄生して害をもたらします。テッポウムシが幹を食害してしまうと致命傷になってしまいますので対処しましょう。
カエデ類の歴史
カエデ類はカエデ科カエデ属の木の総称で、さまざまな品種が存在しています。日本原産の品種も20種類以上がありますし、生息地として東アジアを中心として中国や北アメリカなども挙げられます。日本国内のカエデの代表的なものにはイロハモミジがあります。
紅葉の代表種としても知られ本州以南の平地から標高1000メートルほどにかけての低山に自生しています。観葉植物としても愛されていることから、さまざまな園芸品種があります。江戸時代頃には品種数も増加し、明治時代から昭和まで保存されてきました。
日本で改良されたモミジはアメリカやヨーロッパなどでも愛され、日本から苗木や成木が輸出されています。色鮮やかで美しい紅葉が鑑賞によいことから、庭木や盆栽に利用するために品種改良がおこなわれ、明治時代以降に西洋でも紹介されてから人気が出たとされています。
カエデという名称は、葉の部分がカエルの手に似ていることからカエルデと呼ばれていたのが転訛していったことが由来だとされています。カエデ類には、代表的なイロハモミジの他にもフカギレオオモミジやヒロハオオモミジ、ハウチワカエデ、コハウチワカエデ、
オオイタヤメイゲツ、アサノハカエデ、コミネカエデ、ウリカエデ、ウリハダカエデなどさまざまな種類があります。現在では庭園樹や生け垣、公園樹、環境緑化樹、街路樹などとしてカエデ類が広く利用されています。樹液が甘いころからメープルシロップにされたりしています。
カエデ類の特徴
カエデ類は一般的に高木になり、落葉樹が多く落葉広葉樹林の主要構成種だとされています。一般的に切れ込みのある葉をつけていますが、沖縄県には常緑樹のクスノハカエデが自生していますし、切れ込みのないものもあります。
カエデはとても小さな花が春頃になると咲きますが、花よりも樹形を楽しむことが多いです。花粉媒介を風に頼る形の風媒花で花弁もあまり目立たなくて小さいという特徴があります。葉を対生につけ、果実は片翼の翼果が2つずつ種子側で密着したようにつき、熟してくると分かれて別々に落ちていきます。
翼果の開く角度などは、亜種によって変化が大きいとされています。翼果が落ちていく時間が長いことから風に乗って遠くまで飛ばされていきます。翼果が分かれて別々になるためクルクルと回転しながら落ちていくのですが、分離しなかった場合は回転しません。
カエデは自然樹形を楽しむことが多いため整える必要は特にないのですが、重なっている枝や風通しが悪くなる中に生えている邪魔な枝などを落としていくこともあります。むやみやたらに刈り込みをしてしまうと枯れてしまうケースがあります。
邪魔な枝を落としていく場合は、ノコギリやハサミなどを使わずに手で折ることがおすすめされています。そのため太い枝などは折らず手で折ることができるような若い枝を落としていきましょう。切り戻すことによって脇芽が出て樹形が乱れてしまうことがありますので、できれば自然樹形が好ましいです。
庭木の育て方など色々な植物の育て方に興味がある方は下記の記事も参考になります♪
タイトル:コブシの育て方
タイトル:カンガルーポーの育て方
タイトル:モミジの育て方
タイトル:センリョウの育て方
タイトル:キンモクセイの育て方
-

-
モッコウバラの育て方
花の中でも王様と呼ばれるほどバラに魅了される人は多いです。そのためガーデニングをはじめる際にバラを育ててみたいと思う人は...
-

-
ショウガの育て方
現在では日本人の食生活にすっかりと定着しているショウガですが、実は原産地は熱帯性の動植物の生息地である熱帯アジア(インド...
-

-
クレピスの育て方
クレピスは学名で、モモイロタンポポ(桃色蒲公英)というキク科の植物です。ただし、クレピスの名前で呼ばれることも多いです。...
-

-
食虫植物を育ててみよう
ホームセンターで比較的安価に購入することが出来る食虫植物の育て方について記述していきます。食虫植物にはいくつかの種類があ...
-

-
ベルフラワーの育て方
ベルフラワーはカンパニュラの仲間で、カンパニュラはラテン語の釣鐘を意味する言葉から由来しており、薄紫色のベル状のかれんな...
-

-
ハオルチアの育て方
ハオルチアはもともと南アフリカ地域の原産のユリ科の多肉植物で、水分が多くなると生育できないことが多いので日本で栽培をする...
-

-
シコンノボタンの育て方
シコンノボタンは野牡丹の一種です。野牡丹の生息地は、熱帯や亜熱帯で、比較的暖かい地域が原産です。日本にも自生しているもの...
-

-
ゴールデンクラッカーの育て方
この花についての特徴としてはキク科、ユリオプス属になります。花が咲いている状態を見るとキクのようには見えませんが、黄色い...
-

-
チグリジア(ティグリディア)の育て方
チグリジアは別名ティグリディアとも呼ばれるユリに似た植物ですが実際にはアヤメ科の仲間になっています。チグジリアの仲間アヤ...
-

-
月下美人の育て方
月下美人とは、メキシコを中心とした中南米を原産地とする多肉植物です。名前は、夜に咲き始めた美しい花が翌朝にはしぼんでしま...




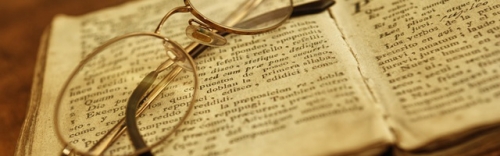





カエデ類はカエデ科カエデ属の木の総称で、さまざまな品種が存在しています。日本原産の品種も20種類以上がありますし、生息地として東アジアを中心として中国や北アメリカなども挙げられます。