アイノカンザシの育て方

育てる環境について
アイノカンザシの育て方はたくさんある植物の中でも難しい方になるでしょう。これはやはり日本の風土にもかなり影響しているのではないでしょうか。植物にとって環境はとても大切ですが、ちょっとした湿度や温度変化などがダメージを与えてしまう事も多いです。特にこの植物の場合はそうした部分でとてもデリケートかもしれません。
ものによっては暑さが苦手でも寒さは大丈夫という具合にどちらかに得意分野があったりするのですが、アイノカンザシの場合はそういった事もあまり見られないようです。高温多湿に弱いのでそういった事にならないようにしてあげる必要があるでしょう。例えば夏場は特に要注意です。温度も高くなりがちですし湿度が高くなることもあるでしょう。
できるだけ風通しのいい場所に置き、半日陰になるようにしてあげます。夏場を乗り切るのはとても難しいのですが、こまめに湿度や温度管理をしてみましょう。また寒さもとても苦手です。日本の冬は地域によってはとても寒いですので気をつけなければいけないでしょう。耐寒温度は5度と言われていますので、
それ以上に冷え込みそうなら室内にいれてあげるようにしましょう。温暖地域でそういった心配がないのなら屋外でも大丈夫です。その他春や秋は気候もいいので比較的過ごしやすいのですが、最近は春でも日中温度が高くなったり湿度変化も心配です。気候がいいからといって安心しないで注意深く様子をみて管理した方がいいでしょう。
種付けや水やり、肥料について
アイノカンザシの水やりですが、高温多湿が苦手という事を念頭においておこなっていくといいでしょう。負担をかけないようにできるだけ気をつけます。水をあげるタイミングですが、多湿が苦手ですのであげ過ぎに注意しましょう。表面の土が乾いているかどうか確認します。もしも乾いているのが明らかなら水をあげましょう。
この時は鉢の下に出てくる位あげてもかまいません。アイノカンザシの場合は多湿が苦手ですが、多少の乾燥には強い性質を持っています。ですから表面が乾燥しているからといってそれほど神経質になる必要はないでしょう。普通に乾いている程度なら弱ることもほとんどありません。
ただ、水をあげるタイミングとしてあまり表面が乾いていない時は控えた方がいいでしょう。まだ少し水分が残っているようならそれ以上あげると多湿になる可能性があります。心配になってつい毎日水をあげたくなるのですが、我慢します。またこれについては屋外で育てている場合は少し注意が必要です。
自分では水をあげていないつもりでもその日の天候によっては雨が降って必要以上に水が加わってしまう場合があるからです。知らないうちに多湿になって枯らしてしまう事のないようにしましょう。その他、肥料については花が咲いた後に液体肥料をあげるようにします。ただそれほど必要ありませんので、頃合いを見計らって与えてあげるといいでしょう。濃度は通常より2倍ほど薄くしてもいいです。
増やし方や害虫について
アイノカンザシは栽培するのはとても難しい植物です。日本の風土も影響しているのですが、年間を通して育てつづけるのはなかなか厳しいでしょう。高温多湿が苦手ですのでどうしても途中で枯れてしまう事が多く、そこから繁殖させるというところまで行きつかないからです。ですから自分でそれを増やすというのはあまりないでしょう。
ほとんどの場合は花が咲いたものを購入してくるという事になるのではないでしょうか。またその花を楽しんだ後は夏の暑さで弱ったり枯れるという流れになりそうです。その他、植え替えなども必要に応じてやってあげましょう。根を崩さないように慎重に行います。根に傷がついたりするとその後の成長にも影響がでてしまいます。
また根詰まりを起こしている場合も植え替えを行いますが、できるだけ春に行いましょう。その他、この植物の場合はあまり害虫などの心配はなさそうです。虫が苦手な人にとってはとても助かるのではないでしょうか。害虫は少しでもついてしまうと手がかかるのでお世話も大変になってしまいます。
害虫があまりつかないというだけでも気が楽かもしれません。ただ高温多湿が苦手ですのでその点では気をつけた方がいいでしょう。害虫は大丈夫でも、そうした環境の管理で失敗し枯らしてしまう事も多いようです。特に花が咲いた後の夏場は管理もとても難しく、一度きりしか花を楽しめないこともあるでしょう。無視よりも環境管理の方が手がかかるかもしれません。
アイノカンザシの歴史
アイノカンザシはユキノシタ科の植物ですが、別名をエリカモドキともいいます。植物の中でも呼び名がとても印象深く、イメージもいいのではないでしょうか。それだけで興味を持つ人もいるのかもしれません。どういう植物なのか見てみたいと思ってしまうような名前です。ただこの名前は輸入業者がつけたもので流通する際に使われているという呼び方です。
本来は学名でバウエラ、また別名としてエリカモドキというものがありますので合わせて覚えておくといいでしょう。アイノカンザシは流通名として知られており、こちらの方がよく使われているようです。別名のエリカモドキについてですが、この植物がエリカにとてもよく似ているからという理由でついた名前ようです。
確かにパッと見た感じでは見分けがつかない位似ていますので、そういう名前がついたのもわかります。また流通名についてはその花の可愛らしさからきているとも言われています。髪飾りに可愛い花がついているようなイメージでしょうか。これらの名前を比較してみるとわかるのですが、やはり流通名で使われているものの方が印象もぐっとよくなるのではないでしょうか。
流通する上でつけられた名前ですから当たり前かもしれませんが、そう考えると名前も重要なポイントと言えるのかもしれません。アイノカンザシですが、原産はオーストラリアの南東部となります。花が咲くのはだいたい3月から5月頃でとても愛らしい花をつける事で知られています。
アイノカンザシの特徴
アイノカンザシの特徴はピンク色の可愛らしい花をつけることで知られています。真ん中が黄色でその周りにピンクの花弁をつけるので、見た目の印象がとても愛らしく、またその花の大きさも小さいため全体的に愛らしさが特徴の花となっています。その他葉っぱも花と同様に小さいものがたくさんついており、アイノカンザシという名称がぴったりの植物と言えるでしょう。
またこれとよく似た名前でハナカンザシという植物もありますが、それとは全く別のものですので間違えないようにしましょう。ただ栽培についてはやや難しい部類にはいるようです。というのももともと日本の風土には合わない植物のため、それを栽培するのはどうしても難しくなってしまうからです。
生息地としてはオーストラリアになりますが、日本で育てるとなると季節による温度や湿度の変化もあり、なかなか厳しいようです。残念ですが、この植物にとっては適している風土と言えないのではないでしょうか。1年を通して育てていくのはかなりしんどいでしょう。育て方も難しく、初心者向けの植物というよりも上級者向けのものとなりそうです。
特に日本は梅雨がありますので、どうしてもじめじめとした期間ができてしまい湿度も高くなりがちですが、多湿がとても苦手です。また冬場も気温が下がり過ぎるとすぐに弱ってしまいますので越冬するのは難しいでしょう。そのため花が咲く時期の春に合わせて栽培を楽しんだりすることもあるようです。
-

-
サクラの育て方
原産地はヒマラヤの近郊ではないかといわれています。現在サクラの生息地はヨーロッパや西シベリア、日本、中国、米国、カナダな...
-

-
ロウバイの育て方
強い香りをあたりに漂わせ、どの樹木よりもいち早く春の訪れを告げる花ですが、江戸時代の終わり頃に、中国から朝鮮半島を経て伝...
-

-
オカヒジキの育て方
オカヒジキの原産地は日本や中国、シベリア、ヨーロッパ南西部です。「ヒジキ」と言いますが海藻ではなく海辺の砂地などを生息地...
-

-
ドドナエアの育て方
ドドナエアという木は葉を楽しむ木です。原産はオーストラリアでポップブッシュとも呼ばれています。生息地はもともと日本ではあ...
-

-
ブルビネラの育て方
ブルビネラは南アフリカやニュージーランドを原産とする花であり、日本で見ることが出来るようになってきたのはごく最近のことで...
-

-
コリゼマの育て方
オーストラリア原産の”コリゼマ”。まだ日本に入ってきて間もない植物になります。花の色がとても鮮やかなオレンジ色をしており...
-

-
上手な植物の栽培方法
私たちが普段生活している場所では、意識しないうちに何か殺風景だなとか、ごちゃごちゃ物がちらかっているなとかいう、いわゆる...
-

-
サトイモの育て方
サトイモの原産地はインド東部からインドシナ半島にかけてだと考えられています。少なくともインドでは紀元前3000年ごろには...
-

-
バイカオウレンの育て方
バイカオウレンは日本原産の多年草の山野草です。生息地としては、本州の東北地方南部から近畿、中国地方西部などであり、深山の...
-

-
メギの育て方
メギはメギ科メギ属の仲間に入るもので、垣根によく利用される背の低い植物です。メギ属はアルカロイドという成分を含んだ種類が...




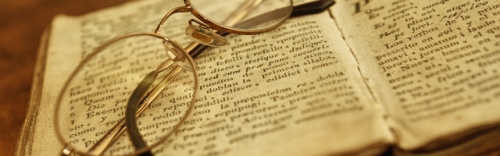





アイノカンザシはユキノシタ科の植物ですが、別名をエリカモドキともいいます。植物の中でも呼び名がとても印象深く、イメージもいいのではないでしょうか。それだけで興味を持つ人もいるのかもしれません。どういう植物なのか見てみたいと思ってしまうような名前です。