チンゲンサイの育て方

土づくりと種付け
野菜を栽培する場合、種付けをして苗を作り定植して苗から栽培するという育て方をしないとうまく育たないことが多くあります。しかし、このチンゲンサイという野菜は、種からでも簡単に栽培することができますので野菜作りの経験が少ない人にも向いている野菜といえます。プランターに種まきして日当たりのよい場所で育てることで問題なく収穫することができます。
チンゲンサイの種まきのの時期は、4月頃から10月頃までで収穫の時期としては5月から11月頃となります。ですが、育て方に慣れないうちは秋に蒔いておくと生育期に害虫の被害を受けにくくまた、高温による病気の発生を気にしなくて済みます。チンゲンサイの発芽温度は15℃~35℃で、育成に適した温度は15℃~20℃と低めを好みます。
このことからも秋の時期に種付けをして育成期に夏の高温期が重ならない、という育て方をしたほうが良い結果が得られます。連作被害もありますので1年以上の間を空けた土地を選ぶ必要があります。菜園で栽培する場合は、種を蒔く2週間ほど前に苦土石灰を1㎡あたり100gほどと堆肥を1㎡あたり2~3㎏混ぜ込みよく耕します。
その後1週間前には化成肥料を1㎡あたり150gほどの割合で施し,畝を立てておきます。種付けは、15㎝間隔で4~5粒ほどを1か所に蒔きます。種付けをした後は、たっぷりと水やりをしておきます。プランターでの栽培は、標準的な60㎝ほどのサイズのものを用意します。多少小さくても問題なく育てることができます。このプランターに市販の培養土をウォータースペースを取ってプランターに8分目ほど入れます。
蒔く種の種類はプランターではミニチンゲンサイといわれる品種が人気です。葉の丈が10~15㎝に育つもので、プランター栽培に向いた品種です。この土に浅井まき溝を作って条まきにします。間隔は1~1.5㎝ほどにとって種付けし、薄く土をかけておきます。この時あまり深く植えると発芽しにくくなりますので注意が必要です。種付けの後はたっぷりと水やりをしておきます。
大体2~3日すると発芽します。発芽するまでは、土を乾燥させないように気を付けてこまめに水やりをします。発芽したばかりのころは芽を倒さないように水やりの時の水の勢いに気を付る必要があります。
発芽後の育て方
芽が出た後の水やりは、土の状態を見ながら乾いてきたら、たっぷりと水やりをするようにします。チンゲンサイの場合元妃を施しておけば十分育てることができますので追肥は必要ではありません。しかし、水遣りの途に適宜に液肥を与えると質の良いものが収穫できるでしょう。
菜園で育成している場合本葉2~3枚ほどに育った頃に株間を5~6㎝になるように間引きし、本葉が5~6枚になった頃に1株に間引きします。プランターの場合は、10日ほどたった頃、双葉が開いたら1回目の間引きをします。育ちの悪いものから間引きし株間を3㎝ほどに調整します。2回目の間引きは本葉が3~4枚ほどになったら株間を5~6㎝ほどになるように間引きし1株になるように調整します。
この時間引きが遅れると育ちが悪くなってしまいますので注意が必要です。チンゲンサイによく見られる害虫としてコナガの幼虫があります。これが発生しているのを見逃していると、葉を穴だらけにされてしまいます。コナガは春と秋に多く発生しますので日常よく観察して早期発見をするようにします。そして、見つけ次第ただちに駆除するようにします。
また、種付けのすぐ後に不織布などで覆って防虫しておくと被害を少なく資することができます。病気は、高温であったり風通しが悪かったりするとべと病が発生しやすくなりますので、株間を広めにとったり敷き藁などして土の跳ね返りを防止すると効果的です。
収穫と利用法
チンゲンサイの収穫に適した時期は、草丈が12~15㎝ほどになった頃です。育ち具合のよいものから、順番に刃物で根元から切り取り収穫します。ミニチンゲンサイの場合は、20日~30日ほどで収穫できます。この品種の場合は丸ごと引き抜いて収穫します。収穫したらなるべく新鮮なうちに食べたほうが美味しく食べられます。
保存する場合は、乾燥しないように新聞紙やキッチンペーパーなどを濡らして包み、ビニール袋や掘り袋に入れて冷蔵庫の野菜室に立てた状態で保存します。また、冷凍保存も可能です。まず、軽く塩ゆでして冷水につけ熱を取ったら水気をよくとってラップなどに包み、冷凍しておきます。しかし、一番おいしいのは収穫したてのものですのでなるべく収穫したものは使い切るようにしましょう。
中華料理の炒め物のイメージが強いですがおひたしや和え物にしてもよいし漬物にも向いています。また、茹でてラーメンの具などにも使えます。味に癖がなく煮崩れしにくいのでどのような料理にもアイディア次第でいくらでも使うことができます。特に自分で栽培したものは新鮮さでは店頭のものとは比べ物になりません。また、思い入れも違いますので一味上のチンゲンサイとなります。
チンゲンサイの歴史
チンゲンサイの原産地は、中国の華中、華南といった地域が原産地ではなかったかと考えられています。アブラナ科で原種とされるものは地中海沿岸あたりを生息地としていたとされていてその原種が分化してわかれた品種が中国へ伝わったと考えられています。その野菜が中国の華中、華南で改良、栽培が行われこの地で野菜としてのチンゲンサイが作られることとなりました。
この野菜は、結球しないツケナ類である小白菜として分けられています。この小白菜は中国では古くから好んで食べられています。日本に初めて紹介されたのは1972年の日中国交回復したときです。この時ほかにも様々な中国野菜がもたらされたのですがこの野菜は日本人の味覚にあっていたのか高い人気を得ることになりました。この時、まだこの呼び名では呼ばれておらず、当時軸の色が青いものを「青茎」と書き、発音が「パクチョイ」と呼ばれました。
もう一種類の軸の白いものが「白茎」と書き,これも発音は「パクチョイ」と呼ばれ、紛らわしいことから青いものをチンゲンサイ白いものをパクチョイと呼び名を統一されることになりました。日本での栽培の歴史は20年そこそこということになり、比較的新しい野菜ということができます。
チンゲンサイの特徴
大きな蓮華を重ねたような形状のこの野菜は、アブラナ科の中国野菜です。茎は淡い緑色で幅広で厚みもあります。熱を加えると甘味が出てます。それいてシャキシャキした歯触りが失われることがなく煮崩れしません。このため炒め物やスープなどの熱を加える料理によく利用されます。旬は秋から冬になりますが、一年中売られています。
担々麺やスープ野菜炒めなど中国料理に使われるイメージがありますが彩もよく煮崩れしないことなどから日本では鍋物にもよく利用されています。チンゲンサイには様々な栄養素が含まれていて様々な効果が期待できます。まず、ビタミンAの働きを助けるベータカロチンが多く含まれており、このビタミンA由来の効果である粘膜の強化に一役買ってくれます。
粘膜が強くなることで風邪や感染症の予防になります。また、ビタミンCも含まれており、風邪の予防とともに美肌効果も期待できることになります。その他、カリウムも豊富です。このカリウムは取りすぎた塩分を体外に排出する働きがあります。これにより高血圧の予防やそれにまつわる数々の成人病の予防にも効果があります。また、人間の基本的な構成要素の一つであるカルシウムも含まれており、歯や骨を丈夫にして骨粗しょう症の予防に効果があります。
野菜の育て方など色々な植物の育て方に興味がある方は下記の記事も凄く参考になります♪
タイトル:タカナ類の育て方
タイトル:漬け菜類の育て方
タイトル:タアサイの育て方
タイトル:ハクサイの育て方
-

-
カレンジュラの育て方
日本ではキンセンカという名でよく知られているカレンジュラのことをよく知って育て方を工夫しながら栽培していきましょう。カレ...
-

-
木立ち性シネラリアの育て方
木立ち性シネラリア(木立ち性セネシオ)は、キク科のペリカリス属(セネシオ属)の一年草です。シネラリアという語呂がよくない...
-

-
ダボエシアの育て方
ダボエシアは学名でDaboeciacantabrica’bicolor’といいますが、分類で言うとツツジ科ダボエシカ属に...
-

-
アスパラガスとスイゼンジナの栽培方法
まずはアスパラガスの育て方を説明します。保健野菜で有名なアスパラガスには、缶詰用のホワイトと生食用のグリーンとの二種類が...
-

-
ロータスの育て方
「ロータス」は、北半球の温帯、主に地中海付近の島国を原産として約100種類もの品種が存在するマメ科ミヤコグサ科の多年草で...
-

-
アピオスの育て方
アピオスは食材で、北アメリカは北西部が原産地のマメ科のつる性植物で肥大した根茎を食べます。アピオスは芋でありながらマメ科...
-

-
チョコレートコスモスの育て方
チョコレートコスモスは、キク科 コスモス属の常緑多年草です。原産地はメキシコで、18世紀末にスペインマドリードの植物園に...
-

-
ヘレボルス・アーグチフォリウスの育て方
特徴としては花の種類として何に該当するかです。まずはキンポウゲ科になります。そしてクリスマスローズ属になっています。属性...
-

-
ミニカボチャの育て方
ミニカボチャをはじめとするカボチャの原産地は、インド地方やナイル川の沿岸地域、南米大陸北部のペルー、アンゴラなど様々な学...
-

-
ヤグルマギクの育て方
この花の特徴としてはまずは菊の種類であることです。キク目キク科の花になります。野生の状態で青色の状態になっています。です...




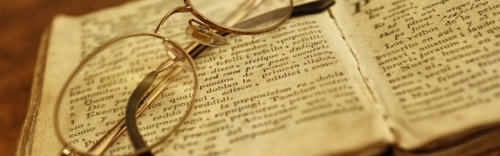





チンゲンサイの原産地は、中国の華中、華南といった地域が原産地ではなかったかと考えられています。アブラナ科で原種とされるものは地中海沿岸あたりを生息地としていたとされていてその原種が分化してわかれた品種が中国へ伝わったと考えられています。その野菜が中国の華中、華南で改良、栽培が行われこの地で野菜としてのチンゲンサイが作られることとなりました。