ウメ(花ウメ)の育て方

ウメ(花ウメ)の育てる環境について
育てる環境については鉢植えと庭植えとの両方とがあります。日本全国で栽培できるのですが、品種によって寒さへの強さが異なりますから注意が必要です。特に寒い地域で育てるのなら、それに合った品種を選ぶことが必要です。鉢植えの場合にも庭植えの場合にも、水はけが良くて肥沃な土壌を好みます。
湿気に弱く、乾燥に強い傾向がありますから、あまりにも水はけの悪い状態は適していません。とは言っても、日本の家庭の庭に植えるのであれば特に問題はありません。また、日当たりを好みますから日当たりの良い場所に植えると良く育ちます。
鉢植えの場合にも同じ事が言えるのですが、日当たりが良すぎると鉢が熱を持ってしまうことがありますから注意が必要です。根っこまで熱くなってしまうとそれが原因で枯れることがあります。ですから、鉢植えにする場合にはは鉢にあまり日が当たらないように注意しなければなりません。
風通しについては良好な場所が適しています。風通しが悪いと虫がついてしまうこともあります。観賞用であれば手入れして小さくすることが多いですが、実を収穫するためであれば大きく育てなければならないこともあります。
高さ、幅ともに6メートルくらいにまで育つことがありますから、できるだけ広い場所に植えた方が良いです。また、落葉植物ですから秋から冬にかけて多くの葉っぱが落ちるという点に注意が必要です。落葉しても良い場所に植えるようにしましょう。
種付けや水やり、肥料について
ウメは苗を植え付けて育てるか、あるいは接ぎ木をして育てるのが一般的です。種付けから育てるのは一般的ではありませんが、蒔けば生えてきます。種は夏頃に採取します。そのまま蒔いても冬にならないと発芽しません。
逆に、冬になると寒くても発芽しますから、たとえば冷蔵庫で保存しておいても芽が出てくることがあります。実を採取する場合、食用にするのなら固い内に採取するのが一般的ですが、発芽させるのなら完全に熟した状態の方が適しています。
それをそのまま土に埋めておくと、冬になると発芽します。水やりについては、庭植えの場合にはあまり気にする必要はありません。あまりにも暑くて晴れの日が続いているような状態であれば水をやった方が良いですが、水をやりすぎると逆に弱ってしまうこともありますから注意が必要です。
鉢植えの場合には定期的に水やりをしなければなりませんが、やり過ぎるとやはり弱ってしまいますから注意が必要です。表面が乾く前に水やりをするのではなく、完全に乾いた状態になってから水をやったほうが良いです。肥料は好む植物です。
苗から植え付けをするときには、植える時には掘った穴に堆肥を混ぜて埋め戻します。冬を越す12月から1月には有機肥料を株元の周辺に埋めておくと良いです。肥料が少ないと花をあまりつけませんし実もあまり多くはなりません。花を楽しみたい場合も、実をとりたい場合にも肥料はしっかりとやっておきましょう。
ウメ(花ウメ)の増やし方や害虫について
ウメの増やし方は実生、接ぎ木、挿し木などによって増やすことができます。最も一般的なのが接ぎ木です。ウメは高度に品種改良が進んでいますから、実生で増やした場合には、元も軽質とは異なる形質が発現します。花の色が悪かったり、あるいは花があまり多くなかったりすることがあります。
基本的には別のものが発現すると考えておいた方が良いでしょう。ですから、接ぎ木のほうが適しています。接ぎ木で増やす場合には台となる木が必要となりますが、これは実生で増やしても問題はありません。接ぎ木する場合には2月頃に枝をとって起きます。
そして、3月頃に台となる木に接ぎ木するのが一般的です。接ぎ木の方法は一般的なもので、形成層を密着させて固定すれ乳母良いです。病気や害虫の被害に遭うことがありますが、この場合には薬で対処することもできるのですが、やはり環境は重要です。
風通しが良くて適度に日光が当たる場所におけば病気も害虫もあまり発生しません。害虫としてはアブラムシやオビカレハ、コスカシバがあります。被害を受けると葉が萎縮する原因となりますから注意が必要です。オビカレハはウメ毛虫と呼ばれることもあるくらいで、
何もしないでいると発生して増えることがあります。冬を越すときに卵を木に植えますから、この塊を除去してやると増えるのを防ぐことができます。風通しの悪い場所に植えてしまうと害虫が発生してしまうことがありますから、定期的に防除すると良いです。
ウメ(花ウメ)の歴史
ウメの系統をたどっていくと、サクラやモモと同じように、もともとトルコやイランなど、中東の地域を原産とする植物だと考えられています。現在のウメに近い植物の元々の生息地は中国で、それが東アジア全体で栽培されるようになったと考えられています。
それが日本にもたらされたのはいつの頃なのかは分かっていないのですが、日本では奈良時代にすでにあったことが知られています。かつては「花」という言葉は梅の花を指すことが多かったのです。古典の世界では「花」は梅の花を指します。
江戸時代以降になって桜が多く見られるようになったために、現在では桜を指すことが多いのですが、昔はウメこそが花の中で最も美しいものとされたのです。なお、ウメと言った場合には実をとるための農産物としてのものを指す場合もあります。
歌に詠まれる場合には観賞するための花ウメを指すことが多いです。梅の名所としては神戸の岡本が有名で、古来からウメが最も美しい地域とされていました。いつから栽培されているのかは分かりませんが、豊臣秀吉が訪れたと言うことが記録に残っていますから、かなり昔から栽培されているようです。
歴史的人物としては菅原道真が込んだことは有名なことの一つです。奈良時代には文様として用いられていたようです。家紋が梅鉢の家計もあると思いますが、これが用いられ始めれたのはやはり菅原道真によるところが大きく、彼がウメを好んだことから使われるようになったと考えられています。
ウメ(花ウメ)の特徴
ウメは早春の花とされていて、正月の行事が終わった頃に花を楽しむことができます。科カジキは1月から3月と幅広いです。地域や場所、あるいは天候や育て方などによって違いが生じます。5月から6月に実をつけます。元々は大きな木であったものが現在のようにして用いられるようになりましたから、
手入れをしないでいるとかなり大きくなります。5メートルから6メートルくらいになることも珍しくはありません。毎年手入れをしていると小さく育てることも可能です。盆栽として用いられることもありますし、庭木として用いられることもあります。
花や香りを楽しむだけではなくて、食物としての栽培も行われています。果実は2センチから3センチくらいの大きさになります。梅干しや梅酢、梅酒などの味からも分かると思いますが、酸性の強い実をつけます。この賛成はクエン酸です。ウメの未熟な実には毒性があると言われますが、
これはウメに含まれる成分が体内で反応してシアンを合成するからだと考えられています。けいれんや麻痺、呼吸困難を引き起こすこともあり、最悪の場合には死亡することもあるそうですから、栽培するときには注意が必要です。
ウメは古い時代から栽培されている植物ですから、品種改良も進んでいます。そのため、細かく分類をするのは難しいのですが、大きく分ければ観賞用の花ウメと果実を収穫するための実梅の二つに分けられます。花ウメはさらに、いくつかに分類されますが、それぞれで花の色や形が異なります。
庭木の育て方など色々な植物の育て方に興味がある方は下記の記事も凄く参考になります♪
タイトル:シキミの育て方
タイトル:カルーナの育て方
タイトル:アンズの育て方
-

-
一重咲きストック(アラセイトウ)の育て方
一重咲きストック、アラセイトウはアブラナ科の植物です。原産地は南ヨーロッパで、草丈は20センチから80センチくらいです。...
-

-
アボカドの栽培について
栄養価が高く、サラダやサンドウィッチの具材としても人気の高いアボカドですが、実はご家庭で観葉植物として栽培することができ...
-

-
アングレカムの育て方
アングレカムはマダガスカル原産のランの仲間です。マダガスカル島と熱帯アフリカを生息地とし、およそ200の種類があります。...
-

-
ギョリュウバイの育て方
ギョリュウバイはニュージーランドとオーストラリアの南東部が原産のフトモモ科のギョリュウバイ属に分類されている常緑樹で、日...
-

-
ブラシノキの育て方
フトモモ科ブラシノキ属するブラシノキには34種類あるといわれ、オーストラリア全域からニューカレドニアが生息地です。低木か...
-

-
トリテレイアの育て方
トリテレイアは、ユリ科に属する球根性の多年生植物で、かつてはブローディアとも呼ばれていました。多年生植物というのは、個体...
-

-
アスプレニウム(Asplenium spp.)の育て方
アスプレニウムは5月から8月頃にかけて植え付けをします。土は水はけが良く、通気性が良いものを使います。例えば小粒の赤玉土...
-

-
バラの鉢植えでの育て方のコツ
植物の栽培を趣味にしている人は多いですが、そういった人でもちょっとハードルが高く感じてしまうのがバラです。ミニバラを育て...
-

-
プチアスターの育て方
キク科カリステフ属のプチアスターというこの花は、中国北部やシベリアを原産国とし1731年頃に世界に渡ったと言われておりま...
-

-
ノウゼンカズラの育て方
ノウゼンカズラの歴史は古く、中国の中・南部が原産の生息地です。日本に入ってきたのは平安時代で、この頃には薬用植物として使...




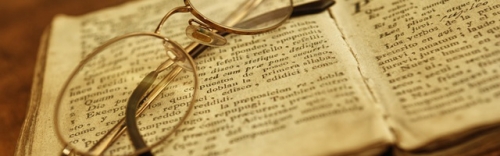





ウメの系統をたどっていくと、サクラやモモと同じように、もともとトルコやイランなど、中東の地域を原産とする植物だと考えられています。現在のウメに近い植物の元々の生息地は中国で、それが東アジア全体で栽培されるようになったと考えられています。