カルーナの育て方

カルーナの育てる環境について
カルーナは涼しい気候を好みます。育て方自体は難しくはありませんが、いくつか注意するべき事があります。まず、やせた酸性度を好むことが特徴としてあげられます。他の植物があまり育たないような環境を好み、高温多湿には弱いです。風通しの良いところを好みますが、乾燥はあまり好みません。
冷涼な気候を好みますから耐寒性はあるのですが、耐暑性はあまりありません。特に夏はできるだけ涼しい環境で育てるようにします。風通しが良い状態を好み、蒸れてくると生育が衰えることもありますから注意が必要です。あまり大きく育てると株の内部の風通しが悪くなって生育しなくなることもあります。
花が咲き終わった時期を見計らって全体を半分くらいの高さに刈り込むと良いです。日当たりの良い場所を好み、日照が不足すると葉の色が悪くなったり花がつかなくなったりすることもあります。耐寒性はありますが、日本の寒い風が直接当たるような場所は避けた方が良いです。室内に取り込む必要はありません。
室内に取り込むと日当たりが悪くなることもありますから、室内に取り込んで育てたい場合には、ときどき日当たりの良い場所におくようにすると良いです。紅葉を楽しみたい場合には環境に注意が必要です。
気温によって紅葉するかどうかが決まりますから、紅葉するはずの品種がずっと緑色のままだという場合、少し温度の低いところにおいて育てるなどの工夫をすると、紅葉することもあります。
カルーナの種付けや水やり、肥料について
カルーナは湿り気の多いところで育てると根腐れを起こしやすいです。ですから、水のやり過ぎには注意が必要です。それとともに乾燥に強くはないという特徴もあります。ですから、水切れを起こさないように注意しなければなりません。特に夏は水が不足すると弱ってしまうことがありますから注意が必要です。
土の表面が乾くと水をたっぷり与えるようにします。乾く前に水やりをすると根腐れを起こしますから、表面が乾いてから水やりをするようにします。用土も水はけの良いものを選ぶと良いです。鹿沼土を多く含む土壌が適しています。また、肥料はあまり好まない性質があります。
肥料を多く与えすぎると根が弱ってしまうことがありますから、どちらかというと肥料は控えめにすると良いです。植え付けるときにはある程度の肥料を混ぜておきますが、この際にも速効性のあるものは適していません。植え付けの時に肥料をやって、そしてその後は月に1回くらいで十分で、それ以上やると逆効果になります。
土壌についても肥料成分があまりないものを選んだ方が良いです。特に酸性土壌を好むという点に注意が必要です。たとえば、ピートモスなどを用いるのが良いです。色々な用途に使えるようにするために、
酸度を調整したピートモスも販売されていますが、カルーナを育てるのであれば、酸度の調整を行っていないピートモスを用いる方が適しています。酸度を調整していないピートモスを土壌に混ぜ込んでおくのも良い方法です。
カルーナの増やし方や害虫について
増やし方の基本は挿し木です。適した時期は4月から5月です。土壌については水はけの良い酸性土壌が適しています。腐らないようにするためには水はけの良いものを選ばなければなりません。肥料のない状態を好みます。枝の先端を3センチから5センチくらい切り取り、水につけて水を吸わせ、その後に用土に植え付けます。
根が出るまでは乾かさないように注意しなければなりません。1日に1回から2回は水やりをするように心がけます。日差しの強いところだと乾燥してしおれてしまうことがありますが、光が当たらないと育ちません。ですから、直射日光の当たらない日陰におくのが良いです。
また、風が強いと傷んでしまうことが多いですから、風があまり当たらないところに置く方が良いです。温度については20度から25度くらいがベストですが、日本の気候で言えばつゆ頃が最も適しています。害虫についてはアブラムシが発生することがあります。春から秋に発生しますから、見つけたらすぐに薬剤で防除すると良いです。
早めに防除しておくのも良い方法です。アブラムシ以外にも害虫が発生することがありますが、この場合にも早期発見が大事で、できるだけ早い段階から薬剤で防除しましょう。園芸用の殺虫剤を用いるのも良い方法ですし、繁殖力を低下させる薬剤を散布して駆除するのも良い方法です。毎日観察をするにようにしていれば害虫が発生していないかどうかを確認することができるでしょう。
カルーナの歴史
カルーナはヨーロッパや北アフリカなど、地中海の周辺に生息する植物です。カルーナという言葉は「掃く」という意味に由来します。かつては枝を使って箒を作っていたために、このような名前がつけられました。伝統医学では薬としても用いられてきた歴史もあります。
知性作用があるとも言われていて、泌尿器系の症状に対して使われてきたそうです。医学の進歩した現在では、アルグチンなどの成分が含まれていることが分かっています。生息地としてはヨーロッパが主なもので、ヨーロッパではごくありふれた植物です。
酸性土壌の荒れている土地であっても元気に育つことから、他の植物が育たない荒れ地に繁殖し、歴史的に見ても人間の生活と密接に関係してきました。たとえば、燃料として用いられたり、濾過するためのフィルタとして用いられたり、あるいはベッドに用いられたりと、色々な使い方がされてきました。
荒れた土地では植物があまり育たないために、このような地域で育つ植物は重宝がられたのです。箒として使われたのも、他に使うものがなかったと言うことが理由だとも考えられます。現在はこのような使われ方はあまり見られませんが、
それでもやはりヨーロッパの形式を代表する植物だとも考えられていて、現在では観光開発のために植えられるなど、保護しようという動きが多く見られています。原産はヨーロッパですが、日本でも栽培されています。日本では庭園植物と言うよりも鉢植えで育てることが多いです。
カルーナの特徴
カルーナはツツジ科に属する植物で、多くの品種が作られています。ヨーロッパや北アフリカの荒れ地に育つと言うこともあって、酸性土壌でも育つという特徴があります。高温多湿にはあまり強くはありません。葉は日本のツツジとは異なり、多肉異質です。
緑色のは野茂のだけではなくて、黄色や赤色など色々な色の花があるために、観賞用として用いるのには最適です。常緑の低木ですから背丈はあまり大きくはなりません。花弁はあまり大きくはなりませんが、がくが大きく色づいて花弁のように見えます。
ツツジ科の植物でありながらも、形状がコニファーに近く、そのために寄せ植えとしても用いやすいです。常緑ですから冬でも葉をつけたままですから、寒冷地の庭にも適しています。品種改良が行われていますから、色々なものを楽しむことができます。
冬になって赤や黄色に色づくものなどもあります。日本で品種改良が行われたことによって、寒い時期に開花するものを入手できます。日本で寒い時期に庭を華やかにする植物として用いられていて、たとえば年越しができるものもあります。このようなことから開花期は様々ですから、
状況に応じて使い分けていくと良いでしょう。鉢植えで育てることが多いですが、地植えして楽しむことができる地域もあります。紅葉する品種は、その後落葉するのではなくて、暖かくなると緑色に変化するという特徴を持っています。置く場所によって色の付き方が異なります。
庭木の育て方や色々な植物の育て方に興味がある方は下記の記事も参考になります♪
タイトル:ドウダンツツジの育て方
タイトル:セイヨウヒイラギの育て方
タイトル:シキミの育て方
-

-
アークトチスの育て方
アークトチスはキク科の可愛らしい植物です。とてもかわいらしく可憐な雰囲気のある花ですが、キク科という事もありとても身近に...
-

-
しばざくらの育て方
しばざくらの特徴は、その名の通り、芝のように地面を覆って花を咲かせることでしょう。花は桜の花に似ており、4?5月に満開を...
-

-
パンクラチウムの育て方
パンクラチウムはヒガンバナ科パンクラチウム属の植物です。原産はスリランカで、地中海沿岸に生息地が分布しています。17世紀...
-

-
ロムレアの育て方
南アフリカはアヤメ科の球根が、たくさん栽培されていて、ロムレアもその仲間のひとつです。手に入りにくい球根と言われていまし...
-

-
カタセタムの育て方
カタセタムの科名は、ラン科、属名は、カタセタム属になります。その他の名称は、クロウェシアと呼ばれることもあります。カタセ...
-

-
ディッキアの育て方
まだまだ我々日本人にとって馴染み深いとは言えない植物、ディッキア。数多くの種を保有する植物群のなかでも、かなり特徴的な形...
-

-
シロハナノジスミレの育て方
スミレ科スミレ属の多年草ですが日本ではどこでも比較的見られる品種で、本来のスミレよりも鮮やかな色で、素朴なスミレらしさは...
-

-
家庭菜園でサヤのインゲンの育て方
サヤインゲンには、つるあり種とつるなし種があります。つるあり種は、つるが1.5m以上に伸びますし、側枝もよく発生するので...
-

-
トキワマンサクの育て方
トキワマンサクは日本をはじめ中国やインド、台湾などにも生息地があります。もともと日本に自生していた植物ではなく、原産地の...
-

-
インゲンの育て方
豆の栽培は農耕文化が誕生したときから穀類と並んで始まったと言われています。乾燥豆は品質を低下させずに長い期間貯蔵できるこ...




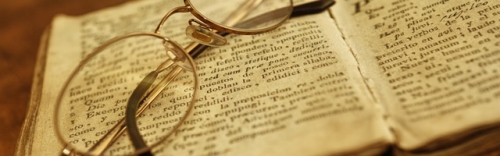





カルーナはヨーロッパや北アフリカなど、地中海の周辺に生息する植物です。カルーナという言葉は「掃く」という意味に由来します。かつては枝を使って箒を作っていたために、このような名前がつけられました。