シュンランの育て方

シュンランの育てる環境について
シュンランは元来、里山や傾斜地などに生育しています。日当たりが悪くても育ちますが、少なくとも木漏れ日程度の光は必要です。また夏は涼しいほうがよく、冬の寒さも厳しくない環境が育てやすいと言えます。基本的にシュンランは、風通しの良い日なたで育てます。
冬は休眠期なので、あまり日光を気にする必要はありませんが、春から秋にかけては日当たりの良い場所に出してやることが大切です。そうしないと花のつきが悪くなります。ただし真夏の直射日光は葉を傷める原因になります。夏季はよしずを掛けるなどして、直射日光が当たらないよう工夫する必要があります。
また色や柄を楽しむ品種の場合、葉や花が焼けることを嫌って、一年中日陰で育てることもあります。どちらが適当かは、園芸店などで確認してください。冬は零度ぐらいまでの寒さには耐えるとされています。しかし霜が降りたり土が凍ったりすると枯れることがあります。
また寒風にさらされると葉が痛んでしまいます。温暖な地方では軒下やベランダで冬越しさせることも可能ですが、大事を取るなら室内に入れたほうが安全でしょう。ただし暖房が直接当たらないようにしてください。
シュンランは体内に水を貯めることができ、やや乾燥した土壌を好みます。逆に年中湿っているところには弱く、根腐れを起こすこともあります。日本に自生している植物なので、育て方全体にそれほど難しいことはありませんが、園芸品種にはそれなりの気遣いを要します。
種付けや水やり、肥料について
シュンランをはじめとするラン科の植物は、一般にラン菌と呼ばれる菌類から栄養を取ることで知られています。小さな種には栄養分がほとんど含まれていないため、発芽の際には周囲の土に含まれる菌類の助けが必要です。また発芽してからも、地下でラン菌から養分を取り、長い間腐生植物のように生活します。
このため、種から育てようとすると、花が咲くまで5年~10年以上もかかることがあります。園芸店などで流通している品種は、株分けして増やしているのが普通です。シュンランに水をやるときは、土が十分に乾燥してから、たっぷりと与えるようにします。
乾燥を好むといっても、与える水の量が少なくて良いという意味ではありません。ただしいつも土が濡れているようだと、根腐れの原因になるので気をつけてください。特に受け皿に溜まった水は、必ず捨てるようにしましょう。以上は春から秋にかけての話で、冬季は水やりを控えます。
1か月に1~2回、もしくは全く与えないという方法もあります。与えた水分が凍結しては困るので、午後遅くには水をやらないようにします。肥料は市販されている洋ラン用の置き肥を使うこともできますし、油粕と骨粉を混ぜたものでも構いません。
早春に花芽が伸びはじめたら、花芽を傷めないよう、株から少し離して肥料を与えます。その1~2か月後、植え替えのタイミングに合わせて、追加の肥料を与えると良いでしょう。それ以外には特に肥料は必要ありません。
増やし方や害虫について
シュンランを植えるには、水はけの良い土が適しています。鹿沼土や日向土に赤玉土を少量混ぜるか、市販されている東洋蘭の土を使用します。根が伸びるので、縦に長い素焼きの鉢が向いています。プラスチックの鉢を使うなら、通常よりも水はけの良い土を使うようにしてください。
3年に1回ぐらいの割合で、植え替えを行ないます。時期は4~6月ごろが適当です。まず鉢から株を取り出し、新芽を傷めないよう注意しながら、土を払って根の状態を確かめます。腐った根や枯れた葉は取り除き、形を整えてから、バルブが半分ほど隠れる深さに植えていきます。
植え替えと合わせて、株分けを行っても良いでしょう。ただし小さすぎる株には花が付かなくなるので、頻繁に株分けをするのは考え物です。ひとつの株にバルブが3個以上付いていることが目安になります。また株分けは基本的には手で行ないます。
ハサミを使う場合は、よく消毒しておく必要があります。ウイルス感染が心配なら、株を消毒液に浸す方法もあります。シュンランはウイルスに感染しやすいという弱点があります。発病すると治すことはできず、ほかの株にまで伝染して、最終的には枯れてしまいます。
また梅雨時にはカビやナメクジが発生することもあります。植え替えの際には器具の消毒が大切です。それ以外の時もこまめに様子をチェックして、害虫にやられた場合は駆除剤を使用し、ウイルスに感染した株は早めに取り除くようにしてください。
シュンランの歴史
シュンランはラン科シュンラン属の植物で、洋ランとして馴染みの深いシンビジウムの一種です。原産は東アジアで、日本の森林にも自生しています。日本では北海道から九州までと生息地が広く、木の密生していない人里近くの雑木林などを好みます。
日本以外では中国、朝鮮半島、台湾にも分布しています。厳密には日本原産のものを日本春蘭、中国原産のものを中国春蘭と呼んでいます。園芸植物としては中国春蘭のほうが古い歴史を持ち、もっぱら花の形や香りが珍重されました。日本春蘭は並物と呼ばれる一般的な品種のほか、
花の色が普通とは異なる花物や、葉に斑が入った柄物などの品種があり、それらを楽しむのが栽培の目的のひとつです。ただし現在では、どちらもシュンランの名で親しまれています。シュンランは古くから日本人に愛されてきた花です。春蘭秋菊ともに廃すべからずという諺があり、
菊とともに美しい花の代名詞とされていました。日本画の画題とされたり、漆器や陶磁器のデザインに用いられることもありました。また塩漬けにした花に白湯を注いだものを蘭茶または蘭湯といい、祝いの席に供されました。ツボミを酢の物や天麩羅として食べることもありました。
身近な花であったシュンランには、ホクロ、ジジババ、ジイサンバアサンなど多くの別名があります。花びらの斑点を老人のシミに見立てたとか、花の姿を頭巾やヒゲに見立てたとかいう説がありますが、正確なことは分かりません。
シュンランの特徴
シュンランの葉は硬くて細長く、周囲に細かい鋸歯があってギザギザしています。長さは20~35cmほど、幅は0.5~2cm程度です。地面から複数の葉が真っ直ぐに立ち上がり、先は垂れ下がるのが特徴です。太くて長い根がたくさん生え、古い株の根元は球根のように膨らんでバルブ(偽球茎)を作ります。
これは実際には根ではなく茎の一部です。根は水平方向には伸びず、バルブが分かれて新しい株になります。春になるとバルブから1本の茎が伸び、その先に1輪の花を咲かせます。花茎は鱗片に包まれ、葉に隠れて目立たないことが多いようです。ごくたまに1本の茎に複数の花をつけることもあります。
普通種では花は5cmほどの大きさで、がくは薄い黄緑色、花びらは白に紫の斑点が入っています。香りは弱いものが多いのですが、園芸品種では芳香を放つものもあります。花の後には花茎が葉の上まで伸び、紡錘形の果実をつけます。
果肉は硬いですが、熟すると裂けて種子をばら撒きます。種子は非常に小さく、ひとつの果実に数え切れないほど入っています。また晩秋には地下に新しい花芽を生じます。しかし伸びることはなく、そのまま冬を越して翌年の春を迎えます。
園芸品種のうち、花物には赤花・白花・縞花などの種類があり、柄物では虎斑・縞・蛇皮などが知られています。古くから育てられてきた植物だけにバリエーションも豊富ですが、種から育てるのは時間がかかるという特徴もあります。
花の育て方など色々な植物の育て方に興味がある方は下記の記事も凄く参考になります♪
タイトル:シュスランの育て方
タイトル:サギソウの育て方
タイトル:アングレカムの育て方
タイトル:エビネの育て方
-

-
サボテンの育て方のコツとは
生活の中に緑があるのは目に優しいですし、空気を綺麗にしてくれるので健康にも良いものなのです。空気清浄機のように電気代がか...
-

-
緑のカーテンの育て方
緑のカーテンの特徴としては、つる性の植物であることです。主に育てるところとしては窓の外から壁などにはわせるように育てるこ...
-

-
ブルビネラの育て方
ブルビネラは南アフリカやニュージーランドを原産とする花であり、日本で見ることが出来るようになってきたのはごく最近のことで...
-

-
マルバノキの育て方
木の種類としては、マンサク科、マルバノキ属となっています。別の名称としてベニマンサクと呼ばれています。園芸分類としては庭...
-

-
ハバネロの育て方
ハバネロはトウガラシの一種で、原産地はアマゾンかその周辺の地域だといわれており、そこからユカタン半島に伝わったと考えられ...
-

-
イベリスの育て方
アブラナ科のイベリスは、地中海沿岸が原産の花です。ヨーロッパから北アフリカ、西アジア原産で、その可愛らしホワイトカラーの...
-

-
ハナモモの育て方
ハナモモというのは、中国が原産地で鑑賞をするために改良がなされたモモですが、庭木などにも広く利用されいます。日本へ入って...
-

-
バーベナの育て方
バーベナは、クマツヅラ科クマツヅラ属(バーベナ属とも)の植物の総称です。様々な種類があり、基本的には多年草、あるいは宿根...
-

-
グズマニアの育て方
パイナップル科グズマニア属の観葉植物です。常緑性で、熱帯アメリカが原産です。背丈は25〜50cmほどで、横幅は35〜60...
-

-
スターフルーツの育て方
スターフルーツは南インド等の熱帯アジアを原産としているフルーツです。主に東南アジアで栽培されている他、中国南部や南アメリ...




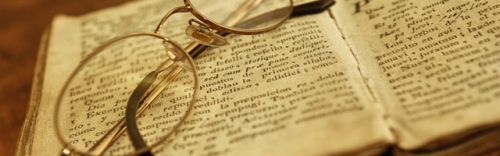





シュンランはラン科シュンラン属の植物で、洋ランとして馴染みの深いシンビジウムの一種です。原産は東アジアで、日本の森林にも自生しています。日本では北海道から九州までと生息地が広く、木の密生していない人里近くの雑木林などを好みます。