サルビア・レウカンサの育て方

サルビア・レウカンサの育て方
基本的な育て方としては、日当たりがよく風通しと水はけが良い場所であれば育ちます。サルビア・レウカンサは夏の直射日光に負けない植物で乾燥した環境を好みますが、夏の西日が猛烈に照り付けるといった極端に乾燥するような場所で栽培することは好ましくありません。
西日があまりに強すぎる場合には鉢植えなら場所を移動させるか、日よけなどをして日光があたりすぎないような工夫をすることが好ましい育て方です。原産地がメキシコや中央アメリカだけあって、やや乾燥した状態の方がよく育ちます。水はけのよい土壌を好みますが、夏場は乾燥しすぎないように水をしっかりと与えましょう。
乾いたら水やりをする、という頻度が丈夫な育て方のコツです。庭に植えるような場合には水やりをしなくても降雨だけで充分ですが、夏場にあまりにも日照りが続くようならば様子を見て水を与えた方が良いです。用土は草花用培養土を使用するか、赤玉土に腐葉土を適度に混ぜたものを使用すると良いでしょう。
栽培中に注意したいこと
サルビア・レウカンサは夏から秋にかけて咲き、毎年花を咲かせる多年草で比較的大型になります。横にもよく広がる性質があるため、あまり大きく育てたくないという場合には7月頃にばっさりと短く刈り込むことをおすすめします。夏以降にあまり大胆に刈り込むと冬の寒さを乗り切れない可能性があり、開花しなくなってしまうことがあるため注意しましょう。
その他には夏の時期が来る前に摘芯をすることで、成長をおさえることが可能です。摘芯とは芽を摘み取ることで「ピンチ」と呼ばれることもある剪定方法の一種です。成長しすぎてかたちが乱れがちな植物の姿を整えたり、わき芽を増やして花をたくさん咲かせるために行います。
背が高くなりすぎると強風のときは倒れやすくなります。せっかく丹精した大切な植物ですから、倒れたり吹き飛ばされたりして傷まないようにしたいものです。サルビア・レウカンサの花の時期は日本では台風が来るときと重なる場合が多いため、支柱などをたてておくと安心です。
鉢植えにした場合は屋内に一時的に取り込んだ方がより安心できます。冬場は根本を腐葉土やバークチップなどで厚めに覆ってやり、根を寒さから守ります。この方法はマルチングといって、冬の寒さから植物の根を守ったり傷まないようにするために有効な方法です。
寒さから守るためだけでなく、水分の蒸発を防ぎたいときにはミズゴケなどを利用する場合もあります。鉢植えと地植えの両方で使用することができます。冬の間も見た目は枯れてしまっても常にマイナス3度以下になるような厳寒地でない限りは根の部分は生きているため、水やりの必要があります。
冬場であっても土が乾いていれば水やりをしましょう。地上部分が枯れてしまっても、越冬に成功すれば、春の訪れとともに根本から再び芽吹きます。もし、対策をしても外の寒さが不安な場合には屋内の日当たりの良い場所に取り込むという方法もあります。日光がなければ光合成ができずに枯れてしまいます。
室内に取り込んだ場合でも、天気の良い温かい日には外に出して日光浴させるようにするといいでしょう。栽培中、病虫害の心配はほとんどない植物ですが春先にはアブラムシが発生することがあります。発生したときに慌てないように専用の薬剤を用意しておきましょう。高温乾燥時はダニ類が発生することがありますが、あまり神経質にならなくても大丈夫です。もし不安ならば葉の表面が乾燥しすぎないようにときどき霧吹きをするといいでしょう。
サルビア・レウカンサの増やし方
サルビア・レウカンサは花だけでなく、シルバーがかった葉の緑が美しく、花の時期以外に葉を観賞して楽しむことができます。ぜひ増やしたいと思ったときは、種付けをするよりも株分けをして増やしましょう。種付けをするためには種の採取が必要ですが、園芸品種として一般的に手に入るサルビア・レウカンサに種ができることは非常にまれだといえます。
種付けをするために必要な種の販売もあまり一般的ではありませんので、挿し木や株分けという方法をとる方が増やし方としては無難だと考えられます。種付けすることにあまりこだわらず、家庭で栽培するという場合には挿し木や株分けをしましょう。株分けの方法はとても簡単です。3月下旬から4月頃までに株を鉢から抜いて、余分な古い土を取り除き根本から二つに分割します。
もっと細かく分割することもできますがあまり細かくすると株を傷めることにつながるため、慣れないうちは二分割程度にした方が安全です。根がからみあいすぎて手でほぐせないときには刃物を使って半分に切ってもよいですが、あまり大胆にし過ぎると根を傷めてしまうので注意しましょう。庭植えにして大きく育っている場合には挿し木する方法がらくです。挿し木に適した時期は初夏頃です。剪定した枝を利用することができるので、試してみましょう。
サルビア・レウカンサの歴史
サルビア・レウカンサの原産地はメキシコや中央アメリカです。別名を「メキシカンブッシュセージ」「アメジストセージ」といい、シソ科多年草の植物です。ハーブの一つとしても知られています。サルビアはもともとラテン語で治癒や健康を意味する言葉が語源となっており、この種類の植物は薬用とされることが多いことが由来しています。
日本には明治時代以降に渡来したといわれています。ハーブの一種だけあって爽やかな香りが楽しめ、鉢植えでも庭植えにしてもその姿が様になることから、日本の一般家庭でも多く栽培されている種類の草花です。もともと生息地としていたメキシコや中央アメリカが乾燥しているせいか、過湿な環境は少々苦手としています。
別名のアメジストセージという名前からもわかるとおり、紫水晶のような色あいの花を咲かせます。同じ株でも、白い花と紫の花が咲く場合があります。レウカンサは「白い花」を意味する言葉なので、もしかしたらもともとは白い花を咲かせていたのかもしれません。
サルビア・レウカンサの特徴
草丈は1.5mにもなるためサルビアの中でも大型の種類といえます。背が高くなるため見ごたえがありますが、鉢植えで育てる場合には強風などで倒れやすいため注意が必要です。育てる環境によっては2m近く育ってしまう場合もあります。可能な場合には、鉢植えごと花壇スペースなどに掘って埋めてやると倒れるのを防ぐことができます。
サルビア・レウカンサは一日の日照時間が短くなる時期に咲きだす短日植物です。短日植物は必ずしも明るい時間にさらされるよりも暗い時間が長いことが必要というわけではなく、一定時間以上の暗い周期と明るい周期が交互に繰り返されることにより花芽をつけます。
短日植物としては他にキク、コスモス、イネなどがあげられ、夏から秋にかけて開花する植物に多いという特徴があります。サルビア・レウカンサの花は一見すると花というより穂のように見えますが、ビロードやフェルトを思わせるような少々毛羽立つような見た目をしています。
花が少なくなる秋から晩秋を彩ってくれる貴重な草花です。冬になると地上部が枯れますが、地下の根が生きていれば温かい季節がくればまた息を吹き返します。見た目だけでなく香りを楽しむことができるハーブの寄せ植えを作る際には、ぜひ主役にしたい草花です。ハーブといっても食用には適さず、観賞用として育てる他にポプリやドライフラワーとして楽しむことができます。
花の育て方など色々な植物の育て方に興味がある方は下記の記事も凄く参考になります♪
タイトル:サルビア(一年性)の育て方
タイトル:アルメリアの育て方
タイトル:ケマンソウの育て方
タイトル:プルネラの育て方
タイトル:セージの育て方
-

-
コキアの育て方
南ヨーロッパや温帯アジアが原産とされ、日本へは中国から伝わってきた植物で、詳しいことははっきりと分かっていませんが、「本...
-

-
ニューサイランの育て方
ニューサイランはニュージーランドを原産地としている植物であり、多年草に分類されています。ニューサイランはキジカクシ科、フ...
-

-
インドゴムノキ(Ficus elastica)の育て方
日本でも一部の温暖な地域では戸外で育ちますが、寒冷地では鉢植えで育てます。ミニサイズの鉢から大型のものまで、様々な趣のあ...
-

-
オヒルギの育て方
オヒルギはマングローブを構成する植物の種類のうちの一つです。仲間の種類として、ヤエヤマヒルギやメヒルギなどがあります。自...
-

-
ヘスペランサの育て方
ヘスペランサは白い花を持つ美しい植物でり、日本だけに留まらず多くの愛好家がいます。花の歴史も深く、大航海時代にまで遡る事...
-

-
家庭菜園でサヤのインゲンの育て方
サヤインゲンには、つるあり種とつるなし種があります。つるあり種は、つるが1.5m以上に伸びますし、側枝もよく発生するので...
-

-
バナナの育て方
バナナの歴史は非常に古く紀元前10000年前には既に人間に認知されており、栽培もされていたと言われています。現在我々が口...
-

-
サルナシの育て方
見た目が小さなキウイフルーツの様にも見える”サルナシ”。原産国は中国になり、日本でも山間部などを生息地とし自生している植...
-

-
ムベの育て方
植物の種類としては、キンポウゲ目、アケビ科となります。園芸をする上でどのように分類されているかですが、まずは庭木であった...
-

-
ヒトツバタゴの育て方
20万年前の近畿地方の地層から、泥炭化されたヒトツバタゴがみつかっています。しかし、現在の日本でヒトツバタゴが自生するの...




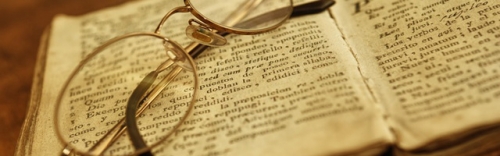





サルビア・レウカンサの原産地はメキシコや中央アメリカです。別名を「メキシカンブッシュセージ」「アメジストセージ」といい、シソ科多年草の植物です。ハーブの一つとしても知られています。サルビアはもともとラテン語で治癒や健康を意味する言葉が語源となっており、この種類の植物は薬用とされることが多いことが由来しています。