キングサリの育て方

育てる環境について
キングサリはアルプスを含むヨーロッパ中南部の山地、林の中や潅木地帯が原産生息地です。そのため寒冷地に適しており、寒さに強く、高温多湿に弱い植物です。積雪にも耐え、関東以北での栽培に向いています。キングサリを大木に育てるには寒冷地がよいですが、
盆栽や小ぶりで楽しむといった育て方の場合には西日本の暖地でも栽培できます。風通しのよい半日陰で育てます。高温多湿の環境では弱ってしまいます。真昼の直射日光や高温になる夏の西日の射す場所は向いていません。蒸し暑さでも痛むことがあります。
建物の東側など、午前中に日光があたり、午後には日陰になるような場所を探すとよいでしょう。完全に日が当たらない場所ではよく育たず、花つきも悪くなります。乾燥には強く、水はけのよい土なら土壌を選ばず栽培できます。肥沃であればなおよいでしょう。
枝葉はすぐ成長しますが、成長しても幹が細いことが多いので、若木のうちは支柱が必要です。枝が柔らかいので、アーチや棚に誘引し、藤のように花を垂れさせて楽しむこともできます。小さく仕立てれば、鉢植えや盆栽としても栽培できます。
積雪する地域では、若木のころは雪の重みで幹や枝が折れてしまうことがあります。雪よけをするか、支えを立てるなど対策をとります。適さない環境で苗を入手した場合は、しばらく鉢で育て、栽培環境に慣れさせます。
あまり剪定しない育て方にすると5~7メートルと大きくなるので、育った後の環境も考えて植生場所を選びましょう。冬には落葉することも忘れないようにしましょう。
種付けや水やり、肥料について
植え付けの時期は、落葉した後の11~12月と、芽が動く直前となる2~3月です。寒冷地方では秋に植えると寒さで枝が弱り、枯れやすくなるので避けましょう。キングサリは根に根粒菌の入った結節を持ち、移植を好みません。成長してから場所を変えてしまうと、根が土になじまず、枯れこんでしてしまいます。
移植は6年ぐらいまでの若木が限度です。植える場所にバーク堆肥や培養土を混ぜておきます。水はけが悪い粘土質の土は、よく耕し腐葉土や赤玉土、川砂などを混ぜます。土の保水力が高ければ根の成長も早く、根がしっかりしていれば水の吸収がよくなります。
植え付け時には根を痛めないよう、根鉢は崩さず、注意して植えます。麻布などで包まれていればそのまま、ビニールテープで固定されていたら切り取ってください。植え付け後2年ほどのうちは、土の表面が乾いたころ、たっぷり水をやります。
庭植えでも降雨だけでは足りないことがあります。乾燥に弱いので、風通しがよすぎたり日の強い場所では、適宜水やりを増やします。水切れしないよう、真夏は気をつけてください。寒肥として1月ごろに堆肥を根元にやり、花が終わったら化成肥料をひかえめにやります。
マメ科のキングサリは根粒菌と共生しており、根粒菌は土壌中の窒素を固定し植物に与えています。窒素分が多くなると、枝葉は豊かになりますが花つきが悪くなります。窒素分は控え、リン酸やカリが中心になった化成肥料をやります。
増やし方や害虫について
実生か挿し木で増やせます。10~11月にサヤから熟したタネを採ってそのまま蒔きます。寒冷地では、冬に凍らないよう保存して翌年3月ごろに蒔きます。キングサリのタネには強い毒性があるので、保存する際には十分注意をしてください。
挿し木は3月ごろ、昨年に伸びた枝のうちで元気なものを選び、15~30cmに切ります。水揚げし、土を入れた鉢か、栽培場所へ挿します。鉢に挿したものは、直射日光が射さない場所で水を切らさないように管理し、十分成長したころ、春に植え付けをします。
花が終わった6月ごろ、剪定します。7月には花芽形成するので、剪定時期が遅れると翌年に花がつかなくなります。樹形はあまり乱れないので神経質になる必要はありません。枝同士が当たると傷つきやすいので、枝先を切り詰めます。混み入ってしまう場所では枝を整理し、樹形を乱す方向へ伸びる枝も払います。
花が咲く直前には蕾が見えるようになるので、4月ごろに不要な枝を切ることもできます。アーチにするなど誘引が必要なときは、固定具はゆるめにします。成長していくと幹や枝は太り、固定具が食い込んでしまいます。そこから栄養が滞ったり、
折れたりすることがありますので、余裕を持たせておきましょう。カイガラムシやアブラムシがつきます。これらは風通しが悪いと発生しやすくなります。カミキリムシの幼虫が幹を食い荒らすことがあります。見つけたら殺虫剤で駆除します。
病気はあまりありませんが、胴枯れ病などに注意しましょう。これは過度に剪定したり、太枝を切るとかかりやすくなります。切り口は殺菌剤やコールタールなどを塗ってふさいでおきましょう。
キングサリの歴史
キングサリは、ヨーロッパでは古くから知られた植物でした。古代ローマ、西暦22年生まれの大プリニウスが著した『博物誌』「植物篇」のなかに、キングサリについて触れられています。木材としての使用、花の房の形などを記述してあり、その当時から身近なものであったことが知れます。
イギリスではジョン・ジェラードが1597年の『奔走あるいは一般の植物誌』に、原産地以外のヨーロッパで街路樹として使用されていることを書いています。またこのころにはキングサリの葉の薬効や種の毒性もよく知られていました。
キングサリは西洋文化にも影響を及ぼしている歴史があります。1799年生まれのトマス・フッドは、『I Remember, I remember』のなかでキングサリに触れています。少年時代の思い出として、美しい花々の咲く庭の一角に弟がキングサリを植えたことを詠っている詩です。
宗教詩人フランシス・トムソンは『Sisters Song』を1895年に書き、キングサリを神秘的に描写しています。トムソンに触発された作家のJ・R・R・トールキンは、死後である1977年に出版された『シルマリルの物語』において、神木のモチーフとしてキングサリを使用しました。
花の時期が近く華やかなことから、キリスト教の復活祭の飾りとして使われることもありました。花が美しいため、観賞用として庭園や公園などで広く栽培されていたほか、木材としての利用も多く行われてきました。古くは弓を作るのに使用し、
現在では、家具や木管楽器の素材として使用されています。硬く色が黒いため、高価な黒檀の代用としても使われています。日本では明治初期に渡来したといわれ、主に園芸品種が栽培されています。
キングサリの特徴
マメ科の小高木です。フランスからバルカン半島にかけてのヨーロッパ中南部が原産で、山地に自生します。いくつかの種類は小アジア、アルプスを生息地としています。一般的にGolden Chain、Golden Rainと呼ばれ、日本ではキバナフジとも名づけられています。学名Laburnum anagyroidesから、ラバーナムと呼ばれることもあります。
高さは5~7メートルで、寒冷な環境では10メートルにもなります。5~6月ごろに明るい黄色の花をたくさん咲かせます。花は2cmほどの蝶のような形で、主軸に沿って等間隔につき、長い軸は枝から下へ垂れます。このため一見藤の花のように見えます。
花の房の長さは20~30cmになり、種類によって70cmにまで伸びます。おしべとめしべをもち、主に昆虫によって受粉します。キングサリの名前がついたのは、この花が金の鎖のように連なって咲くためです。葉は長い柄の先端に、小さな楕円形の葉が三枚つく形です。
4~5cmほどで、互いちがいに枝につきます。11月に落葉します。花のあとに緑色のサヤがつき、中にはマメがなります。10~11月に黒くなり、収穫できます。キングサリは植物全体が有毒ですが、特にマメは食用のエンドウとまちがえて
食べてしまう危険性があり、注意が必要です。このため、中国ではキングサリを「毒豆」と呼びます。毒性は主にシチニンというアルカロイドで、大量に摂取すると、嘔吐や痙攣などの症状が出ます。
-

-
パンジーの育て方
パンジーの原産はヨーロッパで、生息地は世界世界各国に広がっています。パンジーは交雑によって作られた植物です。その初めはイ...
-

-
ムシトリスミレの仲間の育て方
この花については、キク亜綱、ゴマノハグサ目、タヌキモ科となっています。その他の名前としてはピンギキュラと言われていて、ピ...
-

-
アブチロンの育て方
アブチロンはアオイ科の属の一つで、学名はAbutilonです。別名としてウキツリボクやショウジョウカ、チロリアンランプと...
-

-
植物の育て方について
タイトルにもあるように、私達に生活に溶け込んでいる植物ですが、育て方や栽培方法はどのようにすれば、良いのでしょうか、一般...
-

-
ブルビネラの育て方
ブルビネラは南アフリカやニュージーランドを原産とする花であり、日本で見ることが出来るようになってきたのはごく最近のことで...
-

-
リキュウバイ(バイカシモツケ)の育て方
リキュウバイは別名バイカシモツケと言われています。育て方も簡単で、原産地は中国北中部が生息地になっています。栽培して大き...
-

-
サンチュの育て方
サンチュの歴史は、古代エジプト時代に栽培が始まったとされており、朝鮮半島では4~6世紀頃の三国時代から食されていた野菜で...
-

-
ソバの育て方
この植物の歴史では、奈良時代以前に栽培されていたということは確実で、700年代前半の書物に関係の内容が書かれているという...
-

-
サボテンやアロエなどの多肉植物の育て方
多肉植物は、葉や茎に水分を蓄えることのできる植物です。サボテン科、アロエ科、ハマミズ科、ベンケイソウ科など様々な種類があ...
-

-
ガクアジサイの育て方
一般名として、ガクアジサイ(額紫陽花)といい学名はHydrangeamacrophyllaf.normalis。分類名は...




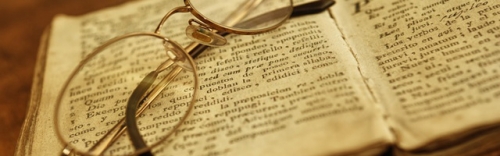





キングサリの科名は、マメ科 / 属名は、キングサリ属です。キングサリは、ヨーロッパでは古くから知られた植物でした。古代ローマ、西暦22年生まれの大プリニウスが著した『博物誌』「植物篇」のなかに、キングサリについて触れられています。