ヒメツルソバの育て方

育てる環境について
どんな環境でもしっかりと成長しますので、育て方は手がかからず、園芸が苦手な人や初心者でも上手く育てることができます。日蔭でも比較的元気に育ちますが、花をたくさんつけさせたいと望むなら、やはり日当たりのよい場所が適しています。
夏の暑さには非常に強いものですが、それに比べ若干冬の寒さには弱く、北の地方で大地まで凍るような土地であれば、根まで凍って、春に芽を出さなくなってしまう可能性もあります。鉢植えであれば、冬の間は屋内にいれたり、霜を避けた場所で日光にあたらせてあげたりなどすると、
ちゃんと冬を越します。またどうしても冬の寒さを越せないような地域では、地面に落ちたタネが地中で春を待っていることがあり、それによって春になるとまたその場所で成長してくれることがあります。またもし環境が許すのであれば、寒くなってきた時点で挿し木などを作っておき、
家の中で管理した後、適した季節に植え戻してやるなどすれば、ずっと楽しむことができます。挿し木は慣れていないと難しそうに感じますが、ヒメツルソバの場合には、かなり簡単です。切り戻しで切った蔓などを、葉が2枚程度ある程度で2センチほどの長さに切り、
それを柔らかめの腐葉土などを入れたポットに差して水をあげていれば、根を付け始めます。植え替えにも技術的なことはあまり必要がなく、成功します。店先には春と秋によく並び、ポット植えで売られているのを目にします。鉢植えにして切り戻しを上手く行うと、こんもりとした形状に仕上げることも可能です。
種付けや水やり、肥料について
植え付けや植え替えに適している時期は3月から5月ですが、真冬を除き、年間を通じてどの時期に行ってもしっかりと根を貼ってくれます。乾燥に強く、庭に植えているのであれば、水やりはほとんど必要ありません。あまりにも日照りが続き、見るからに元気がなくなった時に掛けてあげる程度でよいでしょう。
鉢植えの場合にも、土がカラカラになったら水をたっぷりあげるようにし、緩急をつけることが大切です。また水はけと通気性に富んでいる状態を好みますので、鉢植えには保水性を持っている土を用いるとよいでしょう。赤玉土小粒6に対して腐葉土4で配合されている土がオススメです。
肥料あまり必要ありませんが、、鉢植えではじっくりと効いてくるタイプの緩効性化成肥料を使います。肥料が多すぎるとかえって花のツキが悪くなりますので、追肥は行いません。庭植えは基本的に肥料は必要なく、余程葉の色や花ツキが悪い時などには、
活性化させるような液剤を水に混ぜて掛けてあげる程度でよいでしょう。日蔭でも育つというものの、全く陽のあたらない場所では育ちは悪くなります。柵や木などの陰になっていても、陽のあたる方向に自分で伸びてゆきますが、延びても50センチ程度です。
50センチ延びてもなお日蔭という場所は、植えるのは適していないと考えられます。ただし1年2年と時間を掛ければ、延びた場所にタネを落とし、徐々に陽のあたる場所を探して広がってゆくことはあります。
増やし方や害虫について
タネでも増えますので、勝手に周辺に落ちたタネか芽を出すことが珍しくはありません。しかし意図的に増やす時には、一般的に挿し木をおこないます。広がり過ぎて困る場合にはマメに切り戻しを行っておきますが、その枝を使うとよいでしょう。
2センチほどに切ってそのまま地面に差すだけでも、挿し木が出来てしまいます。確実性を上げるなら、ポットに柔らかめの土を入れて差します。差した時にはたっぷりと水を上げ、乾燥したらまた水やりをするなど、乾き気味にしておきましょう。
水やりをしすぎると、かえって良い状態ではありません。また性質が強権で、茎の節が地面につけば、そこに根をおろします。この根の部分が付いている茎を数センチの長さに切って差すと、更に成功率が高まります。非常に丈夫ですから、特に病気や害虫の心配はありません。
ただし庭植えなどをしていると、葉影が多く、その陰はナメクジなどがかくれるのに適しています。特にそのナメクジがヒメツルソバに害をなすということはありませんが、苦手な人もいるでしょう。ヒメツルソバの天敵は病気にしても虫にしても見受けられませんが、
ヒメツルソバ自体がその繁殖力の強さゆえに、他の植物に影響を与えてしまうことはあります。回りを囲まれて成長が悪くなったりしてしまうことは充分に考えられます。他の花と一緒に植えるには、場所などを良く考えたり、、切り戻しをマメに行うなどして、他の植物を守ってあげることに配慮が必要です。
ヒメツルソバの歴史
ヒメツルソバは原産国がヒマラヤの、タデ科の植物です。姫蔓蕎麦と書くことからも知れるように、花や葉が蕎麦の花に似ています。学名はPersicaria capitataです。カンイタドリ、ポリゴナムとも呼ばれています。日本では明治時代にロックガーデン用に取り入れられた多年草です。
花が淡いピンク色をし、小さい花が多数集まって直径1cmほどの金平糖のような形を作ります。その愛らしい姿からイメージされるように、花言葉は「愛らしい」「気が利く」「思いがけない出会い」などとなっています。花を付けている期間が長く、毎年長期間楽しませてくれる花です。
栽培はさほど難しくなく、初心者でも失敗はほとんどありません。緑色でV字形の茶色い模様が入った葉は、秋に紅葉します。匍匐によってどんどん増えてくれますので楽しいものですが、庭植えなどで半野生化した時の繁殖力は強く、驚くほど広がってゆきます。
そのため他の植物を駆逐してしまうこともあります。背丈はさほど高くはなりません。花の高さが、高くても3センチほど程度です。もともと丈夫ですので、過酷な状況下でも枯れることなく、グラウンドカバーとしても用いられることも多く見られます。
放置していても枯れることがほとんどなく、空き地などでも、雑草と同じようにたくましく生きているのを目にすることもあります。園芸種はこの原種のほかに、班入りヒメツルソバがあります。班入りの葉が寒い季節には緑、白、紅色の3色が混じり、大変きれいです。
ヒメツルソバの特徴
一つの株で50センチ程度は普通に延びるため、少ない株でもしっかり広がってくれます。成長点を止めるように切り戻しを行えば、回りに広がるように発育してゆきます。踏まれても元気に育ち、グランドカバーや石垣を彩るのに最適です。
比較的夏の暑さにも冬の寒さにも強く、それによって弱ってしまうこともあまり見られません。強いて言えば真夏よりも真冬の方が苦手で、霜が降るなどすればさすがに地上部は枯れてしまいます。しかし土の中が凍結してしまわない限りは、しっかり生きています。
頃合いの良い季節になれば、また新芽を出します。西日本の比較的温暖な地域であれば、冬を越すのに問題はありません。庭植えなどをして、他の植物も植えてあると、広がり過ぎてその成長に影響を与えてしまうこともあります。その時にも切り戻しをしますが、
次に延びてくる時に方向を誘導してあげるとよいでしょう。花の時期は4月から11月と大変長く、真夏には若干花が止まりますが、全くなくなるということはありません。 秋の紅葉もきれいですので、花とともに葉の眺めを楽しむこともできます。
同科別属に日本や朝鮮半島、台湾、東南アジアといった温暖な地域の海岸近くを生息地にしているソバツルがあります。こちらは葉も大きく 、ドクダミによく似ています。見た目も性質も ワイルドなことから、園芸植物として売られていることはあまり見られません。花の時期がヒメツルソバよりも短く、1月から12月まで程度です。花が白色です。
-

-
キャッツテールの育て方
キャッツテールの原産地はインドで、ベニヒモノキにも似ています。しかし匍匐性の小型種であり、亜熱帯地方や亜熱帯を生息地とし...
-

-
オレンジ類の育て方
インドのアッサム地方が生息地のオレンジ類は、中国からポルトガルに渡ったのは15世紀から16世紀はじめのことでした。地中海...
-

-
オカヒジキの育て方
オカヒジキの原産地は日本や中国、シベリア、ヨーロッパ南西部です。「ヒジキ」と言いますが海藻ではなく海辺の砂地などを生息地...
-

-
ランタナの育て方
一つの花の中にとても多くの色を持つランタナは、とても人気の高い植物で多くの家の庭先で見かける可愛らしい花です。ランタナ(...
-

-
きゃべつの育て方を教えます。是非、挑戦してみて下さい。
きゃべつは涼しい所を好み低温に強い作物です。また、冬を越して作られる品種は甘みが強く、生食でも加熱しても食べる事が出来ま...
-

-
スクテラリアの育て方
この花については、シソ科に該当します。花の大きさとしては20センチぐらいから1メートルぐらいになることもあります。花が咲...
-

-
スノードロップの育て方
真っ白な花に緑色の斑が美しいスノードロップを自宅で育てることができたら、まるでヨーロッパの庭のように美しい景色を作ること...
-

-
セイロンベンケイの育て方
セイロンベンケイというのは、ベンケイソウ科リュウキュウベンケイ属の植物で別名トウロウソウと呼ばれることがあります。ベンケ...
-

-
ハナモモの育て方
ハナモモというのは、中国が原産地で鑑賞をするために改良がなされたモモですが、庭木などにも広く利用されいます。日本へ入って...
-

-
ロニセラの育て方
ロニセラは北半球に広く分布するつる植物で、北アメリカの東部や南部が原産地です。初夏から秋まで長期間開花し、半常緑から常緑...




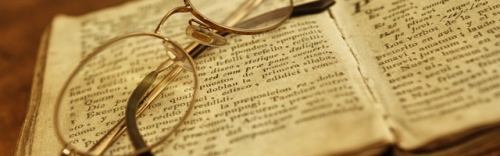





ヒメツルソバは原産国がヒマラヤの、タデ科の植物です。姫蔓蕎麦と書くことからも知れるように、花や葉が蕎麦の花に似ています。学名はPersicaria capitataです。カンイタドリ、ポリゴナムとも呼ばれています。