セイロンベンケイの育て方

育てる環境について
セイロンベンケイの育て方としては、1年を通して日当りのよい場所を選ぶことが好ましいとされています。セイロンベンケイは常緑多年草ですが、多肉植物として育てていくよりも耐寒性にはあまり強くない観葉植物として栽培していくことがおすすめです。
11月頃から5月頃までは、室内で栽培してできるだけ日当りのよい場所に置いてあげましょう。戸外のビニールハウスなどで栽培した場合は越冬することができずに枯れてしまうケースがあります。冬越しをする場合には、室内の窓際近くの日当りのよい場所で管理してあげるとよいでしょう。
夜になると冬場は気温が下がっていきますので窓際かだ移動させた方がよいとされています。乾燥にはあまり強い方ではありませんので、冬場でも乾燥には注意してあげましょう。夏場の気温が高くなり乾燥もしやすいシーズンには、多湿に弱いセイロンベンケイは株が弱まってしまうことがあります。
株が溶けてしまったりふやけてしまわないように、50パーセントくらいの遮光をしてあげることがおすすめです。また風通しをよくしておくことも大切になってきます。葉の部分に子株を付けたままにしていると親株の栄養分が吸収されていってしまいます。
親株が枯れてしまわないように秋頃になったら子株を取り除いていくメンテナンスを施してあげてください。秋頃になって日が短くなってくると花芽をつけるのですが、夜間に照明などがあるような場所に置いていると花が咲かなくなってしまうことがありますので注意してください。
種付けや水やり、肥料について
セイロンベンケイは12月頃から4月頃になると、比較的乾かし気味にして管理することがおすすめされています。春頃から11月頃までは土の表面絵が乾いてきたと感じたら水をたっぷりをあげるようにしていきます。夏場は乾燥しやすいためたっぷりと水やりをしたくなりますが、
水のやり過ぎにも注意するようにしましょう。また、日照時間が短いと直ぐに徒長するのでやや水やりを控えめにしてください。加湿に弱い性質を持っている植物ですので、土がまだ湿っているような状態で水やりをしないように注意しましょう。5月頃から9月頃になると、
緩効性化成肥料を定期的に施していくことがおすすめされています。10月、11月頃には液体肥料も施してあげると効果的です。植え付けや植え替えをするのに適しているシーズンは、5月6月頃と9月頃におこなうことがよいとされています。
花芽は植え付け作業をした後およそ年から3年くらいで出てくるのが一般的となっています。12月中旬頃になってくると花芽が伸び始め、花茎部分が50センチメートルほどに生育したら2月の半ばくらいから3月にかけて開花することが多いです。
植え替えをする場合は、2、3年に1回はおこなうことが必要です。根鉢を崩していき古い土と根を半分くらい落としていって、少し深めに植え付けをおこなっていきましょう。開花シーズンの1月頃から4月頃までは終わってしまった花をこまめに取り除いていくようにしてください。
増やし方や害虫について
セイロンベンケイの増やし方は、葉挿しや挿し芽による方法でおこなわれています。葉挿しをする場合は、4月から7月頃と9月頃が適しているシーズンとなります。葉を切り取ったら土の上に置いておくだけでも葉の縁部分に子株ができてきます。
株ができてきたらそれを切り離して植え付けをおこなっていくことで増やすことができます。挿し芽による作業も4月頃から7月頃と9月頃におこなっていきます。茎の部分を2、3節くらいに切り取って土に挿していきましょう。テッサ、ウェンディやエンゼルランプと呼ばれている鉢花の場合は、
葉の部分に株が生じないため挿し芽をして増やしていくことがおすすめです。大株になってくると冬から春にかけて開花しますので、株が大きくなって開花後枯れてしまった花茎などで美観を損なうような場合は切り戻しをおこなっていきましょう。
花が終わってしまう5月頃から6月頃の間に草丈をおよそ30センチメートルくらいまで切り戻していくことがおすすめです。セイロンベンケイの主な病気には灰色かび病があります。11月頃から5月頃に低温多湿の環境になってくると発生することがあります。
低温多湿になりやすい環境にある場合は換気をするなどの対策をおこなっていきましょう。害虫にはアブラムシやカイガラムシなどが挙げられます。アブラムシは、1年を通して発生しやすく新芽や蕾の部分に見られることが多いとされています。カイガラムシは風通しが悪いと発生しますので注意してください。
セイロンベンケイの歴史
セイロンベンケイというのは、ベンケイソウ科リュウキュウベンケイ属の植物で別名トウロウソウと呼ばれることがあります。ベンケイソウ科は、種子植物の内一般的に花と呼ばれる生殖器官の特殊化が進んで、胚珠が心皮にくるまれて子房の中に収まったようになる被子植物の科の1つです。
リュウキュウベンケイ属というのは、カランコエとも呼ばれ多肉質の葉を持つ多年草、短日植物のことを言います。ブリオフィルム節の植物はほぼすべて、マダガスカルに固有の植物ですが、セイロンベンケイの原産は南アフリカや熱帯地方などで広く分布しています。
日本国内であれば沖縄や小笠原諸島などに帰化しています。比較的日当りのよい場所を好みますのが、まれに隆起珊瑚礁の岩の上などが生息地であったりもします。およそ100種以上がアフリカ南部、東部、アラビア半島、東アジア、東南アジアに分布し、暑さと乾燥に強いとされています。
英語では、Good-luck leaf"(幸運の葉)と呼ばれることがあります。セイロンベンケイの学名Bryophyllumは、ギリシャ語の芽が出るという意味のbryoと、葉という意味のphyllonに由来しています。全草や根の部分には、
消炎作用や解毒効果が期待されていることから中国では関節痛や痛み、腫れなどに利用されていました。ブラジルなどでも炎症性疾患の治療などとして葉のエキスが利用されていました。日本国内では沖縄県などで止血用や虫さされなどで利用されていました。
セイロンベンケイの特徴
多肉質な多年草草本で、茎は直立したように伸び葉は対生につけていきます。草丈はおよそ1.5メートルから2メートルほどにまで大きくなることもあります。葉の部分には柄が入って、葉身は卵形のものや楕円形をしたものなどが見られます。葉の縁の部分はギザギザとしており先端は鈍頭です。
茎の先端部分には筒状の形をした長さがおよそ4センチメートルほどの緑がかった萼片からオレンジ色をした花を咲かせます。茎頂に着いている花序は長さがおよそ50センチメートルから70センチメートルになります。最初の頃は単葉になっているのですが、
生育していくと葉柄の延長になる軸から、左右に小葉がいくつか並ぶ羽状複葉のようになります。開花シーズンは1月頃から4月頃になります。セイロンベンケイは、土の中に埋めたり水がある皿につけると葉から芽が出る無性生殖の性質を持っている植物です。
その性質からハカラメ、葉から芽と呼ばれることもあります。無性生殖というのは、生殖の方法のひとつで、1つの個体が単独で新しい個体を形成する方法のことを言います。根が傷ついてしまったり根が弱ってしまったりした場合には、葉に不定芽をつけて形成していきます。
ベンケイソウ科ブリオフィルム属のコダカラソウによく似ているのですが、セイロンベンケイの場合葉が親株に付いている状態で子株が芽を出すことはあまりありません。またセイロンベンケイの方が葉色が濃くて葉柄が紫色を帯びているのが特徴となっています。
多肉植物の育て方など色々な植物の育て方に興味がある方は下記の記事も凄く参考になります♪
タイトル:コチレドンの育て方
-

-
トリトニアの育て方
トリトニアはアヤメ科トリトニア属の多年草になり、南アフリカ原産の植物です。トリトニアには40種から50種ほどのさまざまな...
-

-
カロケファルスの育て方
見た目からは少し想像がつきにくいですがキク科になります。種類としては常緑の低い木になります。耐寒性としては日本においては...
-

-
リコリスの育て方
種類としては、クサスギカズラ目、ヒガンバナ科、ヒガンバナ亜科、ヒガンバナ連、ヒガンバナ属になります。園芸上の分類としては...
-

-
オカトラノオの育て方
オカトラノオはサクラソウ科の多年草で、その歴史としては中国を生息地としていたこの種類の植物が朝鮮半島を経由して日本に入っ...
-

-
サクラソウの育て方
サクラソウとは、サクラソウ科サクラソウ属(プリムラ属)の植物で、学名をPrimula sieboldiiといいます。日本...
-

-
ホースラディッシュの育て方
アブラナ科セイヨウワサビ属として近年食文化においても知名度を誇るのが、ホースラディッシュです。東ヨーロッパが原産地とされ...
-

-
マンションで育てて食べよう、新鮮な野菜
皆さんは野菜はスーパーで買う方が多いと思います。とくに都会に住んでいる方はなかなかとれたての野菜を食べる機会は少ないと思...
-

-
コルチカムの育て方
コルチカムの科名は、イヌサフラン科で属名は、イヌサフラン属(コルチカム属)となります。和名は、イヌサフランでその他の名前...
-

-
エゴノキの育て方
日本全土と中国、朝鮮半島を生息地とするエゴノキは、古くから日本人の生活になじみ深い樹木です。チシャノキやロクロギなどの別...
-

-
カラスウリの育て方
被子植物に該当して、双子葉植物綱になります。スミレ目、ウリ科となっています。つる性の植物で、木などにどんどん巻き付いて成...




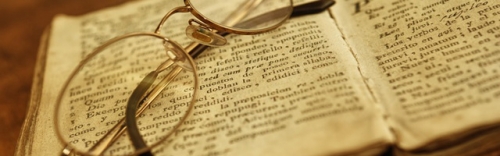





セイロンベンケイというのは、ベンケイソウ科リュウキュウベンケイ属の植物で別名トウロウソウと呼ばれることがあります。ベンケイソウ科は、種子植物の内一般的に花と呼ばれる生殖器官の特殊化が進んで、胚珠が心皮にくるまれて子房の中に収まったようになる被子植物の科の1つです。