ラグラスの育て方

育てる環境について
秋にまくと、15度から20度程度で発芽しますから、特別室内でなくても、自然の中で育てることができる、比較的手のかからない植物です。原産である地中海との違いは、大差ない上に、強い野草ですから、環境における考慮は、不要に近い植物です。しかし、どんな草花も、日を好むのが当たり前で、それで体内に栄養を作りますので、日当たりが良いというとこは、必須です。
ラグラスは、やせた庭や乾燥した土地でも育ちますが、小さくはびこっている雑草にしか育ちません。栽培植物としては、あまりにも貧相になります。また、寒さに強い分、夏の日差しに弱く、枯れてしまう心配もあります。それに、やせた土地に強いということは、湿地は苦手ということでもありますから、水はけのよい土壌づくりと湿気ないように風通しの良い環境設定は、とても大事です。
それは、一般的な植物を育てる基本ですし、良い結果を生み、開花後の観賞をする喜びにもなります。だから、環境を整えた上で、花壇にするか、鉢植えにするか、寄せ植えにするかなどを決めましょう。手で茎を引っ張るだけで簡単に抜けるほどの植物ですが、移植は、嫌いますので、種の場合は、直植えかポット植えにしましょう。
切り花やドライフラワー、玄関に飾る寄せ植え、単独で愛らしい、小さな鉢植えなどと利用の仕方を考えているでしょうから、移植するなら、小さいうちに植え替えておきましょう。ラグラス栽培の一回目の経験をもとに、次は、どこにどのように、どの性質のものをどう植え、後はどう楽しむのか、考え直すというのもまた園芸の楽しみとなるでしょう。
種付けや水やり、肥料について
日当たりと水はけの良いところに、秋に種まきをします。ラグラスは、移植を嫌いますから、ポットまきか直まきが良いでしょう。こぼれた種でも発芽するほど、発芽の率は、とても良いです。種まきをする前に、水はけを確認し、種をまく5から7日くらい前に、腐葉土や牛糞と一緒に石灰を混ぜるなど、多湿化や酸性化しない良い土環境を設定しておくことが、大切です。
鉢植えやプランターなどの人工的な環境づくりをする場合は、一般的な栽培用の用土作りで大丈夫です。種まき後40日程度の初冬には、草丈が5cmぐらいになりますので、直植えは、間引きをして、20cmほどの間が空くようにし、ポットまきも同様に、水はけの良い場所に移して、株の間をある程度開けて、密生をしないように植えつけましょう。
そして、真冬に突入しますが、霜にも強いラグラスは、そのまま越冬できます。初春には、無事に苗に育っています。植えつけの後は、水は、乾けば気を付ける程度で十分ですし、肥料も、育ちが悪ければ少し与える程度で十分です。移植を嫌う植物ですから、大きくなってから移すというのはやめて、するのであれば、
植えつけなどの、まだ小さい時に、植えたいところに移すと良いでしょう。雑草の部類と言っても、輝きのないものには、育てたくありませんから、ラグラスの特質をよく知って、その植物が、より喜ぶ環境の中で育てるようにしましょう。栽培により、野草を楽しめる洗練された花とするのが、園芸の価値ですし、園芸家としての充実感もあります。
増やし方や害虫について
ラグラスは、どんなところでも自生できる強さを持った野草ですから、自然の中の自生できる環境下においては、病気も害虫も心配することは、ありません。けれども、日向を好む野草に日陰や多湿な場所を与えてしまうと、色んな病気も起きますし、草花を選ばず食べる害虫たちも集まってきます。土壌が酸化して、根が腐ることもありますし、細菌がわいて、それにやられてしまうことも考えられます。
適した環境にあってこその病気知らずということです。植物によっては、適した環境を与えても、デリケートで敏感なものは、病気や害虫に気を付けることとなりますが、適度の日光浴と密生しないように配慮された風通しや適度に肥えていて、適度に保水もある、水はけのよい土地を保つことができれば、ラグラスには、病気も害虫も心配ありません。
この植物の強さは、乾いた土地でも生きるということであり、湿気や日陰であっても強いということではありません。乾いた、からっとした地中海性の気候の下では、病気も害虫も心配なかったのだと考えるべきであり、ラグラスは、不死身の野草で、雑草的に生き、繁殖できるなどと考えては良くありません。
自生する場所は、選ばないというものの、生息地は、山の中などの多湿で陰のあるところの育つ野草とは、性格を全く異にする、湿気のないところです。どんなところにでも育つという言葉を勘違いせずに、環境を整えてあげましょう。そうすれば、病気にも害虫にも負けません。
ラグラスの歴史
ラグラスは、ふさふさした穂がかわいらしく、野兎のしっぽの意味を持つ名前で、イネ科の植物です。原産地は地中海沿岸で、秋まきの一年草ですが、穂が長く持ちますから、形の面白いキュートな姿を、長い期間楽しめます。同じラグラスでも、横に広がりやすいものは、寄せ植えには向きません。性質の違いで株の大きさが異なりますし、容姿の特質も違いますから、用い方も、
切り花向きのもの、寄せ植え向きのもの、じかに植えるものと、その姿の様子から分けると良いでしょう。と言っても、背丈は、高くても50cm程度ですし、横への広がりも40cmまでです。春から初夏が一番の見どころで、それ以降は、葉や株が横に広がってしまいますので、キュートさは半減してしまいます。生息地にこだわりなく根付く植物ですから、
やせた土地や乾燥気味のところでも、しっかり生きることができる丈夫さを持っています。育て方に特別気遣いが不要であることも、魅力的なところでしょう。けれども、水はけが悪いと、生きることはできても、生育が悪くなり、良い育ち方をしません。単に、生えてくれば良いというのでは、雑草の域から脱していません。
やはり、栽培というのは、観賞に耐えうるものにすることですから、栽培の基礎である用土作りにおいて、植物が育つのに適した、水はけの良い環境づくりをしておくことは必須です。適した土に育てば、後は、別に手間暇をかけずに、切り花や寄せ鉢植え、庭のチャームポイントとして、ラグラスを楽しむことができます。
ラグラスの特徴
ラグラスは、春から初夏にかけて咲く、2から4cmほどの花穂が愛らしい植物です。だから、ギリシャ語でウサギのしっぽを意味する、この名前がついています。エノコログサの仲間で、野草ですが、栽培したいと惹かれるほど、白くて、ふさふさしたところが素敵なイネ科の耐寒性の一年草です。猫じゃらしやネコヤナギに似たイメージの植物ですから、
他の植物たちと一緒にいることで、引き立て役をしたり、愛らしさや優しさのイメージを添えたりする役目が多いです。地中海沿岸に自生していたため、本来寒さに強く、どんなところでも育つというところが、この植物の特徴ですが、その分暑さに負けることがありますから、世話いらずと言っても、栽培の基本である、程よい日光と水はけのよい土と風通しが確保できる環境を整えてこそです。
矮性のものは、草丈が15cm~25cmで、背丈が低くて横広がりですが、高性のものは、すらりと縦に伸びますから50cmほどになります。横広がりか、縦広がりかで、用い方も違います。それだけでもかわいらしいですが、地味な分、アレンジ的に使われることが多いですから、寄せ植えにするか、じかに植えるか、
単独で鉢植えにするのかなど、栽培する人の判断で、適した利用をすると良いでしょう。ただ、庭まきでも、ポットまきでも、育ってくれますが、移植を嫌う特質がありますから、どのように植えるのかは、きっぱりと判断することが大事です。そうすれば、開花後は、様々な利用の仕方で、色々な楽しみを得ることができるでしょう。
-

-
ロムレアの育て方
南アフリカはアヤメ科の球根が、たくさん栽培されていて、ロムレアもその仲間のひとつです。手に入りにくい球根と言われていまし...
-

-
リューココリネの育て方
分類としてはヒガンバナ科になります。ユリ科で分類されることもあります。ユリのようにしっとりとしているようにも見えます。園...
-

-
ハスカップの育て方
ハスカップは青紫色の実をつける植物で、スイカズラ科スイカズラ属です。落葉低木と言う事からも、庭木など観賞用で育てたいと言...
-

-
イングリッシュ・ローズの育て方について
自宅の庭でバラの栽培をしてみたいと考える人が大勢いますが、バラの栽培は難しそうだというイメージがあるため、躊躇してしまう...
-

-
ヨウシュコバンノキの育て方
日光を浴びる事で、成長を促進させないと、葉っぱの白い斑が消えてしまう事があります。白い斑は新芽の間の事なので、しっかりと...
-

-
メセンの仲間(夏型)の育て方
この植物の特徴としては、まずはハマミズナ科に属する植物で多肉植物であることです。ですから茎などがかなり太くなっています。...
-

-
ユーフォルビアの育て方
ユーフォルビア、別名、ユーフォルビアダイヤモンドフロストは、トウダイグサ科ユーフォルビア属の植物です。生息地は世界の熱帯...
-

-
プテロスティリスの育て方
プテロスティリスは、オーストラリアの南東部が主な生息地であり、ニュージーランドやニューカレドニア、パプアニューギニアと言...
-

-
カランセの育て方
カランセはラン科エビネ属の多年草です。日本が原産地となっているエビネ属の花もありますが、熱帯原産のものを特にカランセとよ...
-

-
サイネリアの育て方
サイネリアはキク科植物の一つで、カナリア諸島が原産のものだと考えられています。かつては「シネラリア」とも言われていたそう...




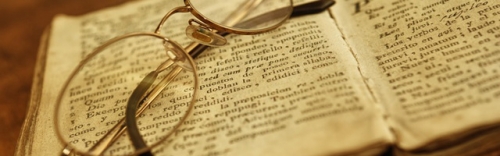





ラグラスは、ふさふさした穂がかわいらしく、野兎のしっぽの意味を持つ名前で、イネ科の植物です。原産地は地中海沿岸で、秋まきの一年草ですが、穂が長く持ちますから、形の面白いキュートな姿を、長い期間楽しめます。同じラグラスでも、横に広がりやすいものは、寄せ植えには向きません。