オレアリアの育て方

育てる環境について
植物を育てる環境というのは、様々な季節の影響を受けますが、何よりも大事なのは水や太陽の光になります。植物の葉っぱが緑色をしているのが多いのは、葉緑体という物質あるからになります。この葉緑体というものがあるからこそ、生き生きと植物は育つことができ、太陽光のエネルギーを使って成長しているということです。
そして葉緑体では、根から吸い上げた水と空気中の二酸化炭素を、栄養と酸素を作りだす作業をします。ちなみに栄養というのはでんぷんになります。オレアリアという植物も日光を好みますが高温多湿に弱いという特長があり、あまり日が当たり過ぎてしまうと弱くなってしまいます。
しかし、ある程度の日の光が当たることによって、より栄養を吸収して土からの力を得ることになるので、とても育てることは簡単です。日本では夏は涼しく過ごせるようにしなくてはいけないので、なるべくならば風通しの良い場所で育てることが一番になります。そして移動できるように鉢植えをしているならば、半日陰の場所へ夏場などは移動させることによって、
より綺麗に成長していきます。乾燥に強いという特性もありますので、あまり水をあげすぎるのは、根を腐らせてしまいます。水をあげるタイミングというのは、土が乾いてきたと思った時には水をあげるタイミングになり、あまりたくさんの水をあげすぎないということが注意点になります。こういった太陽の光や温度、そして水に注意しているといいです。
種付けや水やり、肥料について
オレアリアの種付けなどを行う場合には、まず土の状態がいいものを用意してやっていくことが大事です。状態の良い物を購入してきてもいいですし、農家から良い土をもらってきてもいいですが、何よりも栄養がたっぷりのほうが育ちが良いということがわかります。そして植物に水をあげるのは、成長に欠かせないことですが、その特性を理解して水をあげることをしなくてはすぐにダメになってしまいます。
そして栄養として土に栄養を与えることによって、植物は吸収していきますので、そういった植物の命の恵みを与えることで綺麗に育っていきます。これはオレアリアも同じようなもので、先にあげたように水のあげすぎには注意が必要になりますが、だからといっていつまでも土が乾燥している状態では栄養も行きわたらないので、時期によって肥料などを与えるといいです。
オレアリアでは、肥料を与える時期としては命が芽吹いてくる春に与えるのと、そして冬に備える準備に入る秋に与えるといいです。肥料の種類としては緩効性肥料をやっていくとより効果的です。それか植え付け前に緩効性肥料をやるのも一つの方法になっています。
種付けをした場合には、水のあげすぎに注意してそして肥料にもポイントがあるということを理解しておくといいです。すべての生き物には生きる為のポイントがあり、これらを知っておくとよりその植物を増やしていくことができるので、またガーデニングなどの楽しみも増えてきます。
増やし方や害虫について
上手な育て方には、水はけの良い土に植え替える必要がありますが、根を痛めないようにする事が注意ポイントです。市販されている花と野菜の土でもいいですし、その時には古い土は軽く落とすようにしておくと、より成長を見込めます。植物には新しい息吹が必要になりますので、常に古くなった物を新しくとり変えることによって、植物の成長を促進させていきます。
成長をしてくると一回り大きい鉢に新しい土を足して植え替えをした方が良いです。それまでの大きさの物では対応できなくなるので、しっかりとした大きさの余裕が必要になってきます。こういったことをマメにやっておくことによって、増やし方が簡単になっていきます。その他にも注意点としては、同じ大きさの鉢に植える場合は、3分の1程度根を切ったほうがいいです。
もちろん地上部も同じくらい切り取ってから、新しい土を入れてあげることが望ましいです。挿し木で増やすことができるので、これは若い茎を10cmくらい切っておき、水はけの良い土へ挿していくことによって、増やしていくことが可能になります。気をつける点では、いくら寒いところに強いからと言って、
真冬の霜に当たらないように気を付けなくてはいけないです。あまり放っておいてもよくないということです。害虫には他の植物よりも強いこともありますが、常に気にかけてあげることで成長と共に強くなっていくのが、オレアリアの素晴らしいところになります。
オレアリアの歴史
植物が好きな人はたくさんいて、今ではガーデニングなどが流行っています。花や植物を育てるというのは、心の癒しになりそして日々の楽しみになることから、定年退職した高齢者や家庭の主婦がやっていることが多いです。好きな人では写真にとって、ホームページなどにアップしていたりします。
オーストラリア産で有名な植物では、オレアリアがあり、細かな葉っぱが綺麗に映える植物であります。意外と感じますがキク科の植物になるので、日本にも適用するイメージが強くあります。そして大きさは高さというのは25~60cmになり、そんなに大きくは無いですが、ちょうどそのサイズの植物が好きな人にはとても癒されます。
オレアリアは常緑低木になっていて、生息地のオーストラリアでは130種もあります。それだけ種類があるので実際に楽しみ方の広がってくるものでもあります。更にニュージーランドに25種もあることから、南の温かい地方に多い植物になり、太平洋では南の島々に分布を広げているので、世界的にも180種ほどあります。
日本でも人気のオレアリアでは、そのほとんどがオーストラリアの乾燥地帯に分布しているので、日本に園芸用として入ってきている種類の物では、そんなに多くは無いです。原産がオーストラリアということでは、とても日の当たる気候だということがわかりますし、乾燥している地方もあるので広い意味では、耐性のある植物になりますが、やはり日本で栽培となると種類も少なくなります。
オレアリアの特徴
そしてオレアリアの特長としては、葉も枝もシルバーの軟毛で覆われていることがあります。シルバーの軟毛ということで見た感じは、とても白がイメージされますが、良く観察してみると輝くシルバーという方が当たっているかもしれません。そして成長した成葉になると、いずれは消えていき、やがては緑色になるのも特徴になります。
この緑というのは、植物全般にいえますが色ではなかなか出せないものになり、人間はそういった自然の色を見ることによって、心の癒しができるということも言われています。そしてオレアリアは春や秋に小さな黄色の花を咲かせますが、この黄色も好きな人がいますが、実は鑑賞価値がないともいわれています。そして日本に入ってきている種類では、
かなり耐寒性があるので、寒い季節でも耐えている植物になります。本当によく見てみると、白ではなく独特の色合いのシルバーがありますので、クリスマスシーズンなどには、家庭の庭にあるととても冬の情景を飾ってくれます。こういった美しい色合いが冬にあっているので、日本でも寒い地方では人気があり、
一見自然の物ではないと感じるものになるので、花壇を綺麗に見せる為にも大きな意味を持っています。色としてもシルバーが好きな人が多いので、心の癒しにもなるということは、ちょっとした息抜きにも眺めていると嬉しくなるということでは、この映えるシルバーを出してくれるオレアリアは根強い人気があります。
-

-
バーベナの育て方
バーベナは、クマツヅラ科クマツヅラ属(バーベナ属とも)の植物の総称です。様々な種類があり、基本的には多年草、あるいは宿根...
-

-
ルバーブの育て方
ルバーブはタデ科カラダイオウ属に分類されている、シベリア南部が原産のハーブです。ボルガ河の辺りは、野生種の生息地でもあり...
-

-
チランジアの育て方
チランジアは中央アメリカや南アフリカ、西インド諸島などを生息地とする植物です。銘々はカール・フォン・リンネです。リンネは...
-

-
モナデニウムの育て方
モナデニウムは日当たりのいいところで栽培をします。そして育て方は土が乾いたらたっぷりの水を与えてあげます。塊根タイプの植...
-

-
オギの育て方
イネ科ススキ属のオギは、古くから日本と関わりのある植物です。原産は東アジアで、主な生息地の一つが日本です。ススキとよく似...
-

-
温州みかんの育て方
みかんは、もともとインドやタイ、ミャンマーなどが原産だと考えられています。生息地は、現在では世界各国に広がっていますが、...
-

-
ローダンセマムの育て方
ローダンセマムの開花時期は春から初夏の間です。一般的な色は、薄く淡いピンク色やホワイトなどがあります。ひまわりのように丸...
-

-
ハクサンイチゲの育て方
花の高さは約15センチから30センチで、上記でも述べたように大群落をつくります。その姿は絨毯を敷き詰めたようで圧巻です。...
-

-
オーリキュラの育て方
オーリキュラは、本来はヨーロッパのアルプスに自生する植物です。高山植物として扱われていて、日本でも栽培されています。原産...
-

-
アズマギクの育て方
アズマギクは東北地方、関東地方、中部地方を原産とする日本固有の植物です。キク科ムカシヨモギ属の植物で、植物の中でも最も進...




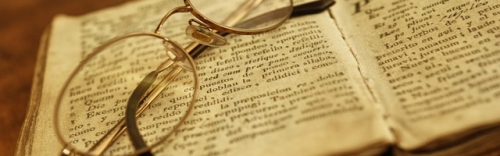





意外と感じますがキク科の植物になるので、日本にも適用するイメージが強くあります。そして大きさは高さというのは25~60cmになり、そんなに大きくは無いですが、ちょうどそのサイズの植物が好きな人にはとても癒されます。そしてオレアリアの特長としては、葉も枝もシルバーの軟毛で覆われていることがあります。シルバーの軟毛ということで見た感じは、とても白がイメージされますが、良く観察してみると輝くシルバーという方が当たっているかもしれません。