コプロスマの育て方

育てる環境について
コプロスマは日当たりの良い場所を好むので、育て方としては日の当たる明るい場所に置いて栽培します。丈夫な植物なので明るい日陰でも十分育ちますが、日照が不足すると冬の時期に赤や褐色などの葉の色が美しく出ないことがあります。
低温になった時の葉の色づきを良くしたい場合には、普段から日光によく当てて管理します。コプロスマは耐寒性のある植物で、種類によってはマイナス5度まで耐えられます。そのため低温によって枯れることは少なく、暖かい地域では屋外で越冬することもできますが、
気温が低くなるときには藁を敷くなどして霜よけ対策をしておきます。関東より北の地域で栽培するときは、冬場は室内で育てるようにしてください。過酷な環境下でも耐える性質があるので、生息地のニュージーランドでは風あたりの強い海岸線や砂地などでも見ることができます。
寒い時期に葉が赤や茶色などの暖色に色づくため、色味がさみしくなる冬場の花壇でも重宝され、庭のポイントになってくれる植物です。生長が早いので形を整えるためには枝を剪定する必要があります。コプロスマも花が咲くのですが、その大きさはとても小さくて目立ちません。
この植物は葉を楽しむ植物になり、花を鑑賞する機会はほとんどないので、剪定する場合もその後の花芽を気にせずに枝を切ることができます。鉢植えで育てる場合には、株が育って大きくなってきたら、適正な時期にひと回り大きめの鉢に植え替えを行います。
種付けや水やり、肥料について
水はけの良い場所を好むので、水やりは土が乾いた時に行うようにします。夏場の土がすぐ乾くような時期には毎日水を与えますが、気温が低くなってきたら水やりの回数を徐々に少なくしていきます。コプロスマは湿度の高い環境が苦手なので、夏でも水を多く与え過ぎないようにしてください。
必要以上に水を与えてしまうと根が腐ってしまい枯れてしまう原因になります。庭植えの場合には、植付けした当初から根付くまでは水をしっかり与えるようにしますが、それ以降は雨が降らずに日照りが続いた時などに与えるようにします。
コプロスマを鉢植えする際の土は、赤玉土と腐葉土を混ぜた通気性がよく腐葉質の高いもの、または市販の草花用の土を使用します。植付けに適した時期は、4月から6月あるいは9月から10月の間になり、適度に根を崩してから植付けするようにしてください。
鉢植えの場合、鉢の底から根が伸びているようであれば、根詰まりを防いで生育を促すため植え替えを行います。植え替えをする時期は4月から5月くらい、大体2年に1回を目安として行います。寒冷地で庭木として育てている場合は、越冬させるために鉢などに移して室内で管理します。
肥料は植付けをする際に、元肥として緩効性ものを土に混ぜ込んでおきます。春と秋には油かすや薄めた液体肥料、緩効性の固形肥料などを与えるようにしますが、過度に肥料を与えるとコプロスマの特徴もである葉の色が悪くなる場合があるので、頻繁に与える必要はありません。
増やし方や害虫について
コプロスマは挿し木で増やすことができます。挿し木をする時期は4月から6月、または9月から10月が適していて、5cmから10cm程度に切り取った挿し穂を準備して、土に挿す部分の葉を取り除いておきます。挿し穂はしばらく先端を水につけておき十分に水分を吸わせておきます。
それを赤玉土などの通気性の良い土に挿し込んで、根が出るまでの間は水やりを忘れないようにしてください。鉢に挿す時は中央ではなく端の方に挿しておくと発根しやすくなります。確実に増やしたい時には、すべての挿し穂が発根するとは限らないので、
複数本の挿し穂を準備して栽培するようにします。挿し穂に利用するための枝を切る時には、早めに根を出したい時は斜めに、太い根を育てたい時には水平にカットするようにします。また挿し穂を土に挿す時には茎で穴を空けるのではなく、茎を傷めずにスムーズに挿せるように、
事前に棒などで穴をあけておきます。また園芸店などで市販されている、発根を促進させる薬剤を挿し穂の枝先に塗っておくと根が出やすくなります。コプロスマは病害虫にかかりにくく、育てやすい植物です。そのため薬剤散布の心配もなくベランダなどでも管理しやすくなっています。
コンテナやバスケットに寄せ植えしたり、品種によっては地面に這う特性があるので、庭先のグランドカバーとしても利用できます。枝が伸びてしまい形が崩れてしまった時には、春先に剪定を行うようにします。
コプロスマの歴史
コプロスマはアカネ科コプロスマ属の常緑低木になり、オーストラリアやニュージーランドを生息地としていてます。コプロスマにはおよそ90もの種類が存在していますが、その多くがニュージーランド原産です。3月から5月ごろに花は咲くのですがあまり目立たず、
葉の色が特徴的なので、観葉植物として栽培されることが多くなっています。雌雄異株になり、品種によって葉の色や大きさに違いが見られます。木立のように直立して育つものや矮性のもの、葉も斑が入ったり、白っぽいもの、褐色のものなどさまざまな葉色が見られるため、
寄せ植えや生け垣などに多く利用されている植物です。学名は「coprosma 」(コプロスマ)で、日本での栽培の歴史はそれほど古くないのですが、生息地のオセアニアではとても一般的な庭木になり、公園などでも利用されています。コプロスマと同じアカネ科には
コーヒー豆が取れるコーヒーノキがあり、コプロスマの中にも「コプロスマコーヒー」という種類がありますが、こちらはコーヒー豆は取れず、気温が下がってくると葉の色がコーヒーのように茶褐色になることが名前の由来となっています。
コプロスマの原種は単色の緑の葉になりますが、交配によって斑入りのものなどが生まれてきました。現在では生け垣などに多く用いられるレペンス種と、レペンス種とアケロサ種の交配種であり、茎が柔らかく地面に這う性質をもつカーキー種などが園芸では多く見られます。
コプロスマの特徴
コプロスマは50cmから100cmほどの丈に生長し、原種の他にも園芸品種として交配が進んでいるので、さまざまな色や形が見られます。園芸店でも多く流通していてよく栽培されている品種では、暖かい時期は緑色ですが冬になると葉が赤茶色になる「コーヒー」、
葉の中央に黄味を帯びた斑が入っている「ビートソンズゴールド」、枝が柔らかくグランドカバーに適していて、葉が白く縁取られている「カーキ」、光沢のある大きな丸い葉が美しい「マーブルキング」、明るい黄金色と茶系の縁取りのコントラストが楽しめる
「パインコラダ」、細長くとがった小さな葉が特徴のある「オータムヘーゼ」など、同じコプロスマでもまったく違った雰囲気があります。また、特徴的な茎に小さな葉のついたシックなイメージの「ピンクステム」、冬になると赤く葉が色づく「夕焼け小焼け」など、
つぎつぎと新しい品種が増えてきているのも魅力となっています。コプロスマは品種によって大きさや耐寒性が変わってくるので、どのような場所で育てるかによって種類を選ぶこともできます。病気や害虫にかかりにくく、比較的丈夫な植物なので育てるのは苦にならず、
園芸初心者にも向いている植物です。鉢だけでなく、ポット苗でも多く流通しているので手軽に植え込みができます。コプロスマの品種の多くが気温によって葉の色が変わってくるため、緑から赤色、胴葉から茶褐色などそれぞれの四季ごとに異なる雰囲気が楽しめます。
-

-
ベゴニア・センパフローレンスの育て方
ベゴニア・センパフローレンスはシュウカイドウ科ベゴニア(シュカイドウ)属に分類される常緑多年草です。ベゴニアはとても種類...
-

-
植物の育て方について
今年はガーデニングで野菜を育ててみようと思っている初心者の方におすすめな野菜の1つがプチトマトです。今まで植物を育てたこ...
-

-
ファセリアの育て方
ファセリアはハゼリソウ科の植物で双子葉植物として分類されていて280種ほどが世界中で栽培されていて、南北アメリカ大陸を生...
-

-
ナバナ類の育て方
ナバナ類と人類との歴史は古く、その関わりは現代でも続いています。地中海沿岸が原産の野菜であり、最初の利用は麦畑を生息地と...
-

-
タコノキの育て方
タコノキの生息地と原産はユーラシア大陸、アフリカ大陸、オセアニア周辺の島などで、温暖な地域に広く分布しています。現在は5...
-

-
チグリジア(ティグリディア)の育て方
チグリジアは別名ティグリディアとも呼ばれるユリに似た植物ですが実際にはアヤメ科の仲間になっています。チグジリアの仲間アヤ...
-

-
アスパラガスとスイゼンジナの栽培方法
まずはアスパラガスの育て方を説明します。保健野菜で有名なアスパラガスには、缶詰用のホワイトと生食用のグリーンとの二種類が...
-

-
セアノサスの育て方
セアノサスはカナダ南部や北アメリカにあるメキシコ北部が原産となっています。花の付き方が似ているという理由から、別名をカリ...
-

-
ニガナの育て方
ニガナはキク科の多年草で、原産地及び生息地は日本や東アジア一帯ということで、広く分布している植物でもあります。日本でも道...
-

-
リグラリアの育て方
リグラリアは菊科の植物で、原産は東アジアの広い地域を生息地にしています。日本においても、かなり古くからある植物で、中国と...




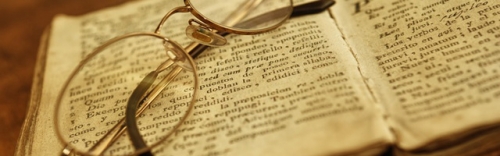





コプロスマはアカネ科コプロスマ属の常緑低木になり、オーストラリアやニュージーランドを生息地としていてます。コプロスマにはおよそ90もの種類が存在していますが、その多くがニュージーランド原産です。